「延寿」という言葉があります。
今この言葉をwikipediaで引くと、「寿命を延ばすこと。長生き。」と出てきます。
延寿、延命。これらは普段我々もよく使う言葉でもあるわけですが、この言葉が出来た経緯が少し興味深いのでここでお話ししたいと思います。
延寿の背景
昔、中国に「智覚禅師」という、周りからとても慕われるお坊様がいらっしゃいました。
この方は初め、官吏だったんですね。要するに国に仕える「役人」だったわけです。
財産も多く、その上、心のまっすぐな「賢者」のような人であると言われていたといいます。
ある時、何を思ったかこの智覚禅師は勤め先の役所のお金を盗んで貧しい人に施してしまったというのです。
これを見ていた役人仲間たちが皇帝に告げ口をするわけですね。
皇帝はそれを聞いて、大変驚き、また同時に不思議に思ったといいます。
智覚禅師といえば真面目で、周りからも慕われるほどの人物。なぜそのようなことをしでかしたのかということを思うわけです。
しかしその盗んだ額が非常に大金だったため、決議の上、敢えなく死罪に処されることになってしまいます。
とはいえ、皇帝は非常にこの智覚禅師のことを信頼していたため、臣下に対し、
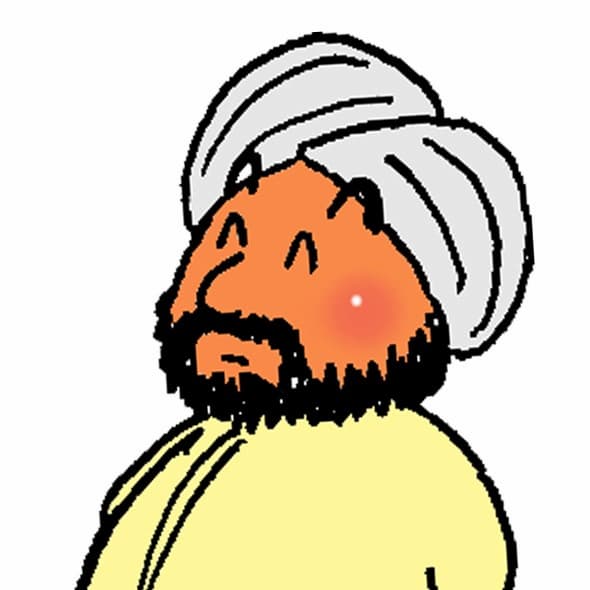
「この者は学問もあり、賢者でもある。それなのにこのような罪を犯すのには何か理由があるはずだ。もし、首を切る時に悲しみ嘆く様子があったら、さっさと切ってしまって良い。しかしその様子がない場合はきっと何かあるだろうから切ってはならない」
このように言い渡すんですね。
当日を迎え、いざ首を切ろうとした時、少しも悲しむ様子がない。かえって喜んでいる様子もある。また智覚禅師は次のようにいうわけですね。



「この度人間に生まれた命は、一切の生きとし生けるものに施すのである」
皇帝はそのことを聞き及び、すぐさま刑の執行を中止したといいます。そしてなぜ今回このようなことをしたのか、その理由を改めて尋ねました。
すると智覚禅師は次のようにいいます。



「私は官吏を辞めたいと思っていた。命を捨てて、施しを行い、生きとし生けるものと仏縁を結び、次の世には修行僧として生まれ、ひたすら仏道を行じたいと思っていた」
皇帝はこの言葉に打たれ、この智覚禅師を許し、出家をさせました。そしてこのことを経緯に「延寿」という僧名を賜ったと言われております。
これが「延寿」という言葉の背景です。
延寿とどう向き合うか
今「延寿」に関連した事といえば、個人的にやりたいことがあって生きながらえたい、あるいは生きながらえさせてあげたい。そのために延命措置をして、命を繋ぐこと。またそれが実現し、みんなが喜ばしい時などに使われたり、捉えられたりするものです。
しかし元々は仏道に生きるため、あるいは自分の身を貧しい人や仏に捧げるために命を惜しまなかった人がいて、その者に対し、感銘を受けた人がその生き方を実現させてあげようと思って、延命させたことがこの言葉の始まりになっているわけです。
仏道に生きたいもの。それを支えてあげたいと思うもの。そう言ったもの同士のやり取りだったわけですね。生きることに対し誠実で、信心深く、また信念を持ったもの同士のやり取りがあったわけです。
その背景を知ると「延寿」と言っても、何のために生きながらえるのか、何のための人生なのか、自分にはそこまでして成し遂げたい何かがあるか、これから自分がやっていくことにそこまで誇りを持てるのか、そういった考察が始まってくるのが面白いです。
仏道とは何か?我々の正しい生き方とは何でしょうか?

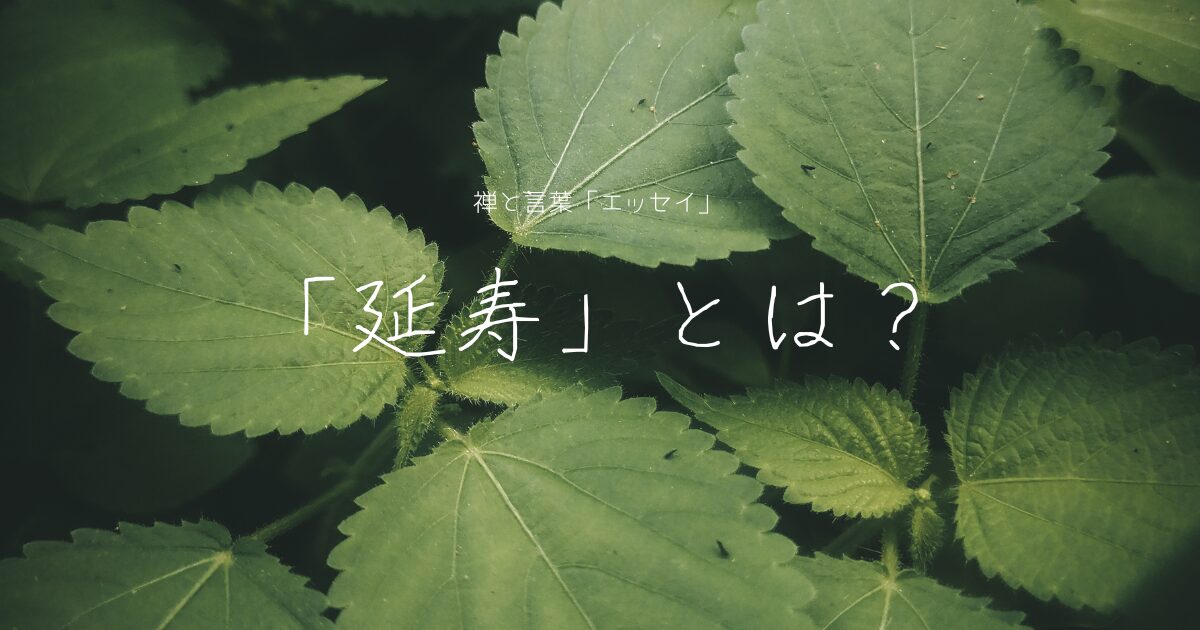
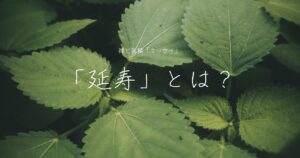
コメント