当blog「禅の旅」は道元禅師の教え、生き方をテーマに扱っております。
ただひたすらに坐禅をする事(只管打坐)が、「悟りである」と説かれた道元禅師。
また世界的名著と呼ぶにふさわしい『正法眼蔵』や『普勧坐禅儀』を記された道元禅師。
道元禅師は幼いながらに、「何故、ひとは生まれながらに仏であるのに、修行をしなければならないのか?」という大きな疑問を持たれました。
しかし当時この質問に答えられる人物が周りにはおりませんでした。
そこで「真の仏法」を求めて中国へ渡り、天童山の如浄禅師とあいまみえ身心脱落の体験をされます。そこで仏法の大意と出会ったわけです。それは普段の日常における、坐禅修行そのものでした。
その後帰国されてからは、中国での経験をもとに、日本にいまだ伝えられていなかった「正しい仏法」を普及されました。
またその後は京都へ移り、脈々と弟子の育成に時間を割いたのち、世界にその名を轟かせるまでになった禅の総本山、「永平寺」を開かれるのです。
本記事では、今見てきた道元禅師のご生涯についてさらに詳しくご紹介します。
なお、本記事は以下の「別冊太陽 道元」監修角田泰隆(平凡社)を一部参考にしながら執筆しています。
それでは参りましょう。

道元禅師がお生まれになった時代背景

道元禅師が生きた中世期時代(西暦1000年 – 1250年)は、顕密仏教(旧仏教)が仏教界に広く浸透していた時代だったと言われております。
顕密仏教が当時の時代を牽引していたんですね。
またそのように顕密仏教が広く根付いていた時代では僧侶が妻帯することは普通とされており、僧侶は仏法を守護する為には武器を手にして敵を倒すことが平気で許されていました。
そのような時代にあって、本当の仏法とは何か?真実の生き方は何か?こうした疑問をもつ若者は多かったはずです。
それもあってか、この時代には後に有名となる、「法然」、「親鸞」、「日蓮」そして「道元禅師」など多くの優秀な人々が輩出されております。
彼ら傑物は仏教の教えを純粋に見つめ直します。そして真の仏法とは何かを探求するのです。
そんな中当時権力をふるっていた顕密仏教は、当時まだ新興宗教としての色が強かった「禅宗」、「専修念仏」を弾圧しようとします。
専修念仏は「天魔」の教え、仏教の敵だとすら言われ、「法然」、「親鸞」らが流罪の刑に処される。時同じく、新興宗教の扱いであった「禅」を据えていた「道元禅師」も隠居を余儀なくされてしまうんですね。
しかし、それでも道元禅師は「真の仏法」を広める事を決してあきらめようとしませんでした。
そのような時代だからこそ、「真の仏法」を広めなければならないそういう思いをされていたのでしょうね。
比叡山での修行生活
「道元禅師」は正治2年(1200年)2月26日に、京都の一般在家のお家に生まれました。
父は「久我通具(こがみちとも)」です。
母については詳細は分かっておりませんが、摂関家の役職であった「藤原基房」の関係の女性ではないかとされています。
「道元禅師」は幼少期から大変頭が良く、聡明であったとされています。
4歳の時には中国の詩人「李嶠」の詩を読んでおり、7歳の時には「春秋」という解説書を読んでいたとされています。
そんな折に「道元禅師」は最愛の母を失います。
道元禅師が8歳のころです。この時の悲しみはとても深い物だったはずです。道元禅師はそこで世の無常さを悟られたのです。
「道元禅師」はその後「藤原基房」の養子となります。
「藤原基房」は「道元禅師」を役職に就かせようとしますが、「道元禅師」は既に「出家」を志していたんですね。幼くして両親を失った経験をされた道元禅師の求道心は凄まじいものでした。
そこで当時、全国にその名を轟かせていた「比叡山」にて修行の道を歩むことを決意します。
当時の比叡山は仏教の総合大学でありました。非常に優秀な人物が一堂に会し、法然上人や親鸞聖人、栄西禅師、日蓮上人など仏教の礎を築く教祖方がこの「比叡山」で「仏教」のいろはを学ばれたんですね。
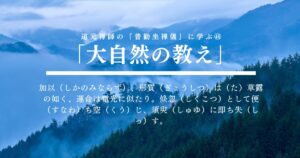
「道元禅師」も比叡山で、13歳から18歳までの6年間修行をしました。
道元禅師が抱いた疑問

しかし、「道元禅師」が比叡山での修行中にみたものは、戒律を守らない僧侶たち、そして名声を得る事や、高い地位に就く事ばかりを願って修行している者達でした。
「道元禅師」は次第にそういった僧侶たちの姿に疑問を覚えるようになりました。「道元禅師」の求める「仏法」の姿がそこにはなかったんですね。
幼い頃から中国の高僧の伝記を記した「高僧伝」を読んでおり、僧侶としての名誉を求める生き方は本当の僧侶の生き方ではなく、むしろ名誉や利益を求める心を捨てて生きる道が、僧侶としてのほんものの生き方であることを知っていたのも関係していたことでしょう。
そんな思いは次第に中国(宋)の禅の高僧へと向けられることになるんですね。
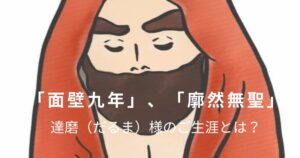
そして丁度この頃、冒頭でもお伝えした、「本来本仏性、天然自性身」(人間はほんらい、仏の心を持ち、生まれながらにし仏の身体を持っている。)という教えに疑問を持つようになるのです。
つまり、「ほんらい仏であるならば、何故仏であることを願い、厳しい修行を積む必要があるのだろうか。」という疑問を持つようになるんですね。
この疑問は道元禅師だけでなく、われわれ一般人にとっても解決しなければならない人生最大の問題と言えるでしょう。
ところが、その問題に答えられる指導者は当時の比叡山には一人もいなかったんですね。
そこで「道元禅師」は中国に二度渡って禅を学んできたという建仁寺の「栄西禅師」を訪ねます。
しかし「栄西禅師」は晩年にさしかかり、会う事が出来ませんでした。
なのでその弟子の「明全和尚」に会うんですね。
「明全和尚」は栄西禅師が認める優れた弟子で、「道元禅師」はこの「明全和尚」のもとで「禅」の教えを学ぶことになります。
そしてこの「明全和尚」も、この道元禅師と共に中国へと渡って「禅」を学びたいという思いを抱くようになるのです。
そうした中「中国留学」が実現します。貞応2年(1223年)の春、「道元禅師」が24歳の時の事でした。
道元禅師の生涯をかえる様々な出会い
その年4月の初旬に中国に到着された道元禅師ご一行。
その中国に到着した折に、「道元禅師」は一人の中国僧と出会います。
道元禅師を乗せた船は、入国審査の関係で停泊を余儀なくされます。
その折に、60歳程の禅僧が「椎茸」を求めてその船にやってきます。
この僧は中国の「阿育王山」という修行道場の「典座」(食料の調達、調理、給仕まですべてを司る責任者の事)であり、食材の材料を求めに来ていたんですね。
この「典座」は買い物を終えたらすぐに、帰るということでしたが、色々話したい事があった「道元禅師」はこの典座を引き留めて接待しようとしました。
しかし典座は、典座という役職の大切さを説き帰っていきました。「道元禅師」はこの典座から「修行」とは坐禅をしたり、教本を読んだりすることだけでなく、日常生活のあらゆる事が大切な修行であるという事を教えられたのです。
「道元禅師」は中国で、こうした貴重な出会いをいくつもされるんですね。
例えばこれも後に「道元禅師」がご修行をされる「天童山景徳寺」での出来事のお話です。
「道元禅師」はある年老いた「典座」が仏殿の中庭で海草を干しているのを見つけました。
その典座は手に竹杖を持ち、炎天下のもと、笠もかぶらずに海草を干していたんですね。
その姿があまりにも辛そうで、「道元禅師」は「何故その仕事を、仕様人に頼まないのですか?」と尋ねるんです。
するとこの老典座は「他人がやったのでは私の修行にはなりません」と返答します。
再度、「道元禅師」が「何故、日中の暑い時間にやるのですか。」と尋ねると、すぐさま「今やらないで、いつやる時がありますか。」という返答がかえってきたのです。
「道元禅師」はこの老典座から自分でやらなければ自分の修行にならない事、またいつかやろうと思っていたら結局出来る物ではないという事を教わることができたんです。
また、ある時「道元禅師」が古人の語録を読んでいると、四川省出身の修行僧に「語録を見て、何の役に立つのですか。」と質問をされるんですね。
「道元禅師」は「国に帰って、人を導くため、沢山の人に利益を与えるため」などと答えましたが、「結局の所、それが何の役に立つのですか。」と問い詰められて答える事が出来なかったといいます。
つまりこの僧から自分自身で教えを実践し、体験し、体得することの大切さを教わるのです。
このようなことで「道元禅師」は語録を読むことを控えるようになり、坐禅の修行に専念するようになるのです。
こうした出会いが道元禅師をどんどん変えていくんですね。
真実の道に引き寄せられていくのです。
如浄禅師との出会い
正師(本物の師)を求める旅も続いていました。
ある日、「老璡」(ろうしん)という僧に出会い、「如浄禅師」に会う事を勧められるんですね。
そして実際に会おうと「天童山」に赴くわけですが、「天童如浄禅師」、この人こそ「道元禅師」が求めていた「正師」でありました。
この「天童山」では「如浄禅師」による坐禅修行を中心とした厳格な指導が行われておりました。
「如浄禅師」は、当時の中国で勢力のあった宗風をくみ取って、独自の宗風を振るっておりましたが、その説法の様子は、厳しく激しく、豪快、破天荒なものであったと言われております。
そんな「如浄禅師」のもとには多くの修行者が入門を求めて訪れておりましたが、「如浄禅師」はそう簡単に入門を許しませんでした。
しかし「道元禅師」が天童山に戻った時、なぜか一目見ただけで「如浄禅師」は入門を許したと言われております。
「道元禅師」の仏道を求める並々ならぬ心の真実を見てとれたからでしょう。
こうして「道元禅師」は天童山において以前にもまして厳しい修行の日々を送ることになります。
「如浄禅師」は常日頃から、「専念すべき修行は坐禅である、坐禅こそが悟りである。焼香、礼拝、念仏、看経をせず、ただ打坐(坐禅すること)すればよいのだ。」と指導しておりました。

一般的に「悟り」とは修行の「結果」として得る物であるとされています。
つまり修行を積んだ、その先に「悟り」があるという考え方が一般的な「悟り」に対する考え方です。
「道元禅師」もそれまではそのように考えていたかもしれません。
しかし「如浄禅師」の捉え方は違っていたんですね。
「坐禅は身心脱落である。」つまり、「坐禅」という修行こそが身心脱落、即ち「悟り」に他ならないというのです。
当時の「道元禅師」にとってこれはまだ理解し難い言葉だったことでしょう。
しかし「道元禅師」はその言葉を信じ、ただ只管(ひたすら)に坐りました。
そしてある日の早朝の「坐禅」。
「如浄禅師」が修行僧が眠っているのを見て、叱りつけるんですね。
「坐禅は身心脱落でなければならない!」その言葉を聞いて、「道元禅師」は「身心脱落」(悟りをひらくこと)したといいます。
如浄禅師の願い
宝慶3年(1227年)に、既に「道元禅師」は「如浄禅師」の認める後継者の一人になっており、「如浄禅師」の側に仕えておりました。
この頃「如浄禅師」はかなり老衰し、余命がいくらも残されてなかったとされております。
しかし、「如浄禅師」の勧めで「道元禅師」は帰国を決意します。
「如浄禅師」の死を看取ってから帰国する事も出来たし、「道元禅師」もそれを望んでいたと思いますが、「如浄禅師」は一日も早い帰国をすすめました。
「道元よ、早く日本に帰り、正しい仏法を広めるのだ。」これが真の師の言葉であり、仏祖方の思いでありました。
「道元禅師」はそのような師の思い、仏祖方の願いを知って帰国を決意したのです。
それから間もなく「如浄禅師」は遷化(僧侶が亡くなること)されました。
安貞元年(1227年)、「道元禅師」28歳の時です。
妥協なき布教
道元禅師は中国から帰国後まもなく『普勧坐禅儀』を著します。
この『普勧坐禅儀』では、「如浄禅師」より教えられた正しい「坐禅」の意義を説き明かすとともに、具体的な作法を示して、あまねく人々に坐禅を行う事の意義を説かれました。
禅師がすすめる坐禅の大きな特徴は、「習禅」(悟りを目的とした手段としての坐禅)ではなく、「坐禅」こそが「悟りそのもの」とする、「安楽の法門」としての坐禅です。
当時「坐禅」というと、一般的には、悟りを得ることを目的とした修行であり、言い換えれば「悟りを得る一つの方法」くらいにしか思われておりませんでした。
「道元禅師」は「坐禅」をすすめるにあたって、人々に根付くそのような「誤解」を正さなければなりませんでした。
前述しましたが、「坐禅」は悟りを得る為の手段ではなく、「お悟り」そのものであり、「仏の行」でもあったわけです。
しかし正しい仏法を国中に広めたいとの強い願いをもった「道元禅師」でしたが、このようなことは当時の人からは受け入れがたく、布教は簡単な事ではありませんでした。
また当時の仏教界は弾圧が激しく、かつて「栄西禅師」は純粋な禅の教えを日本に広めようと志しながら、仏教界との衝突を避けて天台や真言の教えの布教もかね備えた道場を開いたという経緯もありました。
なので「道元禅師」にとって、禅の流れをくむ「正伝の仏法」の布教は非常に困難であり、縁ある所に身を寄せなければならなかったのです。
興聖寺を開く
そのような経緯で、定まった布教拠点のなかった「道元禅師」でありました。
それでも真の仏法を語る「道元禅師」の名声は日をおうごとに高まっていくんですね。
在家の信者も次第に増えてついに、中国から帰国した6年の歳月を経て、天福元年(1233年)、京都の深草に「興聖寺」を開くことになりました。
この頃から、「道元禅師」の代表作となる「正法眼蔵」の撰述も始まります。
また「興聖寺」を開いた翌年には後に「道元禅師」のあとを嗣ぐ「懐奘」が入門します。
「懐奘」は「道元禅師」と時間を共にしていくのですが、「道元禅師」の教えが真実の仏法であると信じ、「道元禅師」の一番弟子となります。
そして、修行僧をたばねるリーダーになるんですね。
その後、「道元禅師」の名声はますます上がり、多くの僧侶や一般の信者が集まるようになりました。
この頃、道元門下の修行僧は50人を超えて、一般信者は2000人を超えていたと言われております。
比叡山の圧迫と人々の支え
「道元禅師」は「興聖寺」を得たので、いよいよ「真の仏法」を世に打ち出す好機を迎えておりました。
しかし、ここでも比叡山から強い圧迫を受けてしまうんですね。
比叡山は、自らのより所である天台宗のほかに、新しい宗旨や信仰の興る事を警戒し、すでに念仏宗の布教を停止させてしまいました。建久5年(1194年)には、「大日能忍」の達磨宗や、「栄西禅師」の禅宗の停止を朝廷に願いでます。
その結果、達磨宗の「能忍禅師」は日本にいられなくなり、今の奈良県に逃れますが、その後無念の死を遂げてしまいます。
「道元禅師」や「興聖寺」も例外ではありませんでした。比叡山の度重なる圧迫が続けられたのです。
こんなことをしている場合ではない。とにかく弾圧を避け、仏法を伝えなければ。そのための道場を確保しなければ。
そんな中ある時、「道元禅師」は京都の武士であり、檀家さんでもあった「波多野義重」の家へ赴いて説法をする機会があったんですね。
そこで「波多野義重」を始め、武士たちは「道元禅師」の説法を難しいと思いながらも、心に響くものを感じておりました。
常に「生と死」のはざまにいた武士たちにとって、神仏の加護、あるいは魂の拠り所が必要であったのでしょう。
「道元禅師」は間違いなく、彼ら武士たちの心の拠り所となっておりました。
彼らはそのような「道元禅師」を支え、道元門下を助けようとしてくれたのでした。
永平寺の誕生
比叡山の圧迫が激しさを増した寛元元年(1243年)、「道元禅師」の身にも危険が迫っていました。
そのような状況を見て、「波多野義重」は、自領地であった「越前」(福井県)への移住をすすめるんですね。
そして「道元禅師」はこのすすめに便乗するんですね。
「道元禅師」の脳裏には、決して権力に近づくことなく、深山幽谷でひたすら修行しなさいという「如浄禅師」の教えがあったに違いありません。
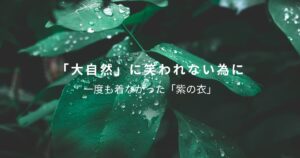
「道元禅師」はそれまで拠点としていた深草の「興聖寺」を弟子たちに任せて、「越前」に移りました。
「道元禅師」が44歳の時でした。
そして越前に移った「道元禅師」の僧団は、「波多野義重」の協力もあって、次第に修行道場の伽藍(禅道場の建物)を整えていきました。
この間も「道元禅師」は「正法眼蔵」の撰述を続けながら、同時に「道元禅師」が修行された中国の「天童山景徳寺」をモデルとした本格的な禅道場の建立に準備を進めます。
そしてついに寛元2年(1244年)に「大仏寺」(現永平寺)が誕生します。
その後、寛元4年(1246年)6月、「大仏寺」を「永平寺」と改称しました。
ここに名実ともに、正伝の仏法を実践できる礎が築かれ、僧団が確立しました。
道元禅師と永平寺との日々
それからというもの、永平寺ではとても厳格な仏道修行が日々行われておりました。
「道元禅師」は日常生活におけるすべての行いが修行であり、その修行は悟りを開くための手段ではなく、悟りそのものであると説きました。
まさに一瞬一瞬を大切に、真剣に生きる修行が続いておりました。
「道元禅師」はたとえ、一人でも半人でもよいから自分が中国から伝えた正しい教えを継承する真の弟子の養成を考え、力を尽くしました。
どの世界でもそうですが、いくら大勢の弟子がいようと、自分と同等の優れた後継者を育て上げる事が出来なければ、その道はすたれていきます。反対に、たった一人でも、自分の全てを受け継ぐ後継者がいれば、道は確実に保たれていきます。
弟子にとっては正しい師匠を選ぶことが大切ですが、それ以上に師匠が本物の弟子を育て上げる事が大切なのです。
本物の弟子を得たとき、師匠は「これでわしも死ねる。」と言えるのです。
真剣に師を求める弟子と、本物の弟子を育てようとする師匠、その二人の出会いによって仏教は代々伝わってきました。
「道元禅師」は永平寺から離れることなく、弟子たちに教えを説き、共に修行しました。
「道元禅師」にとって最も幸せな時期であったと思われます。
晩年

建長5年(1253年)、「道元禅師」の身体は、弟子たちへの熱心な説法や厳しい修行の中で、しだいに衰弱し、病魔におかされていきます。
この年の夏、病状はさらに悪化し、弟子の「懐奘」は看病の日々を送っておりましたが、「道元禅師」の病はその後も回復する兆しはなく、半月ほどの月日が流れました。
京都の「波多野義重」からは病気療養のためにぜひ上洛していただきたいという再三の要請もあり、「道元禅師」は「義介」に永平寺の留守を任せて、「懐奘」とともに上洛する事を決意します。
京都は「道元禅師」の生まれた故郷でもあります。
しかしこの旅路は恐らく辛い旅路であったであろうと思われます。
「釈尊」も自身の死期を悟った後に、生まれ故郷に向かって旅をします。
弟子の「阿難」に支えられての苦しい旅の様子が「大般涅槃経」に記されていますが、ある時は足の痛みを訴え、またある時はのどの渇きを訴えながら、故郷を目指しました。
しかし、その途中の、クシナガラでご入滅されます。
この「釈尊」の最後の旅路と、「道元禅師」の京都への旅が一つに重なるように思われます。
永平寺を決して離れまいと言った「道元禅師」が死期を悟って京都へ旅立ったのは、「釈尊」を慕っての事だったのでしょうか。
京都では、俗弟子の「覚念」の家に滞在し、療養しました。
8月15日の中秋には、次のような句を詠んでいます。
また見んと おもいしときの 秋だにも 今宵の月に ねられやはする
嗚呼、また見たいものだと思っていたこの中秋の名月を、こうしてまた見ることができた。ありがたいことだ。こうして今宵の月を、いつまでも眺めていたくて今日は寝られそうもない。
しかし、弟子たちの願いもむなしく、建長5年(1253年)8月26日、「道元禅師」は示寂(亡くなること)されます。
54歳という年齢でした。
次の「偈」は道元禅師が亡くなる寸前に残されたものです。
五十四年、第一天を照らす。この勃跳を打して、大千を触波す。ああ 渾身もとむることなく、活きながら黄泉に陥つ。
五十四年の間、ひたすら第一天を照らし、ひとすじの仏法を求め、、飛び跳ねて宇宙の果てまで駆け巡り、正伝の仏法と巡り合った。ああ、いきながら黄泉におちようとも、もう何ももとめる事はない。
「道元禅師」亡きあと、「懐奘」は永平寺を受け継ぎ、「道元禅師」の書き残した教えなどを整理し、書写、編集して正伝の仏法を後世に伝える事に力を尽くしました。
「義介」は「懐奘」の後の永平寺を継ぎ、その興隆に努めました。
その「義介」は中国へ渡り、中国の叢林の様子を視察し、これを日本に持ち帰って、永平寺を復興しました。その後今の曹洞宗教団を作り上げるに至った「瑩山禅師」を育てました。
この「瑩山禅師」によって「道元禅師」の思いは見事に花開くことになったのです。
道元禅師の生涯 まとめ
以上、「道元禅師のご生涯」をお伝えしてきました。
当時1つの大きな疑問を抱き、中国へと渡った道元青年。
その中国では様々な体験をし、実際に正伝の仏法を手にしております。正しい師匠とも出会い、その師匠からも認可を受けております。
しかしそんな中国での経験を経たのち、日本へ帰る際は「空手」だったのです。
「真実」はこの「空手」だと言うんですね。
生きるとは何か?真実とは何か?
我々にとってはここを解き明かすことが人生における最大の目的です。そしてそれを元に生き続けていくことが、我々にとっての正しい生き方であり、救いなのです。成仏なのです。
道元禅師がおつたえになられた「坐禅」。また中国から帰国する際は「空手」で、「眼横鼻直」なるものを説かれました。
それは我々は常に真実の命に生き、真実の世界に身を置いているということです。誰もが優劣のない生き方、死に方ができるということだったのです。
道元禅師の教えがいかに重大なものか、これから共に参究していきましょう。


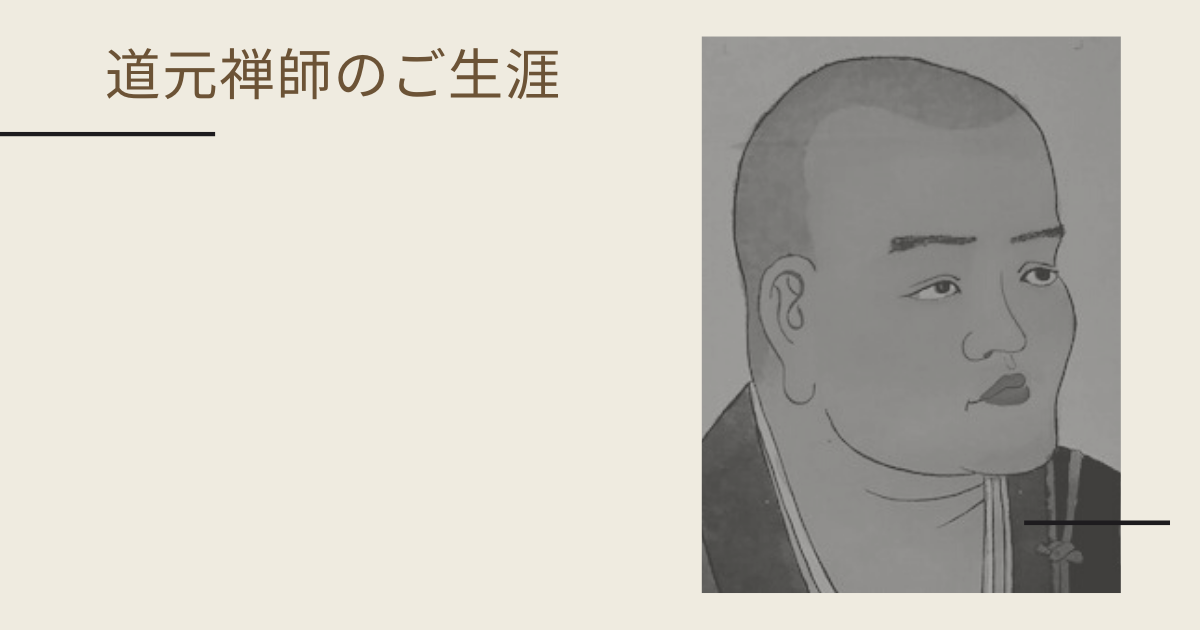


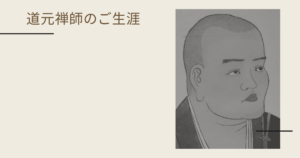
コメント