本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、前回の
という部分の復習から入っていきます。のちに新しい部分に触れます。
今回も前回と同じ内容が多くなりますが、この部分は重要な部分となりますので懲りずにお付き合いください。
それではまず初めに前回の、
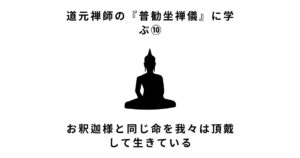
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「祇園」とはお釈迦様の事を指す。
- お釈迦様を始め、我々人間はこの仏の体をもってして生まれながらに悟っている。
- お釈迦様の生涯を参考にはしてほしいいが、自分たちも何一つ無駄にならない一瞬一瞬を生きている。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。
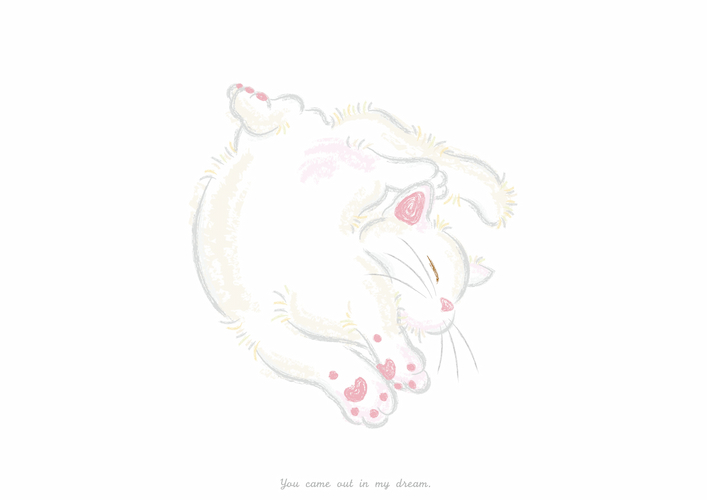
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。矧(いわ)んや彼(か)の祇薗(ぎおん)の生知(しょうち)たる、端坐六年の蹤跡(しょうせき)見つべし。少林の心印を伝(つた)ふる、面壁九歳(めんぺきくさい)の声名(しょうみょう)、尚ほ聞こゆ。古聖(こしょう)、既に然り。今人(こんじん)盍(なん)ぞ辦ぜざる。所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。
お釈迦様の歩まれた道をきちんと見なさい
今回は前回と同様、
という部分を解説していきます。
何故今回も前回と同じ内容に触れるのかというと、仏教をお開きになったお釈迦様の生涯に関する内容だからですね。
重要な部分となりますので、念入りに行いたいと思います。
まず「彼の祇園の生知たる、」という部分。
「祇園」というのは、「祇樹給孤独園精舎」の略字でありますね。
「祇陀(ギダ)王子」と「給孤独長者(きゅうこどくちょうじゃ)」、この二人の力添えもあり、この「祇園」という僧園を寄付してもらうことができたお釈迦様。
そしてお釈迦様はこの「祇園」があったおかげで、晩年の間そこに住むことができたんですね。
晩年におけるお釈迦様は、その「祇園」にて「説法」をされ、「修行」をされ、「生活」をされました。
「仏教」の礎を築いた重要な場所だったわけです。
この「祇園」にお釈迦さまは滞在されたということで「祇園」といえば「お釈迦様」自体を指すのです。
そして、「端坐六年の蹤跡見つべし」というのは、そのお釈迦様の歩まれた道をちゃんと見なさいという事であったわけです。
他との兼ね合いに本当の安心はない
お釈迦様(ゴータマ・ブッダ)は皆さんもよく飯ご存知の通り、釈迦族の「浄飯王」と「摩耶夫人」。
このお二人のご夫婦の元でお生まれになった一人王子であります。
またお二人がだいぶ歳をとられてから生まれたのがこのお釈迦様です。
待望のご子息であったわけですね。
「浄飯王」も自分の後にこの国を治めてくれるであろうと、非常にこのお釈迦様に期待しておられたんですね。
なのでお釈迦様は何もしないでいてもいずれは「国王」になれたでしょう。
或いはインドで一番豊かな国土を持つ釈迦族の「土地」も、「富」も、「美しい女性達」も何なりと手に入るはずでした。
そういう存在でありながらもお釈迦様は全てを手放し、出家をされてしまうんですね。
同じく道元禅師もまた、当時貴族の名門でもあった「久我家」の跡取りとして将来を期待されておりました。
しかしそんな道元禅師も14歳の時に「富」や「名声」を手放して「比叡山」に上られました。
両者とも、誰しもが羨ましがる「名声」や「富」が、自分の心が本当に安らぐ場所ではないという事を知っていたんです。
だから全てを手放し、家を出たんですね。
そしてそのお二人が命がけで実践された「坐禅」。
ということは「坐禅」をしたからといって名声を得られるとか、一儲けできるとか、根性が付くとか、そういうのは一切見当はずれだということがわかるんです。

「本当の安心」は、そのような社会における「他との兼ね合い」に生まれる物ではないということが予想できるわけです。
他との兼ね合いとは?
それでは今申し上げた「他との兼ね合い」とは何でしょうか。
例えば「国王」というのは「平民や家来」に対しての「国王」である為、それは他との兼ね合いです。
また「富」というのも「貧しさ」に対する「富」なので、これも他との兼ね合い。
詰まるところこのようなものは、概念だということです。その概念には形がありません。定義がありません。
概念は実際には手に取ることができないわけですね。頭の中だけに存在しており、人によってその捉え方が異なります。
そもそも実体がないので支えにならないんですね。人の支えにならないのです。
そのような他との兼ね合いに安らぎを求める事は、お釈迦様も道元禅師もやめてしまわれました。
そこで他との兼ね合いにではなく、
「自己」を生き切る世界
に安らぎを求められた訳ですね。
確かなものに安心を求められたのです。
他との兼ね合いというのは概念である上、相対的であるわけですね。
相対的であるということは、他にいつも振り回されてしまうということなんです。
これでは少しも安らぎがありません。いつまでたっても安らがないんです。
そしてそれを「世間」や「社会」と言うんですね。もしくはこの他との兼ね合いと言います。
例えば「私は10万円もしたこんな素晴らしいネックレスを持っているのよ!」と言っても、「100万円もするネックレスを持っている人」が、目の前に現れた途端に自分の持っていたネックレスがくすんで見えてしまう。
他との兼ね合いというのはこういうもので、実体がない。またそれはいつも他に評価を握られているようなものなんです。
しかし本来の我々の命には評価がないわけです。大自然に評価はないわけです。
足を組めば痛い。無条件に呼吸を繰り返す。無条件に排泄をする。無条件にカラスの鳴き声が聞こえる。
こうしたものに我々は支えられ、生きることができるわけです。
その私と大自然との関係性があって、我々は常に救われているわけです。私が私を常に救っているわけです。
こんなにもありがたい命をいただいている。それでいいわけです。
他に安らぎを求める事自体、本来お門違いの訳です。
だから、お釈迦様、道元禅師、このお二人に限らず過去の祖師方もみな他との兼ね合いに安らぎを求める事はやめてしまわれたんです。
自分に本当の安心を求められたんです。
それは出家者だからという事ではないですね。一般社会に生きる我々においてもそうであります。
皆同じ世界にいき、皆同じ人間だからです。
天上天下唯我独尊
お釈迦様はお生まれになった時に「天上天下唯我独尊」と言われました。
天上にもこの世において、我こそが最も尊いと言われたんですね。
「唯我独尊」
これは一見、非常に我がままな発言と捉えられます。
しかしこの「唯我独尊」の本来の意味はそうではありませんね。
先ほども言いましたが、我々の命というのは他との兼ね合いによって存在するものではありません。
本来の命、本来の自己というものには一切、階級がないわけなんですね。
そして他との兼ね合いがないから「天上天下唯我独尊」という訳ですね。
これは我々一人一人の命だけでなく、この世界の全てがそうですね。
どの壁を殴っても痛い。またどこにいても、どのカラスの鳴き声によっても自分の耳が震える。
この世界のどれもが「真実の命」のわけです。どこにいても、誰もが真実むき出しのわけです。
そのような世界、そもそもの大自然の在り方をこの「天上天下唯我独尊」というのです。
お釈迦様がお生まれになってすぐ、「天下唯我独尊」と述べられたのは、「大自然の在り方」を述べられたという風な解釈なんです。
ですから「生知」と言います。
生まれながらにその「大自然の在り方」、「真実」を知っているという意味の「生知」。
誰しもが他とは決して比べられないこの仏の体を生まれながらに持っている。
これが大自然の在り方なわけです。
みんながみんな「天下唯我独尊」なわけなんです。
なので決してお釈迦様だけが「天下唯我独尊」という訳ではなく、我々一人一人が「天下唯我独尊」として存在し、そして生まれながらの仏であるのです。
それに一番初めに気付かれたのがお釈迦様であったということですね。
オギャーオギャーと泣く、これこそ「天下唯我独尊」だったわけです。この世界の真実だったわけです。
そのお釈迦様によって提示された「真実の道」、つまりは「仏道」が代々伝えられて、今日まで伝えられました。
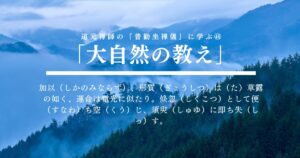
その間にも沢山の祖師方がこの「仏道」と真剣に向き合ってこられました。
例えばその中でも、有名な方として知られるのが、お釈迦様から数えて二十八代に「菩提達磨」という方です。
この達磨様は西天二十八祖、東土の初祖とも言われますが、元々インドにあった真実の仏法を中国へ初めて伝えた方ですね。
それで次回の『普勧坐禅儀』の、
という部分で、この達磨様のお話に繋がってくるわけです。
自己の尊さ
今回の『普勧坐禅儀』は、前回の復習がてらお釈迦様がお生まれになってすぐにおっしゃった
天上天下唯我独尊
という仏教において非常に有名なポイントを交えて解説をしてきました。
本記事のポイントは前回のポイントを踏まえ、以下のようになるかと思います。
- 「祇園」とはお釈迦様の事を指す。
- お釈迦様を始め、我々人間はこの仏の体をもってして生まれながらに悟っている。
- お釈迦様の生涯を参考にはしてほしいいが、自分たちも何一つ無駄にならない一瞬一瞬を生きている。
- 我々の命というのは他との兼ね合いによって存在するものではない
- 大自然の在り方を唱えたのが「天下唯我独尊」
さて今回取り上げた「天上天下唯我独尊」については諸説あり、様々な考察がされております。
果たしてお釈迦様は本当にこのような事を実際言われたのか、それとも後の人間によって作られたおとぎ話なのか今となっては誰にも知る由はありません。
しかしお釈迦様はそのご生涯を通して自分を傷つけるような苦行をやめ、他との兼ね合いに安心を求めず、自己こそ最も尊い存在であることを証明し続けてこられました。
是非今回の内容を踏まえて、自己の尊さ、この体、この命の尊さをかみしめて頂けたらと思います。
次回は再度『普勧坐禅儀』の内容に戻り、
という部分を読んでいきたいと思います。
お読み頂きありがとうございました。


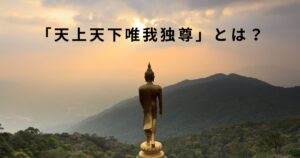
コメント