本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
まず初めに前回の、
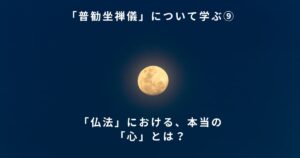
のポイントを振り返りたいと思います。
- ストーブの音やカラスの鳴き声が聞こえてくる。「聞いている対象」と「聞かれている対象」という分け方はなく、「仏法」においては全てが溶け合った、「ひとつなぎの命」である。
- 何故なら「ストーブの音がうるさい」、「壁を殴れば拳が痛い。」など世界で起こる事実は自分以外の物から出来ており、自分を生かしているのは自分以外の物だから。
- 「仏法」における「心」とは自分と自分以外が一つに繋がった「真実の在り方」の事を言う。
- しかし、仮にそのような仏法の入り口を少しだけ理解し、「真実」を求め、本当の「心」を理解する意気込みがあったとしても、「俺こそは」と有頂天になり、他に誇り、訴えようものなら、それは仏法の何も理解できておらず、失っている。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。矧(いわ)んや彼(か)の祇薗(ぎおん)の生知(しょうち)たる、端坐六年の蹤跡(しょうせき)見つべし。少林の心印を伝(つた)ふる、面壁九歳(めんぺきくさい)の声名(しょうみょう)、尚ほ聞こゆ。古聖(こしょう)、既に然り。今人(こんじん)盍(なん)ぞ辦ぜざる。所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。
お釈迦さまのことを「祇園」と呼ぶ

本日は、
という部分を読んでいきます。
まず、「彼の祇園の生知たる」という部分。
「祇園」についてですが、平家物語の冒頭にも、
祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理を知る。
とありますね。
誰もが一度は耳にしたことがある有名ものだと思います。
そして今回の「祇園」は、その際の「祇園精舎の鐘の音」の「祇園」のことを言っているんですね。
お釈迦様は晩年の二十年ばかりを、この「祇園精舎」という所で生活をしていたと言われておりますが、そこでの生活をしていたお釈迦様の事をこの「祇園」という言葉で表現しているんですね。
つまりお釈迦さまのことを言っているわけです。
少し余談になりますが、おしゃか様が何故「祇園」と呼ばれるようになったのかその経緯について少しお話させてください。
祇園の由来
昔、お釈迦さまがいた時代に「シッダ長者」という非常にお金持ちの資産家がいました。
その「シッダ長者」が、「今日は皆、家の者がソワソワしている。一体どうしたことか?」
と仕様人に尋ねるんですね。
すると仕様人が、

実は今日、インドで初めて真実に目覚めたと言われている若き青年僧、「釈迦牟尼仏」が大勢のお弟子さんを連れてこの街においでになるそうなんです!それで、その「釈迦牟尼仏」のお話を聞こうと思って、みんなで今からソワソワしているのです。
と答えます。
「シッダ長者」も、「そんなに素晴らしい人なら私もお話を聞きに行きたい!」というので「釈迦牟尼仏」のお話を聞きにでかけるんですね。
そして「釈迦牟尼仏」の話を聞きにいった「シッダ長者」もすっかりお釈迦様の「人柄」や「説法」の内容に魅せられてしまうのです。
そもそもこの「シッダ長者」自身も、「給孤独長者(きゅうこどくちょうじゃ)」と言われ、社会事業をされるほど立派な人物であったと言われております。
孤独な者に給するという意味で、「給孤独長者」。非常に立派な人だったんですね。
人に施すことに喜びを感じていた「シッダ長者」だったので、このお釈迦様の為にも、住むところを提供してあげたいと思うんですね。
そして相応しい場所はないかと、色々な所を探し求めるわけです。
そんな中、「祇陀(ギダ)王子」という太子が所有する場所が、この「お釈迦様」の僧団が修行するのに適した場所だと判断するんです。
なので「シッダ長者」が、「祇陀(ギダ)王子」に「どうか、譲ってくれないか?」と掛け合いに行くんですね。
しかし「祇陀(ギダ)王子」もその指定された場所を非常に気に入っていたので少しも譲ってくれないんです。
なんとか掛け合いに来たこの「シッダ長者」を諦めさせようと、「祇陀(ギダ)王子」は次のように言われます。
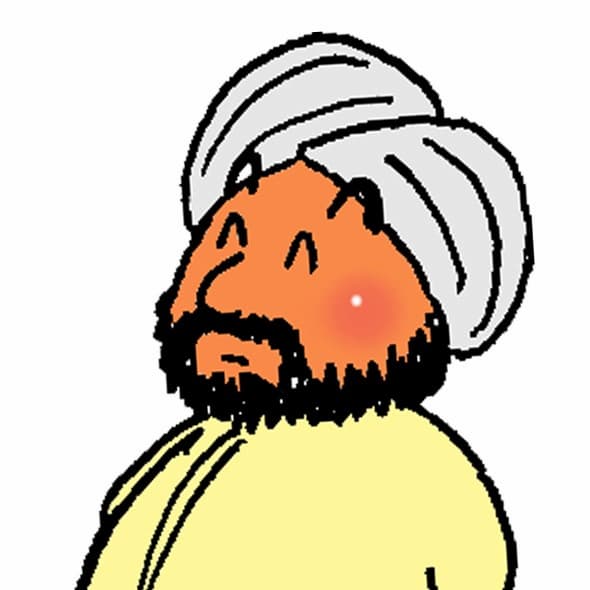
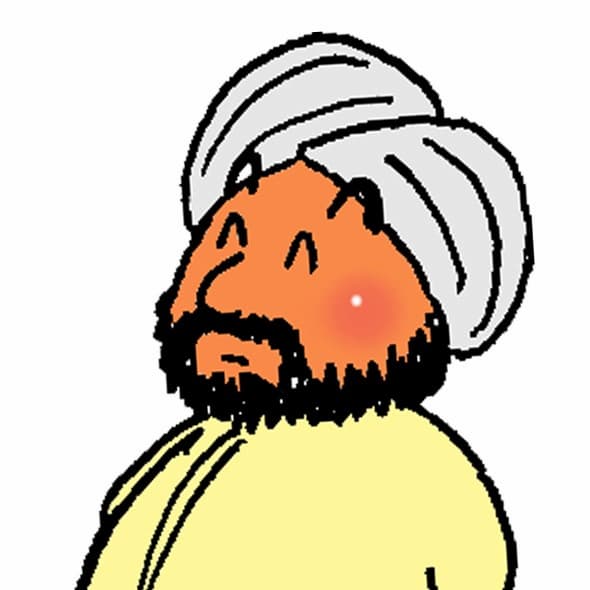
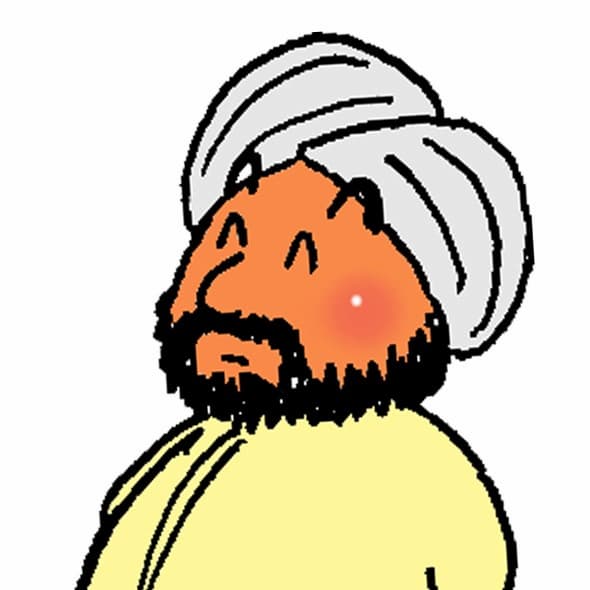
もしこの「ギダ林」を譲ってほしいのであれば、あなたの持っておられる黄金でこの「ギダ林」を埋め尽くしてください。それが出来ればあなたにこの「ギダ林」を譲ってあげましょう。
そこで「シッダ長者」は諦めるかと思いきや、「はい、わかりました。」と答え、次の日から「象」に自分の倉庫にある黄金を担がせて、「ギダ林」に黄金を敷き始めました。
それを見た「祇陀(ギダ)王子」はビックリしてしまいます。
「まさか、本当に・・・」という思いがあったのでしょう。
そして一体何故そこまでこの「ギダ林」に執着するのか?と「シッダ長者」に聞くんですね。
すると「シッダ長者」は、「いや実は、この世において初めて真実に目覚められたお釈迦様の為のお住まいを作ってお寄進をしようと思っているのですが、このギダ林がその場所に相応しいと考えたのです」と答えるんです。
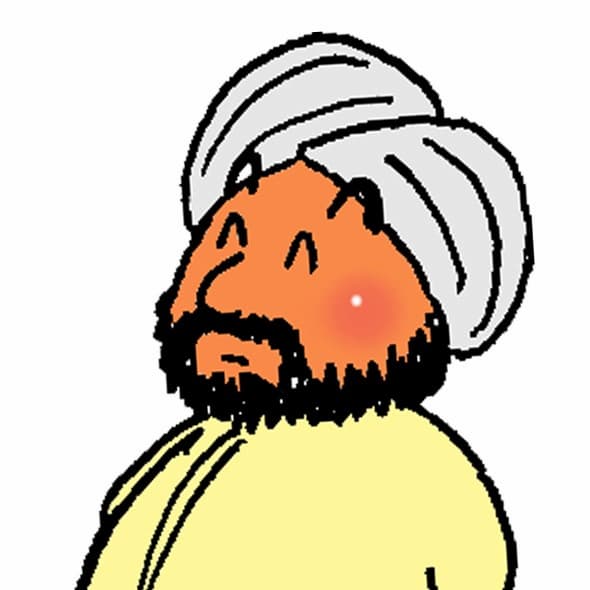
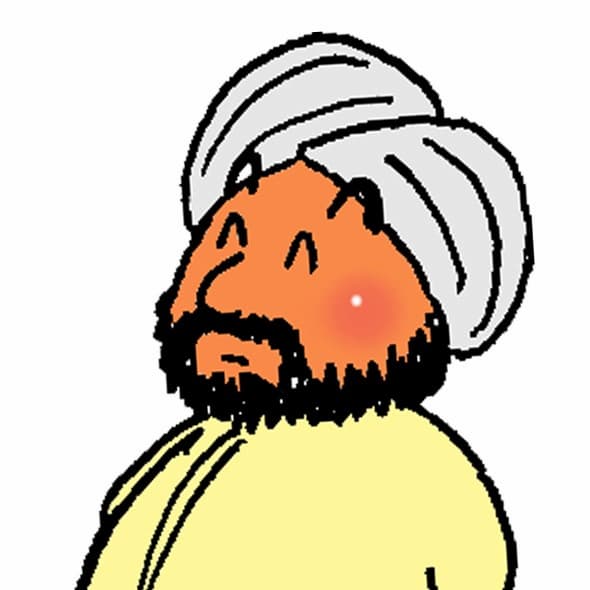
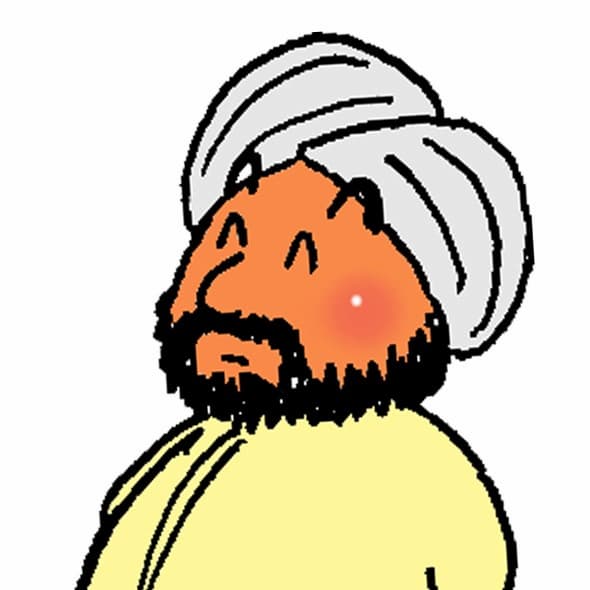
そんなに素晴らしい人物なのですか?
「それはそれは素晴らしい方です。」
それで「祇陀(ギダ)王子」も、せっかくだと言うのでお釈迦様の説法を聞きに行きにいくんですね。
そしてこの「祇陀(ギダ)王子」もお釈迦様の「人柄」、「説法」の内容に魅せられて参ってしまったのです。
そこで、
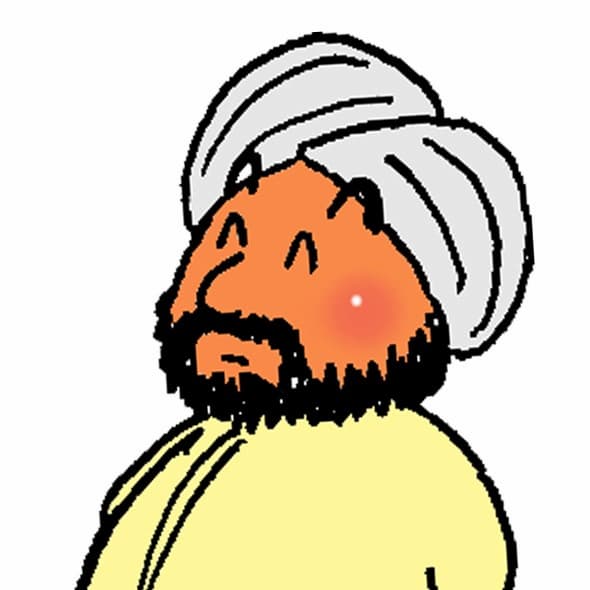
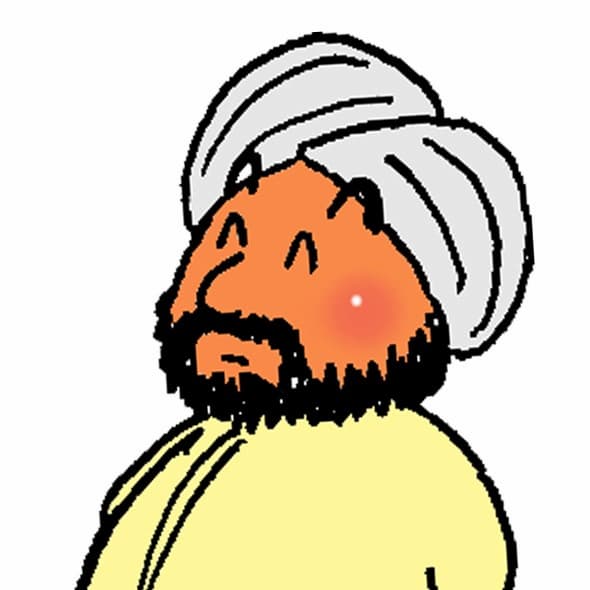
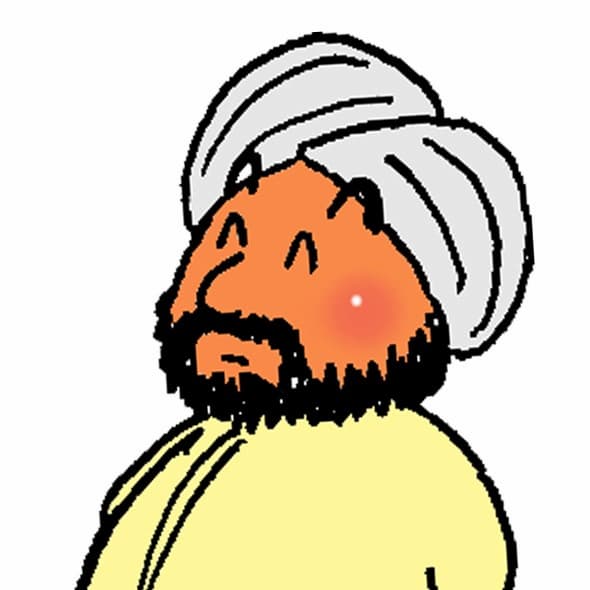
どうか私にも寄付させて頂きたい。私は「ギダ林」というこの林を寄付させて頂く。「シッダ長者」はどうか「家」を建てて、「寺」を建てて下さい。
といい、二人で力を合わせて「僧園」を作るんです。
この僧園のことをこの「祇園精舎」と言うんですね。
この「祇園精舎」は、この二人の「祇樹給孤独園精舎」という名称からとった略称とされております。
そしてその「祇園精舎」において、お釈迦様は晩年の二十年近くを過ごしたと言われており、「祇園」と言ったらお釈迦様の事を指すようになったというわけです。
お釈迦様へあてた敬意を表する言葉
そういった経緯がこの「祇園」にはあるんですね。
覚えておいて損はありません。
それでは今回の『普勧坐禅儀』に戻します。
「彼の祇園の生知」ですが、「生知」というのは、生まれながらに知っているという意味です。
「生まれながらに真実に目覚められている」、というので「生知」と言うんですね。
或いは生まれながらに知ると書いて「生知」。
お釈迦様は生まれながらにして「真実」に目覚めておられました。
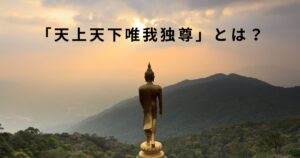
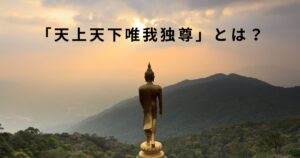
なので今回もお釈迦様の事を「祇園の生知」と言うわけです。
お釈迦様が12歳を迎えたとある冬の日に、ある通りを歩いてたらお百姓さんが畑で鍬を振るっていたんですね。
すると、冬眠していた虫が這い出てきた。
そしてその這い出てきた虫を今度は鳥がついばむ。
その一連の様子をご覧になって、お釈迦様は「無常」を感じられたと言われております。
普通の人間であれば、中々このようなことに気付けませんね。
お釈迦様は非常に感性豊かな方であったのだと予測されるわけです。
お釈迦さまは19歳で出家をされたあと、30歳で真実に目覚められました。
感性が非常に豊かで、生まれながらに真実に目覚められるような人物であったお釈迦様。
なので道元禅師もこのお釈迦様に敬意を込めて、「祇園の生知」という風にここで言う訳です。
生きていく過程で何一つ無駄にならない、だからこそその経緯に着目しなさい
お釈迦様は出家された後、初めに「苦行林」という山の中に入って、厳しい苦行にいそしんでおられました。
そこで6年間もの「苦行生活」をしておられたんですね。
毎日ゴマ「一粒」しか食事を取らなかったり、絶対に「横」にならなかったりなど非常に厳しい修行と言うよりはもはや「苦行」をしておったんです。
しかしこの「苦行」を一生懸命修行したとしても「真実」には目覚められないと気付かれるんですね。
そしてその「苦行林」を一人抜け出します。
すると最初からお釈迦様に付き従っていた一番弟子の「五比丘」達がこのお釈迦様の行為を痛烈に批判するんです。
そもそもこの五比丘はお釈迦さまの父である浄飯王(じょうぼんのう)が差し向けた付き人であったと言われています。
しかしその五人の付き人達はお釈迦様に対して、
折角出家しても、務まらないのか!
と言ってお釈迦様の行為に対して後ろ指を指すんですね。
それでもお釈迦様はその「苦行林」を一人抜け出すんです。
そこでひょんなことから「ニレンゼンガ」という所で沐浴をされます。


それまで「自分の体」はどうなってもいいと、無茶苦茶な「修行」をしておったお釈迦様。
しかし、「沐浴」をされて「我々のこの体」というものが非常に大切だという事が分かるんですね。
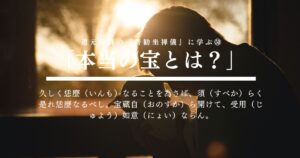
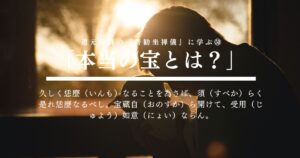
それまでは「自分の思い」で、この体なんてどうなってもいい、「体」なんて二の次、三の次にして「苦行」に邁進しておりました。
しかしそこで「沐浴」して初めて、この「生かされている体」ということに気付くことができたのです。
人が鍬をふるい、虫が出てくる、そしてその虫を鳥が啄む。全ての命のおこりは全体なのだと。つながっているのだと。私のこの体もその全体であると、全体と同一であると。自分のものではないと、そう気づかれるわけです。
それまで断食を繰り返した生活をしておりましたが、堰を切ったかのようにお腹が空いてしまい、村の娘「スジャータ」という人から乳粥のご供養を受けられて、体力を回復されます。
そして「ブッダガヤ」という地で三週間の「坐禅」をされ真実に目覚められたというのがお釈迦様の成道に至った経緯であります。
その経緯をよく見なさいというのが、「端坐六年の蹤跡(しょうせき)見つべし」ということなんですね。
そこで大切なものに気づくことができるからと。
またここでいう「六年」は一般的には悟る前の六年間という風に思われております。
しかしこのことに関して語るとき、「悟る前」、「悟った後」という区分はできません。
その前の「祇園の生知」にもありますが「生まれながらに真実に目覚められたお釈迦様」という解釈ですので、苦行から脱し沐浴をしたことで「悟った」という意味ではないのです。
つまり、生まれながらに悟っておられた訳です。悟っていたのはお釈迦さまではなく、この体が生まれながらに悟っていたということですね。
私が悟ったわけではないのです。そもそも私の体は悟っていた。その真実の体を常にいただいていたということに気づいたということです。
その「真実の体」があったからこそ、この六年にも及ぶ修行が出来た訳なんですね。断食も、呼吸も、排泄も、なんでもできたわけです。
これまで見て来た経緯があったから「悟った」というわけではなく、お釈迦様は元より我々も生まれながらに悟っているわけであるからして、「生きていく過程で何一つ無駄にならない、その生きる過程全てに着目しなさい」という意味でこの「端坐六年の蹤跡見つべし」という風に受け止めて頂けたらと思います。
まとめ
今回は、お釈迦様の生涯を参考に『普勧坐禅儀』の
という部分を解説してきました。
それでは最後に本記事のポイントをおさらいしておきましょう!
- 「祇園」とはお釈迦様の事を指す。
- お釈迦様を始め、我々人間はこの仏の体をもってして生まれながらに悟っている。
- お釈迦様の生涯を参考にはしてほしいいが、自分たちも何一つ無駄にならない一瞬一瞬を生きている。
以上お読みいただきありがとうございました。

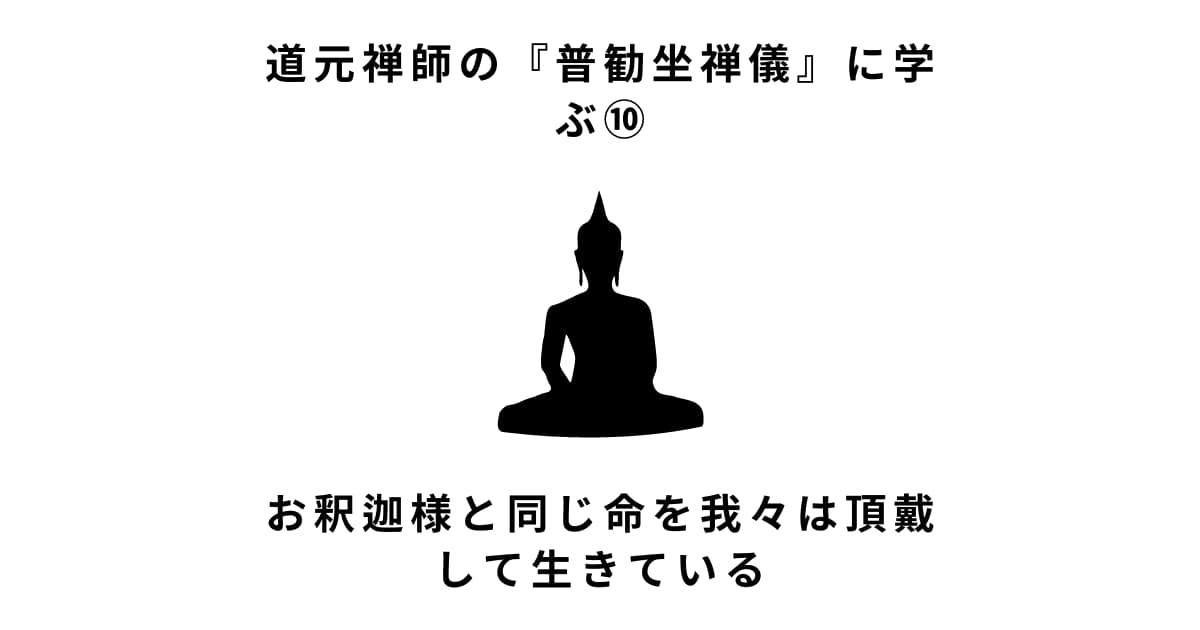
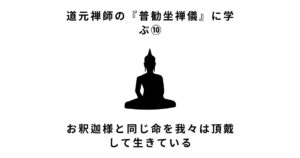
コメント