本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
まず初めに前回の、
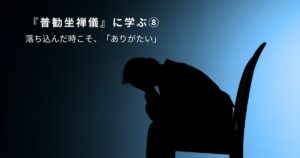
のポイントを振り返りたいと思います。
- 我々の命は今立ちどころに仏の命を生きている、またそれを証明しているのが「坐禅」
- しかし寸分の狂いで、行き着く場所は天と地をほど違ってしまうのが我々の行い、従って坐禅の意義も正しく捉えなければいけない。
- 「思う」という行為は自分がやっていることではない
- 海の量は一定なのだから、自分だけで大満足である。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。
誇る相手すらいない
今回は、
この部分を解説していきます。
少し長いですね。頑張りましょう。
またこの段は重要かつ少し難しい部分でもありますので、慎重に読み進めて参りたいと思います。
まず、
「直饒(たとい)」というのは、「仮にも」という意味ですね。
また、「会に誇り」の「会」というのは、「理解する」という事で、頭で考えて物を判断する事をこの「会に誇り」と言います。
「誇る」という事ですから、当然そこには「誇る」相手がいるわけですね。
相手がいない以上、何かを「誇る」ことができませんからね。
しかし本来、誇る「相手」というものはいないんですね。
この世界において、目の前に展開する全ては「自己」であり、全て「自分の命」でるからです。
目の前の一切が自己であるという、その理由については以下の記事よりご確認ください。

しかしこの「会に誇る」、「相手に誇る」という事は他を認めているという事で、それは正しい世界の捉えかたではなく、それはまやかしの人間の概念が作り出した比較の世界でしかありません。
なのでこの「直饒(たとい)、会(え)に誇り、」という部分に関しては、
仮に自分で理解して、その内容を他人に誇る
という意味になるのです。この「仮に」という部分が味噌です。
この詳細は後ほど解説します。
続いての、
「悟に豊かにして」という部分ですが「俺は悟った」といって他に誇っているような、自己満足をしている状態です。
次の「瞥地の智通を獲、」という部分。
「瞥地」というのはちらっと垣間見る事を「瞥地」と言います。
「智通」というのは「真実」のこと。
なので、
真実を垣間見る
という意味になります。
更に続いての、「道を得、心を明らめて」という部分。
「心」とここではありますが、これは「心」という普段我々もよく目にする、あの「心」ではありません。
「仏法」における「心」とは、我々が普段受け止める「心」とは少し違います。
自分を生かしているのは自分以外。命に線引きはない。
道元禅師は中国の「天童寺」、「如浄禅師」の元で真実に目覚められました。
どのように「真実」に目覚められたかというと、「身心脱落」したわけです。
「身心脱落」、つまり「身」と「心」が脱落したわけです。
それは「身」と「心」その二つの間に、分け隔てがなくなってしまったのです。そのことに気がついたのです。
我々は普段、この「脳みそ」を使って色々と物事を分析します。
例えば、「あぁ今、ストーブの音がしているな」、「カラスが鳴いているな。」、「目の前に柱があるな」とか。
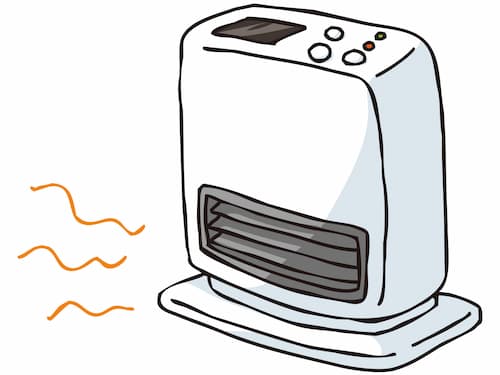
頭の中で、それを言葉として捉え、認識する。またその際、耳で聞いたり、目で見たりしてそう判断しております。
認識する「対象」があって、それに対して「うるさいな」とか「これは壁」だなとかって認識する訳ですね。
このように我々の感覚では、自分がする「認識」と、そしてその自分に「認識される対象がある」という風に我々は一般的に受け止めている訳です。
つまり「自分」と「世界」という物事を二つに切り離して物事を考えているんですね。
しかし我々が生きているという世界、そしてその世界の「事実」において、このように「認識するもの(自分)」と、「認識されるもの(ストーブ)という風に区別されるものは一つもありません。
例えばストーブの音が聞こえるというのは「ストーブによって我々に与えられた命の出来事」だからです。
要するにストーブによって、自分の命が発生したということはストーブが自分で、「我々の命」と「ストーブ」とは同じ命ということなのです。
その両者に境界線はないのです。
もし「我々の命」と「ストーブ」が本当に二つに分かれた存在なら、ストーブの音を「うるさい」と感じないはずだし、ストーブの暖かさも感じる事ができないはずです。
しかしそんなことはないですよね?
よって、ストーブそのものが我々の「感覚」と言えるのです。もしくは「命」そのものと言えるのです。
これが事実なんですね。世界のあり方なのです。物事は全て1つにつながっている。
あるいは「呼吸」もそうですね。
市外かもしくは県外か、はたまた国外か。どこからやってきたのかもわからない酸素を吸って我々は呼吸ができるんですから、その酸素も、その酸素を発している木々も我々の命と呼べるはずです。
それを「ここからここまでが俺の命」だと仮に呼べてしまうのなら、即座に我々は窒息死してしまうはずです。
しかし我々は概念を持ち合わせているので、認識という手段をよく使います。
そこでは「自分」と「ストーブ」、「自分」と「あなた」という風に物事を対象化し、区別して考える癖があります。
そして他人に嫉妬し、憎い、うらめしいと思う。
しかし事実はそうではないということなんですね。本来、全てが一繋ぎの「仏の命」だということなんです。
すべてが溶け合っているんです。私はあなたで、あなたは私なんです。
意識せずとも、カラスの「カーァ」という声が聞こえてくる。車の音「ブーン」という音が聞こえてくる。
そしてそれらが実際に耳を鳴らし、「うるさいな、」と感じられる。命を生んでいる。
「ストーブの音がうるさい」、「壁を殴れば拳が痛い。」、「椅子に小指をぶつければ痛い。」
「自分を生かしているのは自分以外」なんです。我々の「命」というものには「線引き」がないのです。
それによって、常に生かされている。救われている。救われないなんてことがない。
こんなにも尊い命を我々は普段生きているのです。全てが溶け合った紛れもない真実の世界を。
話を戻します。
「道を得、心を明らめて」。
この世界は全てが1つとして溶け合っている。それが真実であると。
私というのも全体であり、世界そのものであると。その私の心というのも全体であり、世界そのものであると。
つまりここで言う「心」とは、我々が普段したしんでいる「心」という意味合いではなく、「真実」という意味になります。
その「真実をあきらかにする」という意味です。
このストーブの事を「心」と言っても間違いではありません。全てが心、全てが私。全てがストーブなのです。
心とは?

昔、「如何なるかこれ心」という問いに対して、「障壁瓦礫(しょうへきがれき)」と答えた禅僧がいました。
その禅僧が言うには石ころや瓦礫が「心」だと言うんですね。
或いは道元禅師は「山河大地これ心なり。」とおっしゃっております。
「山」や「河」や目の前に展開している自然界が「心」であると。
「日月星辰」、「太陽」や「月」や「星」などが「心」であると言うんですね。
ここまでで紹介してきた「心」とは、我々が生まれてから長い事、何十年も培われ、概念固めされている、「心」とは違いますね。
我々が普段親しんでいる世界とは、考える主体(自分)があって、そしてその対象となる「ストーブ」や「石ころ」、「大自然」があります。
つまり世界がふたつに分かれてしまう、「概念」の世界のことですね。
そしてそういう世界においてこの「心」は単なる「概念遊び」の道具にしかならないわけです。
しかし本当の「心」はそうではありませんね。
本当の「心」とは先ほども言ったように物事が二つとして分かれない世界そのもの、他と自分が一つに重なり合った「真実」のことを指します。
例えば今単布団の上で「坐禅」を組むと、「自分」が「ストーブ」と一つであるという事が良く分かります。
「自分」が自動車の音、或いは「石ころ」だというのがよく分かるんですね。
「仏法」の場合は、「心」をこのように理解し、受け止める訳であります。
勿論「唯識学」という「心」についてしっかり定義付ける大乗仏教の学問もありますが、少なくとも道元禅師の文章の中で「心」と出てきたならこのような受け止め方をします。
なので、
というのは、
世界の「真実」を明らかに、「心」を明らかにする
という意味になるのです。
ここで一旦今の段は以上とします。
次の「衝天の志気を挙し」ですが、「衝天」とは上り詰めた世界ですね。
天の一番の頂き、つまり人間における気持ちが有頂天になっている状態のことです。
「衝天の志気」というのは、俺こそはとのぼせて、有頂天になる様子を言うんですね。
そして、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。について。
「入頭の辺量」とは、「ほんのわずかに仏法の入り口に立ったとしても」という意味です。
また「幾ど出身の活路を虧闕す。」とは、「全くと言っていいほど、仏法の自由自在なる方法を欠いている。」という意味になります。
すみません、最後はかなり駆け足で解説してきてしまいました。
ここで今回の、
の内容をまとめてみましょう。
以下の通りになります。
仮に自分で仏法の入り口を少しだけ理解し、「真実」を求め、本当の「心」を理解する意気込みがあったとしても、「俺こそは」と有頂天になり、他に誇り、訴えようものなら、それは仏法の何も理解できておらず、失っている。
要するに、
仮に「真実」について理解しようという気持ちがあっても、俺こそはという自我を立てて、そこで知識や、認識をもって仏法のするなら、本来の自己に出会うという事を失っている。または入り口で満足してしまっている。
という意味になります。
本当の「心」とは?
ここまで「心」だとか「真実」だとかと色々と解説してきました。
しかしそのような知識を得て満足してしまったら、それは単なる認識でしかなく、仏法をまるで理解できていないということなんです。
真実にむしろ反しているぞと、そう言われるわけですね。
私もそうですが、この記事を読んでいただいたあなたはおそらく、仏法における「真実」、あるいは「心」について多少は理解できたはずです。
しかし、そもそもそのように「仏法」や「真実」を認識で捉えてしまうようなら、それは本来の「真実」に出会えていないということなんですね。
「仏法の入り口にしか立てていないぞ!」という事なんです。
意地悪な話で申し訳ございません。
今回は『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- ストーブの音やカラスの鳴き声が聞こえてくる。「聞いている対象」と「聞かれている対象」という分け方はなく、「仏法」においては全てが溶け合った、「ひとつなぎの命」である。
- 何故なら「ストーブの音がうるさい」、「壁を殴れば拳が痛い。」など世界で起こる事実は自分以外の物から出来ており、自分を生かしているのは自分以外の物だから。
- 「仏法」における「心」とは自分と自分以外が一つに繋がった「真実の在り方」の事を言う。
- しかし、仮にそのような仏法の入り口を少しだけ理解し、「真実」を求め、本当の「心」を理解する意気込みがあったとしても、「俺こそは」と有頂天になり、他に誇り、訴えようものなら、それは仏法の何も理解できておらず、失っている。
以上お読みいただきありがとうございました。

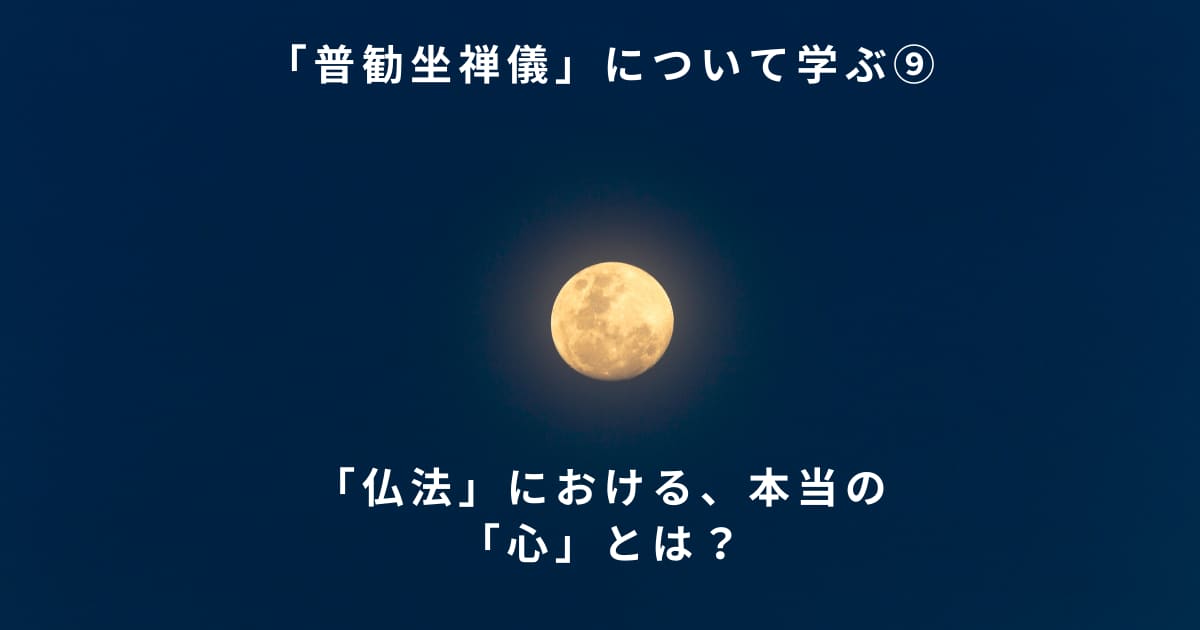
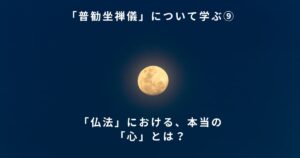
コメント
コメント一覧 (1件)
hurusuke様にただ感謝申し上げたく、コメント欄を活用させていただきます。
小生、66歳の男性です。
1ヶ月ほど間に「不思量底、思量、非思量」について検索している時にharusuke様のブログに出会い、それ以降ランダムに貴記事を拝読させていただいております。
深淵な“真理“を平易な言葉で簡潔に解説してくださっていて、小生のような“ボロ雑巾組の凡夫“にも理解できる解説に感謝申し上げる次第です。
今後とも「不思量底を思量する」を脳みそでではなく、一如なる心身で体得できるよう坐禅を行じ続けたいと思います。
ありがとうございます。