道元禅師の『普勧坐禅儀』は、在家の者、出家の者問わず普く人々に「坐禅」とは何か?その坐禅の「意義」と「作法」についておしるしになった「坐禅の奥義書」であります。
その『普勧坐禅儀』の一文で次のようなものがあります。
この一文はこの『普勧坐禅儀』において非常に大切な箇所であり、先人たちや現代の僧侶のバイブルとして古来より受け継がれてきました。
今回、恐れ多くもこの「不思量底」とは何か?を参究してまいりたいと思います。
以下の記事でも軽く今回の「不思量底」について触れておりますので宜しければご参考ください。
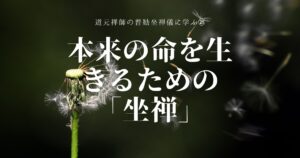
不思量底とは?
この「不思量底」とは何か?を参究するにあたって、昔のある逸話をご紹介したいと思います。
昔、中国に薬山惟儼(やくさん・いげん。七四五~八二八)禅師という方がおられました。
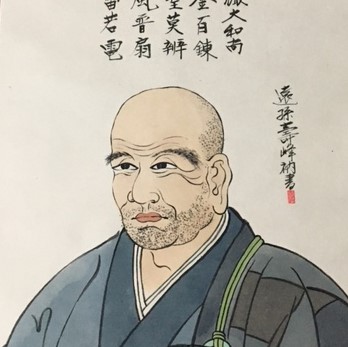
この薬山惟儼禅師は、山西省、新絳県(しんこうけん)の出身で、俗姓は韓(かん)氏と言います。
17歳の時に潮陽西山の慧照禅師によって出家しました。
そして29歳で衡岳(こうがく)寺の希操律師から具足戒を受け、石頭希遷禅師に参じた有名な禅僧です。
その薬山惟儼禅師が「坐禅」をしているある日、一人の修行僧が次のような質問をしました。

兀兀地何をか思量せん。
つまり、「そのように不動の姿勢で大地に腰を下ろし、坐禅をして一体何を思量するのですか?」と質問をします。
この時、この質問をした修行僧は薬山禅師が「何か考え事をしている」んだと思っていたのですね。
薬山禅師の不動ともいえるその坐禅中の姿を見て、何かを深く瞑想しているのではないかと思ったのかもしれません。
するとその質問を受けた薬山禅師は次のようにお答えになります。



箇の不思量底を思量す。
ここで今回の「不思量底」という言葉が出て参るわけですね。
この薬山禅師がお答えになった「箇の不思量底を思量す。」の意味を簡単に言えば、
思量しないところを思量するのだ。
となります。
いかにも「禅問答」らしい受け答えですね。
そう答えられた修行僧は続いて次のように質問を返します。



不思量底、如何が思量せん。
つまり、「思量しないところをどのように思量するのですか。」と。
まぁこの疑問は最もな事でありますよね。
私も同じ立場だったら同じように質問してしまうことでしょう。
その質問を受けた薬山禅師は次のように答えて言われました。



非思量。
つまり「非の思量である、思量に非ず」と答えられました。
そうしてこの問答は一件落着してしまうのです。
一体これはどのような問答であったのでしょうか。
「不思量底」の問答について分析
先ず、事の始まりは、坐禅をしておった薬山禅師に修行僧が質問をします。



兀兀地何をか思量せん。
一体何を思量しているのですか?もしくは何を瞑想してらっしゃるのですか?と。
弟子が師匠の修行観について知りたいと思うのは当然の事。
なのでこのように質問をするというのは良く理解できます。
すると質問を受けた薬山禅師が答えて言います。



箇の不思量底を思量す。
「この思量出来ない所を思量しているのだ。」と。
それではこの「思量できない所」というのはどういうことなのでしょうか?
それはつまり、
言葉では説明できないところ
という意味です。
勘の良い方なら既にお察しかと思いますが、「言葉では説明できないところ」という事をこうして私は今こうして「言葉によって説明」してしまっております。
なので本当の意味で「言葉で説明できないところを説明する」ためにはどうしたらよいでしょうか?
それが薬山禅師が実践されていた「坐禅」であり、生命の実践なのです。
そしてそれを薬山禅師は「不思量底」とおっしゃったわけです。
またこの「坐禅」に留まらず、我々の生きている姿、これを「不思量底」と言います。
例えば、
- 我々が物を考えている、これも不思量底である。
- 今日は幾分寒い、その寒暖を感じるのも不思量底である
- ストーブの音が聞こえてくるのも不思量底である。
- 雨音が聞こえてくるのも不思量底である。
- 前の物が見えるのも不思量底である。
- 寒ければくしゃみをするのも不思量底である。
このように生命活動には様々な表情があります。
そしてそれらはすべて「自分が行っている」ものではないでですね。
「大自然」によって行われているんです。
だから「不思量底」なんです。
「生命の実物」、これは「自分」でやっているものではない。だから「不思量底」というわけですね。
「坐禅」をくめば足が痛くなる。これはどうすることもできない大自然の行いですよね。
この「坐禅」に限らず、本来の我々の生活というのは誰一人例外なく、この「大自然」の恩恵にあやかっているんです。
ですからその「自分ではどうすることもできない」もの、あるいは「生命の実物」を実践することを「不思量底を思量す」と言う訳です。
この「坐禅」こそ「不思量底を思量す」と呼ぶに相応しいわけですが、薬山禅師がおっしゃりたかったのは特別なことでもなんでもないのです。



何も特別なことなんてないよ。本来の世界のありのままの真実を「不思量底を思量す」と表現しただけじゃ。
不生の仏心ですべてが調っている
その昔江戸中期頃、盤珪永琢(ばんけいようたく)禅師(元和八年〜元禄六年、1622 – 1693)という方がおりました。
この盤珪禅師は臨済宗の名僧で、網干(あぼし)に盤珪禅師ありと全国に名を馳せた非常に有名な僧侶です。
この人は何を質問されても「不生の仏心ですべてが調っている」とお答えになって解決してしまいました。
どんな質問を受けても、



不生の仏心ですべてが調っている
と回答し、解決してしまうのです。
この「不生の仏心ですべてが調っている」というのも先ほどの「不思量底」と同じことですね。
言い方を変えれば「何も解決などしない」ということで「何の問題もそもそも起きていない」という風にも捉えられます。
生命の実物、自然界には何の問題もそもそもなく、解決しなければならないものなど何もないという事です。



例えば雀が鳴けばチュンと聞こえるし、カラスが鳴けばカーと聞こえるじゃないか。そのように本来の世界には解決しなければならない事など何もないし、行き詰まりなど何一つないのである。それを不生の仏心と言うのじゃ。
この盤珪禅師はそのような事で、何を質問されても「不生の仏心で調っている」と回答していたというのです。
どんな事を質問されても「不生の仏心で調っている」。
どんな事があっても「不思量底」。
生命の実物には何の生き詰まりもなく、言い得る事が何もできないということです。
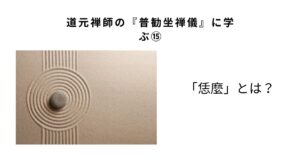
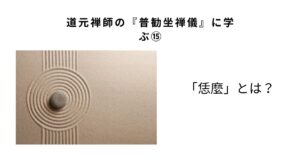
生命の実物を「不思量底」と言うのなら、大自然の在り方も「不思量底」と言えます。もしくは生きている姿を「不思量底」と言うこともできるはずです。
「不思量底を思量す」とは「一秒も休まず、命を実践していること」
道元禅師の有名な詩歌に、
「春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さへて涼しかりけり。」
というものがあります。
非常に有名な歌で、誰しもが一度は耳にしたことがあるでしょう。
しかしそんな世代を超え沢山の人から共感を得られているこの歌ですが、単に「大自然の姿」をお詠みになっただけです。
ありのままの姿を詠んだだけにもかかわらず何故ここまで多くの人の心に響くのでしょうか?
大自然の在り方には人間の考える「大きい」も「小さい」もありません。
「美しい」、「汚い」もありません。
この大自然の本来の姿を言い得るとしたら「不思量底」もしくは「不生の仏心」にしかとどまらないんです。
同じように我々の普段のこの命も大自然の姿であります。この「坐禅」も大自然の姿であります。
- ゲンコツもらえば痛い!これも不思量底であります。
- 熱い物に触ればアチッ!となる、これも不思量底であります。
- 腹が減ればなんか食べたくなる、これも不思量底であります。
- 坐禅をしていると次から次へと色々な思いが浮かんでくる、これも不思量底であります。
全て「不生の仏心で調い」、「不思量底」で言い表すことができます。
これら全ては、大自然の四季折々の風景と全く同じであります。
「春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さへて涼しかりけり。」
我々の命も道元禅師のこの詩に出てくる大自然となんら変わらないのです。
春になれば花が咲くように我々も不思量底を思量しております。
薬山禅師は、「坐禅」のことを



箇の不思量底を思量す。
とおっしゃいました。
「不思量底を思量する」というのは、
春になれば花が咲く大自然の在り方と同じような我々の様々な命の風景
であるということが言えるのです。
つまり、
- 聞こうとしなくても耳に自然と音が聞こえてくる
- 頭に自然に思いが浮かんでくる
- 心臓が自然に拍動する
- 寝ている間にも呼吸をし、食べ物を消化してくれている
これらも全て大自然の様相であり、不思量底を思量している姿であります。
すべてが「不思量底を思量している姿」なのです。
さきほどの問答に戻りますが、薬山禅師は、



箇の不思量底を思量す。
と、修行僧にお答えになりました。
この時、何故「坐禅」のことをこのようにお答えになったか、その訳は「一秒と休まずこの体は様々な命の風景を実践してくれている」という事を修行僧にお伝えになりたかったからです。
つまり一秒も休まず「不思量底を思量している」。
つまり一秒も休まず「坐禅」をしている。
もしくは、一秒とも漏れず我々は真実の命を生きている。
しかしこの修行僧は「箇の不思量底を思量す」という薬山禅師の答えがあまりよく理解できなかったのでしょう。
そして再度薬山禅師に質問をします。



不思量底如何が思量せん。
どのようにしたら不思量底を思量する事などできるのですか?と質問をするわけですね。



「不思量底を思量す」とはつまり何も考えちゃいかんということですよね?しかし何も考えない所をどうやって思量するんですか?
と。
この修行僧は「箇の不思量底を思量す」という事を単純に受け止めたのかもしれません。
ですから「不思量底如何が思量せん。」と。
このように再質問をしたくなる気持ちも凄く分かりますね。
恐らく私であっても今述べてきたような参究は恐らく瞬時には出来ませんから、同じように質問をしたかもしれません。
我々の今生きている命に理由などない
我々人間というのは「何故?」、「どうして?」と思った時、納得する答えがないと次には進めません。
しかし先ほども申し上げたように大自然には納得などありません。
本来、我々の生きている命には問題など何もなく、行き詰まりもないのです。
それなのに我々は、
- どうして心臓は動いているの?
- どうして呼吸を繰り返せるの?
- どうしてお前は犬なの?
こんな事を疑問に思うものです。
この時の修行僧も、



思わない所を思うって一体何なんだ?
こう思ったのでしょう。
つまり大自然の在り方を、
人間の理屈で解決したいと思った
訳ですね。
しかし薬山禅師が言った「不思量底を思量す。」とは、本来人間の理屈が一切通用しない大自然の命の表情のことを言っているので、この修行僧は中々理解ができないのです。
大自然には何も議論の余地がありません。
例えば、「呼吸とは酸素を肺が吸って、二酸化炭素を吐くことである」というメカニズムを説明したところで、そんなものは人間が後からそれぞれに名前を付け、定義付けただけにしか過ぎません。
「呼吸」のメカニズムが理解できたとしても何故そんな事が行われているのか分からないし、寝ている間にその呼吸を止める事などできないのですから。
これが人間の理屈ではどうすることもできない、「大自然の行い」ですね。
つまり自分の思惑ではこの大自然の営みは一切管理ができず、ただ大自然によって行われるのを受け入れるほかありません。
このように大自然というものには人間の理屈が入りこむ余地などなく、理屈は一切通じないのです。
それなのに我々人間はいつも理屈での解決を求めてしまいます。
この時の修行僧も同じです。
生命現象や大自然というものは本来手が付けられません。
理由は一切なく、個人が考える理屈とは一切関係がありません。
どうして血液は流れている?どうして皮がくっついているんだ?どうして中に骨があるんだ?
これらすべてに理由などありません。
今生きている自分の命に対しては理由付けはできません。
理由付けをして納得しようとしているのは我々の頭の中の脳みそだけの話であります。
しつこいようですが、大自然にはそのような理屈や理論や理由は、一つもないのです。
理屈や理論、理由があるのはこの私の頭の中だけであります。
概念や理屈だけが先走り、にっちもさっちも行かなくなっているのが現在の我々の日常です。
不思量底、思量、非思量、それらは単なる言い方の違い
さて「生命の正体」を理屈で解決をしようとする修行僧は、「不思量底は一体どうしたら思量する事ができましょうか?」
という質問をしましたね?



不思量底如何が思量せん。
すると、薬山禅師は、



非思量
という風にお答えになりました。
「思量に非ず」つまり「非の思量」であると。
さてこの「非の思量」とはどういうことでしょうか?
「非」というのは手の付けられない事を「非」と言います。
不生不滅の「不」もそうですね。
人間の理屈では手の付けられない事を、仏教においてはこの「非」や「不」という否定語を用います。
我々の脳みそでは手が付けられないことだったり、人間の業では手が付けられない事を「非」と言ったり、理由が無い世界の事を「非」と言います。
つまり大自然の世界の事を「非」と言うのですね。
我々の頭に次から次へ浮かんでくる思いというのは「非」であります。
つまり「非の思量」であり、自分がやっていることではなく、仏様の考えであるということです。
例えば、次から次へと浮かんでくるこの「思い」というのは自分ではどうする事も出来ないし、コントロール出来ないですよね?
なので「非の思量」であります。
自分の思惑で理解をしようとする修行僧に対して、



非思量
という風にお答えになりました。
先ほど「非思量」とは自分の考えではなく、仏様の考えだという風に言いました。
これはどういうことでしょうか?
我々は普段からどうしもうもない大自然によって生かされております。
寝ている間に休まずに呼吸をしているのもそう、食べたものを消化し、栄養に変えてくれるのもそう。
このようにどうしもうもない「大自然の力」によって毎日生かされておるのです。
最後の「非思量」に限らずここまでに「不思量底」、「思量、「非思量」と、この三つの言葉がこの問答には出てきました。
しかしこの三つはどれも同じことで、同じ内容であります。
我々が生きている事実の事を「不思量底」とも言い、「思量」とも言い、「非思量」とも言う。
何故ならそれらすべて、どれをとっても「大自然の行い」であるからです。
「不思量底」、「思量」、「非思量」、どう表現しようが、全てどうしもうもない「大自然」の、「仏」の命の事をこのように言っておるのです。
不思量底とは-まとめ-
今回、「不思量底とは何か?」という事を薬山禅師の有名な問答を参考に解説してきました。
道元禅師の有名な詩の、
「春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さへて涼しかりけり。」
にもあるように、この「不思量底」とは、春になれば花が咲く様々な命の風景といえるでしょう。
この「不思量底」に限らず、命の風景には様々な言い方があります。
全ては大自然によって生かされている一つながりの仏命です。
お読みいただきありがとうございました。

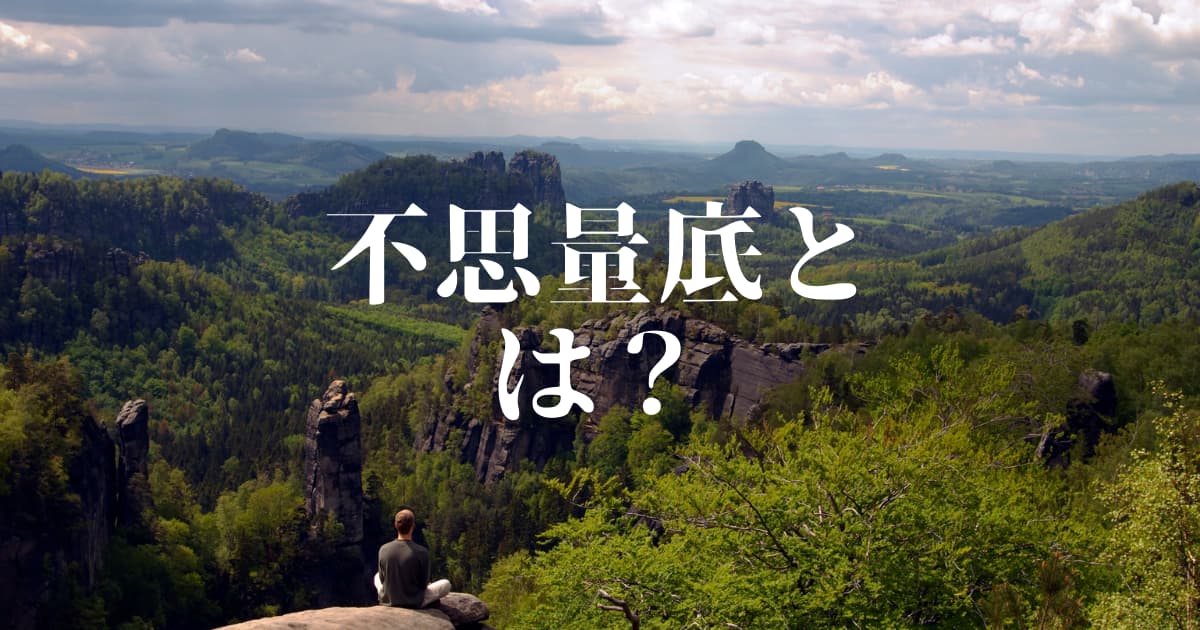
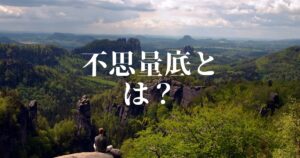
コメント