本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
それではまず初めに前回の、
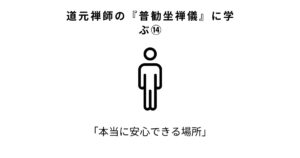
のポイントを振り返りたいと思います。
- 無我でなければ「仏法」ではない
- 他人の評価で成り立つ「相対的な世界」ほど曖昧で不安定なものない
- 「思う」という事は大自然の行い
- 「身心脱落」は元々の自然の姿であり、本来の実物の世界のこと。
- 思いを手放し、この元々の「実物の世界に」帰ることが「坐禅」
- そしてその「実物の世界」こそ真の人の安心する場所。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。矧(いわ)んや彼(か)の祇薗(ぎおん)の生知(しょうち)たる、端坐六年の蹤跡(しょうせき)見つべし。少林の心印を伝(つた)ふる、面壁九歳(めんぺきくさい)の声名(しょうみょう)、尚ほ聞こゆ。古聖(こしょう)、既に然り。今人(こんじん)盍(なん)ぞ辦ぜざる。所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。
「鴨」は「自分」
まず前回の、
という部分は、この『普勧坐禅儀』において非常に重要な部分となりました。
なので、前回の内容もおさらいしつつ、本記事の内容に迫っていきましょう。
昔、鏡清道怤(キョウセイドウフ868-937年)禅師という人がいました。
この方は今の浙江省温州市永嘉県の出身で、俗姓を「陳」氏といいます。
ある日この鏡清道怤禅師が静かに坐禅をしていると、「雨垂れの音」が聞こえてきました。

雨が降ってきたんですね。
すると鏡清禅師が弟子に向かって次のように質問します。
 鏡清道怤
鏡清道怤門外何の音ぞ
「門の外でなんか音がしているようだが何の音かね」と質問をするのです。
すると弟子が次のように言います。



雨滴声。
「雨垂れの音ですよ、和尚さんこれは雨垂れの音じゃないですか」と答えます。
すると鏡清禅師が再度言います。



衆生顚倒して、己れに迷うて物を逐う
つまり、
お前たちは「外の雨垂れ」、そういうものばかりを追いかけている。外向きな目をしているからいつも外の物ばかりに惑わされるのだ。
というわけです。どういうことでしょうか。
「鴨」は「自分」
また馬祖道一禅師と百丈懐海禅師の公案もここでご紹介したいと思います。
このお二人は、弟子と師匠の関係に当たります。
ある日お師匠さんの馬祖道一禅師と弟子の百丈懐海禅師が二人で散歩をしていたんですね。
すると丁度二人の足音に気付いたのか、「鴨」がバタバタバタバタと飛んでいきます。


「ガーガーガーガー」と鳴きながら南の空に飛んで行ったのです。
すると師匠の馬祖道一禅師が、
次のように言います。



一体鴨は「どこ」へ行ったのかね?
すると弟子の百丈懐海禅師が答えます。



たった今、南の空へ飛んでいきましたよ。
すると師匠の馬祖道一禅師が弟子の百丈懐海禅師の「鼻」を思い切りつまんで、捻じ曲げたのです。
弟子の百丈懐海禅師は、



痛い痛い!師匠、何をするんですか!
と、反応的に答えます。
そこで師匠の馬祖道一禅師は、



なんだ、「ここ」にいるじゃないか!お前は南の空に鴨が飛んで行ったと言うけども、「鴨」はちゃんとここにいるじゃないか。
と言うわけです。
さて、ここまで2つのお話をご紹介しましたが、この2つの公案でいいたいことはなんでしょうか?
我々は気付かぬうちにすっかり「概念」に囚われて、本来の在り方を忘れてしまいます。
そして先例の「外から雨垂れの音が聞こえる」だったり後の「鳥は南の方へ飛んで行った」とか。
このように物事を自分から切り離して判断してしまう。捉えてしまう。自分と「雨の音」、自分と「鳥」このように切り離してしまう。
しかし物事というのは、全てが1つにつながっている。「雨の音聞こえる」のは雨の音が自分の耳を震わせる、つまり自分の命だからです。雨が自分だからです。
鳥の鳴き声が聞こえるのも同様です。
これがなかなかわからない。
そこをこの「鼻」を捻じ曲げる事によって、より本来の「在り方」を思い出すことができるのです。
というのも「鴨はちゃんとここにいた」と認識できるのは「鴨を見た」からできたことです。そもそも自分が「鴨」が飛んでいくのを見ることができるのは「見る」というそもそもの行為があるからできるわけですよね?
つまり自分がいないことにはその「見る」行為ができないわけで、「見る」行為ができないということは「鴨」がいないということなんです。
つまりここで言う「鴨が飛んでいく姿を見た」というのは「自分の命」があって初めて生まれる物であるんですね。
ということは、「鴨」は「自分の命」そのものであるとも言えるのです。「鴨」が自分なのです。
「雨垂れの音」もそうです。
「雨垂れの音」も自分自身の「耳」が聞かなかったら「雨垂れの音」になりません。
自分の耳があって初めて「雨垂れの音」が生まれる。
自分と他が一つとして生きているから「物を見たり」、「音を聞いたり」という事ができる訳であります。
こういう考え方は「学校」では教えてくれませんね。
本来「真実」とはそういうもので、そのような「捉え方」をしていかなければならないと思うんですよね。
なぜなら何事も認識というのは正しくなければならないからです。
しかし小学生の内にこのような真実に対しての「考え方」の授業は行われませんね。
だからみんな好きなように「考え方」を解釈してしまう。
「私がみる」、「おれのもの」。
このように真実が置き去りにされてしまう。
物事は全て一つに繋がっている「仏の命」、「全ては自分と共にある」。
しかしそうは言っても、我々の「考え方」はいつも「外向き」であります。
なかなか「考え方」の根本を見直す事は難しいですからね。
また外向きだから「自分と他人」、「自分の体と自分の心」、「自分と鴨」、「自分と雨音」という風に物事を対象化し、2つに分けて考えてしまうのです。
そして物事の「本来の在り方」を忘れてしまうのです。
自分の目があるから鴨がみえる、耳があるから雨音が聞こえる、壁を叩けば手が痛い、自分がいるからあなたがいる。
本来は全て一つに繋がった「仏の命」、「全ては自分と共にある」。
これこそが、「大乗仏教」や道元禅師、お釈迦様が一番におっしゃりたいことのはずです。
我々はいつも「物」を追いかけて自分自身を忘れている。
すべてはここにあり、自分こそ「全て」である、これが「真実」です。
何故なら自分とあらゆる世界は1つに繋がっているからです。
なので、



そこをしっかりと回向返照し(内向きにし)、自分という本来の世界に気付いてください。そうすれば身心自然に脱落して本来の面目が、すっかりとそこから見えてくるはずです。
と言う訳です。
ここまでが前回のおさらいとなります。
非常に重要な部分なので、振り返ってみました。
物事には「名前」がつけられない
それではここからは、本記事の内容に入っていきたいと思います。
この「恁麼」についてですが、何とも名づける事が出来ないものをこの「恁麼」と言います。
意味としては今で言うところの、「あれ」とか「それ」に該当し、今でいう昔の指示代名詞のようなものです。
「何とも名づけられない」、「どうしようもない」もの。
またこの「恁麼」と似たような言葉で、このブログでもよく使う言葉ですが「仏」という言葉もそれに該当します。
我々は生きていると腹が減ります。坐禅を組むと足が痛くなります。
しかしなぜ腹が減るか、なぜ足が痛くなるか、その原因はわかりません。何がなんだかわからない、どういう仕組みになっているのか、言い当てることもできない。
おそらく今後もきっと解明できません。言い当てることもできません。
そう言った「解明できないもの」、「言い当てることのできないもの」によって我々の命は支えられているわけです。我々の命のわけです。
つまり「我々の生命の実物」、「我々が生きている事実の事」はこの「恁麼」であって、「仏」であるというわけです。
例えば「チョコレート」と言うとします。我々はその言葉が出た瞬間に、かの「チョコレート」を想像でき、そこからお互いコミュニケーションをとることができるようになります。
「チョコレート」という「名前」は「人間」のコミュニケーションのために作られるもので、それはつまり「人間の概念」なんです。
しかし実際はその「チョコレート」に関しても言い当てることなどできないのです。例えばその「チョコレート」を食べたとして、数時間後にそれは便として排泄されるでしょう。
そうなった時それは「チョコレート」ではなく「便」に成り変わるのです。
このように物事においては、どんなものにも定義がありません。また1秒ごとに賞味期限が迫り、腐っていく。「チョコレート」だと言い切れるものがないのです。
この名前や定義というのは人間がコミュニケーションを図る上で架空に作られたもので、本来の姿ではないのです。
また理解し合う必要がなければ「名前」などいらないし、「アレ」や「コレ」でいいわけです。他人と理解しあわなくとも、腹は減るし、消化は行われるのです。
「名前」が付けられるという事は、何も変化がないような気がするから行えるんですよね。
真実を見逃しているのです。真実が見えていないのです。
だから名前をつけられると思っている。概念が絶対だと思っている。概念に固執する。
名前があるというのは「本来の在り方」として相応しくないんですね。だから真実は「恁麼」なんです。真実の仏法は「恁麼」でいいんです。「恁麼」でなければならないのです。「わからない」でなければならないのです。
例えば「誕生」と「死」も単なる「概念」なんですね。本来の世界には「誕生」も「死」もありません。
何故なら物事は無常であって、いつも変化してやまないからです。いつでも変化しているところに「誕生」も「死」も割ってはいれないですよね?「誕生」も「死」も止まった状態だからです。真実にそのような状態はありません。
我々が生きている「真実の世界」というのは壁を叩けばわけもわからないけど自分の手も痛くなる「自分と世界が一つに繋がった世界」です。
「自分」もいなくなれば「世界」もいなくなる、つまり「自分」などない「真実の世界」です。
だから真実の世界を「無我」というんですね。この「世界」を2つに分ける事ができません。
そしてそこには「理解するもの」と「理解されるもの」という区別がないので、名前が付けられない。だから「恁麼」と言うんですね。
「仏」や「真実」には決して名前が付けられない。
真実を実践できていれば、それは真実を掴めていることである
なので「恁麼」と言う。
それでは何も言い表せないこの「恁麼(真実)」とはどのように付き合えばいいのか?
それはただひたすらに「坐禅」をするということです。
ここが非常に大切であります。
何故なら「坐禅」は「生命の実物」を行じているからなんです。
「生きている今の事実」を行じている事といってもいいかもしれません。
もっと言えば「すべてがそこにあるから」といってもいいかもしれません。
この一秒一秒朽ちていく「真実」。
瞬く間に形を変え、固定化することなく、名前すら付ける事ができないこの「真実」を唯一掴んでいるのがこの「坐禅」と言えるのです。
というのも「坐禅」は、
一秒一秒姿を変える「生命の実物、この世の正体」を実践しているから
です。
「自分の命を実践している」ということは「仏と自分がひとつに繋がった真実の世界を証明している」ということ。
そしてその「真実」を実践できているということは、「真実そのもの」であるということですよね?
「自分の命の実践」が、「真実」そのものであるといえるのです。
だから自分の命を実践する「坐禅」でのみ、この世の正体を掴むことが出来、証明できるわけです。
だから道元禅師は「坐禅」をおすすめになるわけです。
だからこの一文では、この「真実」を掴もうとしたならば、急に直ちに、この「坐禅」を務めなさい。とおっしゃるわけであります。
我々が行じている「坐禅」こそが、「恁麼の事(仏、真実)」であります。
生命の実物を行じることでのみ、真実を掴むことが出来るというわけです。
生命の実物を行じることでのみ、真実を掴むことが出来るーまとめー
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の
という部分を解説してきました。
記事の前半部分は前回の復習にあてましたが、後半部分も『普勧坐禅儀』においては重要な部分でした。
最後に本記事のポイントをおさらいしておきましょう。
- 「恁麼」というのは何とも名づける事が出来ないものを「恁麼」と言う。
- 「真実」だけでなくあらゆる「物事」は何とも名づけられない
- 「真実」は何とも名づけられないため「恁麼」と表現する
- あらゆるものは一秒一秒形をかえ「無常」である
- 一秒一秒姿を変える「真実」を掴むためには一秒一秒「真実」を共に行じるしかない
- 「真実」を共に行じることができるのは「坐禅」のみ
以上およみいただきありがとうございました。

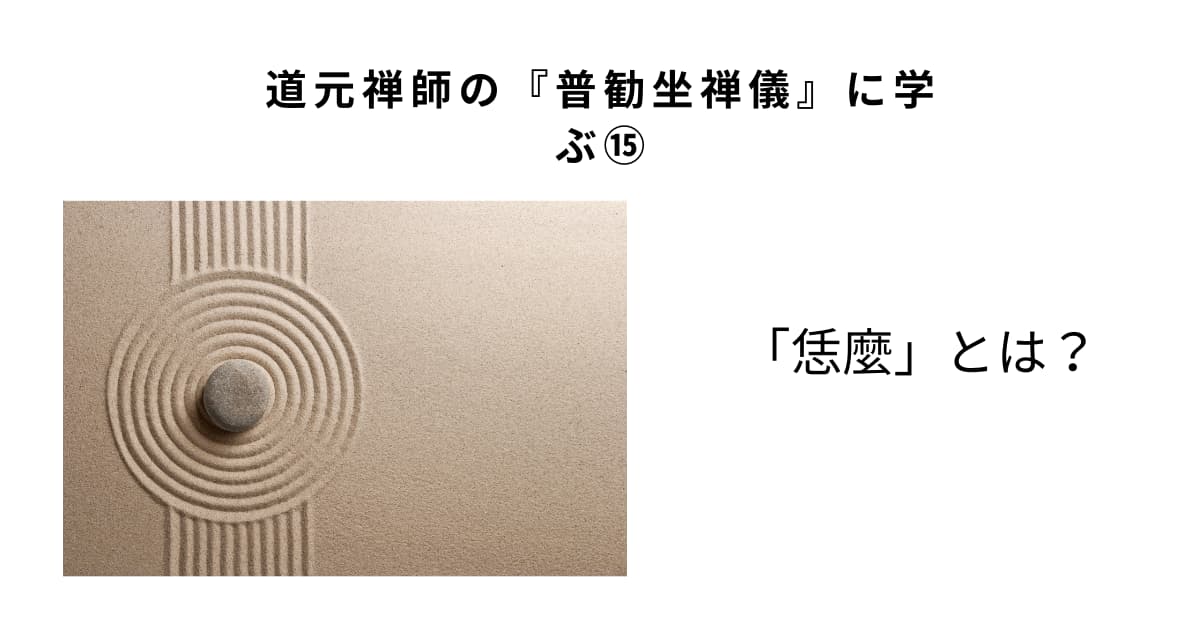
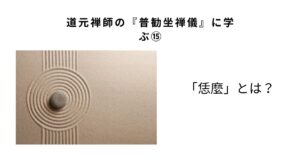
コメント