本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
それではまず初めに前回の、
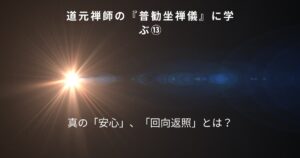
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「言葉」や「概念」は人間だけのコミュニケーションツールであり、「実物」ではない。
- 「言葉」や「概念」をもってして「真実」にはたどり着けない。
- 真の「安心」を得るためには光を「外側」ではなく、「内側」に向ける。
- 「内側」とはつまり「自己」を指す
- それが即ちわたくしが今ここに生きている「実物」に立ち帰るという事(坐禅)
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。夫れ参禅は静室(じょうしつ)宜しく、飲飡(おんさん)[飲食(おんじき)]節あり、諸縁を放捨し、万事を休息して、善悪(ぜんなく)を思はず、是非を管すること莫(なか)れ。心意識の運転を停(や)め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて、作仏を(と)図ること莫(なか)れ。豈に坐臥に拘(かか)はらんや。
無我でなければ「仏法」ではない
今回は、
という部分を読み進めていきたいと思います。
まず初めの「身心自然に脱落して、」という部分。
道元禅師が中国へ赴き、天童山の景徳寺において「真実に目覚められた時」のことをこの「身心脱落」という言葉で表現します。
少しここでそのときの経緯についておさらいしておきましょう。
当時、天童山景徳寺の「坐禅堂」において、道元禅師が熱心に「坐禅」をしておったんですね。
その時隣で「坐禅」をしていた修行僧が盛んに居眠りをしていたんです。
するとそこの住職であり、道元禅師の正師でもある天童如浄禅師が、その時履いていた靴でその寝ておった修行僧をぶち叩いたんですね。
そして、
 天童如浄禅師
天童如浄禅師只管に坐睡してなんたるや!坐禅は「身心脱落」なり!
と叱咤するわけです。
その様子を見ておられた道元禅師が「身心脱落」、つまり「真実の在り方に目覚めた」というのがその経緯です。
仏教の基本は無我であります。
つまりこの世界には「俺」という自我はないんですね。


「諸法無我」という仏教用語もありますが、あらゆるものは無我であります。なぜならこの世界には「自我」がないからです。この「俺だ」と思っているものは、単なる認識であり、実際の世界には存在しておらず、実際の世界はというと、誰かとぶつかり合えばお互いが痛くなり、カラスの鳴き声が自分の耳を震わせ、壁を殴れば痛い。このようなあり方になっている訳です。
つまり他によって自分の命が起こる。他によって自分は生きることができる。つまり他が自分だということだからです。
これがもし仮に自我というものが実際に存在したとして、ここからここまでが俺の命という風な線引きができたとしたら、例えば呼吸なんかも場所によっては思う存分できなくなり、死んでしまうことになります。
しかしそうはならない。いつでもどこでも思う存分に呼吸をすることができ、自分「俺」が寝ている間にも食べたものを消化してくれていたりする。
全てとこの命は共鳴しあっている。全てによってこの命は起こされている。全てが1つにつながっている。
いわゆる「無我」なんです。
「無我」でなかったら真実ではありません。その真実のことを「仏法」と言いますから、「無我」でなければ仏法とは言えないんですね。
そもそも、仏教の教えには「三宝位」という三つの旗頭があります。
- 「諸法無我」(諸法は無我である。)
- 「諸行無常」(諸行は無常である。)
- 「一切皆空」(一切は皆空である。)
その三つの旗頭の一番基本となるのが、今の「諸法無我(諸法は無我である。)」なのです。
もっとも大切な教えということですね。
しかし我々には、生まれてからいつの間にか獲得していった「自我」というものがあります。
これは我々が生まれた時から持っていたものではなく、生まれてから次第に獲得していったものであります。
例えば赤ん坊のころはなかった「これは私のもの」、「これは俺のもの」という考えは、成長するにつれ段々と、芽生えていきますよね。
そしていつの間にか「自分のもの」、「俺が」という「自我意識」が強くなりすぎて、がんじがらめになっている。
それはある意味、大自然の産物、自分ではどうすることもできないもの、人間の特性と言えたりもするのかもしれませんが、しかしそれは概念です。
それは人間同士のコミュニティによって生み出されるもので、犬がそこに入ったとしても自我は形成されません。つまり本来の大自然ではないのです。
また小さいときというのは自分の事を紹介する時に「さっちゃんはね、」と言ったりしますよね。
そのように、幼いころというのは「自我意識」がきちんと確立されていないから「傍観者」として自分自身を見ている時期があるのです。しかし徐々に意識が確立されていく。「俺が」、「私が」というものが徐々に確立していくのです。
その自我意識というのは本来この世界にあるものではないのです。存在していないものなのです。
コギト・エルゴ・スム
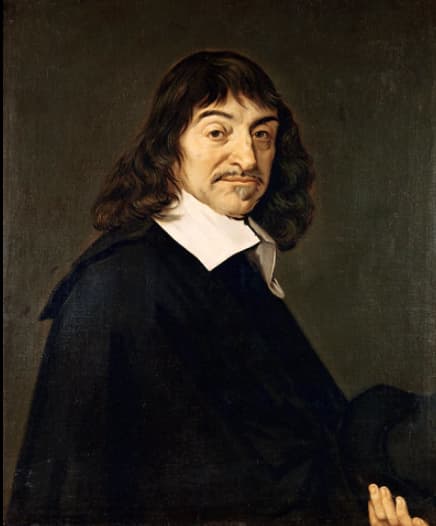
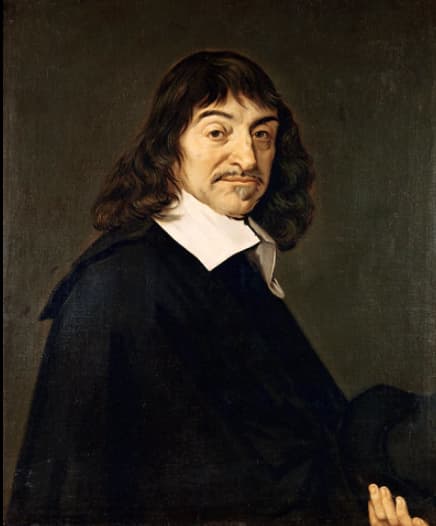
西フランス出身の、哲学界の巨人「デカルト」(1596-1650)が、ラテン語で「コギト・エルゴ・スム」という言葉を残しております。
これを日本語に直すと、
思う故に我有り。
という意味になります。
つまりどんなことがあろうと最終的にはこの「我」があり、すべてのはじまりはこの「我」だというんですね。
「色々疑問に思うこと、そうおもうことが全てであり、そのための出発点、最終点には我がいる、私がいる、自我がある」といった考え方ですね。
この「自我」や「我思う故に我有り」という考え方が出発点となり西洋の自然科学というものが確立していきました。
しかしこのデカルトの言う「我思う故に我有り」という考え方と、さきほどの仏教による「無我」というのは相反するものです。
例えばこのデカルトが言うには、私が「物を見る」、私が「ガラスを見る」、私が「畳を見る」、私が「本を見る」、というように外界の物を「客体」としてまず大自然から切り離す。
本来は1つとして溶け合っている事象を、切り離すということです。
- 私がガラスを見ている
- 私は本を読んでいる
- 私はバナナを食べる
常にこうして「主体」と「客体」と2つに分けて世界を眺めており、「真実」を相対の世界の出来事という風に見てしまっているんですね。
しかし繰り返しになりますが「真実」の世界、「大自然」の世界のあり方はそうではありませんね。
物が当たれば痛い。足を組めば痛い。鳥の声が自然と自分の耳に入ってくる。おならの嫌なにおいがする。
このように本来の世界では、客体と自身が「同時」であることがわかる訳です。客体によって自分の命が起こされている。すべてが1つとして繋がっているんです。
それにそのように相対の世界という風に世界を見てしまっては、常に他者によって自分の存在が証明されなくてはいけません。
相対の世界では個々が「確立された世界」なので、お互いが証明しあわなければならないのです。
だから自分の証明を他に求める。自分が生きているのか証明してほしい。自分がどれくらい優れているのか証明してほしい。
このような不安定な精神状態になってしまう訳です。
しかしそんなことしなくてもいいのです。カラスがいる。B子ちゃんがいるということは、それはあなただということです。
何かが聞こえる。それで十分あなたの存在の証明であるわけで、それ以上に求めるべきものもありません。
庭前の栢樹子
趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)禅師という有名な中国の禅僧がおります。


この方は「禅の巨人」とも言われる非常に有名な方ですね。
その趙州禅師の有名な話で「庭前の栢樹子」というものがあります。
これは「如何なるかこれ仏法の大意」という「仏法の大義」を問う問答に対して、この趙州禅師が「庭前の栢樹子」と答えたという内容に基づいたもので、非常に有名な公案として現代でも語り継がれているものです。
つまり「何が仏法ギリギリの教えですか」という問いに対して、「寺の庭に立っている、柏の木だよ」と答えたんですね。
「真実」とは何か?と聞かれ、「庭の栢樹子」と答えるのですから、さきほどのような「相対の世界」で見たらこの公案の真髄は決して分からないでしょう。
というのも、自分と世界は一体で、その自分こそが紛れもない真実であるわけです。足を組めば痛い。問答無用で腹が減る。その映画を見て感動するな!といっても感動してしまう。
坐禅をしていると、それが本当によくわかります。だんだんと足が痛くなってくる。そしてその痛みは誰かと比較した痛みではありません。紛れもない宇宙いっぱいの痛みです。痛いから痛い。その痛みです。
坐禅はこの世界の真実を捉えている。この世界の真実そのものであるわけですが、このような紛れもない、絶対的な命を誰もがいただいているわけです。
そしてその坐禅はどこでやっても同じです。アメリカでやってもイギリスでやっても同じです。またどこにいてもカラスや人の声、サイレンの音が聞こえてくるように、世界とは常に真実むき出しなのです。
どこにいても真実いっぱいなのです。
「真実」は常に今ここにある。自分と常に一つであり、目の前に展開する全てのものがその「真実」であるわけですから、この「庭前の栢樹子」と答えたというわけです。
仏法においてこれ以上の答えはないんですね。
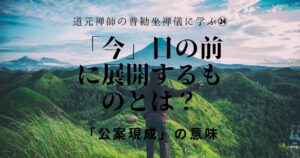
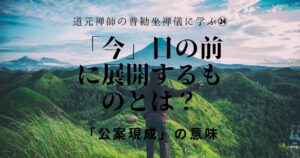
身心脱落は人間の脳みその話ではない
もちろんこの「何かを認識する」という行為は特に現代の人間の生命活動において重要な事です。なぜなら人間は人間社会で生きていかなければならなくなり、その人間社会というのはコミュニケーションが必要だからです。そしてそのためには「自我」の確立がなければコミュニケーションをとることができないからです。
いくら「真実はいつも1つとして繋がっているのだっから、俺の物もなければ、お前の物もない!」といっても現代において人のものを盗んでしまってはそれは「窃盗罪」になって捕まってしまいますし。殺人なんてのもはもってのほかです。
しかし、それと真実のあり方とは関係がないんです。
理解というのは、単なる後付けで、真実があって、人間の趣味としてその理解があるからです。理解がなくてもこの呼吸は行われ、消化も行われるからです。
だから先ほどのデカルトの言う「我思う故に我有り」とつじつまが合わないことが段々理解できてくるんですね。
つまりそれは単なる「概念遊び」に過ぎず、真実の命の的を射ていないのです。
「寝ていて、自我意識が無い状態」の時でも、朝起きればきちんと食べたものは消化されるし、呼吸もされています。生命活動において何の理解も必要ないんですね。
人間の理解が及ぼないといってもいいかもしれません。
どんなにつらいことがあっても腹は減る。呼吸もせねばならない。理不尽なほど排泄感を催してくる。
繰り返しになりますが、生きていく上でこの「認識」するという行為は直接的には必要ないのです。
話がいくらか脱線してしまいましたが、先程も申し上げた「主体」と「客体」という風に、物事を分ける以前、認識する以前の事を「身心脱落」というんです。
なので先ほど言った「庭前の栢樹子」という事例も、「私が庭前の栢樹子を眺めている」となったらこれは「身心脱落」になりません。
何故なら「私」と「庭前の栢樹子」という風に物事が2つに分かれてしまっているからです。物事が分かれる以前の事を「身心脱落」と言うからです。
非常にここが重要な所です。
先程のデカルトに見るように「自我」や「私が」という所から人間生活や西洋の自然科学は出発し、今日の発展を遂げて参りました。
しかしこの物事を「分ける」とか、「理解する」、「物を概念化し他の人々と共有していく」という行為は全て人間の頭の中だけの話です。
「本来の世界」、「実物」の世界というのは、2つとして分かれないし、「私が」という世界は人間の脳みそ以外どこにも存在しないのです。
「如何なるかこれ仏法の大意」・・・「庭前の栢樹子」
これが全てなんですね。
「真実」は「庭前の栢樹子」なんです。
「思う」という事は「私」がやっていることではない
道元禅師のおしるしになった『正法眼蔵生死の巻』に次のような一文が出てきます。
ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ、仏となる。仏となるに、いとやすきみちあり、もろもろの悪をつくらず、生死に著するこころなく、一切衆生のために、あはれみふかくして、上をうやまひ下をあはれみ、よろずをいとふこころなく、ねがふ心なくて、心におもうことなく、うれふることなき、これを仏となづく。(一部抜粋)
まことに恐れながら、少しだけ解説してみたいと思います。
とありますね。
ここで言う「仏」というのは今長々と説明させていただいた「真実」の事をさします。つまり今、ここに生きている「事実、実物」や「目の間に展開する一切」を「仏」と言うんですね。
我々は日々色々な思いによって振り回されてります。
そんな中でも、「坐禅」を通してこの「真実(仏)」に帰っていく尊さをここで道元禅師はおっしゃっているんですね。
そしてそれが「仏」となるいとやすき道だと。
我々人間は本来「真実(仏)」の世界に生きています。それは真実の世界だということです。足を組めば痛く、カラスの鳴き声や笹の葉の音が自分の耳をふるわせる。自分の屁は自分でこかなきゃならない。そういう紛れもなく絶対的なノンフィクションの世界です。
そしてその世界は1つに繋がっております。
物が当たれば痛い。足を組めば痛い。鳥の声が自然と自分の耳に入ってくる。おならの嫌なにおいがする。
こうした2つとして分かれない、1つに繋がった世界を生きているわけです。
なので頭で考えて難しく考える必要はないんですね。
「坐禅」を通してその「真実」、あるいは「実物」に立ち帰るだけなんですね。
「ざる」で「水(仏)」をすくおうとしてもすくえません。いくつもの網目からするすると溢れ出てしまいます。そんなことはしなくても、「ざる」を「水」につければいいのです。それが坐禅なのです。
「自我を忘れ、自我を全部、仏の家に投げ捨ててしまう、そして本来の世界に帰る」それが仏になるいとやすき道である。
「坐禅」が悟りにおいて「手段」ではなく「目的」とされる理由がここなんです。
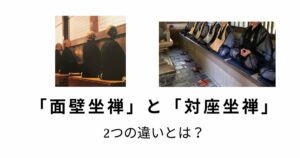
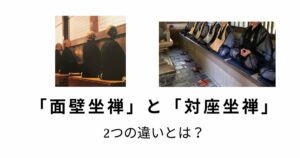
足を組めば痛い、この「坐禅」こそがまぎれもなく真実、「生命の実物」であるからなんですね。
「坐禅」こそが「真実」だからなのです。
元々が「身心脱落」
その「真実」や、「人生以前」、「物事が分かれる以前」、「父母未生以前」を行じていくのがこの「坐禅」、つまりは「只管打坐」であります。
以上のことを踏まえ、ようやく本記事の内容でもある、『普勧坐禅儀』に話を戻したいと思います。
この一文で高祖様は「自然に身心脱落す」とおっしゃっております。
これはどういう事かと言うと、「力をもいれず、心をも費やさず元々の在り方」こそが「身心脱落」であるということですね。
例えば今から100m先にこの「身心脱落」があるというわけではありませんません。
元々が「身心脱落」ですので、「坐禅」を通し、その元々の世界に帰る。
つまりその構築してしまった「俺」という「自我意識」を手放し、「坐禅」さえすれば自然と「身心脱落」するという訳なんです。坐禅さえすればいいんですね。坐禅をした瞬間、たちまちに真実だということなんです。
何か「努力」をし、その結果としてこの「身心脱落」があるわけではないのです。一生懸命「修行」を頑張った、その結果として「身心脱落」するという訳ではないのですね。
元の姿が「身心脱落」であり、その「元々」の世界に帰ることが悟りという考え方なのです。
なのでむしろ「考え」や「修行」、「悟り」そういった頭で考える事を放棄し、「本来」の世界に帰った時、「真実」、つまり「悟り」に出会えるということなんです。
「悟り」とはこの問答無用で痛いということです。問答無用で聞こえてくるということです。問答無用で呼吸がされるということです。
我々が普段から振り回されている「脳みそ」の中の話を全部手放しさえすれば自然と「身心脱落」になる。大自然に戻れる。本来の面目に出会える。
そういうことなんです。
そのための気づき、人生においてこの気づきが大切ですね。
なので本当の「修行」とはこの気づきを得ること、自分で構築してしまった「自我意識」を手放す事ともいえるかもしれません。
決して「身心脱落」というのは「心境」の問題ではなく、元々の「今ここに生きている実物」を「身心脱落」というわけであります。
今ここに生きている事実の「証明」
つまりは「坐禅」を通し、「今ここに生きている実物」を行じていく事。
これが人間にとっての一番の「安心」のしどころでもあります。
何故ならそれが「全て」だから
痛いから痛い。それはもう十分なほどこの世界における真実で、お悟りだからです。またそれは自分が生きていると実感させられることにもなり、この全世界と、A子ちゃんやB子ちゃんと繋がることができていると実感させられるからです。
例えば隣にB子ちゃんが坐禅をしたとします。B子ちゃんがおならをしてしまった。そのおならの匂いが臭ってくる。臭いと感じる。つまりB子ちゃんは私なんです。
我々人間はこの「生きている実感」が無い為に不安になり、その実感を他人との兼ね合いの中で得ようとします。
「他人から認められたい、他人に褒めてもらいたい。」そういう相対的な世界の中から「生きている実感」を得ようとするんですね。
しかし非常にこれは不安定な話であり、人間を不安にさせる一番大きな原因です。
なぜなら「他人から認められたい、他人に褒めてもらいたい。」というのは、相対的な不安定な話あり、自己の権限を他に握られているようなものだからです。
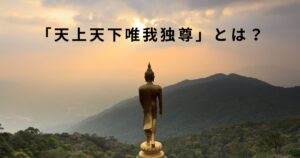
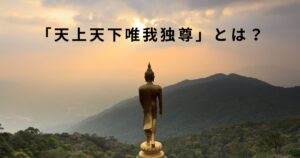
しかし、これまでにお伝えした来たように「真実」の世界はそんなものではないですよね?
「真実」の世界はいつも1つに繋がっているのです。また「足を組めば痛い」そういう紛れもない真実で成り立った世界なんです。
手に取れる、本物や、実物がちゃんとあるんです。人間がちゃんと安心できるものがあるんです。
だから「他人との兼ね合い」をこの坐禅では行じてもらう訳ではないんですね。「坐禅」を通し「今ここに生きている実物」を行じていく事、それが一番の人間の「安心」のしどころであります。
坐禅をすると痛いです。しかしこの痛みに落ち着いていく事が我々の一番の安心であり、唯一の安心できる場所です。
今ここに生きているこの生命の実物を行じる事(坐禅)が我々の生きる「目的」であり、ここで言う「本来の面目」と言うのかもしれません。
なぜならそれは「真実」の行い、あるいは「仏の行い」だからです。
この世界は仏の世界で、我々もその仏の世界の子であり、仏だからです。そこでは仏行をしなければならないからです。
それそした時我々は本当の意味で生きることができます。仏である我々は成仏ができます。
坐禅をすると痛い。しかし痛いのは紛れもないということです。この世界の「正しいあり方」だということです。この世界の「正解」だということです。



自然に身心脱落すれば、そこに本来の面目があるではないか。
「坐禅」を通し、我々の本来の面目を行じているのがこの道元禅師のお勧めになるこの「只管打坐」であるということです。
生きる目的、本来の面目とは
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の
という部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントをおさらいしておきましょう。
- 無我でなければ「仏法」ではない
- 他人の評価で成り立つ「相対的な世界」ほど曖昧で不安定なものない
- 「思う」という事は大自然の行い
- 「身心脱落」は元々の自然の姿であり、本来の実物の世界のこと。
- 思いを手放し、この元々の「実物の世界に」帰ることが「坐禅」
- そしてその「実物の世界」こそ真の人の安心する場所。
本記事はこの『普勧坐禅儀』において非常に重要となる部分です。
何度もお読み頂ければ幸いです。
以上、お読みいただきありがとうございました。

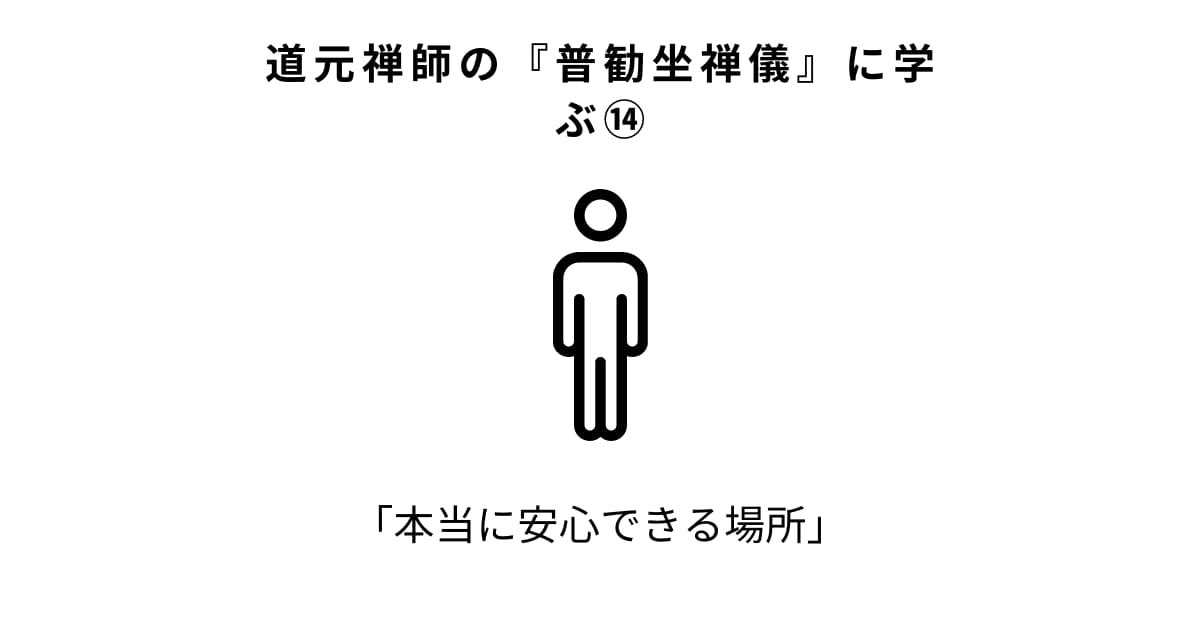
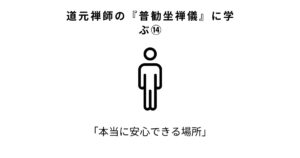
コメント