本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきたいと思います。
今回は前回の内容も踏まえつつ、
という部分を解説していきます。
まず前回の、
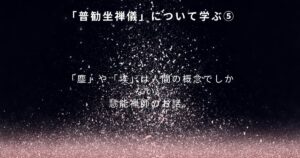
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「塵」や「埃」というものは人間の概念でしかない
- その「概念」も含めた、我々人間の命
- そしてその「人間の全体の命」を行じるのが道元禅師のお示しになる「坐禅」
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。
寒山(かんざん)と拾得(じっとく)
前回の記事では、
という部分を解説しました。
その際、六祖慧能(えのう)禅師の、
菩提元樹なし、明鏡また大にあらず。本来無一物、いずれのところにか塵埃のあらん。
という見偈を例に、この世界には拭うべき「塵」や「埃」はなく、それは人間の概念でしかないというお話をさせていただきました。
今回もその内容についてもう少し深堀していきたいと思います。
中国に「寒山(かんざん)」と「拾得(じっとく)」という非常に有名な仙人のような生活をした二人のお坊さんがおりました。
この「寒山(かんざん)」と「拾得(じっとく)」は、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)様、普賢菩薩(ふげんぼさつ)様の生まれ変わりだともいわれておりますが、この名を耳にしたことのある人はおおいのではないでしょうか?
架空の人物であったという説もありますが、禅画の画題として用いられることから今でも非常によく目にする機会の多い人物です。
寒山寺にいた寒山(かんざん)と、天台寺にいた拾得(じっとく)。
詩人としても有名なこのお二人でしたが、二人とも奇行が多かったことでも知られています。
下の画像をみてください。

この画像をみると「拾得」の方がですね、箒を持って片一方の指で天を指しております。
「寒山」の方はというと、箒も何も持っていません。
この画像にまつわるお話を今回少しさせていただきますね。
道元禅師は何故坐禅をされるのか?
恐らく二人で仲良く庭掃きをしていたのでしょうね。
楽しそうな話ごえが今にも聞こえてきそうです。
ある日、箒を持っていない「寒山」の方が、
払うべき埃もなきに箒持つ奴の心ぞ塵となりぬる。
と言います。
つまり、
払うべき埃もないのに、箒など持ってどうするのだ。そのようなお前さんの心こそ塵ではないか。
と「寒山」は言う訳です。
この世の中に厭うべき「埃」も「塵」というものは一切無いのに、箒を持って払おうとする。そのお前の心が塵や埃ではないか、という訳です。
この世界は全て尊い仏様である、仏性である。そんな捉え方をされていたのでしょう。
一方箒を持っている、「拾得」の方は、
払うべき埃もなしと言う奴を払わんが為の箒なりけり。
というんですね。
つまり、
ああだこうだ理屈を並べ立てて、掃除をしないお前のような奴を払うための箒である。
このやりとりの場合、どちらの意見がどうという訳ではありません。またどちらの言い分もわかるわけです。
このような非常に面白いやりとりがこの『寒山拾得図』のなかには隠れているわけですが、このやりとりを踏まえ、今回の普勧坐禅儀の内容に入っていきたいと思います。
つまり、
 道元禅師
道元禅師あなたの「思惑」で、修行をする。そのような手段としての「坐禅」を一体誰が信じるというのでしょうか。
と、道元禅師はいうわけです。
つまり「坐禅が全体」「坐禅が全て」であるのに、どうして「手段」として「坐禅」を用いるのか?ということですね。
一方で今回「寒山」が言うのはこの世の中は何一つ「塵」や「埃」が無い、一体どこにそのような「塵」や「埃」があるんだと。
両者が述べられていること、少し似ていますよね。
しかし道元禅師が言わんとしていることはそうではありません。
寒山様は「払うべき「埃」も「塵」もない。そのように言うのなら、そもそも「掃き掃除」なんてしなくても良いではないか?」と述べられました。
これって見方を変えると「全てが悟り」だというのなら「坐禅」などしなくてもいいのではないか。このように言い換えることができるわけです。
しかしこれはあくまでも「考え」なんですね。つまり人間の概念であり、人間の駄々こねなんです。ただ頭で考え、口でそう述べているだけなんです。「悟り」を知った気になっているだけなんです。
寒山様のいう通り、この世界の全ては仏様のお命です。そのお命が1つとして繋がっているのみです。これは疑いようのない事実です。
それが「真実」だとして、
そのことを証明できるのは「坐禅」や「掃き掃除」だけなんです。
何故なら、「概念」とは違い、「坐禅」や「掃き掃除」は確かな生命の実物だからです。この世界に存在しているものだからですね。
心や概念、これは残念ながら存在していません。今こうして頭の中にあるではないか!そう思っても、実際に手に取ることはできないんです。差し出すことはできないんです。
差し出すことができないのは「無い」からなんですね。
例えば我々の頭の中に今「憂鬱」な思いが生じているとします。しかしそれが存在できるのは「憂鬱」という言葉を知っているからなんですね。
「憂鬱」という言葉を知らない生まれたての子供にはこの「憂鬱」は存在しません。同じく猿やチンパンジー、ゴリラにもこの「憂鬱」は存在しないのです。
このように概念というのはあくまでも概念であって、存在しているように思われるだけなんですね。実際の世界にはこの「憂鬱」という物体は存在しないのです。
世界はいつもいきつまりはなく、真実のみです。そこに対し、人間が勝手に概念をあてがってしまうだけなんですね。
「生命の実物」であること、「生き詰まり」がないこと、これが大自然であり、「お悟り」です。
そして「概念」は「概念」なんです。
寒山様の「この世界は全てが悟り」であるという真実を概念で捉えてしまったらのなら、それは概念だということです。
だから、
- 払うべき「埃」も「塵」もない。そのように言うのなら、そもそも「掃き掃除」なんてしなくても良いではないか?
- 「全てが悟り」だというのなら「坐禅」などしなくてもいいのではないか。
というのはどちらも誤りなんですね。それは単なる人間の「概念遊び」なんです。
今申し上げたことを道元禅師は踏まえていたから、ひたすら「坐禅」にうちこむわけです。
只管打坐
大自然の「生命の実物」を実践するわけです。坐禅こそがお悟りだと。坐禅がこの仏の世界そのものだと。この世界の真実そのものだと。
我々は仏の子であるからに、その仏が常にいるべき場所だと。
そう言われるわけです。
ここが両者の見解の異なる点なんですね。
「すべてが悟り」だと「証明」しているのはこの「坐禅」だけなんです。
それを踏まえた上で道元禅師は、
とおっしゃるんですね。
本来「払うべき埃はない」とおっしゃるんです。
犬の糞もフランス料理も、同じ「実物」であるわけですね。
どちらも大自然の命です。
その生命の実物には、人間の判断価値や優劣が入りこむ余地がありません。
同時に我々も「坐禅」を組まねばならないし、「掃き掃除」をしなければいけません。
何故なら「坐禅」は生命の実物であり、大自然の命だからです。
「掃き掃除」は生命の実物であり、大自然の命だからです。
なぜ坐るか?なぜ掃くか?それは、坐ること、掃くことが、お悟りであり、本来の世界を生きることであり、我々の生きる呼吸だからです。
生きるために必要な呼吸だからです。
仏性を誰もが持ち合わせているという事を証明するためには
また今述べた内容に関するお話がもう一つありますので、そちらのお話もさせていただければと思います。
昔、麻浴宝徹禅師という人がいました。
よほど暑かったのでありましょう。
暑いのでうちわで仰いで居りました。
扇風機もクーラーも無い時代であります。
暑い中、うちわで一生懸命仰いでおったんです。
すると一人の修行僧が「風性は至る所にある」と、この麻浴宝徹禅師に聞くんですね。
つまり「風の性は至る所にあるではありませんか?風の性というのはどこにでもあるではありませんか?」と聞くんですね。



和尚さんは何故風の性が至る所にあるというのに、扇などを使うんですか。
と、こう質問した訳です。
「風の性は至る所にある。」これは「仏性はみんな持っている」といっているわけですね。
なのでこの質問は、「仏性をみんな持っているというのにどうして和尚さんは坐禅をするんですか?」という質問になるわけです。
我々は「仏性」をみんな持っている、「仏の命」として生まれ、「仏の命」として生きている。
なのに何故わざわざ「坐禅」をしなければいけないのか?
というわけなんです。
するとこの麻浴宝徹禅師は、



あなたは風が至る所にあるという事は知っているが、働きによってその風を導き出すということをまだ知らない。
と、そのような回答をその修行僧にされたんですね。
そしてその際、ただ「扇で仰いで見せた」という教えが残っているんです。
この話で言いたいのは、
風はどこにでもある。しかしお前はその風がどこにでもあるということは知っているが、扇がなければ風の働きは起こらないという事をお前は知らない。
ということなんです。
つまり、
みんな平等に仏性を持ってるという事は知っている。しかしそれはただの「概念」である。「仏性」は「概念」ではなく「生命の実物」だからこそ、実際に手に取れるからこそ「仏性」なのである。
ただ扇を「使う」こと。
或いは「坐禅」を行じることにおいてのみ「仏性」は存在し、「悟り」は証明されるという訳なんです。
扇を「使う」ことによって「風至らざる所なし」、という事を証明していく。
これが仏法の理屈です。
またこれは道元禅師のおすすめになる「坐禅」の理屈でもあります。
「概念」でこのことを理解しようとしたならば、単なる「理解」で話が終わってしまう。そしてそれは単なる概念であり、誤りだと。
肝心な仏性は存在してこないと。
しかし、仏法は頭で理解するような「概念」の教えではありません。
そもそもこの世界に概念は存在しません。手に取ることができないからです。
「生命の実物」である「坐禅」を実際に「行じる」こと。或いは言い方をかえれば「真実」を「真実」することで初めて、我々人間が「仏」であることを証明できるし、「仏性」を持ち合わせているという事を証明することができるのです。
人間は仏であることを証明するために「仏の行い」を行じなければいけない。
今回は『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 生命の実物としては「塵」や「埃」というものは存在しない、実物に人間の価値判断は付けられない
- 概念としてなら「塵」や「埃」、きれいな物、汚い物と、人によって価値判断が分かれてくる。
- 物事の正しい姿は全て「実物」としての姿。
- 「塵」や「埃」は払うという実践を通して始めて、「塵」や「埃」を実物としてとらえる事が出来る。
- 「風」は至る所にあるが、仰いで始めて「風」が至る所にあるという事を証明できる。
以上が本記事のポイントとなります。
お読みいただきありがとうございました。

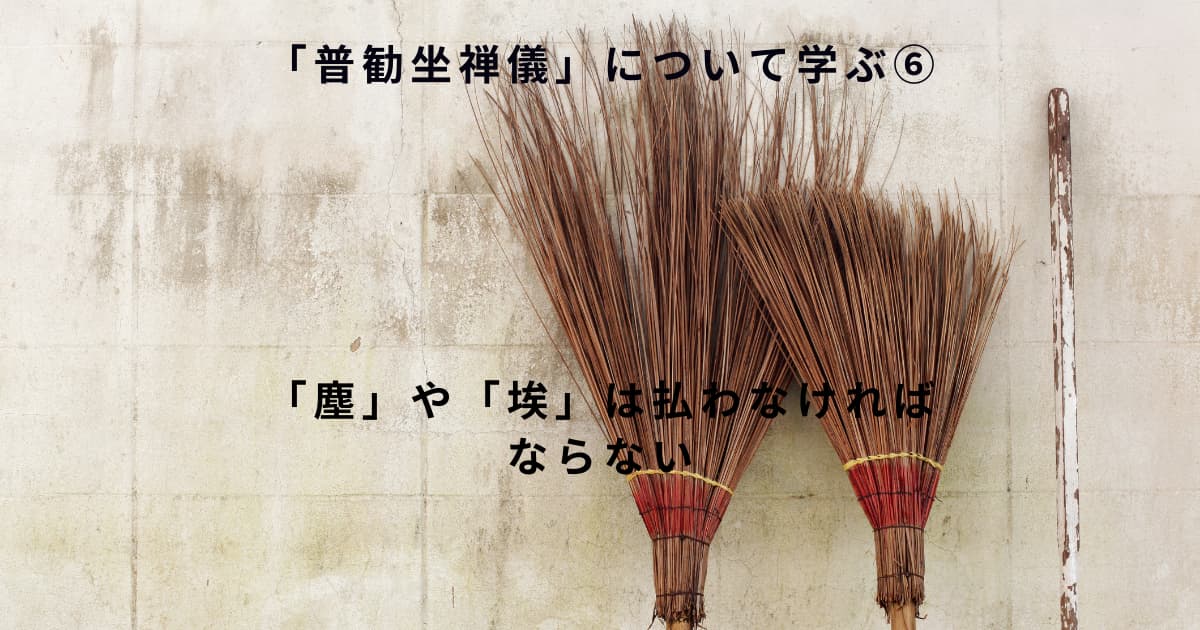
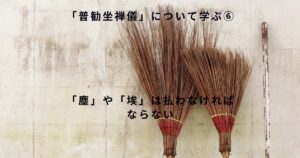
コメント