本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
まず初めに前回の、
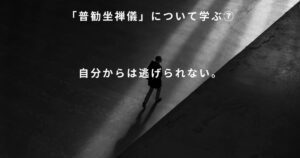
のポイントを振り返りたいと思います。
- 親指を石ころにぶつければ「痛い。」これが全てである。外に求める必要は何もない
- 今ここにある「自己」こそ真の仏法
- どんなに遠くに移動しようと、自分からは一切逃れる事は出来ない。つまり「仏」から逃れる事ができない。
- 何故ならすべては「一つ」に溶け合っているから。
- 自分は全体で、全体は自分だから。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。
一超直入如来地(いっちょうじきにゅうにょらいち)
今回の内容に入る前に、少しだけ前回の内容を復習してみたいと思います。
この「大都(おおよそ」、というのは「大体」という意味です。
なので「大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず」というのは、
大体(全ては)がここを離れない。
という意味になります。
我々が坐禅を行う際のはこの「単布団の上」ですね。
或いは運転をしている時は車の中にいます。
もしくは食事をしている時はテーブルの上にいます。
どのような状況であっても今、ここのみ。
「事実(全て)」というのは、「当処を離れず」なんです。
誰しも、「今ここにいる自分」から決して離れる事ができない。
誰しもが「当処、ここ」を離れる事ができない。
そしてその場所で、「生命の実物」を現成しております。紛れもなく生きており、生かされております。
どんなぐうたらな生活を送っている人間でであっても、その場所でまぎれもない「生命」を現成している。
それなのに、
何か目的を持って、目指す者になりるべく「一生懸命修行する」必要がどうしてあろうか。
どこか移動しなくても、そこが全てで、その場所には全てがあるではないか、その場所で既に「成仏」しているではないか、とおっしゃりたいのですね、道元禅師は。
例えば今のうちに「坐禅」をすれば、来年の今頃はもう少しマシな人間になっているのではないかという期待を、我々は抱きます。
しかし悟りを得て「成仏」するというのではなく、「今、立ちどころに」既に「成仏」であるという考え方なんです。
この世界には「今」しかないからですね。昨日や過去を思い描いたり、明日や未来のことを思い描くのが我々ですが、それらを思うのは「今」です。
そしてその「今」がこれまでずっと、あり続け、これからもその「今」があり続けるわけです。
昨日や過去、明日や未来というのは存在していない概念なんです。そんなものはないんですね。
例えば「一超直入如来地(いっちょうじきにゅうにょらいち」という言葉があります。
これは今この瞬間に立ちどころに「仏の世界が開けてくる」という意味の仏語です。
或いは「沢木興道(さわきこうどう)」老師という明治から昭和にかけて活躍した、現代にも多大な影響を与えた有名な禅僧がおりますが、その沢木興道老師も次のように言っております。
石川五右衛門だけが盗人であるわけではない。ちょっとした出来心で他人の物を盗ったらこれはもうりっぱな盗人である。それと同じくお釈迦さまだけが仏なのではない。仏のマネして坐禅すれば、仏である。
と。
かの大泥棒、「石川五右衛門(いしかわごえもん)」の真似をしたならば「一超直入泥棒地」我々も即座に泥棒になってしまう。
一方で「仏の真似」をして「一寸」でも坐ればそれはもう立派な「仏」であるというんですね。
「坐禅」をして、だんだんと仏になるのではない。
そういった「手段」として坐禅があるのではない。
今、坐ればたちどころに「仏」なのだということなんです。
因果の法、あらゆることは「いま、ここ」です。「今、ここ」だけなんです。今を除いて何もないということなんですね。
だから道元禅師は、
と、言っているんですね。
つまり「今、ここを離れて何か目的を達成しようとしなくてもよい」と言っているんです。
寸分の差で、行き着く場所は天と地をほど違う
さて、以上を踏まえて本記事の内容に移りたいと思います。
まず、「然れども」というのは「そうではあるが」という意味です。
さきほどの「一超直入如来地」のように即座に、みんな仏の世界が開けてしまうということが本当であるのなら、皆何もせずに、のほほんと、ただ単布団の上に坐っていればいいんだなという風に思ってしまいそうです。
しかし「そうではない」ということなんですね。
我々は何もせずとも救われている、それは違うということなんです。我々は何もせずとも仏である、それは違うということなんですね。
ですから、「然れども」という言葉をお使いになっているのです。
そして、今の内容に関しての「毫釐も差あれば、天地懸に隔たり」という話に移っていくんです。先ほどの仏の真似事をする必要についての話になっていきます。
「毫釐(ごうり)」というのはこれは「寸法」という意味です。
「毫(ごう)」というのは「毫毛」という熟語にも由来していますが、「蚕」の吐く糸、この一本を「一毫」と言うんですね。
そしてそれが十本集まると「一釐(いちり)」と言います。
なので「一毫」というのは、「非常に細い僅かな」という意味なんですね。
ここで少し余談をお許しください。
これは少し前の話になりますが、2020年に小惑星探査機「はやぶさ」が、地球に無事帰還しました。
その「はやぶさ」が何をしたかと言うと、小惑星に行って、「生命の誕生」を探ったり、石を持ち帰ってきてくれたんですね。
「生命の起源」というのは、元々小惑星が地球に運んできたのではないかという推測がされていたんです。
そしてその証拠を探るために「はやぶさ」が飛び立って、小惑星に旅立だったんですね。
この「はやぶさ」は非常に遠い距離をこれから旅する訳ですが、出発する段階で中々発射できなかったんです。
天候の影響などがあったのかもしれません。
だったらもっと天気の良い日に、打ち上げをしたらいいのではないかと、我々素人は考えてしまいます。
しかしそうなると小惑星に辿り着けないというんですね。
仮に一日でも出発日が違えば、「到着する場所が全く違ってしまう」と言うんですね。
ほんのわずかな違いによって行き着くところが違うのですから、まさに「天地懸隔(てんちけんかく)」であります。
天地が懸かに隔たってしまう。
つまりこの「はやぶさ」において出発点がほんの少しずれただけで、天地の隔たりは非常に大きくなってしまうと言うのです。
この仏法の世界も同じく、「毫釐も差あれば、天地懸に隔たり」です。
同じように「坐禅」をしたとしても、そのやり方がわずかに違っただけで各段の差であるというのですね。
大きな差が生まれてしまうというのです。
またこれは別の話になりますが、とある集落のはずれに「お地蔵」さんがおりました。
そしてその「お地蔵」さんの前で、一生懸命手を合わせてる二人がいました。
一人の方は「どうか私の家に泥棒さんが入ってきませんように」と、一生懸命お祈りしてた。
しかしもう一方はというと、「どうか泥棒に上手く入れますように。今日は良い物品が手に入りますように。良い盗みができますように」と一生懸命お地蔵さんに手を合わせていたというんです。
同じような形でお地蔵さんに手を合わせていますが、まさにその行き着く所は「天地懸隔」であります。
またこれも別の話になりますが、「精進料理を食べる」言いますね?
実に感心なことです。
精進料理を一生懸命食べて、「坐禅」をすると言えばそれは実に感心なことです。
しかしそれで「泥棒」をしたならばとても感心できませんね。
精進料理を食べて「坐禅」をしたならば、これは「精進坐禅飯」になります。
しかし精進料理を一生懸命頂戴して「泥棒」をしたらそれはただの「泥棒飯」になってしまいます。
同じような精進料理を食べてもこれでは「天地懸隔」になってしまう。
「毫釐も差あれば、天地懸に隔たる。」つまり人間の思いによって何かを行ったならば、そこにはこの「差」が必ず生じてしまうんです。
全く異なってしまいます。
だから気を付けてくださいといわれるわけなんですね。
正しく坐禅を行うこと。それであれば仮に仏の真似事であっても仏であると。一寸坐れば一寸の仏であるということです。
しかし人間の狙い、悟りを得る手段としての誤った坐禅をしてしまうと、それは坐禅ではない、むしろ仏を殺してしまうことになると。
そうならないためにも正しく坐ることが大切であると、またそのためにも正しい坐禅の意義を捉えなさいということです。

海の量は一定だから、自分だけで大満足である
続いての、
という部分。
まず「違順」の「違」というのは、「違う」という事です。
そして「順」ですが、自分の思いに叶う事、「順じる」という意味で「順」と言います。
人間は生きていれば自分の思いが叶う事もあるし、叶わないこともある。
それはそれでいいんですね。
しかしそういった人間の思いによって、事を運ぶから「紛然として心を失す。」と言われるのです。
それが、
ということなんですね。
我々が「ああだこうだ」、思う事、この「思い」も生命の実物であり、自己の正体であります。
どんな「下卑」で「下品」な事を想像してもこれは生命の実物である。
自然と湧いてきた「思い」は生命の実物であります。
何故なら、この「思う」というのも「自分が行っていることではない」からです。
だからどんな恥ずかしい事がフッと浮かんできたとしても、それは「生命の実物」であります。
なんら恥ずかしい事ではありません。
なのでそれはそれでいいんです。
しかし、人間はそこからドンドン妄想を膨らませて、幻想をドンドン拡大していきます。
自然に湧いて来た「思い」を自ら追いかけて、幻想を拡大させてしまう。
こうなって自ら追いかけてしまうと、「自然の行い」ではなくなってしまう。
どんどん生命の実物から離れていってしまう。
その事実から離れていく事によって我々は狂い、苦しんでしまう。
なぜならそこには救いがないからです。本来であればこの世界は救いのみですが、その本来から遠ざかると、そこには救いがありません。
人間同士の概念のやり取りには行きつまりがあるのです。
自然に浮かんだ「思い」をそのままにしておけばいいものを、追いかけて幻想に振り回されていく。
それが、
「紛然として心を失す。」ということなんですね。
本来の在り方から離れていってしまう。
しかし本来の我々の世界の在り方、生命の実物というのは「不増不減」であります。救いのみです。
般若心経にも出てきますが、「不増不減(ふぞうふげん)」。
海の水は「増えもしなければ、減り」もしない。
常に「海の量」は一定です。
しかし我々は「海の波の部分」だけに振り回され、何かにつけては落ち込み、自分がすり減ったような気がする。
人格的にも減ったような感じがする。
或いは逆に宝くじが当たったり、嬉しい事があれば「有頂天」になる。
ただ「波」の表情に振り回されるだけの生活を送っているんです。
しかし有頂天になろうが、落ち込むことがあろうが、「生命の実物」は増えもしなければ、減りもしません。
「海の量」は一定なんです。
「海の量」は一定なのだから、他の兼ね合いに振り回される必要などないし、「自分」で十分な訳です。
「自分」だけで全てが足りておるわけです。
なので人間の思いによる「違順」、そのどちらにも振り回されないように日常生活を送ることが非常に大切だと言うんですね。
「命の実物」に常に立ち帰り、「違順」に振り回されないことが大切だと言うのです。
まとめ
今回は『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してきました。
それでは最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 我々の命は今立ちどころに仏の命を生きている、またそれを証明しているのが「坐禅」
- しかし寸分の狂いで、行き着く場所は天と地をほど違ってしまうのが我々の行い、従って坐禅の意義も正しく捉えなければいけない。
- 「思う」という行為は自分がやっていることではない
- 海の量は一定なのだから、自分だけで大満足である。
以上、お読みいただきありがとうございました。

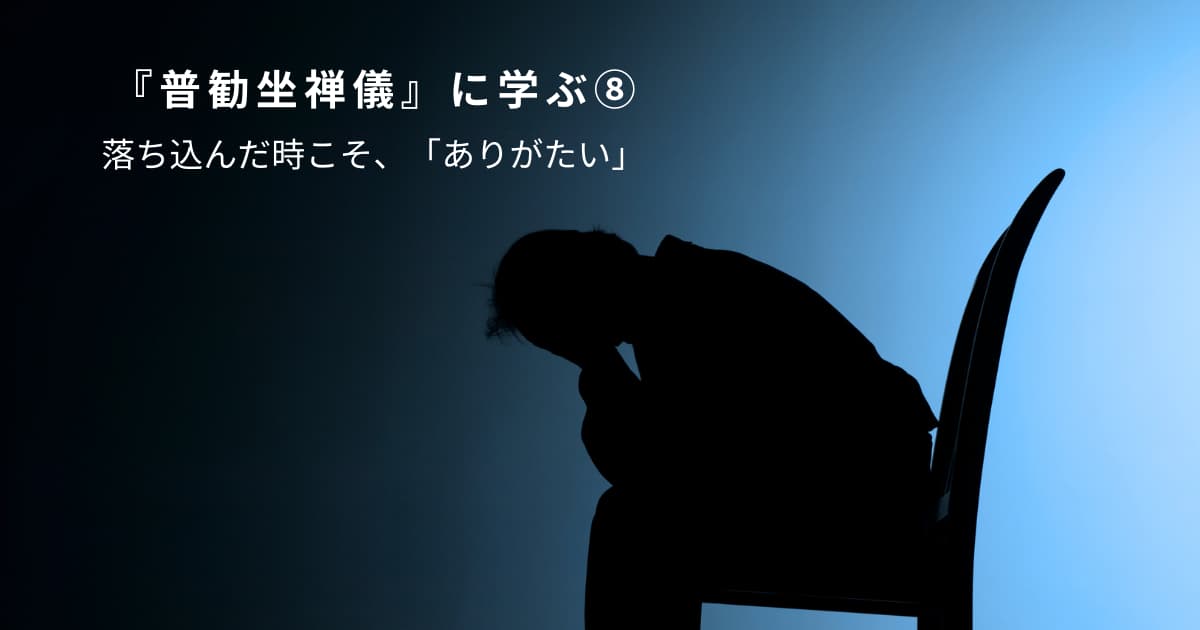
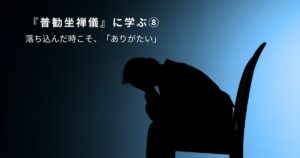
コメント