本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきたいと思います。
まず前回の、

のポイントを振り返りましょう。
- 「宗」とは大元、命の源という意味。
- 「乗」は一人も漏らさずみんなが乗れる乗り物。つまり大乗仏教の意味。
- 「宗乗自在」とは「生きながらに既にみな「仏(仏法)」という救いの世界にある」ということ。
- 「何ぞ功夫を費さん。」というのは、「それにもかかわらず何故、個人の救いを得ようとするのか」ということ。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事読み進めていきたいと思います。

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。
仏法は全体を説く
今回はこの部分を重点的に読んでいきます。
「況や、全体迥かに」というのはどういうことでしょうか?
「全体」というのは「仏法の真実」の事です。物事の「本来の在り方」とも言えると思います。
というのも、この世界というのは「一つなぎ」です。例えば今カラスの鳴き声が自分の耳を震わせるのはカラスの鳴き声が自分の耳だからです。つまりカラスが私だからですね。あるいは壁を殴れば痛くなるのも壁が自分だからです。スクランブル交差点で誰かと肩をぶつけた時自分が痛くなるのも相手が自分だからなんですね。
世界はこのように全て1つとして成り立っているんですね。世界というのは自分で、自分が世界。今ここの自分は世界と溶け合っているということなんです。
つまり我々が今ここに生きている事実の事を「全体」と言うわけです。
世界というのは常に「全体」なんです。2つとして分かれないんですね。
なのでこの世界に個人は存在できません。個人の考えも存在できません。
そもそも「概念」というものがこの世界には存在しないからです。
そのため個人の考えである、「俺が、わたしが」というのも存在せず、それは「全体」ではないということなんですね。
「仏法」はどこまでも全体を見ます。この世界の事実のことを説きます。その事実しかこの世界には存在しないからです。
話が前後しますが、この呼吸一つとっても「おれ」がやっているわけではありません。寝ている間にもそれは行われ、それに必要な酸素の供給も、市外いや、県外、あるいは国外から届いているものかもしれない。
命に境界線はなく「俺」という命に境界線はないのです。
消化もそうです。
「おれ」が寝ている間にも、きちんと食べたものを消化してくれています。
このように人間一つとっても「個人」がやっている事など何もないんですね。
それが事実です。この世界にはこの事実しかないわけです。
「仏法」はこの事実を非常に重んじます。
「個人」の話ではなく、「全体」を説くのです。
海全体を眺める
ここで少し余談をさせていただきます。
昔、宮城県の増島温泉という所に泊まった事があります。
その増島温泉のホテルに私の師匠でもある父と、父の御友人のお坊様方そして私を含む4、5人で泊まったんですね。
時節は非常に台風が来ておりまして、すぐに帰るのは危険ということでそのホテルへ泊ったわけであります。
またそのホテルは海に面した露天風呂が売りで、数多くの宿泊客から人気のホテルです。
私も夜その絶景の露天風呂に入ったわけですが、荒れ狂う波が台風の影響で目の前まで迫ってくる。
怒涛の波が露天風呂のすぐ傍まで来ている。
そんな中、お風呂にはいったわけですから荒波に吸い込まれるようなとても恐ろしい思いをしたんです。
その後一晩経ち、改めてお風呂に入ろうと思い、同じ露天風呂にはいりました。
すると昨日あのように荒れ狂った海が、今では穏やかに「鏡」のように静かになっている。
まっ平で本当に静かな波になっているんです。
昨日すぐそこまで押し寄せてた波がずっと下の方にあったんですね。
目の前に迫っていた波がずっと下の方に沈んでいる。
そしたら師匠の御友人である一人のお坊様が次のように言われたのが今でも印象に残っております。

海の水の量というのは太古の昔から一つも増えもしなければ、減りもしない。一定なんですよね。
その話を聞いて私はなるほどなと思い、何故かとても安心したの覚えております。
我々はいつもそうやって海の「波や凪」という表面的な部分に始終しております。
海全体を眺めるという事はまずありません。
表面的なものにいつも振り回されているのが我々人間であります。
例えば仏教に求める「転迷開悟」というのも、この波の表面と同じことをしているのです。
迷いを転じて悟りに至ることを「転迷開悟」と言いますが、これも人間の表面的なものを追いかけ回しているに過ぎないんですね。



修行をして、悟りを開けばもっと違う自分や世界と出会えるはずだ!
いつもそういう表面的なものに振り回されているのが我々人間です。
しかしそうではない。この世界は常に全体で、私もその全体の一部なんです。全体のみなんです。
個人の考えも、私自身も、その全体に溶けているんです。それが事実なんですね。
だからこそ、仏法はその「全体」を眺めます。
ここでいう「海全体」を見渡すんです。
表面的なものに始終するのではなく、全体を見ていく。
それしかないからですね。全体のみだからです。
そして道元禅師のおすすめになる「坐禅」こそ、その「海全体の行」なんですね。
世界と同時である私が今、確実に足が痛くなる坐禅を組む。すると私の命が動き出します。するとその私と同時の世界も動きはじめ、呼吸をはじめ、生きてくるわけです。
つまりこの坐禅が世界を私を呼吸させ、救う行にもなるわけですね。
また別の見方としてあるいは、坐禅を組むということは、足が痛くなるということ、何もせずともカラスやストーブの音が耳に聞こえてくるということ、隣の人の異臭が匂ってくること。
このどうしようもない真実の世界を行じているということになるわけです。2つと分かれない真実の世界に帰っている行とも言えるわけです。仏である我々が仏という本来の世界に帰っている。仏としているべき場所にいる。
本来のあり方とも言えるわけです。我々が本来常にいなければいけない場所。それが坐禅を組んだ世界なのです。
だから坐禅は仏の行と言われるわけですね。真実の行と言われるわけです。
坐禅そのものが「お悟り」なのです。
表面的な喜怒哀楽や、「転迷開悟」を追いかけるのは本来の「坐禅」ではありません。
全体を行じていくこと、真実を行じていくこと、これが「坐禅」なのです。
しかしこの「全体を行じる坐禅」というのが中々、人間には理解できないんですね。
迷いを悟りに転じるための坐禅の方が非常に分かりやすく思えるんです。
坐禅をすれば悟りを得られるぞ!と、そう思いたいのです。
しかしそれは「真実」ではないんですね。
何故なら「大自然」にはそのような「迷い」だとか「悟り」だとかがないからです。
我々の体にも「迷い」だとか「悟り」はないからです。
先程も言ったように、平気で呼吸したり、平気で消化しているこんなにも尊い体が我々にはすでにあるではありませんか。
我々はその救いのみの世界から「個人の命」という一線を画し、その救いから遠ざかってしまいます。
ざるでなんとか「水」を掬い上げようとしてしまうんです。
しかしそんなことをする必要はない。ざるを「水」につければいいだけなんです。それが坐禅なのです。
高祖様のお示しになるのはそういった坐禅です。
我々は常に「真実」なのです。救いのみなんです。全体の「坐禅」なんです。


全ては「この世で出会った客人」
「沢庵さん」という和尚さんがその昔おりました。
皆さんもご存知、あの「たくあん漬け」で有名な沢庵和尚です。
その沢庵和尚が説教の中で次のような話をしております。



此世の人、客に来たとおもへは、苦労もなし。心に叶ひたる食事にむかひては、よき馳走におもひ、心に叶わず時も、客なれは、ほめて喰わねはならす。夏の暑さをもこらへ、冬の寒さも、客なれは、こらへねはならす。孫子兄弟も相客と思へは、仲良く暮らして、あとに心を残さす、おいとま申すへくそうろう。
・此世の人、客に来たとおもへは、苦労もなし。
この世の人達が来たと言いますがどこから来たのでしょう。あの世から来たのか、お客さんとして来たのか。いずれにせよ来てくれたと思えば苦労はなし。
・心に叶ひたる食事にむかひては、よき馳走におもひ
心に叶った食事に出会えたならば、非常に美味しいご馳走に出会ったと思う。
・心に叶わず時も、客なれは、ほめて喰わねはならす
心に叶わない食事が出た時ですね、客人であれば褒めて食わねばなりません。お客さんですからね、こんなまずいもの食えるかとは言えない。褒めて食わなければなりません。
・夏の暑さをもこらへ、冬の寒さも、客なれは、こらへねはならす
お客さんである以上は夏の暑さにも、冬の寒さにも耐えなければならない。
・孫子兄弟も相客と思へは、仲良く暮らして、あとに心を残さす、おいとま申すへくそうろう
孫や子供、兄弟も相客である。隣合わせた客人であると思えば、仲良く暮らし、時が来れば、名残惜しいなと思わずにさらっと去っていくのがよい。
またそれ以外にも、



たらちねに よばれて仮の客に来て 心残さず 帰るふるさと
という和歌も残されております。
「たらちね」というのは母親に対する掛け言葉ですが、「父母に」と言ってもいいと思います。
父と母に呼ばれてこの世のお客人としてやってきた。 しかし我々にはちゃんと帰る故郷がある
という意味です。
沢庵和尚は言います。
「どんな事に出会ってもこの世で出会った客人と思えばいい」と。
不味い物を出されてもそれは「お客さん」、地獄のような辛い経験に出会ったとしてもそれも「お客さん」である。
どこに行っても「お客さん」であるし、お客さんであるならば、どんなことにも耐えなければなりません。
ありがたくその提供されたものを頂かなければなりません。我々はこの仏の世界のお客様なのです。



たらちねに よばれて仮の客に来て 心残さず 帰るふるさと
しかしそんなことを忘れ、我々はいつも表面的な波の部分に振り回されてしまう。
「世界」は「全体」だけなんですね。
壁を殴れば痛い。
「おれ」が寝ている間にも食べたものが消化されている。
木々が出してくれる「酸素」のおかげで呼吸が出来ている。
そのように「ここからここまでが俺の命」という線引きができないんです。
全てが「俺一杯」なんです。
見えている表面上の「波」も「海」なんですね。
「人間の悩み」も「全体」なんです。
「全体の一部」でしかないんです。
目の前に展開するのはただひたすらな「全体」なんです。
そういう全体を我々人間は生きているんです。
ここで沢庵和尚が言う「ふるさと」というのが、「全体」であり、「仏の命」と言えるでしょう。
だから「坐禅」は「全体」を行じているんですね。
「転迷開悟」の手段として用いられるのが「坐禅」ではなく、全体を行じているのが「坐禅」なんです。
全体を全体していく「坐禅」なんです。
つまり我々の「命」そのものがこの「坐禅」であります。
なので今回の、
というのは、「言わずとも坐禅はただひたすらに全てである」ということです。
命の「全体」を行じる道元禅師の坐禅
今回は、『普勧坐禅儀』の
という部分を解説してきました。
短い内容ですが、重要な部分となります。
- 「全体」というのは仏法の真実の事。
- つまり「全体」とは今ここに生きている事実の事を「全体」と言う
- 道元禅師のおすすめになる「坐禅」は転迷開悟の「手段」としての坐禅ではなく、「全体」の「坐禅」。
- 目の前に展開するのはただひたすらな「全体」。
- 「全体」以外ない。
- つまり坐禅も手段ではなく、ただひたすらに「全体」でしかない。
最後までお読みいただきありがとうございました。

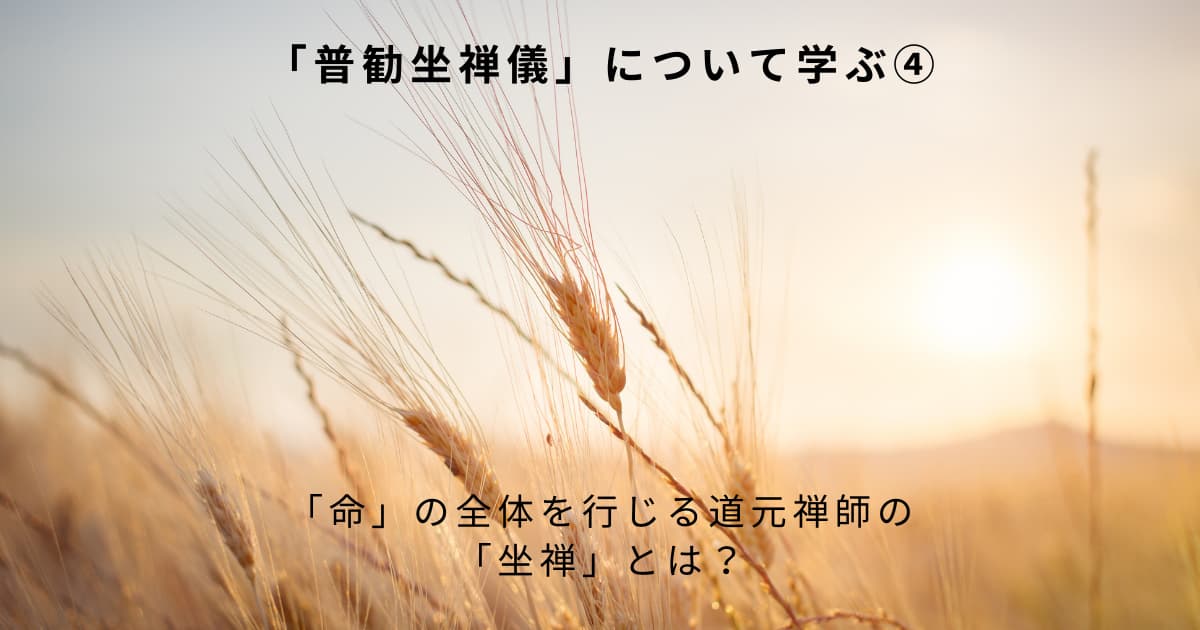

コメント