本記事をもちまして、この『普勧坐禅儀』の講話は最後を迎えます。第「50回目」です。
ここまで連載してこれたのも、日々このblogをチェックしてくださる皆様のおかげです。
心より御礼申し上げます。

普勧坐禅儀を終えるにあたって
この『普勧坐禅儀』は今回の「50回目」でひとまず最後になります。
ひとまずと言ったのは、これまでのブログでお伝えしてきている部分は『普勧坐禅儀』における「触り」の部分とも言えるほど、浅いものだからです。
それは私がこの『普勧坐禅儀』を未だきちんと理解していないことが原因です。
私はこれからもこの『普勧坐禅儀』の参究を重ねていかなくてはならないと思っているし、各所で参禅や勉強をしていくつもりです。今後そこで得た知識や感じたことをこの「道元禅師の旅」で投下していくつもりなので随時、この『普勧坐禅儀』はこれからも話題にはあがってくると思います。
楽しみにしていてください。
さて、この『普勧坐禅儀』、元より「道元禅師」を学ぶためには「人生」をかけなければなりません。
何故なら「道元禅師」を学ぶと言うのは「真実」を学ぶという事に等しいからです。
当然、恐喝じみたことを言ってすみません。読者の皆さんはそのような意気込みで読みたいと思っていないのは重々知っておりますし、これからもただ何となく読んでいただければと思います。
しかし、
「何故人は生きなければならないのか?」
「何故私はこの世に生を受けたのか?」
「人の真の生き方とは何なのか?」
こういった疑問は生きていれば誰しもが抱えるはずです。
いわゆる人生の「テーマ」ですね。
そしてその疑問を誰しもが解決したいと願うはずです。
ただ何となく生きている人でも、この疑問からだけは逃れられないんですね。
「気楽にいきていこー」とか「小さい事は気にするな」とか「生きている意味なんて考えてる暇ないんだよ!」とかそういった考えは勿論かっこいいし、素敵です。
そしてそうやって生きていける人はどこか魅力的ですしね。
しかしそういった人でも必ず考えるんです。
僧侶であっても、一般人であっても、大統領であっても、アーティストであっても。
ヨーロッパの人であっても、アラブの人であっても、南米の人であっても。
誰しもがふとした時に立ち止まり、先ほどのような疑問を必ず抱くんです。
何故なら「僧侶」であっても「一般人」であっても同じ「命」を生きているわけですからね。その命において、先ほどの疑問は必ず生じる通過儀礼なのです。避けては通れない試練なんですね。
我々はその試練にきちんと立ち向かい、「決着」を付けなければなりません。
そこで必要になるのが、道元禅師の「教え」なのです。
人は生まれながらにして仏であるのに何故修行しなければならないのか?
道元禅師は幼いながらに、このような「疑問」を抱かれました。
幼い子供からすれば非常に大きな問題だったと思います。同時に道元禅師の器量が伺われるわけですが、この問題を解決できる人間が当時の道元禅師の周りには誰一人いなかったわけですね。
これは個人の悩みではなく、人類そのものの悩みとも言えるほどの強大な問題だからです。またそれを解決できた時、我々人間に本当の意味で安寧が訪れるはずです。
そこで中国へとわたり、正師とも言える「如浄禅師」とまみえ、身心脱落なるお悟りと出会います。坐禅こそがその身心脱落であると。この坐禅の尊さを学ばれたわけですね。坐禅こそ究極の解であると、坐禅こそが「安楽の法門」であるということを知ったのです。
帰朝の際にはかの「眼横鼻直」という言葉も残されております。
我々は元より悟っており、この世界に1つとして悩めるものはいない。全て真実むき出しで、この上ないあり方として形をなしている。それが全てこの自己の命と共にある。
中国で道元禅師はこのことを知ったのです。
以来、道元禅師のお伝えになる話にはこうしたことがしきりに出て参ります。
我々が従いゆくべきはこの道元禅師の教えなんですね。これは誰もに共通する大自然の教えだからです。我々は仏であり、その仏の教え、真実の教え、それが道元禅師の教えだからです。
なぜ生きるのか?生きる理由は?
時代は変わっても、人間には必ずこの問いが生じます。
しかしその悩みすらも大自然の導き、大自然の命なのだということ。この私も、その私の悩みすらも全て大自然の所有だということ。
普通そんなこと思いもよりませんよね。そういう人がほとんどのはずです。
足を組むと痛くなる。それは紛れもないこの世界の真実です。この世界の正体です。
あるいは今こうしている間にも、鳥の声が聞こえ、車の走る音が聞こえ、呼吸をし、色彩豊かな緑が見えてくる。
我々は紛れもなくこの世界の真実の命をいただいているんです。これ以上も以下もない命を常にいただいているんですね。常に世界の真実と共にあるわけです。だからこうして1秒ごとに老化していく。
気づこうが気づかまいが、我々は救われないことがない。生きている以上救われないことがない。
それに気づかせてくれるのが、坐禅、あるいは道元禅師の教えであるわけです。
我々はいつの世も悩んでばかりいます。救いとは何か、本来の生き方とは何か。しかしそれを求めることは、水の中にいることに気づかず、ざるでどうにか水を掬い上げようと、もがいているようなものなんですね。
この足の痛み。我々は常に仏のみの世界にいるわけですから、そこを出ようとしないで、ただその世界にいればいいのです。それがただ坐るということです。
我々が本来の世界で生きること、真実の命を生きること。それが坐禅なのです。
なので道元禅師はこの『普勧坐禅儀』でもって「只管打坐」を推奨されるわけですね。
このブログもそうですが、道元禅師を学ぶということはこういうことを学ぶわけです。学んでいるわけです。
真実のこと。本来のこと。
とてつもなく巨大なものに我々は立ち向かおうとしているわけです。
相当な覚悟が必要です。先ほども述べたように人生をかける必要があります。
これまでもこれからも、多くの人々の支えになる「道元禅師」。
私のような人間が「道元禅師」について語れることはほんのわずかしかありません。
しかし私自身「死ぬ気」で今後もこの「道元禅師」に関して学びを深めていく所存で、これからのあなたの人生が少しで豊かになればという思いで今後も「発信」し続けて参りたいと思います。
これからますます精進してまいりますので、今後もどうぞこの「道元禅師の旅」を温かい目で見守ってくださればと思います。
今回この「50回目」でこの『普勧坐禅儀』は一旦終わりますが、「道元禅師の旅」は随時、亀のスピードで更新してまいりますので、たまにチェックしてみてください。
前置きが本当に長くなりました。
それでは『普勧坐禅儀』、第「50回目」の参究に入って参りましょう。
宇宙一杯、これに尽きる
さてまずは本記事の内容に入ってく前に前回の、
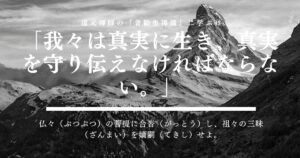
のポイントをおさらいしたいと思います。
- 「三昧」とは「坐禅」をさす。
- 祖師方が伝えられてきたこの仏祖正伝の坐禅を守りながら正しく受け継ぐ人にならなくてはならない
- つまり、我々一人一人が「真実」に生きなければいけない。
- 自我に振り回される、これが人間が陥っている病。
- 自我は実存しない。
- 自我が無くても呼吸ができる、自我が無くても食べたものを消化できる。
- 足が痛くなるは「作り物」ではない。
- 我々はこの「本物」を拠り所とし、それを実践し、守り伝えなければならない。
前回も非常に色濃い内容でした。
まだチェックがお済みでない方は、是非この機にチェックしてみてください。
さて、いよいよ本記事を持ちまして『普勧坐禅儀』のお話は最後になります。
せっかくですので最後に今一度、『普勧坐禅儀』全文に目を通してみましょうか。
原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。矧(いわ)んや彼(か)の祇薗(ぎおん)の生知(しょうち)たる、端坐六年の蹤跡(しょうせき)見つべし。少林の心印を伝(つた)ふる、面壁九歳(めんぺきくさい)の声名(しょうみょう)、尚ほ聞こゆ。古聖(こしょう)、既に然り。今人(こんじん)盍(なん)ぞ辦ぜざる。所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。
夫れ参禅は静室(じょうしつ)宜しく、飲飡(おんさん)[飲食(おんじき)]節あり、諸縁を放捨し、万事を休息して、善悪(ぜんなく)を思はず、是非を管すること莫(なか)れ。心意識の運転を停(や)め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて、作仏を(と)図ること莫(なか)れ。豈に坐臥に拘(かか)はらんや。尋常(よのつね)、坐処には厚く坐物(ざもつ)を(と)敷き、上に蒲団を用ふ。或(あるい)は結跏趺坐、或は半跏趺坐。謂はく、結跏趺坐は、先づ右の足を以て左の![]() (もも)の上に安じ、左の足を右の
(もも)の上に安じ、左の足を右の![]() (もも)の上に安ず。半跏趺坐は、但(ただ)左の足を以て右の
(もも)の上に安ず。半跏趺坐は、但(ただ)左の足を以て右の![]() (もも)を圧(お)すなり。寛(ゆる)く衣帯(えたい)を繋(か)けて、斉整(せいせい)ならしむべし。次に、右の手を左の足の上に安(あん)じ、左の掌(たなごころ)を右の掌の上に安ず。兩(りょう)の大拇指(だいぼし)、面(むか)ひて相(あい)拄(さそ)ふ。乃(すなわ)ち、正身端坐(しょうしんたんざ)して、左に側(そばだ)ち右に傾き、前に躬(くぐま)り後(しりえ)に仰ぐことを得ざれ。耳と肩と対し、鼻と臍(ほぞ)と対せしめんことを要す。舌、上の腭(あぎと)に掛けて、脣歯(しんし)相(あい)著け、目は須らく常に開くべし。鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。
(もも)を圧(お)すなり。寛(ゆる)く衣帯(えたい)を繋(か)けて、斉整(せいせい)ならしむべし。次に、右の手を左の足の上に安(あん)じ、左の掌(たなごころ)を右の掌の上に安ず。兩(りょう)の大拇指(だいぼし)、面(むか)ひて相(あい)拄(さそ)ふ。乃(すなわ)ち、正身端坐(しょうしんたんざ)して、左に側(そばだ)ち右に傾き、前に躬(くぐま)り後(しりえ)に仰ぐことを得ざれ。耳と肩と対し、鼻と臍(ほぞ)と対せしめんことを要す。舌、上の腭(あぎと)に掛けて、脣歯(しんし)相(あい)著け、目は須らく常に開くべし。鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。
所謂(いわゆる)坐禅は、習禅には非ず。唯、是れ安楽の法門なり。菩提を究尽(ぐうじん)するの修證(しゅしょう)なり。公案現成(こうあんげんじょう)、籮籠(らろう)未だ到らず。若(も)し此の意を得ば、龍の水を得たるが如く、虎の山に靠(よ)るに似たり。當(まさ)に知るべし、正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、昏散(こんさん)先づ撲落(ぼくらく)することを。若し坐より起(た)たば、徐々として身を動かし、安祥(あんしょう)として起つべし。卒暴(そつぼう)なるべからず。嘗て観る、超凡越聖(ちょうぼんおつしょう)、坐脱立亡(ざだつりゅうぼう)も、此の力に一任することを。況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
凡(およ)そ夫れ、自界他方、西天東地(さいてんとうち)、等しく仏印(ぶつちん)を持(じ)し、一(もっぱ)ら宗風(しゅうふう)を擅(ほしいまま)にす。唯、打坐(たざ)を務めて、兀地(ごっち)に礙(さ)へらる。万別千差(ばんべつせんしゃ)と謂ふと雖も、祗管(しかん)に参禅辦道すべし。何ぞ自家(じけ)の坐牀(ざしょう)を抛卻(ほうきゃく)して、謾(みだ)りに他国の塵境に去来せん。若し一歩を錯(あやま)らば、当面に蹉過(しゃか)す。既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。仏道の要機を保任(ほにん)す、誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん。加以(しかのみならず)、形質(ぎょうしつ)は(た)草露の如く、運命は電光に似たり。倐忽(しくこつ)として便(すなわ)ち空(くう)じ、須臾(しゅゆ)に即ち失(しっ)す。冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ。直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ。久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし。宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。
こうして今パッと見ただけでもこの『普勧坐禅儀』は本当に難解の書であったことがわかります。
皆様のご理解力と参究心に感服いたします。
さて、今回の、
この部分を端的に言うと、
我々が行じている「坐禅」は、宇宙一杯と繋がった「行」である
ということです。
「大自然と一つの坐禅」、「宇宙一杯の坐禅」であるというんですね。
これまでの解説でも「大自然」だとか、「宇宙一杯」だとか沢山出て参りましたが、最後の段でもやはりこの部分が出て参ります。
最後までこのような話題になるのは、『普勧坐禅儀』で道元禅師が言いたい事は「宇宙一杯」、この一言に尽きるからなんです。
なので今回最後だとしても、懲りずにその「最重要部分」に関して解説をさせていただければと思います。
今まで以上に言葉に熱を込めていきますので、少し暑苦しく感じるかもしれませんがお付き合いください。
どこまでも「俺一杯」

我々はいつも「自我」というものを持ち出し、「宇宙」と「自分」の間にそれを挟んで物事を「認識」しております。
つまり物事の正体を「自我という認識」をもって捉えようとするんです。
しかしこの「自我」や「何かを認識する」という作業は我々の頭を使って行われる「概念遊び」でしかないんですね。
例えば「赤い物をもってきてください」と言えばAさんは「リンゴ」をもってくるが、Bさんは「トマト」をもってきたり。
「黄色い物をもってきてください」と言えば、Aさんは「とうもろこし」をもってくるが、Bさんは「パプリカ」をもってきたり。
このようにそれぞれ人の価値観や過去体験に基づき、「赤い物」の「正体」は変わるんです。
要はここで両者が「正体」だと思っているのは単なる「認識」でしかないんです。
つまり「認識」でもっては「赤い物」の正体を永遠に突き止めることはできないにもかかわらず、その「認識」が全てだと我々人間は思っているんです。
そしてこのように「宇宙」と「自分」との間にこうした「自我認識」を挟むから大きな間違いが生まれてくる。
本来人間の「認識」では物事の正体とはとらえられないんですね。
言い表せないんです。ベクトルがあっていないとも言えるでしょう。物事の本質に関与していない。それが人間の自我意識です。

しかしそれら物事の正体を正しく突き止めているものがあります。
それが「坐禅」です。
坐禅をすると足が痛くなります。それは誰かに比べてやや痛いとか、もう少し痛いとか、これだけ痛いとか、そういう痛みではありません。とにかく痛い。真剣に痛い。痛いから痛い。つまり正真正銘の出来事であるわけです。正真正銘のこの世界の出来事、この世界の命だということです。
どんなに偉い人であろうと、頭の良い人であろうと、外国に人であろうと、「自我認識」や「価値観」、「過去体験」など関係なしに足が痺れる。
このように「坐禅」は「命の正体」を捉えていることが分かるんです。「この世界の正体」、つまり真実をとらえているんですね。
「人間の正体」を行じているんです。この世界の正体を行じている。
また本来この世の全ては「宇宙と一つ」なんですね。例えば鳥の声がこうして聞こえるのも、鳥が自分の耳を震わせるからです。つまり鳥によって自分の命が起こされるからなんです。鳥が自分だということです。
世界と私とは常に1つなんです。1つだから鳥の声が聞こえるし、自動車の音が聞こえるんです。1つだから冬の寒い日にブルッと体が震えるんです。1つに溶け合っているからこうやって老化していくわけですね。
つまり世界とはこの自己なんです。世界とはこの自己の展開なんです。
だからどこにいっても宇宙と1つの自分しかいないんですね。宇宙と1つということは「俺」がないんです。
どこまでも「宇宙一杯」。
「俺一杯」なんです。
- 足を組めば痛い。
- 無意識のうちに呼吸をすってはいている。
- 食べたものを寝ている間にも消化してくれる。
そういった「宇宙」と「自分」に際限のない命、隔たりのない命。
「ここからここまでが俺の命」という線引きが一切できない宇宙一杯の命を我々は今こうして生きているんです。宇宙一杯だから「自我」などというものはあるはずがないんです。
そこで、全世界が自己とも言える世界において、自分が坐る。坐禅をする。すると世界が坐る。坐禅をするのです。自分の命が動く。世界の命が動く。世界が動きだすのです。
これが先ほど述べた、あらゆる物事の正体が「今、ここ、この自分の坐禅」につながっているというわけです。
全ては今、ここ、この自己。そしてその自己を自己たらしめている「坐禅」なんですね。今、ここ、この坐禅が物事、全てを包括しているんです。
ややもすると、自分が坐るということは自分のみならず世界が救われるということなのです。
世界とは自己、世界はすべていま、ここ、この自己の展開なんです。今あなたが置かれている状況は自己に出会っているということ。これからあなたが出会うのも全て自己だということです。
言い当てられないのが「真実」であるのなら言い当ててはいけない
さて、今述べたことを抑えて今回の内容にもある「久しく恁麼(いんも)なることを為さば、」という部分に参りましょう。
ここで道元禅師が言っているのは「坐禅」はこの「恁麼」を行じているということなんです。
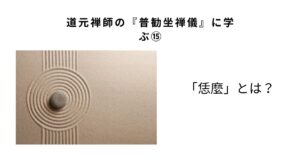
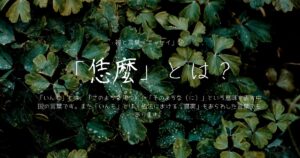
そもそも「恁麼」というのは中国における昔の「俗語」で、「このもの」という意味。
何とも名前が付けられないものをこの「恁麼」と言います。
夕飯の席で「悪いがアレとってきてくれ」の「アレ」ですね。
しかしこれで正しいんですね。
何故ならこれまで述べたようにどのようなものにも「正確な名前」はなく、「正確なもの」だと思っているのは単なる人間の「認識」に過ぎないからです。
「赤い物」を「リンゴ」といったり「トマト」と言ったりですね。
それは人間同士の「概念遊び」に過ぎないからです。人間の自我意識では決して物事を正しく捉えられないからです。
そもそもあらゆる物事というのは、今、こうしている間にも姿形を変えております。今のチョコレートと、1秒後のチョコレートとは全く同じものではないわけですね。人間がそのものの正体を言い当てようとしようと思ってもそれは本来不可能だということです。
そのことを「恁麼」というんですね。本来なにものにも名前は付けられないということです。
すなわち、この「坐禅」においてもこの「恁麼」を行じているというんです。
先ほどあそこまで熱く解説した「宇宙一杯」だとか「真実」だとか「俺一杯」というものも、これも所詮は「認識」に過ぎません。単なる言葉遊びなんです。
結局、「宇宙」だとか「真実」だとか「自己」を言い当てようとしてもそれは無理なんです。
正しく表現するために、この「恁麼」なんですね。
我々が生きているこの「自己」も「生命の実物」も「恁麼」だということです。
言い当てられないのが「真実」であるのならば、言い当てようとしてはいけないし、そもそも言い当てる事ができないんです。
この「アレ」をひたすら行じていくだけなんです。
我々の正体は如来
また「何者か恁麼来」という言葉がある。
これは六祖慧能禅師の所に弟子の南嶽懐譲禅師が初めてやって来た時のことです。
「お前さんは一体ナニモノか?」と弟子の南嶽懐譲禅師に聞くんですね。
「一体ナニモノがやってきたんですか?」と聞くんです。
それから6年間もの間、弟子の南嶽懐譲禅師はそのことを考えながら修行に励むんです。
「何者か恁麼来」と聞かれたが一体どういう意図のなのか?
何者か恁麼来
これは一体どういうことなのか?
例えば「はい、私は○○会社の従業員です。」とか「はい、私は○○寺の住職です。」とか「○○ちゃんのお父さんです」といってもそれは所詮、他との兼ね合いで生まれた「認識」に過ぎません。
先ほど述べた「認識」ですね。
「私には財産が1000万円あります」といってもこれも他との兼ね合いに過ぎません。
つまり他との兼ね合いがあるから「言い表せる」んです。
しかしこの世界は先ほども申し上げた通り「宇宙一杯」、「俺一杯」ですから他との兼ね合いになんてものは何一つないんです。
だから言いあらわせないのが当たり前なんですね。
つまり何が言いたいのかというと、ここでは「何者か恁麼来」。これがそのまま答えになっているんですね。
我々一人一人の命は「恁麼来」として生まれて来た。ですから「恁麼来」のことを如来と言うんですね。
「来るが如く」と書いて「如来」ですが、「阿弥陀如来」とか「釈迦如来」というのはみんな「恁麼来」です。
我々一人一人も「如来」。
「恁麼が来るが如く」です。
「我々の命」、「自己の正体」というのは「何者か恁麼来」なんです。
他との兼ね合いではなく、宇宙一杯の命を生きているから「何者か恁麼来」でいいんです。
「恁麼来」じゃなかったら、あるいは言い表せてしまったら、それは間違いなんですね。真実ではないのです。
繰り返しになりますが他との兼ね合いや「自我」が宇宙と自分との間に入りこむと、間違いが生じる。
本来二つにわかれないこの世界を無理に二つに分けようとするわけですから、間違いだらけの人生になるんです。
本来「恁麼」であるものが「社長だ!」とか「有名人だ!」とか言うから変になるんです。
なので「久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし」とあるのは、その「恁麼」を知っていればそのような間違いをせずに済むということをここで言っているんですね。
道元禅師がは「そこをどうか間違えないでくださいよ」というわけなんです。
本当の宝は自分自身
すみません、ここまで畳みかけるように話してきてしまっておりますが、先に進ませていただきます。
続いての、「宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。」というのは、「宝物が自ずから開けて、自由自在に使う事ができる」という意味になります。
禅の言葉に、
門より入るものは家珍にあらず
という言葉があります。
これは「本当の宝物というのは、門から入るものではない」ということを言っているんですね。
「家の門」とか「山門」とか、そういう出入り口から入るものは本当の宝物ではないというんですね。
ここでいう「家珍」、つまり家の宝物というのは「自分自身」にあると言っているんです。
外から出入りするものは「家珍」ではないと。
例えば、家の家宝というものは大体はご先祖様がどこからか手に入れたものをその家の家宝にするというのが習わしです。
しかし禅の世界では「門より出入りするものは家宝ではない」と言うんですね。
「自ずから開けている」というんです。
ここで「宝蔵自(おのずか)ら開けて、」とあるのは、みんな自分自身に宝物を持っているというんですね。宝物とは自分の内側にあるという話なんです。
そして「宝蔵自(おのずか)ら開けて、」というのは「自分自身で持っている宝物が恁麼を行じることによって自ずと開けてくる」というんですね。
ここで言う「恁麼」というのは先ほども出てきましたが、「坐禅」のことです。
あるいは「宇宙と一つに繋がった」この命のことです。
先ほど全てはこの自己の展開だという風に言いました。宝物でもなんでも、この自己にこそ、それがあるわけですね。見つめるべきはこの自己だけでいいのです。
我々は宝物というと、外にあるものだと思いこんで貪り歩いている。
しかし貪り歩いている限り、それは「貧しい」んですね。
この世界では「自分が自分を自分している、自己の展開」だけですから、誰も貪り歩く必要などないんです。自分が自分すること。これに勝るものはないのです。これ以上の価値、これ以上の宝はないのです。
あるいは我々は何ももっていなくても平気で笑う事ができます。平気でお腹が空く。指をきればちゃんと血が出てくる。
絶対的な命をいただいているわけです。こんな恵まれた命を誰しもが持っているんです。
一体それに加えて何を欲しがるのか?そのことをきちんと踏まえられれば、「受用(じゅよう)如意(にょい)ならん」。
もう自由自在であると。
自由自在に平気で生きていけると。本当の「宝」は自分自身なんです。
西郷隆盛は「金もいらぬ、命もいらぬ、名もいらぬ人はどうすることもできない、お手上げだ」と言うんですね。
そういう人は真に自由だから従える事ができないし、利用することができないというんです。
道元禅師は中国での修行を終えて、日本に帰られてから有名になられました。
またこれから「真の仏法」を世の為に広めているということでそれを聞きつけた当時の天皇から紫の衣を授かるはずでした。
しかし道元禅師は一切その紫の衣を受け取ろうとしなかった。
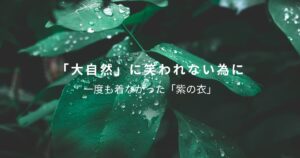
何故なら紫の衣というのは他との兼ね合いの話であるし、「宝蔵自(おのずか)ら開けて、」ということを道元禅師は知っていたからなんです。
「紫の衣」のような他との兼ね合いによって評価されるもの、もしくは他との兼ね合いによって評価される人生を放棄すれば、「受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。」本当に人が自由な人生を歩むことができるということを知っていたからなんです。
このような思いが、この『普勧坐禅儀』の最後の締めの言葉になっているんですね。
道元禅師は「本当の宝」は、「自分自身」だということを『普勧坐禅儀』を通してお伝えになられたかったのだと思います。
この不安でたまらない時代。
そんな時代において「足が痺れてくること」、「寝ている間にも食べたものを消化している事」そのような当たり前の事が本当の安心なんだと、本当の救いなのだということです。
なので我々人間は何よりも、「自分自身」をこころのよりどころにするべきなんだとそう思えてくるわけであります。
もっと自分を大切にしなければと、そういう思いがしてくるわけであります。
最後に
さて以上でこの『普勧坐禅儀』も終わりになります。
最後はうまく話をまとめられなかったかもしれません。
ただ大まかな点はお話できたのではないかと思います。
「坐禅」に関するやりかたにおいては現代にも実に様々なやりかたが広まっております。
そんな中、この道元禅師による『普勧坐禅儀』というのは「普く勧める坐禅」です。それは誰しもが行じることのできる坐禅だとお説きになっているのです。
どんな宗教を信仰していてもいい、会社員でなくてもいい、男でもいい、子供でもいい、明日死ぬ命でもいい。
道元禅師のおすすめになる坐禅は「だれでもかれでも行える坐禅」で、「だれでもかれでも行うべき坐禅」です。
なぜなら「坐禅」は宇宙一杯の行だからです。他との兼ね合いを放棄した「真実」だからです。
我々の命や、我々の生きる世界は本来他との兼ね合いでなりたっているわけではなく、この大自然の所有です。大自然に生かされているのです。仏の命として宇宙一杯に繋がっております。
我々はただこの仏のみの世界で、ただ生きていればいいのです。坐禅を通し、そこにい続ければいいのです。
ただ生きていればいい。生きているだけで誰もが救われないことがない。誰もが救われている。そのことに気づかせてくれるのが坐禅であり、道元禅師の教えです。
我々はこれからも生きていかねばなりません。どんな境遇だろうとです。
なぜ生きるのか?
これは、言い方を変えれば「何が正しい生き方なのか?」ということです。
足を組めば痛いこと。この世界に、これ以上の真実以上の真実はありません。これ以上の正しさはありません。この世界の真実、正しい命、これが坐禅なのです。
なのでこの坐禅をすること、そして生まれたからには可能な限り坐禅をし続けること。これが我々にとって正しく生きるということです。
そしてこれが「なぜ我々は生まれながらに仏なのに修行が必要なのか?」に対する答えです。
生きていくということは坐禅をするということ、しなければならないということです。この坐禅が真実の家、本来の体、その体の呼吸だからです。
呼吸をするために、坐禅をするのです。生きるために坐禅をするわけです。
我々が生きること、それは坐禅することです。修行をするということです。
最後はかなり乱暴なまとめになってしまいました。
ここまで50回にも及ぶ連載をご愛読いただきまして本当にありがとうございます。
次回会える日を楽しみにしております。
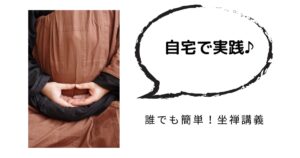
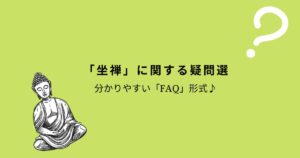

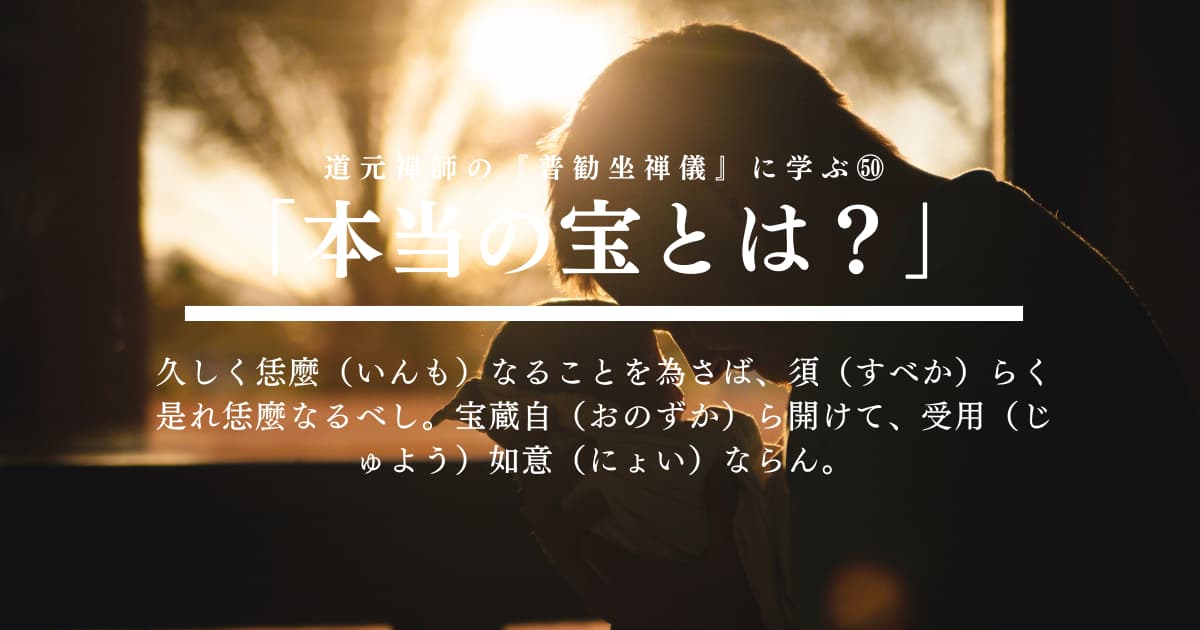

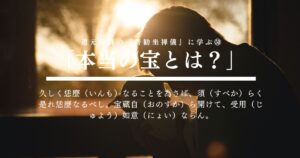
コメント