本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を解説していきます。
まず初めに前回の、

のポイントを振り返りましょう。
- 「直指」は「認識」とは違う。
- 「直指」とはその人が持ち合わせる知識や価値観などの障害物なく、直接実物を見る事、生命の実物にであうこと。
- 「坐禅」こそまさに「直指」で、「直指端的の道」である。
- そしてその「直指端的の道」に励む人を「絶学無為の人」という。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
唯、打坐(たざ)を務めて、兀地(ごっち)に礙(さ)へらる。万別千差(ばんべつせんしゃ)と謂ふと雖も、祗管(しかん)に参禅辦道すべし。何ぞ自家(じけ)の坐牀(ざしょう)を抛卻(ほうきゃく)して、謾(みだ)りに他国の塵境に去来せん。若し一歩を錯(あやま)らば、当面に蹉過(しゃか)す。既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。仏道の要機を保任(ほにん)す、誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん。加以(しかのみならず)、形質(ぎょうしつ)は(た)草露の如く、運命は電光に似たり。倐忽(しくこつ)として便(すなわ)ち空(くう)じ、須臾(しゅゆ)に即ち失(しっ)す。冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ。直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ。久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし。宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。
終わり
運営者からのちょっとしたお知らせ
本記事でこの『普勧坐禅儀』の連載も第49回目を迎えます。
いよいよこの『普勧坐禅儀』も終盤にさしかかって参りました。
今回の49回目、そして次回の50回目という節目を持ちましてこの『普勧坐禅儀』の提唱は終わりになります。
ここで一度お礼を申し上げたいと思います。
ここまで長きに渡り、お付き合いいただきありがとうございました。
またここで少し宣伝もさせて頂ければと思います。
というのもこの『普勧坐禅儀』に関する連載は次回の50回目で一度終わりを迎える訳です。
これまで実に多くの『普勧坐禅儀』について記事を書いて参りました。
過去記事においてかなり読みにくいものがあったせいか、「何がいいたいのか話の趣旨が分からない」といった声を多方面から多くお寄せいただいております。
それほどまで大変多くの皆さんが真剣にこの『普勧坐禅儀』と向き合って頂いているという事に気づき、ありがたくも感じているのと同時に、自分の発信にもっと責任を持たなければという思いに至ったわけであります。
そこで次回の『普勧坐禅儀』の執筆を終えたら一度「リライト(書き直し)」という工程に入って参りたいと思います。これまでの記事の中では、難解な部分や表現がわかりづらい部分などが多くありますので、そこを見直していきます。
これまで読んだ過去記事の中でよくわからなかったという箇所があったという人も、折につけ是非再読していただければと思います。
一緒にもっとこの『普勧坐禅儀』を参究して参りましょう。
その際、何の記事が最新にリライトされたかは、トップページ最上の「記事スライダー」で確認できますので、是非毎日このブログをチェックをして頂ければと思います。
またその際、次のような機能をご用意しました。

これはこの「禅の旅」内にある記事を特定のキーワードごとに配列したものですが、例えば「達磨さま」という見出しを参考にすれば、「達磨さま」の記事をそこで確認することができ、そこから関連する記事を読み進めることができます。
このブログを通してこれまでに分からなかった内容を解消するためにぜひ活用して欲しいです。
かなり便利な機能になっているので、過去記事を振り返る際などに是非ご活用ください。
これからも多くの記事をこの「禅の旅」では投稿していきます。是非これからもこの「禅の旅」を宜しくお願いいたします。
人間が陥っている病

それでは、気を取り直し本記事を参究してまいりましょう。
今回はこの部分を読んでいきます。
まずは「仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、」という部分から。
これは「仏仏祖祖のお悟りに完全に合致した」という意味です。
そして「祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ」というのは、「祖師方が伝えられてきたこの仏祖正伝の坐禅を守りながら正しく受け継ぐ人にならなくてはならない」という意味になります。
この「三昧」というのは一般的には無我夢中になることをこの「三昧」と言いますけども、正式にはこの「坐禅」そのものを「三昧」と言います。
私と世界とは一体です。同時です。世界とはこの私の展開なのです。
その私が坐禅をすることで世界も鼓動します。世界と私とは一体だからです。そんな中にあって私の坐禅こそが世界の全てというわけです。だから「三昧」。私の坐禅こそ「この世界」そのもの、この世界の「すべて」この世界の「真実」そのものだといっているわけです。

この世界には私一人しかいないわけですね。あるいは大自然その人しかいないわけです。全ては2つとして分かれないわけですね。私と世界は1つに溶け合っているから、こうして鳥の声や自動車の走る音が聞こえる。耳を震わせる。命を起こしている。あるいは私と世界は1つに溶け合っているから、こうして1秒ごとに風化していっているわけです。
私とは、大自然そのものなのです。大自然と1つなのです。仏とも1つなのです。実はそのような非常にスケールの大きい命をいただいているわけです。
我々は仏です。仏として生きることが本来の目的であり、役割です。
つまりここでは、我々一人一人が仏であり、「真実」にいきなければならない、過去から伝えられてきた正仏の教えを引き継いで伝えていかなければいけないということを言っているんですね。
我々は仏なのです。仏として正しい生き方があるわけですね。やるべきことがあるわけです。
日本には「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」ということわざがあります。
戦前の日本人には「名誉」のために「名誉ある戦死をしなければならない」こういった風習があったんですね。
「自我」に翻弄された時代があったんです。
いまでは考えられないですよね。
今でこそ、「戦争反対」、「無宗教」という言葉があったりしますが、当時はそんな風習はありませんでした。
そのようにして時代というのはコロコロと様相が変わります。当時は正解だったことも気づけば不正解になっている。
一方で我々の生きている世界、真実にはそのような側面はありません。そのような人間的な自我はなく、通用もしない。我々はそんな大自然の世界において、自我意識を振り回して生きております。
そしてこのような自我が中心の生活では「作ったものから作られる」といった有り様なんですね。
「自我」などというものは本来この世界にはないのにもかかわらず、その「自我」をどんどん形成し、その「自我」によって苦しむ。
まさに本末転倒であります。
仮にこのような「自我」が中心の例えば宗教であれば、「自我」と「自我」の対立が生じてしまいます。
仮に宗教上でなくても例えば一般社会においても、そこに「自我」がある以上、必ず対立が生じるんです。
「自分が信じた考え」、「自分を支えてくれる宗教」、「我々の誇りと名誉を支えてくれる宗教」というようなことであれば必ず対立が生じます。
この「自我」というのは、生まれながらに備わっていないにしても、それぞれの価値観や育つ環境によって段々とみについていきます。また今は人間が生きていく以上、他者とコミュニケーションを図らなければいけないので、自我の構築は必須と言えるでしょう。
この自我は人類が生きる為には非常に大切な「技術」であり、「テクニック」である。
しかし本質ではないんですね。例えば我々は「俺」が寝ている間にも呼吸をしています。「俺がみた」と言いますが、俺がみる前にそれはすでに見えていたものなのです。
あるいは「足を組むとだんだんと痛くなるのは血行が悪くなるからだ」というような説明ができたとしても、そもそもなぜ血行が悪くなるのか?そもそもなぜ足が痛くなるのか?ということです。
「雨が降るのは水蒸気が大気中で冷やされて、それが塊になるからだ」というような説明ができたとしても、そもそもなぜ冷やされるのかということです。そもそもなぜ冷やされると塊になるのか?ということです。
人間の自我意識や概念というのは単なる「後付け」でしかないんですね。大自然とは一切関わりがないということ、その自我がこの大自然には何も影響していないということは忘れてはいけません。
我々が本来いるべき場所がこの坐禅を組んだ世界
それでは仏教も同じようにこの「自我」に振り回されてしまっていいのか?仏教が重きを置いているのは果たしてそのような「自我」なのか?というと、そうではありませんね。
仏教をおひらきになったお釈迦様は、この「自我」というものは何なのか?ということを徹底的に見極めた方であります。
本来、大自然に「自我」がないように、その大自然と同時である我々人間にもこの「自我」というものは存在していません。
この「おれ」とか「わたし」というのは実存しないんですね。あるように思っているだけです。
そもそも「人間」という言葉がありますが、仮に一人の場合は「人間」とは言わないですね。
色々な社会があって、様々な人間に囲まれて初めて「人間」と言う。
誰かがあって始めて生まれることなのです。つまり他者が自分なんですね。他者によって自分は作られているのです。
我々が常に身をおいている環境というのはそういう場所です。
「人間」というのはあくまでも人間同士における「関連性」の名称に過ぎないんですね。
現に今から一人山奥にいったら、この「自我」というのは存在してこないですね。
他人からの評価もなくなり、孤独になる。
そして「自分」と「大自然」が一つになる。
「自我」が段々なくなっていくことに気付けるはずです。
それか一つ、道元禅師がおすすめになる「坐禅」をしてみましょう。
この「坐禅」を一つ組むと、どこからやってきたのか「自分」ではどうすることもできない「足の痛み」に襲われます。
次から次に「思考」に襲われます。
「自分」では手に負えない程の「呼吸」をひたすら繰り返します。
自分が「聞け!」と思う前に「カラスや自動車の音、ストーブの音」が自動で耳に入ってきます。
隣の人の「異臭」だって、自分が命じなくても自動でにおってきます。
このように「坐禅」を一つでもすれば、我々の「命」において「自分」でやっていることなど何一つないというこの世界の「真実の有り様」に気付けるはずです。
また坐禅をすると次第に足が痛くなります。それは誰かと比べてやや痛い、かなり痛いといった痛みではありません。宇宙いっぱいの痛みです。つまりそれは宇宙いっぱいの真実であるわけです。
この坐禅がこの世界の正体なんですね。この世界の真実なのです。真実のあり方なのです。
「坐禅」ではこのように「生命の実物」を実践している、或いは「命の正体」を実践しているのです。
つまり「坐禅」そのものが「悟り」なんです。
だから「坐禅」は「真実の行」、「仏行」なんですね。
我々が本来いるべき場所がこの坐禅を組んだ世界です。常に目指すべきこと、それがこの坐禅です。
足が痛くなるは作り物ではない。
常に「自己の正体」、「真実」に帰っていく。
それが「坐禅」の目的であるわけです。
つまり真実に帰れる「坐禅」こそが「真実」であり、「大自然の姿」そのものなんです。
お釈迦様は徹底的に「大自然」を見つめました。
そもそも「我々の生きる大自然に自我なんてものはないんだぞ」というのが「仏教」の始まりであったわけです。
そしてそれが達磨様、道元禅師、そして我々に今こうして守り伝えられた「真実」だったわけでありますね。
以前『普勧坐禅儀』の内容にもありました。
「坐禅はこれ安楽の法門なり」と。
「坐禅のどこが安楽なのかなぁ?」とここでは思われるかもしれない。
足は痛いし、辛いし、何よりつまらない。
しかし、足が痛くなるというのは、これは「作り物」ではないですね。
冒頭でお伝えしたような、自我によって作られたものではない。
「本物」なんです。
この足の痛みは、誰かと比較したものでもなければ、その誰かや、自我によって作られたものでもない「紛れもない確かなもの」なんです。
「本物」だから人の本当の「安心」に繋がるんですね。あるいは絶対的なものだから。我々が安心を覚えるのは、寄りかかれるからです。その寄りかかる場所というのはグラグラしていてはいけません。絶対的な場所でなければいけないわけです。
足を組むと絶対に痛くなります。この坐禅は絶対にこの世界の真実なのです。絶対に我々の本来いるべき場所なんです。
だから、「坐禅はこれ安楽の法門なり」と言う訳です。
そのような「人間の真なる安心をどうか守り、行じていってください」という意味合いも今回の、
には含まれているわけですね。
我々はいつの間にか「自我」に支配され、その「自我」を中心に生きておりますから「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」と言われると、何だか分かった気になるんですね。
腑に落ちると言うか。
「かっこいい生き方だ」とか「そのように生きるのが人間の使命だ」とか言われているようで納得しやすいんです。
しかしゆくゆく冷静になってものを見つめるとそのような考えは「何故起こるのか?」、「そう考える自我はどこにあるのか?」という疑問に駆られ虚しくなるはずです。
我々の命はそんなものなのか?
本当の命の正体はそんなものなのか?
食べたものを寝ている間にもきちんと消化してくれるこの命こそ、本当の命ではないのか?
このように考えていかねばならないなぁと思う訳であります。

まとめ
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 「三昧」とは「坐禅」をさす。
- 祖師方が伝えられてきたこの仏祖正伝の坐禅を守りながら正しく受け継ぐ人にならなくてはならない
- つまり、我々一人一人が「真実」に生きなければいけない。
- 自我に振り回される、これが人間が陥っている病。
- 自我は実存しない。
- 自我が無くても呼吸ができる、自我が無くても食べたものを消化できる。
- 足が痛くなるは「作り物」ではない。
- 我々はこの「本物」を拠り所とし、それを実践し、守り伝えなければならない。
以上、お読みいただきありがとうございました。

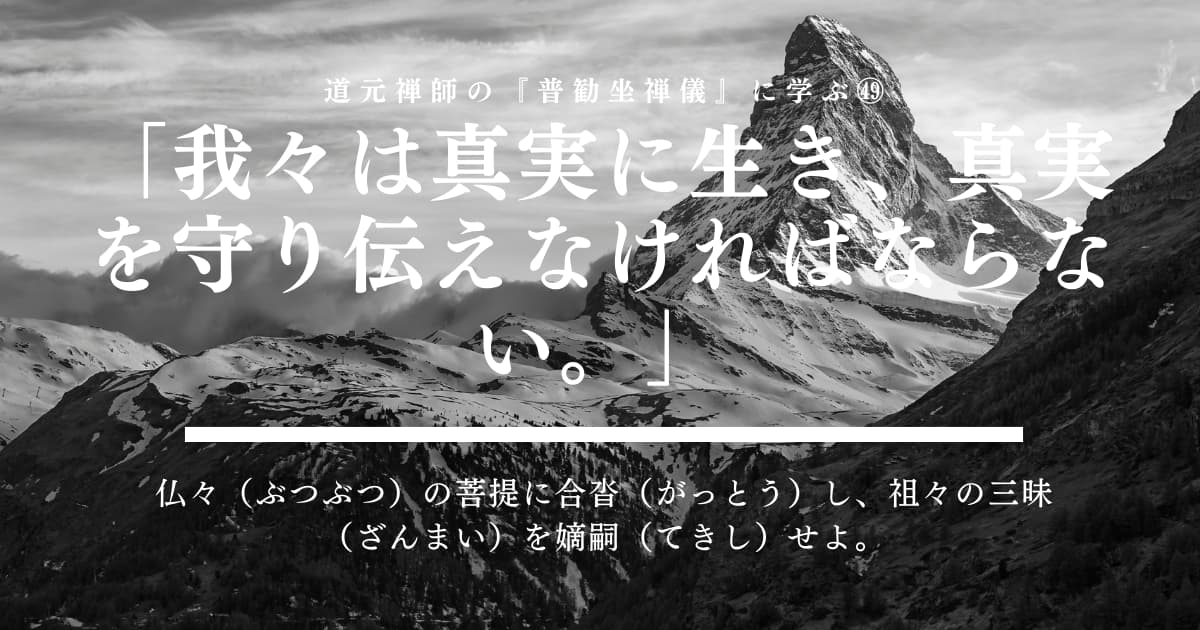
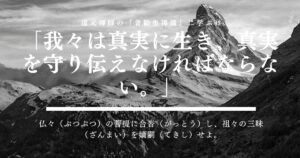
コメント