本記事では道元禅師がしるされた「普勧坐禅儀」について学んでいきたいと思います。
今回は、前回に引き続き『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を解説していきたいと思います。
前回解説しきれなかった部分が残っておりますので、そちらを今回お伝えしていきます。
是非お付き合いのほど宜しくお願い致します。
それではまず初めに前回の、

のポイントを振り返りたいと思います。
- 「普勧」とは特別な人に限ったことではなく、誰しもがということ。
- 『普勧坐禅儀』とは普く人々に道元禅師が「坐禅」の実践方法や心構えをしめしたもの
- 我々の住む世界、我々の生きる命は本来円通である。
- 真実をもとめる為の修行をしなくとも、今こうして真実を実践している。
それではポイントをおさらいしたところで、本記事の内容に進みたいと思います。

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。
普く人々に勧める坐禅儀
今回は、前回に引き続き、
という部分を解説していきます。
改めて『普勧坐禅儀』とはどういう書物なのかについて、簡単に振り返りたいと思います。
坐禅の作法、儀則をしるした「坐禅儀」というのは、道元禅師がしるしたこの『普勧坐禅儀』の他にも数多く残されております。
例えば、長盧宗賾(ちょうろそうさく)という人物のしるした『禅苑清規』(ぜんえんしんぎ)があります。またそれ以外にも『天台小止観』など、坐禅の作法を説いた書物は数多くあります。
一方で過去の偉人たちに伝えられた坐禅儀には色々な物があるわけですが、その中で「普勧」、「普く、勧める」の二文字が付いているのは道元禅師のしるされたこの「普勧坐禅儀」だけなんですね。
「普勧坐禅儀」の意義についてはこの「タイトル」にもあるように「普勧」です。この二文字がすべてが言い表していると言ってもよいかもしれません。
それでは「普勧」、「普く、勧める」と書きますが、一体誰に勧める「坐禅」なのでしょうか?
それは我々一般人にも勧めるわけですね。
限られたエリートだけに勧める坐禅ではありません。
という言葉が後ほど出て参りますが、
- 「上智」素晴らしい能力の持ち主であっても
- 「下愚」愚かで、文字も書けないような者であっても
- 「利人」鋭い者であっても
- 「鈍者」凄く鈍い者であっても
そういう決められた者だけに限らず、この『普勧坐禅儀』をお勧めするという事なんです。
現代社会ではグループから抜き出るようなエリートを育てるというのが、一般的な教育だったりします。
またとある宗派の坐禅堂の聯には「選仏道場」と書いてあったりもしますね。
沢山いる修行僧(仏)の中から、たった一人の仏を打ち出すという意味で、「選仏道場」という表現が使われるわけですが、果たしてこの表現が適切なのか甚だ疑問が残りますね。
そんな中道元禅師がこの坐禅儀を通して言いたいのは「普勧」であります。
沢山いるものの中からたった一人だけの「仏」や「エリート」を見出すための「坐禅儀」ではありません。
普く、勧める坐禅儀。
あらゆる人に勧める「坐禅」で、エリートを育てるという「坐禅」ではないのです。
叢林
道元禅師がお開きになった大本山「永平寺」等、その他修行道場では、「叢林(そうりん)」と表現します。
「叢林(そうりん)」の「叢」は草むら、林という意味ですね。
例えば、その草むらの中で伸びる「高い杉」のような人物を現代の「エリート」に置き換えるとします。
その高い杉はまっすぐ伸びていて、材木としては申し分ない樹木となることでしょう。
しかし実際の草むらには、そういった高い杉だけでなくヨモギのような「雑草」も生えておるわけです。
他にも本当に多くの小さい草花が生えているのが林のあり方のわけです。
このように「叢林」の中には雑草もあったり、高い杉林もあったり、色々なものがいます。
それが叢林であり、本来の命のあり方なんです。物事のあり方といってもいいかも知れない。
背が高い、背が低い、この違いがあったとしても、それらはそれぞれの役割があるからいいというわけですね。
単なる草木の賑わいなんです。
命の価値に差はない。これが本来のあり方で、それを表現しているのが叢林であるわけです。
実際の人間社会もあらゆる者たちが共存し、成り立っております。修行道場においても同じです。
大きいもの、小さいもの、そういったさまざまな物によって世界は成り立っているわけです。
そんな世界のあり方、世界そのものが「坐禅」であるわけです。坐禅がすなわち真実であり、お悟りであるからです。
またこれが道元禅師の捉え方なのでした。よってそのための「坐禅儀」ももちろん普勧でなければならないわけです。
道元禅師が強く説かれているのはこの「叢林」です。
エリートをたった一人育てるという目的の坐禅ではない訳ですね。
誰にでも「坐禅」を勧るのが道元禅師の『普勧坐禅儀』です。
ここをきちんとと抑えておかなければ、この『普勧坐禅儀』は読み進める事ができません。
繰り返しになりますがこの『普勧坐禅儀』は普く、勧める「坐禅儀」という事です。
凝った文章表現で始まっている
またこの『普勧坐禅儀』では、冒頭の「原ぬるに夫れ。」という言葉の後に、「道本円通、争か修証を仮らん、宗乗自在、何ぞ功夫を費やさん。」という言葉が続けて述べられております。
これは前の「原ぬるに夫れ。」という言葉に対して、後の「道本円通、争か修証を仮らん、宗乗自在、何ぞ功夫を費やさん。」という部分が対句になっているんですね。
これは漢文表現の一つの、「四六駢儷体(しろくべんれいたい)」と呼ばれるもので、当時の文章表現で主流となる表現方法でした。
丁度「馬」を、二頭立てにして進んでいる「幌馬車」のような感じで文章が書かれていることからそのように呼ばれるようになりました。
昔はこの対句表現方法を用いる事で、非常に綺麗な品のある文章になるとされておりました。
この『普勧坐禅儀』の冒頭はその「四六駢儷体(しろくべんれいたい)」であります。
そのように非常に凝った文章表現でこの『普勧坐禅儀』は始まっているんですね。
余談でした。
「原ぬるに夫れ、道本円通、争か修証を仮らん。」
それではここから実際の内容の解説に参ります。
まず前回の内容を今一度振り返ってみたいと思います。
という部分ですが、これは
訪ねてみたならば(元々を訪ねてみたならば、)
ということですね。
そして、
というのは「本なる道」ですね。
この「道」というのは我々の「生命の実物」、「生命そのもの」を指しています。
つまり我々が今ここに生きている事実の事をこの「道」と言うんですね。
それではここで言う「我々の生きている事実」とは具体的にどういう事か?
それは「頭」で考えた話ではないということですね。
例えば今「坐禅」をしてみて、「足」が痛くなってきた。或いは「ストーブ」の音がうるさいなと感じているこの私の「生の命」のこと、これが「道本」です。
実際の生命の実物、これが「我々の生きている事実」であるわけですが、そこにおいては行きつまりがないわけですね。
無条件で痛い。無条件で腹が減る。無条件でストーブの鳴る音が聞こえる。
そういった駆け引きのない、行きつまりのない命を常に、どこにいても我々はいただいているわけですね。
例えば今であっても、意識せずとも呼吸をしているはずだし、食べたものなども消化しているはずです。
そういった「確かな、行きつまりのない命」を我々は常に実践しつづけているわけですが、それが非常にありがたいということです。
無条件に生命活動をしてくれるからこうして今も生きていけるわけです。そんなありがたい状況に誰もが身を置いている。誰もがそのおかげで救われないことがない。誰もが常に救われているということです。
そんな命を我々が今事実としてここに行じている、あるいはその生命の実物を繰り返し行じているという意味を込めて「道」と言うのです。
続いて、「道本円通」の「本」。
「本来の」、「元々の」、という意味の「本」。
つまりこの「本」は、
本来の我々の命というものは、我々がここに生きている事実を証明している
という意味ですね。
そしてそれは、
であると。
円通というのは「円(まどか)」にという意味で、行き詰まりがないという事です。
これまでに述べてきたように、我々が生きている事実というのは常に「円通」であるという事です。
諸法無我
観音様の事を「円通」と言ったりします。
我々の事実もこの「円通」であります。
一切行き詰まりはありません。
しかし実際となると、我々は「行き詰まりのない人生」など、とても考えられないですね。
何をやってもうまくいかない、誰も自分のいう事を聞いてくれない。
誰しもが常に「私(わたし)」や「俺(おれ)」という「自我」をむき出して生きているわけですので、自分の思い通りにならないと「生き詰まり」を感じてしまいますよね?
なので「生き詰まり」がないと言われてもかなりの抵抗があると思います。とてもそんな風には思えない。
釈尊の教えに「諸法無我」というものがあります。
これは「あらゆる事物は、変化し続けているため我がない」という事ですが、簡単に言えばこの世界に「俺」という「我」はどこにも存在しないという教えです。
仮に今「俺だ」と思っているこの「俺」があったとしても、しかしそれは1秒後に変化している。それは果たして「俺」と呼ぶべきなのかという話です。確かに俺と断定できるものはこの世界のどこにもないのです。
そこで仮にそうであったとしても、今ここにいるそいつを「俺」と思えばよかろう!という考えが芽生えます。
しかしそう思ったとき、つまりその「俺」とは単なる人間の認識であると気付くのです。
自分というのはこの世界にはないんです。この俺だと思っているものは単なる細胞の集まりです。
我々人間はいつからか、本来存在しないはずのこの「自分」というものに囚われるようになります。産まれたばかりは自我がないのが良い例です。
そしていつしかこの「我」に囚われるようになり、苦しむ。この「自我」に囚われた生き方には行き詰まりばかりが生じます。
釈尊の言う通り、「あらゆる事物は常に変化している為、我がない」わけですから、我々の命も同じで、「円通」そのものなんですね。どこにも定義がない。どこにもとどまるところがない。全てが流動的に流れている。
それがお救いなんですね。流れていってしまうから、苦しみがないんです。苦しみと呼ばれるものがないんです。流れていってしまうから、そもそもこの世界には何もないのと一緒なんですね。
しかしこの全てが流れている。何もない、何も止まらない。それがお救いなんですね。「本来の我々の生命」はお救いであり、「円通」なんです。
常に「生き詰まりなどなく、偏りなしの命」を生きているんです。
「円通」の意味
この「円通」の意味を理解する上で、例として一番分かりやすいのは、この「胃袋」ですね。
例えば、
「なんだ今日はご飯にお茶漬けか、味気ないなぁ。」
あなたももしかしたら今日言うセリフかもしれませんね。
毎日味気ないご飯が出されると、このように愚痴をはきたくなるのが我々です。
そしてこれは「生き詰まりの話」でもありますね。
しかし実際は、味気ない食事だとしても「喉元」を過ぎたならば胃袋は「無条件」で、「生き詰まりなし」に、消化をしてくれます。
高級なフランス料理だとしてもそうです。
どんなものが喉元過ぎて入ってきても、分け隔てなくちゃんと消化をしてくれる。
我々が寝ている時なんかもそうですね。
自分が寝ている時は「自我」がありませんよね?
その「自我」が寝ている時だろうがこの体は休まずに「呼吸」をし続けてくれています。
つまり我々人間は「自我」で生きているわけではないのです。
「自我」で呼吸をしているわけではない。
「自我」で消化をしているわけでもない。
このように「自我」というのは生命活動にとって、何の影響も及ぼさないんですね。単なる認識に過ぎないのです。
「生き詰まり」があるのは我々の脳みそだけなんですね。
その「生き詰まり」とは頭の中だけの話で、現代人に多い「ストレス」の根本ともなっているものです。
我々のこの本来の「在り方」、つまり我々の生きている「事実」は全て「円通」であります。
決してそこに行き詰まりがあったり、偏りがあるという事は一切あり得ず「完全」であり、ひらけた世界です。
ですから最後の、
だと。
つまり今から修行を一生懸命頑張って、その結果として「理想的な人物になろう」という事は、おかしなことだと道元禅師は言われるんですね。
そんなことはナンセンスであるし、なんとしても悟りをひらこう等という考えは実に滑稽なことであるというのです。
何故ならすべては「円通」だからですね。悟るべきものなどそもそも何もなく、もしあったとしたならそれは個人の単なる願望で、それは悟りではないからです。
ですから、
「修行」をして「悟る」のではなく、「悟り」を実践する。
これが道元禅師のおすすめになる「坐禅」なんですね。
この坐禅を行い、今すぐにでも完全無欠のひらけた世界、そこを生きてくださいよと。
これこそまさに「悟り」です。
ですから坐禅は「仏の行」と呼ばれ、このセリフを聞いたことがある人もいるかもしれませんが、
一寸坐れば一寸の仏
と言われるのです。
この世界は常に悟りの世界であるから、その世界に自分をひたす。ざるで悟りを得ようとするのではなく、ざるを仏の水に浸せと。
一般的に「坐禅」と言うと、「転迷開悟」の手段として用いられます。
人は迷いを転じて悟りを開くというのが坐禅の目的であり手段のような感じがしているわけです。
しかし道元禅師の「坐禅」は「悟り」を得るための手段として用いられないんですね。
「悟り」をひたすら実践するのです。
ですからこの「坐禅」は仏行と呼ばれるんですね。
この坐禅を通し「真実」を実践しているからです。真実の「仏」の世界を実践しているからです。
したがって、『普勧坐禅儀』もそういう「転迷開悟」に関する話ではありません。
「坐禅」をして「悟る」だとか、「坐禅」をして迷いを打ち消すという「坐禅」ではないんですね。
繰り返しになりますが、差別なく誰しもが坐れる坐禅を、道元禅師はお勧めになっている訳です。
何故なら我々は平等に分け隔てなく生き詰まりや偏りなしの「本来の命」、そういう「世界」を生きているからです。
誰もが同じこの仏の世界に身を置いているからです。仏の子供だからです。
道元禅師は生き詰まりのない「命」を、皆さんは生きているのだと、生まれながらに救われているのだと、それをお伝えになるためにこの『普勧坐禅儀』を著したわけです。
まとめ
今回は、前回に引き続き『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してまいりました。
最後に本記事のポイントをおさらいしておきましょう。
- 『普勧坐禅儀』に「普勧」が付くのは普く人々におすすめするためのものだから。
- 道元禅師がおすすめになる「坐禅」は、誰にでも当てはまるも、その為「叢林」のようなものである。
- 『普勧坐禅儀』の冒頭はその「四六駢儷体(しろくべんれいたい)」である。
- 生きている事実の事を「道」という。
- 「自我」で呼吸をしているわけではなく「自我」で消化をしているわけでもない。
以上、お読みいただきありがとうございました。

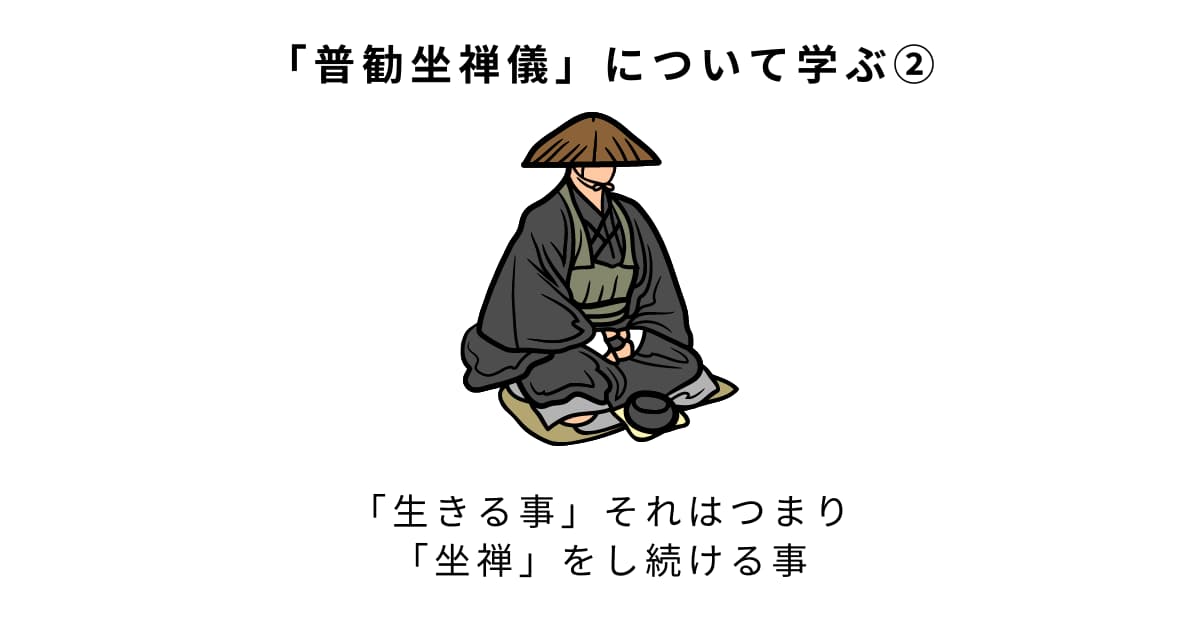
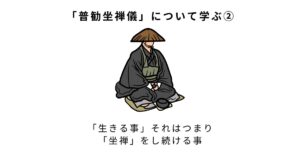
コメント
コメント一覧 (3件)
最近の事ですが、このページに辿り着き本当に嬉しく毎日読み進めています。
つきましては、普勧坐禅儀を1から順に読み進めて行きたいのですが、2から3に行く事ができません。
一覧で出て居るページは無いのでしょうか?
よく使いこなせていない者ですから、右往左往しています。
それにしても難解な禅を、とてもわかりやすく解説して下さり本当にありがたい事です。
これからも毎日、楽しみに学ばせて頂きます。
お忙しいのにお時間を取らせてしまいますが、どうぞよろしくお願いいたします。
池上様
お世話になっております。
そのようなお言葉をいただき誠にありがとうございます。
また併せてご指摘もいただき、ありがとうございます。
ただちにサイト調整いたしますので、もうしばらくお待ちいただけますでしょうか?
また毎日読んでくださるとのこと、大変喜ばしく思います。
今後とも精進してまいりますので何卒宜しくお願いいたします。
合掌
池上様
お世話になっております。
ただいま、各記事の最下部にある「この記事が気に入ったらフォローしてね」という案内の上に「普勧坐禅儀」と記されたタグボタンを設置させていただきました。
そのタグボタンを押していただければ、すべての「普勧坐禅儀」をご覧いただくことができます。
順不同となっており、少々見つけづらくなっておりますが、そこにはすべてがあり、また⓵~㊿の数字がタイトルにふられておりますので、順番にご覧いただければと思います。
今後とも何卒この「禅の旅」をよろしくお願いいたします。
合掌