本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を読んでいきたいと思います。
まず 初めに前回の、
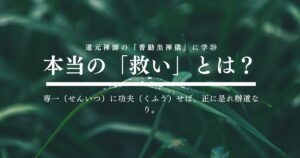
のポイントを振り返りたいと思います。
- 物事をただひたすらに「行じていくこと」を「専一に功夫する」と言う。
- ご飯粒の中には御仏様がいる
- 全てが一つに溶け合った仏の命。二つとして分かれない。
- つまり「俺の考え」とか「ワタクシノ物」というのは妄想にしか過ぎず、真実とかけ離れている。
- 「本当の救い」とは大自然の在り方を行じること
- 「本当の信仰」とは真実の為に真実の行を行う事。
- この世界においてどこを転んでも「花の中」、全部自分の命
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
「説示一物即不中」が命の正体

今回はこの部分の解説をしていきたいと思います。
禅を中国全土に広めた慧能禅師
まず「修証自ら染汚せず、」の部分ですが、ここにはある逸話が関連しております。
中国で「禅」を世間に広めた、六祖慧能禅師という方がおられます。
この六祖慧能禅師というのは「無学文盲」であったと言われております。
読み書きが出来ず、学問のなかった方であったと言われているんです。
しかしこの慧能禅師はその後師匠となる大満弘忍祖禅師に付き、達磨大師から続く仏法の極意をきちんと相続されます。
そして「禅仏法」を中国に広められるんですね。
「無学文盲」であっても、立派な禅僧であられたんです。
ちなみにこの慧能禅師は今でも中国で非常に人気のある人物です。
「無学文盲」であったということ。そして「禅仏法」を広く中国に広めたことが、その理由として挙げられるのかも知れません。いわばヒーローの的な存在で現在も中国の人々に受け止められている部分があります。
作家として有名な「五木ひろし」さんは、中国の本屋さんに行った時、この六祖慧能禅師の漫画本まで出ていたことに非常に驚いたというんですね。その漫画本は累計五千万部も売れているというのです。
今も昔も非常に人気の高い人物であったことがわかるんですね。
余談でした。
この六祖様には五人の有名なお弟子さんがいらっしゃいました。
荷沢神会(カタクジンネ)、慧忠国師(エチュウコクシ)、永嘉玄覚(ヨウカゲンカク)、南嶽懐譲(ナンガクエジョウ)、青原行思(セイゲンギョウシ)。非常に有名となるお弟子さんを育てた方だったわけです。
その中でも南嶽懐譲と青原行思が有名で、このお二人は後の五家七宗(曹洞、臨済、潙仰、雲門、法眼、黄龍派、楊岐派)をしょって立つ指導者を育てた人物です。
そして今回の内容はその内のお一人であります、南嶽懐譲禅師が、師匠である今回の六祖慧能禅師の所に訪ねてきた時の話です。
何者か恁麼来
南嶽懐譲禅師は当時、六祖慧能禅師に会うため、広東省にある「法輪寺」まで訪ねていきます。
そこで六祖慧能が、訪ねてきた懐譲禅師に質問をします。
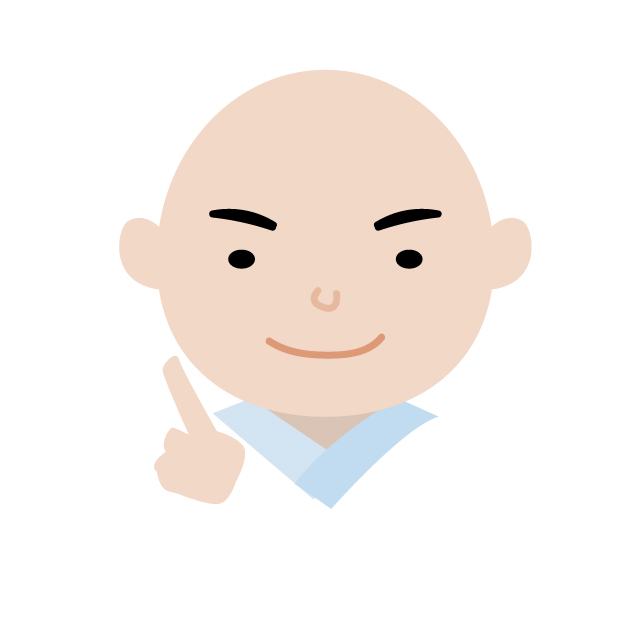 慧能禅師
慧能禅師いずれのところより来る。
「お前さんは一体どこから来たのかね?」と質問されます。
すると懐譲は答えます。



嵩山の安国師の所より来る。
「嵩山(すうざん)」というのは、過去に少林寺拳法で有名な達磨様が住職しておられたあの嵩山ですね。
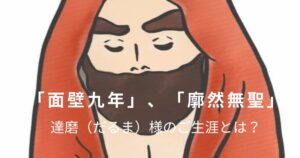
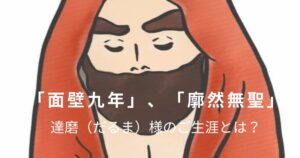
また「安国師(あんこくし)の所より来る)」というのは、六祖慧能禅師と兄弟弟子にあたる慧忠国師によってさしむけられて来たという意味です。
そもそも「本当の仏法を求めたいのなら、六祖慧能禅師の所にいって修行しなさい」と、慧忠国師にさしむけられて六祖禅師の所へ訪ねてきたわけですね。
なので「嵩山の安国師のところより来る」という風にここで言う訳です。
すると六祖慧能禅師は次のように質問をします。
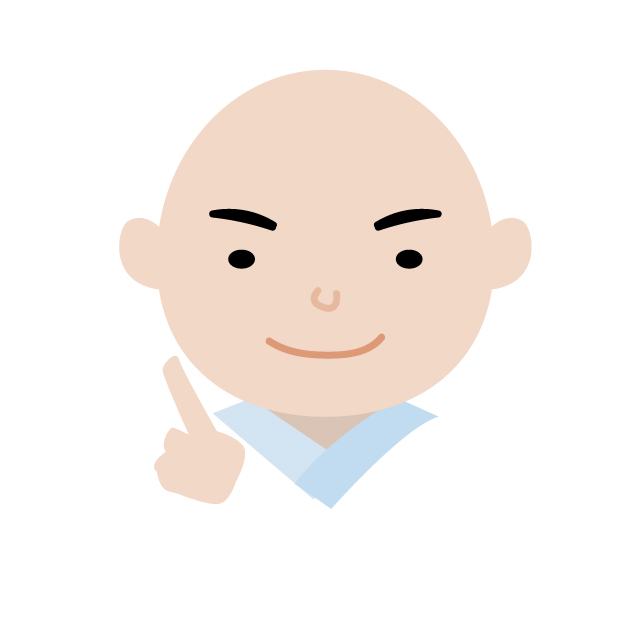
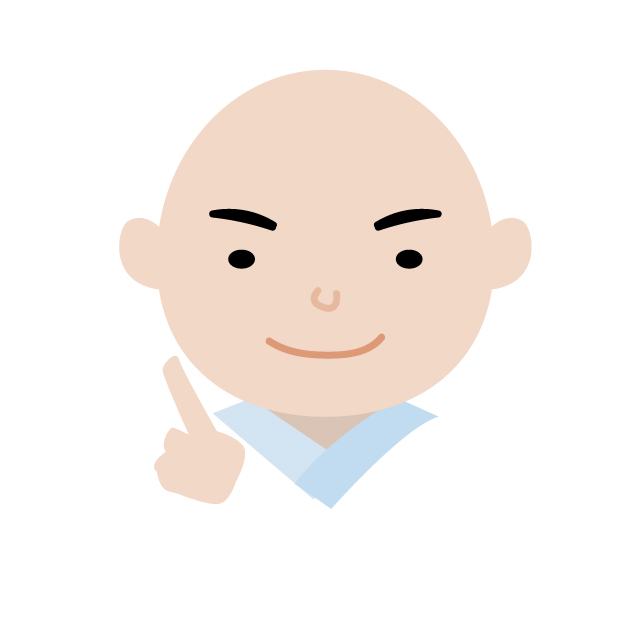
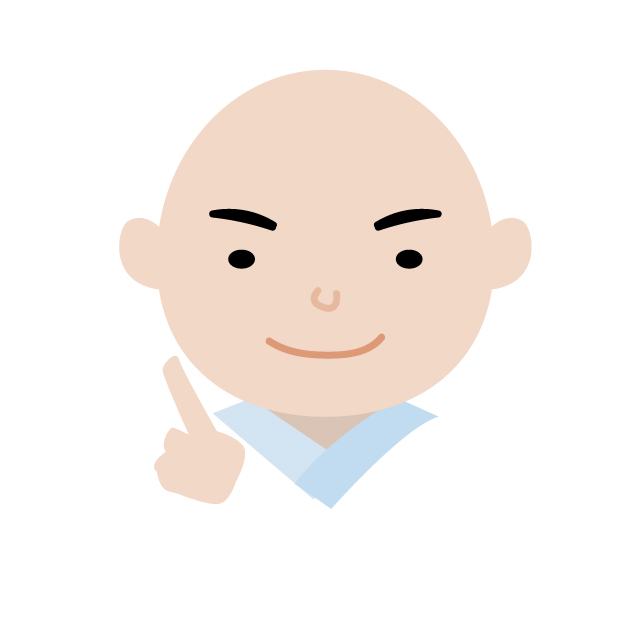
何者か恁麼来
「あなたは何者ですか?」、「お前さん一体何者か?」と聞く訳です。
これは非常に有名な言葉ですね。そして今回の話の「味噌」となる部分です。
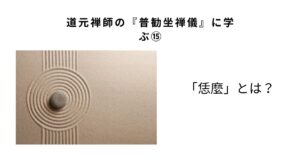
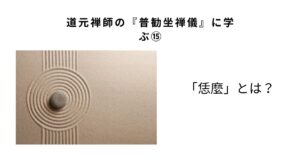
「何者か恁麼に来る。」とは、
「どのように来たのか?」
「何者が何しに来たのか?」
といった意味になります。ここでは「お前さんは一体何者か?」という形にしておきたいと思います。
このように聞かれると普通であれば、「はい、わたくしは〜から参りました。」とかですね、お前さん一体何者だと聞かれれば、「はい、わたしは〜寺の住職をしております。」あるいは「〜店の店長をしております。」と答えるわけです。
「何者か恁麼来。」
しかしこれはそういうことを聞いているんじゃないんですね。もっと奥の深い質問となります。
そのようなことを当時の南嶽懐譲禅師も思ったのでありましょう。色々思案した。しかし相応しい答えを即座に答えられなかったんです。
そしてそれから七年間もの間、ずーっとその「何者か恁麼来」という言葉を温めながら、自分自身念提しながら、その六祖慧能禅師の下で修行をしておりました。
自らを苦しめる「檻」を率先して作り出す人間
人間は「社会的な動物」だと言われております。常に社会との兼ね合いを気にする。あるいはそこで評価されてしまう。このように人間は社会とは切り離すことのできない生き物になってしまいました。
しかし「社長」だとか「住職」だとかというのも、その人間社会だけにおける自分の立場を明確にするための「肩書き」にしか過ぎません。
この「肩書き」がものをいい、その肩書きをを大切にしてしまうのも我々が社会的な動物だと言われる理由です。
我々はこの社会的関連性において、その「肩書き」を大切にしている。それをもとに生きている。自己主張をしている。これは「自我意識」をむきだしにしていると言ってもいいかもしれない。
しかしそもそもそんな社会もなければ、社長も住職もありません。またそのような肩書きや自我意識というのは本来存在していない人間社会によって生み出される物なんです。
例えば山の中に一人住んでいる人物に、「あの野郎俺のことを馬鹿にしやがって!」なんていう「自我意識」は生れません。俺はあいつと比べてダメだ、なんて落ち込むこともないはずです。
この「俺が」という「自我意識」は社会的関連性において、社会で他の人と生活をしているからこそ生まれてくるわけです。
社会的関連性、そのような人との関係性がなければ、「ワタクシガ」とか、「俺こそ」という「自我意識」はでてこないですね。誰とも比べず生きていけるんです。
以前の『普勧坐禅儀』でも取り上げた「虎の山によるに似たり。」にもありましたが、山に住むあの猛獣の「虎」と言うのは人間社会では生きていけないですよね。
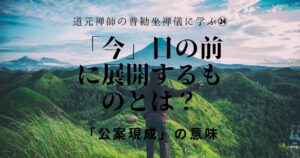
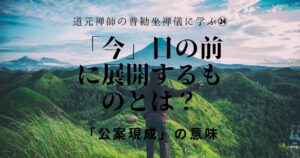
この人間社会に出てきたならば、「檻」に閉じ込められたり、見せ物にされたりする。虎は決して人間社会では生きていけないことでしょう。
なのでやっぱり「虎」は山に住まなければならないですね。この人間社会の関連性の中においては生きられないんです。
そのことを「虎は山によるに似たり」というんですね。
一方我々人間というのはこの社会で生活しております。この社会でしか生きられないというところまで来てしまいました。
しかし「虎」から言わせればここは「檻の中」なんです、我々人間が生きているこの「社会性」というのは。
そしてそこでは少しでも生きやすいように、「ワタクシは社長だよ!」とか「私は住職をしております。」という自我意識を構築し、人と比較している。攻撃している。そんなことばかりをしています。
しかしこれは所詮「檻の中」の話であります。また実際に存在していない世界です。概念だけの世界です。
そういう世界にどんどん入り込み、ついには抜け出せなくなってしまったんですね。それが今の人間です。今だけでなく、概念形成力を持ち合わせた人間にとっては常に切り離せない状況なのでしょう。
何者か恁麼来の意味とは?
今回、六祖慧能禅師が南嶽懐譲禅師に「何者か恁麼来?」と質問しました。
しかしここで言う「お前さんは一体何者だ?」というのは今言ったような「社会的関連性」の話ではないんですね。「俺は社長」であるとか「私は住職」であるといった社会的な「役職」は何か?「肩書き」は何か?ということを質問しているのではないのです。
どことなくそのようなことに気づいていたからか、弟子の南嶽懐譲は七年間もの間、師のもとで修行をし、この質問に対する答えを拈堤していたのです。
そしてついに七年経った時に、自身で温めてきたその答えを南嶽懐譲禅師が言われました。



説示一物即不中
つまり「一物をもって説示する」と。
「物事を相対化したところで、指し示すことはできません」と。
まず、生きている「事実」こそが全てであるということに気づかれたわけですね。今ここ、この事実。今足を組んでいる痛み。これがこの世界の全てであるということに気づかれたわけです。それしかこの世界にはないからですね。今、ここ、この事実しかなく、その事実を証明しているのがこの足の痛みだと。
そしてそれは決して相対化できない話だということにこの南嶽懐譲は気付いたわけですね。それを言葉で説明したり、概念に留めようとしたならば誤りだということに気づいたのです。なぜならそれは本来存在していない物だから。
今述べたように、「生きている事実こそが全てである。」や「今ここ、この事実。今足を組んでいる痛みこそが全てである。」といったこと。
しかしそれが本当だとしても、それを相対化したのならば、頭の中で概念化してしまったのなら、それは間違っているということに気づいたわけです。
なぜなら繰り返しになりますが、それは存在していないし、また「生きている事実」。これは常に今、こうしている間にも変化しているからです。
こんな私でも1秒後には姿を変えているわけですね。言葉や概念でそれを説明しようと思うと、それは常に「後付け」のものとなり、その物事の正体ではないわけです。
また自分だけでなく、この世の全てはそのようなあり方をしています。
要するに何事も人間の頭では説明できない。説明というのは常に正しくないということなんです。
そこを理解した。それは「何者か恁麼来?」という慧能禅師の質問に対して七年間も念提したことで「相対化して理解しようとするのは間違いなんだ」ということにも気づくことができたのです。
それを今回のやり取りで言うと、
「生命の実物」は「説示一物即不中」だという事に気が付いた
と言うことなんですね。
「今(何か)」は言い表せない。「今(何か)」は言い当てる事ができない。「今(何か)」を言い当てようとしたら必ずはずれてしまう。
この世の全てがそのような形をしている。説明の一歩先を言っている。人間の説明というのがそもそもなんの役にも立たないということに気がついたわけです。
またこの「説示一物即不中」という事に気が付いたならば、「修行して悟る」ということの矛盾にも気が付けるのです。
今行じている坐禅そのものが、「何者か恁麼来?」の答えなんですね。今、ここ、この実物、この足の痛みが本当の意味での説明なのです。本当の意味での「何者か恁麼来?」に対する答えなのです。
全てに対する答えなのです。
今この坐禅を行じている姿が全ての答えです。あるいは全て、そのものです。「悟り」そのものでもあるわけです。
いつも「仏法」で問われているのは、この「こと」です。
「何者か恁麼来?」の質問に対して念提すること七年。
南嶽懐譲禅師はその答えが「今ここ。」しかないという事に気付いたんですね。それを「説示一物即不中」という言葉でお返しになったわけです。「物事を相対化したところで、指し示すことはできません」と。説明できないのが答えだと。
いうならば「何者か恁麼来?」その質問自体が我々の正体です。「説示一物即不中」という答えが命の正体なんですね。
事実は人間の価値判断で汚されない
「説示一物即不中」とお答えになった南嶽懐譲禅師に対して師匠である慧能禅師は次のように再度質問をされます。
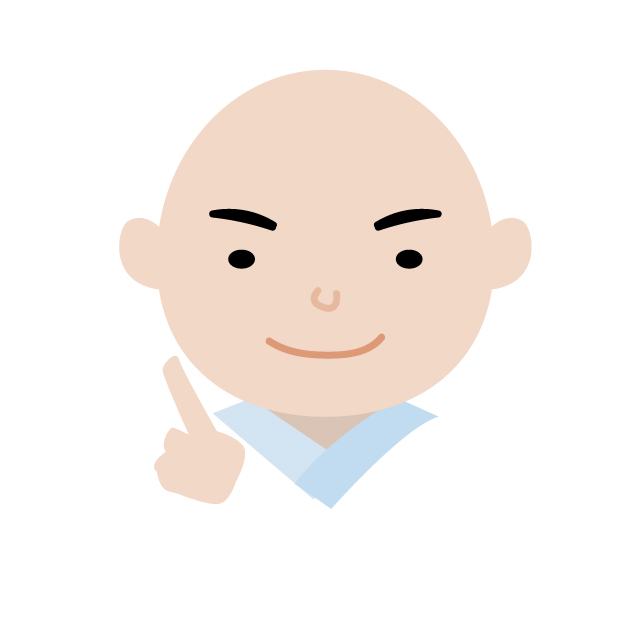
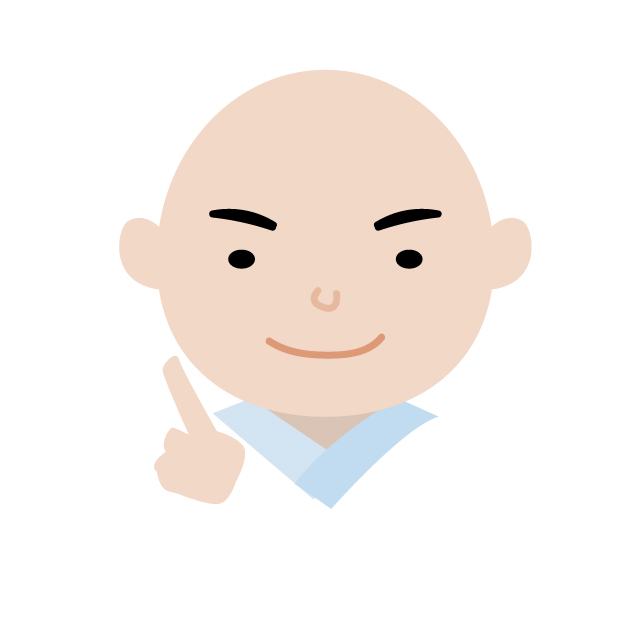
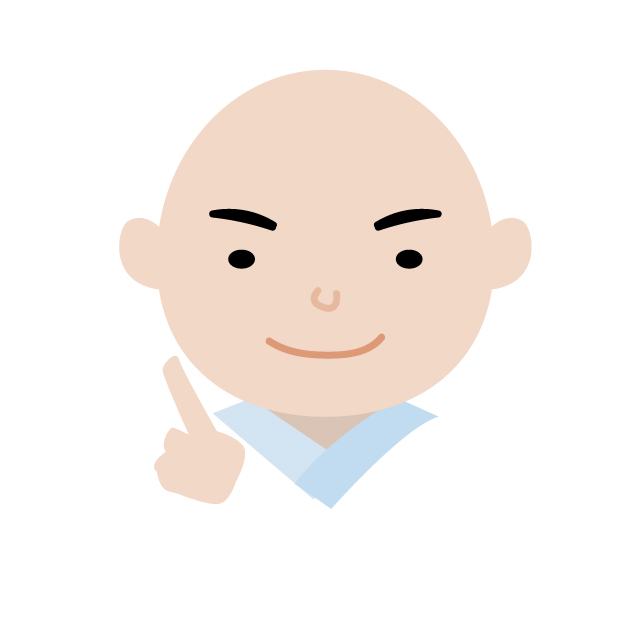
かえって修証かるや否や。
「それならば、修行と悟りというものに区別がありますか?」という風に質問するんですね。
すると弟子の南嶽懐譲が答えます。



修証は即ち無きにあらず。ただ染汚すなわち得ず。
つまり、「修証がないわけではない。」と答える訳ですね。
修行をして、その修行の結果「悟る」という時間的な経過も無い訳ではないとお答えになるのです。
しかし「その修証は染されない。」と言うんですね。
どういうことか?
まず、 「修証は即ち無きにあらず」というのは「修行」だとか「悟り」だとかそういうものは確かにあるだろう、しかしそのように区別するのは頭の中だけの話であると。そういう話もできるが、それは人間だけに通用する話だと。
またそれに続くのは、決して本当の「修証は汚されない」というんですね。
これは「絶対的な事実」と言い換える事もできるでしょう。
我々はすぐ何でも汚してしまうんですね。
「修行」と「悟り」というものを汚してしまうのも、「修行」だとか「悟り」だとか自分の思惑の中で区別し、引き込んでしまうから。人間の手を加え、概念で捉えようとするとことでこのようになんでも汚してしまう。
しかし「修証」というのは、今ここの事実の事です。「坐禅」のことですね。「今」の事です。
そんな今を人間の価値判断で「修行」だとか「悟り」だとか区別できるか。あるいはその事実に手を加えることができるか。その事実の評価を変えることができるか。
できません。どんなに偉い人でもそうでない人でも、1秒ごとに風化していく。我々はこの大自然に抗うことなどできないのです。
よって本当の「修証は汚されない」というんですね。
本来この大自然を2つに分ける事もできないし、言い当てる事もできません。
本来「修行」だとか「悟り」だとか二つに分かれる物ではないんです。
全ては言い当てることはできない。人間の概念が介入できない。だから「説示一物即不中」なんです。
また人間の概念が大自然に全く影響しません。大自然は大自然。常に、そこで100を展開しております。だから「染汚することをえず。」というんですね。
本当は汚すことができないと、区別することができないと。
修証は即ち無きにあらず。ただ染汚すなわち得ず。
確かに「悟り」と「修行」という風に分けることもできるだろう。しかしそれは人間だけに通用する話だ。本当は何も汚されない。
このようにお答えになった弟子である懐譲禅師に慧能禅師はえらく感心されたことでしょう。
その後慧能禅師は次のようの言葉でしめくくられます。
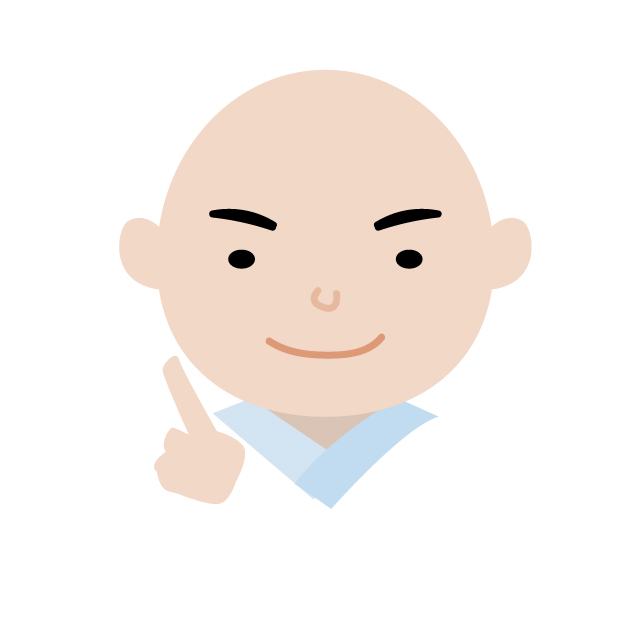
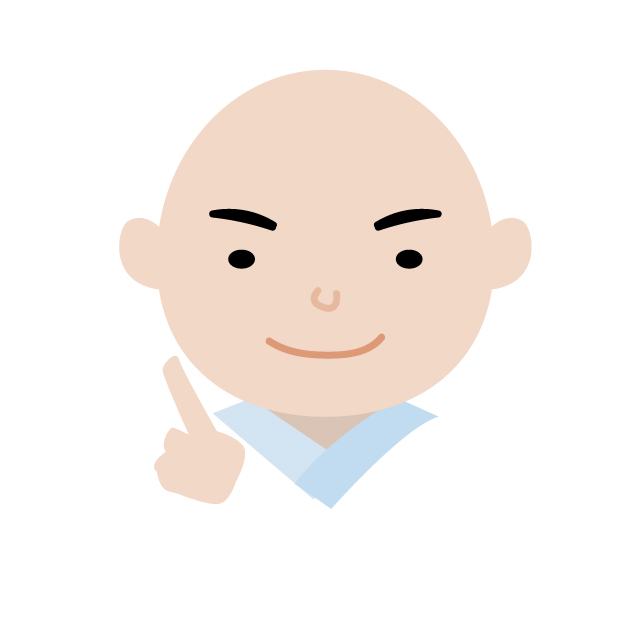
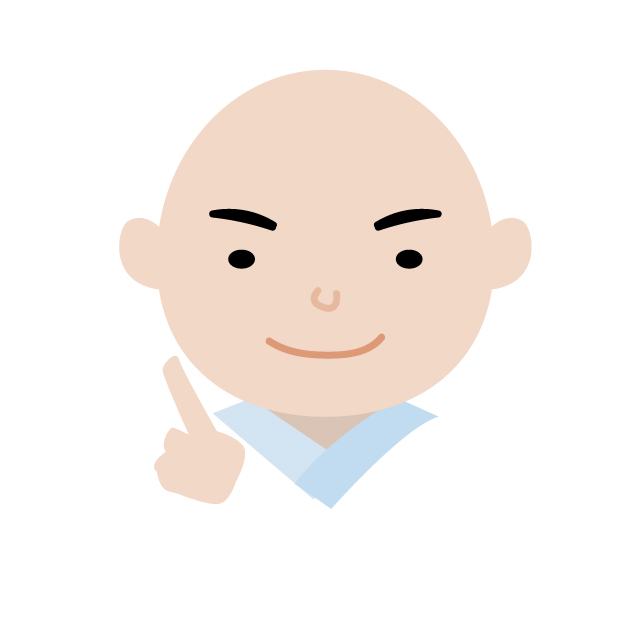
不染汚
つまり、「本当の修証は汚されないな。それでいいぞ」と。
師匠も、そのような境地に達せられたお弟子さんの成長を喜ばしく思われたことでしょう。
今回の、
には、このようなやりとりがあったんですね。仏法史においてとても大切なお話、逸話だったわけです。
なので道元禅師もここで引用されたというわけです。今の我々においても留めておきたいお話ですね。
「説示一物即不中」が命の正体-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
と言う部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 「修証は自づから染汚ぜず、」とは慧能禅師と懐譲禅師の問答の一部を道元禅師が引用されたもの
- 「何者か恁麼来?」その質問に答えられず、七年間も念提していた懐譲禅師。
- 人間は社会的な生き物
- 自らを苦しめる「檻」を率先して作っている
- 「檻」は妄想でしかない。人間がスムーズに事を運ばせるための共通認識でしかない。
- 絶対的な事実とは、「生命の実物」の事、「説示一物即不中」
- そしてその「生命の実物」は言い当てる事ができない、言ったことは全てはずれてしまうだろう。
- 今、行じている「坐禅」が「何者か恁麼来?」の答え
- 「坐禅」が「絶対的な行事」、「命の行事」、「確かなる行事。」
- 本来「修行」だとか「悟り」だとか区別は一切できない
- 本当の修証は「汚されない」、人間判断で「区別できない」
以上お読みいただきありがとうございました。

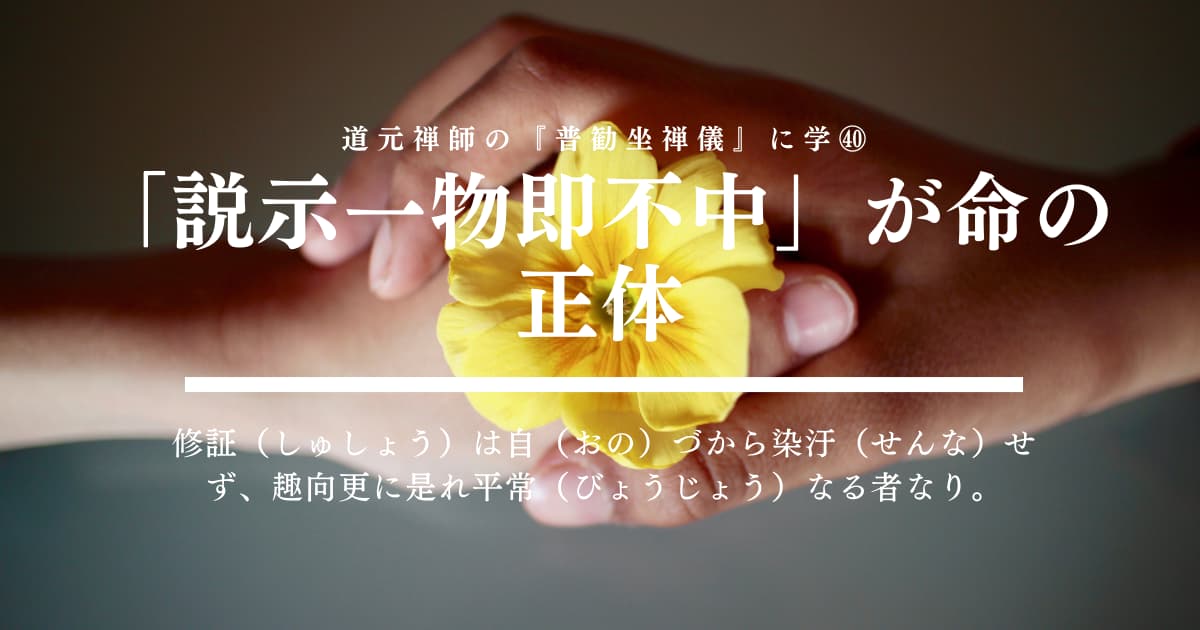


コメント