道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第⑰弾といたしまして、「恁麼(いんも)」についてお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
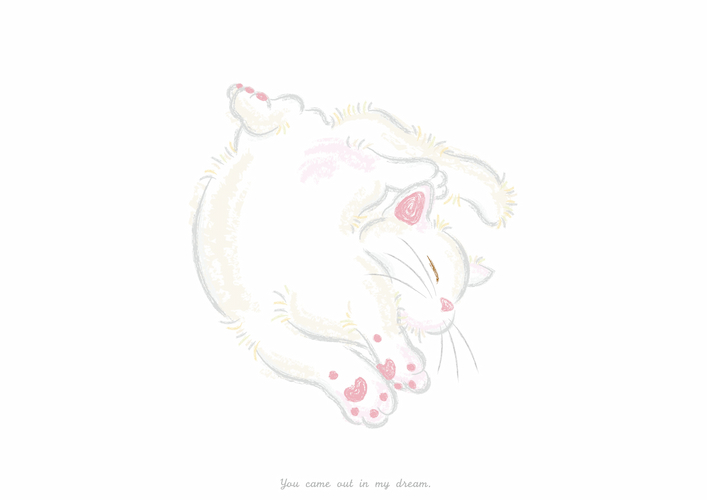
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

恁麼とは
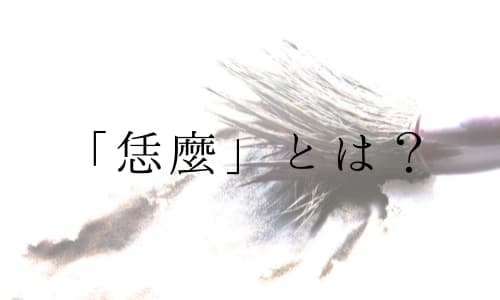
「恁麼(いんも)」とは、「このような(に)」「そのような(に)」という意味を表す中国の言葉です。
我々は普段から「あれ」とか「それ」とか「あの」とか「その」とかって言葉をよく使いますが、中国における「恁麼」もそれらと同じ意味としてよく使われる言葉なんですね。
また同義語には、異没(いも)や、伊麼(いも)、与麼(よも)などがあり、この「恁麼」を疑問形にした「どんな?」や「なんの?」という意味の「什麼(じゅうも)」という言葉もあります。
この「恁麼」は意味にすれば「あれ」とか「それ」に該当します。
しかしこの「恁麼」という言葉の持つ、本来の意味をそう簡単に理解できるものではないんですね。
本blog「禅の旅」でもこれまでに何度かこの「恁麼」について話題に取り上げてまいりました。
そう、「恁麼」とは仏法における「真実」をあらわした言葉なんです。
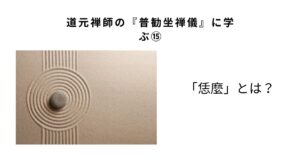
どういうことか以下でおさらいしてみましょう。
恁麼の意味
我々にとっての真実。それが仏法です。
それはつまりどういうことか。そのような参究はこれまで多くなされてきました。
古く歴史のある仏法です。今においても何千年前も前からもそのようなことは行われてきました。
まず参究というのは考えをめぐらし、その真なる部分に行き着くこと。あるいは言い表すことです。
そこでは必ずや「言葉」による考察が必要です。
しかしこの仏法の真実というのはいくら、どのような言葉を重ねようと言い表せないと言うのです。
それでもその言い表せないということくらいは言葉で持って正しく示す必要があります。
それをこの「恁麼」という言葉で述べるわけです。あるいは「真実」というのは「恁麼」としか言いようがないんですね。
例えば我々はいまこうして生きており、我々の身体は一秒一秒姿を変えております。
目には見えませんが、確実に姿を変えているんですよね。
それは疑いようもない事実です。
また人間だけに限らず、目の前の壁も、水も、カーペットも、自動車も、確実に姿を変えている。
それが世界の真実ですよね。つまり真実。仏法はこれだということです。
そこには例外はありません。
あるいはその真実のことを「諸行無常」といったりもしますが、要するに留まるところを知るものは何一つないんですね。
なので、本来どれも名前の付けようがないんです。
しかし人間はそこを名前を付けようとするんですね。
本来名前の付け様のないものに絶対的な安定を求めて、名前を付けようとするんです。
例えばこれは「チョコレート」、「カーテン」といったふうに。
そして「このチョコレートは俺のもの」といったふうに、それをコミュニケーションに用いたりするのです。
これが我々の生活の基盤です。
しかしもとを正せば、それは正しくないわけですね。どれも一定の形はないわけで、それを何かを留めるということは本来できないわけですから。
すべてはうつりゆくもの、風化していくもの、いずれは跡形もなく消え去るもの。
そういった真実に蓋をして、みないようにする。それがいわゆる人間の脳みそによる「名称化」、「固定化」、「概念化」なのです。
これに甘んじたい。自分のものというものを作って安心したい。永遠に変わらないものを信じたい。そこにすがりたい。
そのような思いが背景にあるからなんです。
しかし実際はそのようなものはないということなんです。それは真実に反している。
言葉は真実に反しているということなのです。
それでも何かしらの言葉にしなくてはいけないということで、この「恁麼」なのです。
昔「仏法の大意は何か?」と聞かれて人差し指をスッとその者の目の前につきだした倶胝和尚という方がいらっしゃいました。
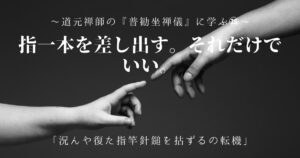
人差し指を出された方は何がなんだかわからない。
この「恁麼」も同じですね。
「仏法の大意」は説明のしようがない、それは「あれ」だの「これ」だの、そういう風にしか言えないわけです。
しかし同時に、それこそが何よりもこの瞬間をとらえた言葉でもあるわけなんですね。真実を捉えているわけです。
一瞬一瞬姿を変えていくこの「真実」を、「かくかくしかじか、酸素がこうなって、血液がこうなって~」と科学的な言葉で言い表せたとしても、そのように言ってる瞬間にはその対象はもうあとかたもなく消えてなくなっているんです。
どんなに頭の良い科学者でも、この「真実」を言い当てることなどできないのです。
あるいは言い得たとしてもそれは単なる「後付け」、「効能書き」だということです。それを言った瞬間にはもうそれは先を行っている。正しくはない。
なので今、指を差し出す。または今、自分の鼻を曲げてイタイイタイ!となる。あるいは「それ」、「あれ」。
これが仏法の全てなんですね。仏法の正体なのです。
そんな仏法の正体を言葉であらわすとしたら「恁麼」という以外ないのです。
恁麼とは?道元禅師の見解
それでは道元禅師はこの「恁麼」のことをどのようにお説きになられているのでしょうか?
道元禅師がおしるしになった『正法眼蔵』第十七に『恁麼』の巻というものがあります。
そしてこの『恁麼』の巻の冒頭には次のような言葉がでてきます。
恁麼の事を得んと欲せば、すべからくこれ恁麼の人なるべし。すでにこれ恁麼の人なり、何ぞ恁麼の事を愁えん。
つまりこういうことですね。
 道元禅師
道元禅師そのようなこと(真実)を得ようとするならば、そのような人となる修行が必要である。ところが、人はすでにそのような人となっているのだから、どうしてそのようなことを憂う必要があるのだろうか?
道元禅師は真実のことを「そのようなこと」、つまり「恁麼」という風におっしゃるんですね。
もっと言えば、



人ははじめから恁麼の人である。すなわちそれは、人はみな仏道の人であり、悟りの人であるということである。そして人だけではなく、目の前に展開するあらゆるものが恁麼であり、真実を現成している。ということは、憂うこと自体も恁麼であるわけで、憂いではない。
このように道元禅師は「恁麼」についてお説きになっておられます。
「恁麼」は人間の価値観や、概念、思想を越えたところをいっているんですね。
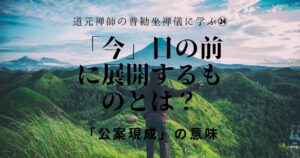
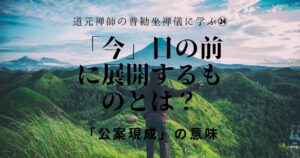
お読みいただきありがとうございました。

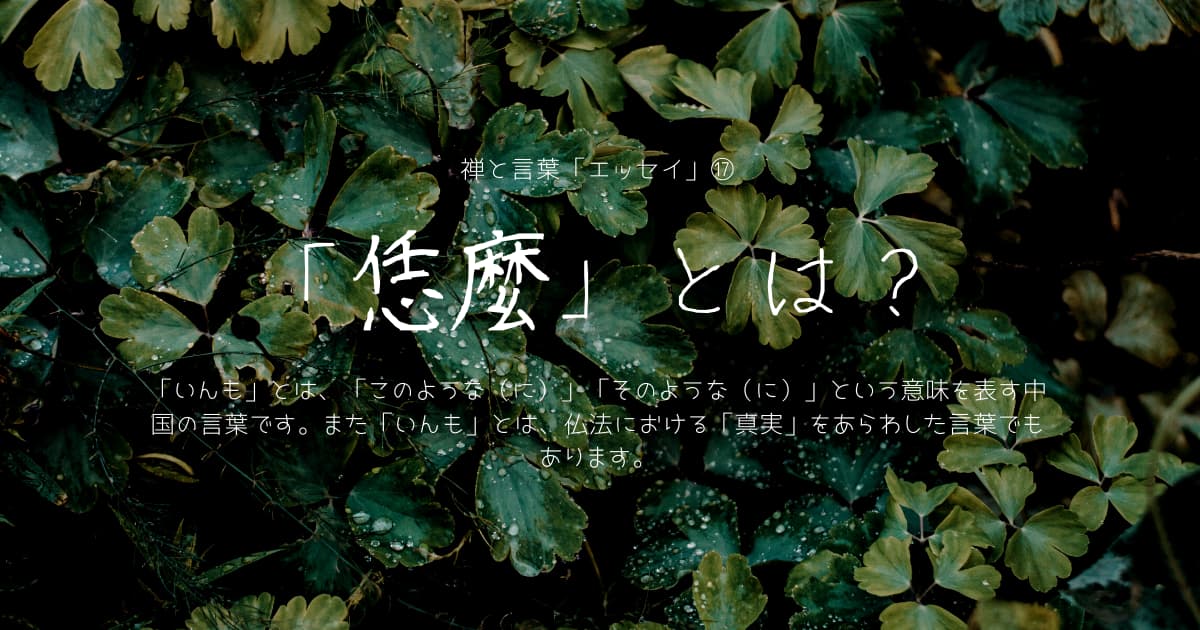
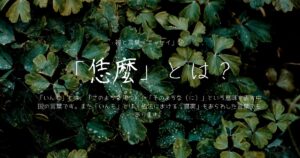
コメント