本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を読んでいきたいと思います。
まず初めに前回の、
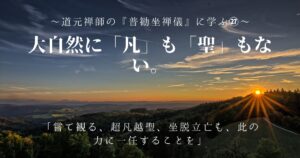
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「超凡越聖」とは「凡」も「聖」も超える事。
- 「仏」は「仏」すら超えていく。大自然の在り方。
- 「坐禅」こそ「超凡越聖」である。
- 自分の外側に「大自然」があるのではない。
- 「死ぬとき」には「死ぬ様」がある。
- 大自然にでっちあげや、ごまかしは一切通用しない。
それではポイントを抑えていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。

卒暴(そつぼう)なるべからず。嘗て観る、超凡越聖(ちょうぼんおつしょう)、坐脱立亡(ざだつりゅうぼう)も、此の力に一任することを。況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
指竿針鎚とは?
今回はこの部分を解説していきます。
この「指竿針鎚」というのは、昔おりました仏祖方が残した逸話に由来して作られた単語です。
その逸話はそれぞれ「指」、「竿」、「針」、「鎚」が絡んでいるエピソードであり、それを一つにまとめたのがこの「指竿針鎚」というものなんですね。
道元禅師はその過去にあったエピソードをここで「一つにまとめて」、またそれを「指竿針鎚」とし、このように『普勧坐禅儀』に落とし込んだわけであります。
そして「拈(ねん)ずるの転機、」というのは その「指竿針鎚に出会うことで人生ががらっと変わる」ということです。
「転機」ですので、その出会いがあれば人生がらっと変わってしまうというのですね。この「指竿針鎚」はそれだけ重大な意味を持つということです。
過去の祖師方が残したこの「指竿針鎚」にまつわるエピソード。
その「指竿針鎚」のおかげで人生が、「転機」する。
それではどのように転機するのか?
それを知る為にも、そもそもこの「指竿針鎚」にまつわるエピソードとは何なのか?を知らなければなりません。
なので今後は「指」、「竿」、「針」、「鎚」を一つずつ分けて、1記事ごとに解説していきたいと思います。
まず本記事では「指」にまつわるエピソードを見ていきたいと思います。
何を質問されても「指一本」差し出す。「一指頭の禅」
昔、倶胝(ぐてい)和尚という方がおりました。
この倶胝和尚というのは人に出会う度に人差し指を「一本」スッと立てる癖があったといいます。
またどんな事を聞かれてもスッ「一本」人差し指を立てる。
それがこの倶胝和尚なりの「教化」の在り方だったと言われているんですね。
そんな倶胝和尚が、あるお寺の住職になられた時のことです。
住職になって役職を日々務めておりましたが、中々ほぞ落ちが出来なかったんですね。
その生活に納得ができなかった。
そんなこんなで悩んでいる最中のある日の晩に、とある尼僧さんがその俱胝和尚の元へ訪ねてきます。
既に夕方で、薄暗くなっていたので「半宿」を頼みに来たんですね。
泊まる場所を探して、尼さんがそのお寺を訪ねてくるんです。
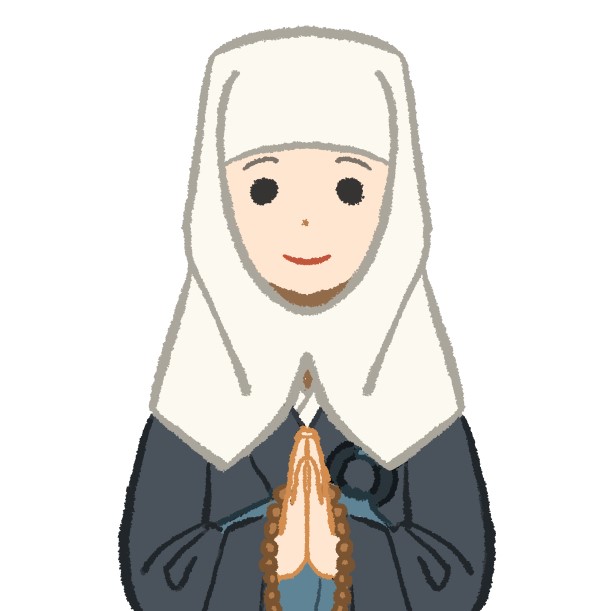 尼僧
尼僧どうか一晩だけ宿を貸してくれませんか?
そう聞かれた俱胝和尚は、



どうぞお泊り下さい。
と答える訳です。
しかしその尼僧さんは何故か、
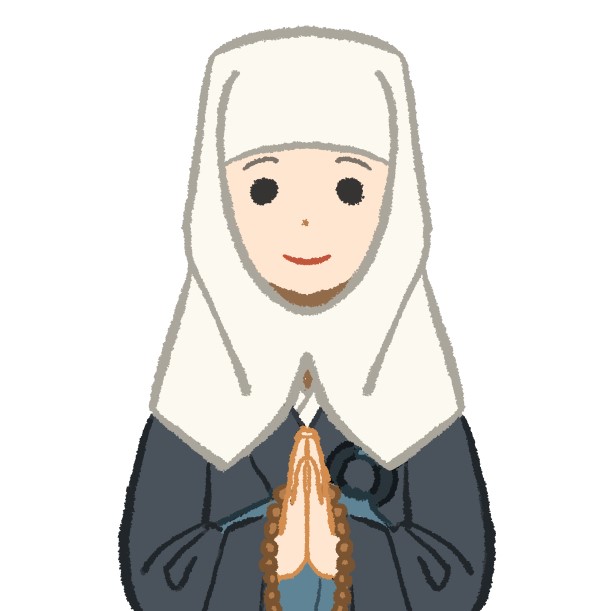
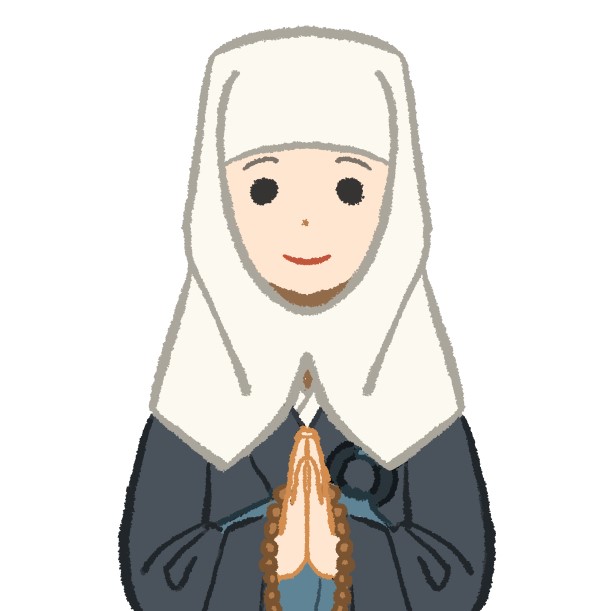
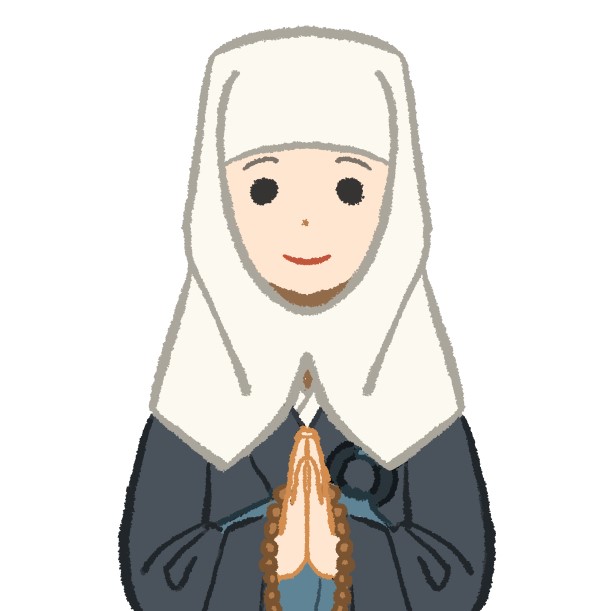
あなたが私の質問に答える事が出来たならば、泊まってあげましょう。
こう言うんですね。
俱胝和尚もさぞ不思議に思った事でしょう。
それなら、
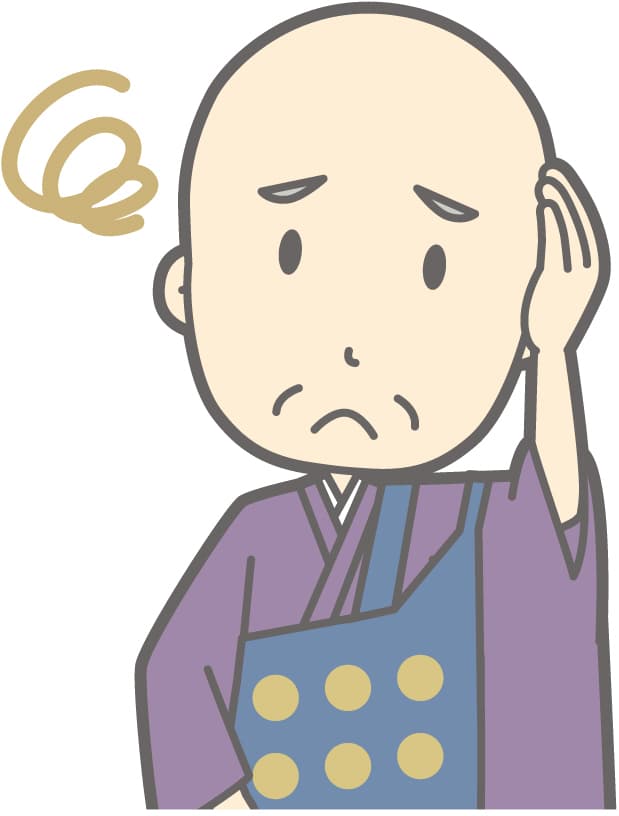
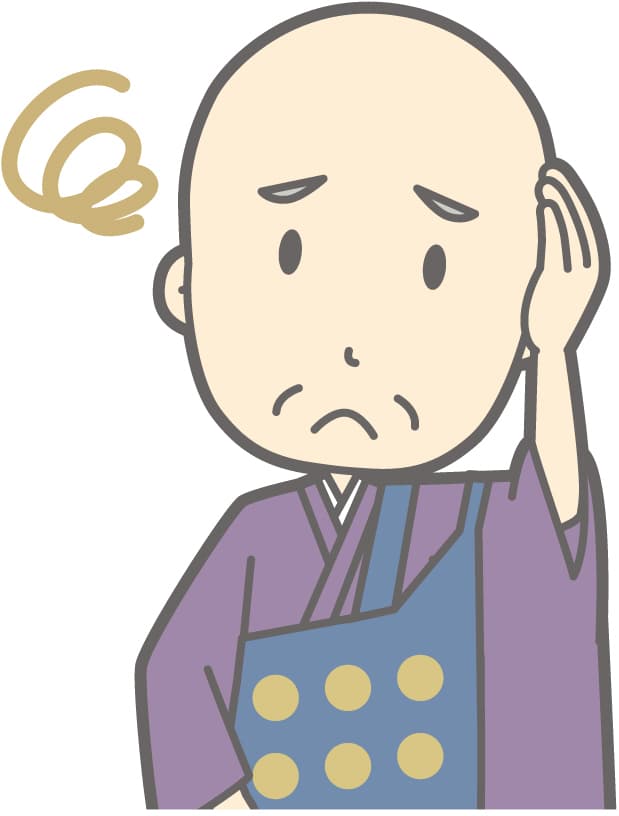
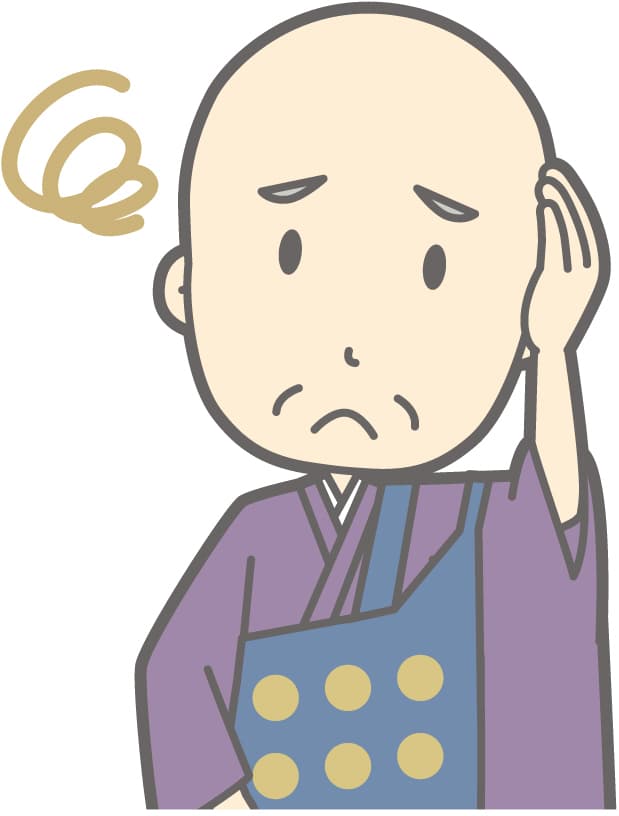
どうぞ質問しなさい。
とその質問を聞いてみる事にした。
するとその尼僧さんは、
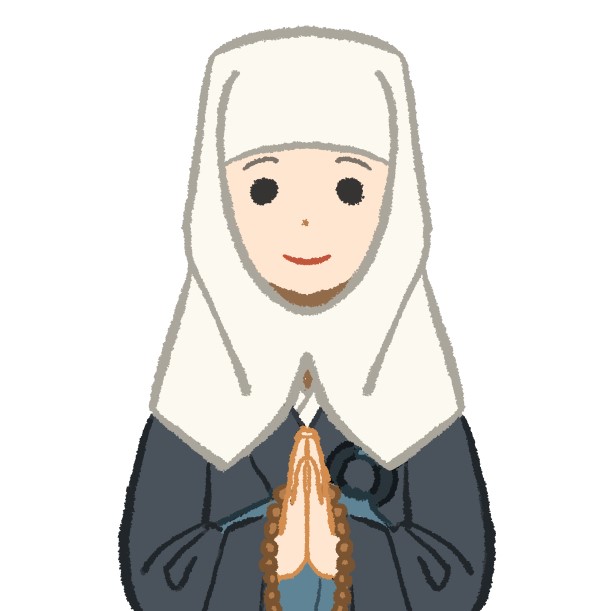
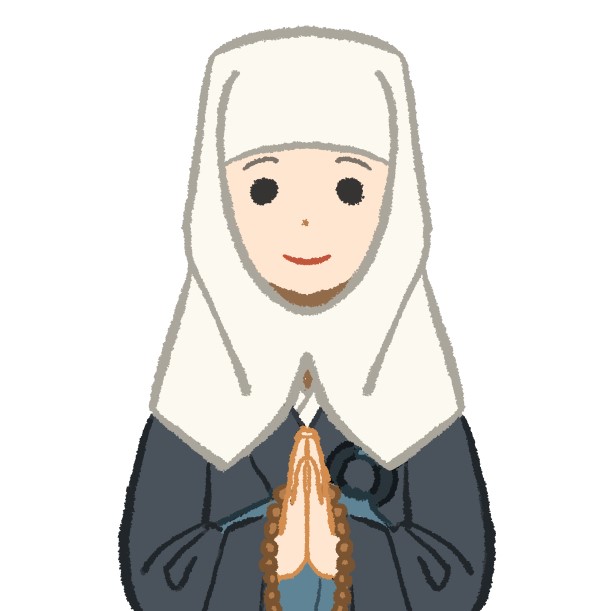
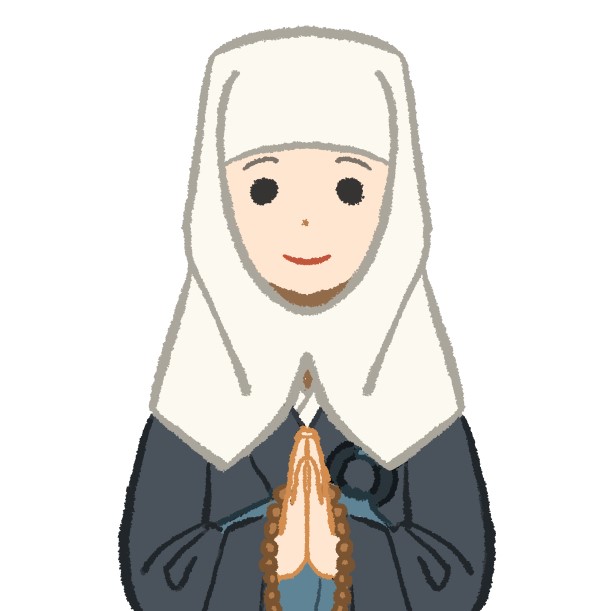
如何なるか是仏法の大意。
このように質問をしました。
そのように質問された俱胝和尚は何も答える事が出来なかったんですね。
何も答えられない俱胝和尚を見て、その尼僧さんは、
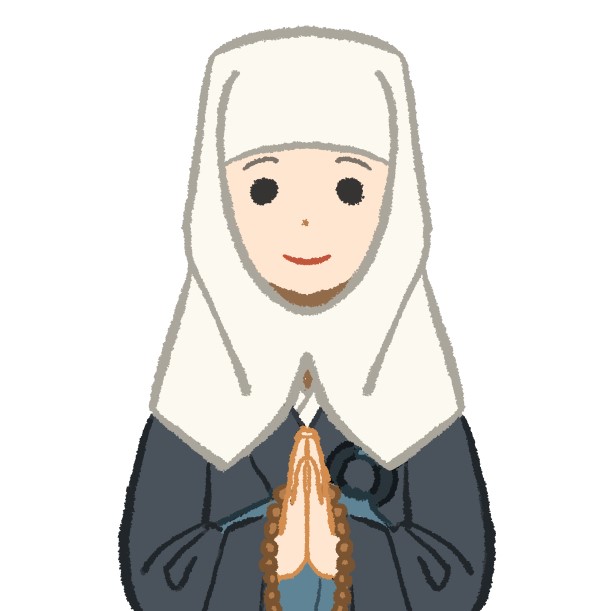
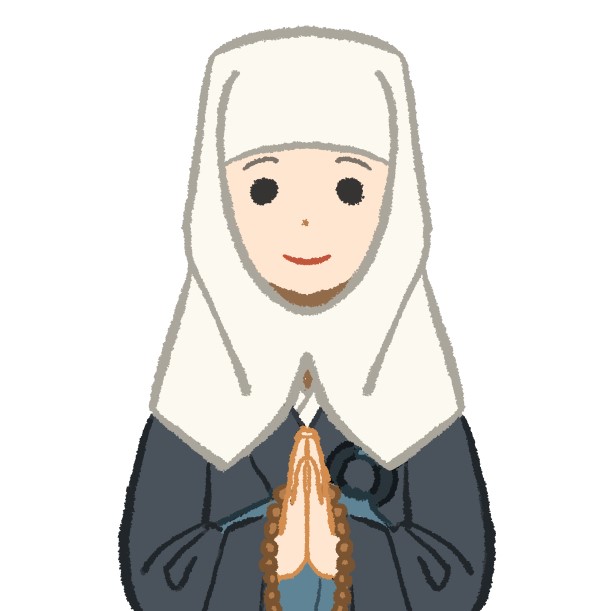
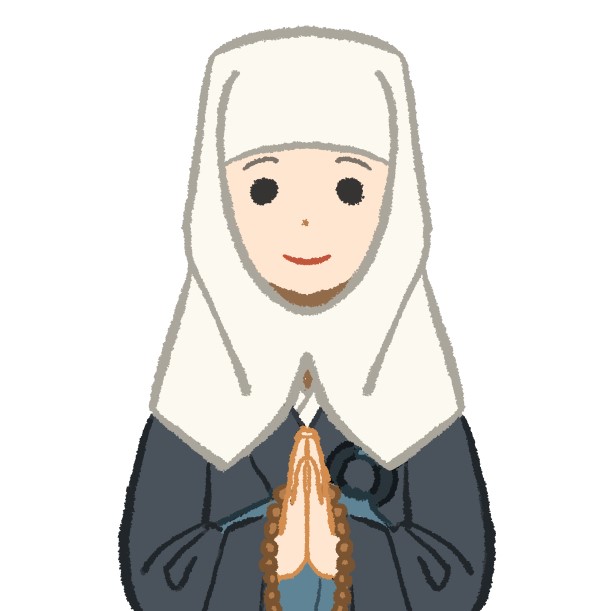
このような質問も答えられない住職の所では恐ろしくて、泊まることはできません。もう私は帰ります、他の所に行きます。
こう答える訳です。
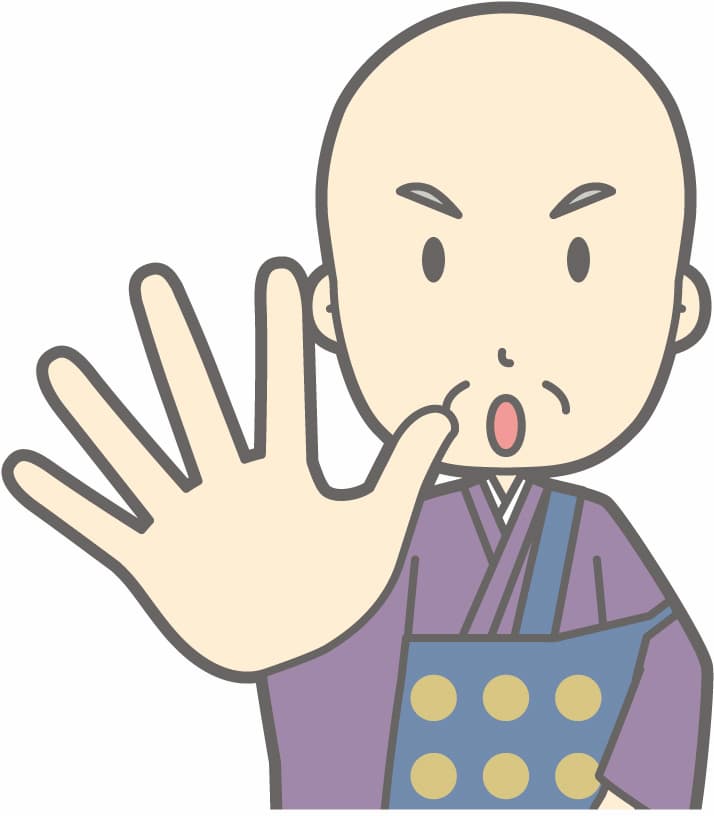
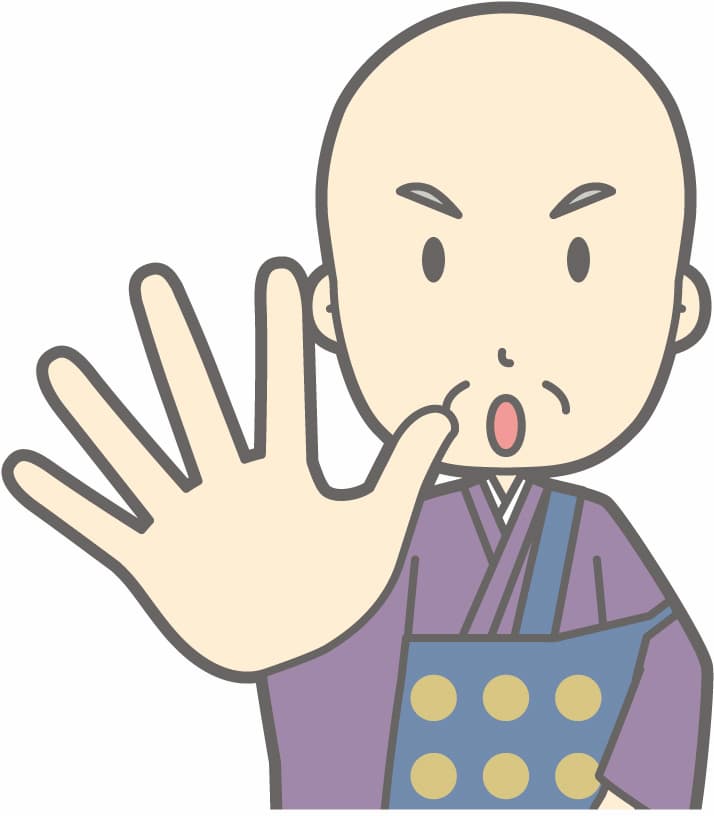
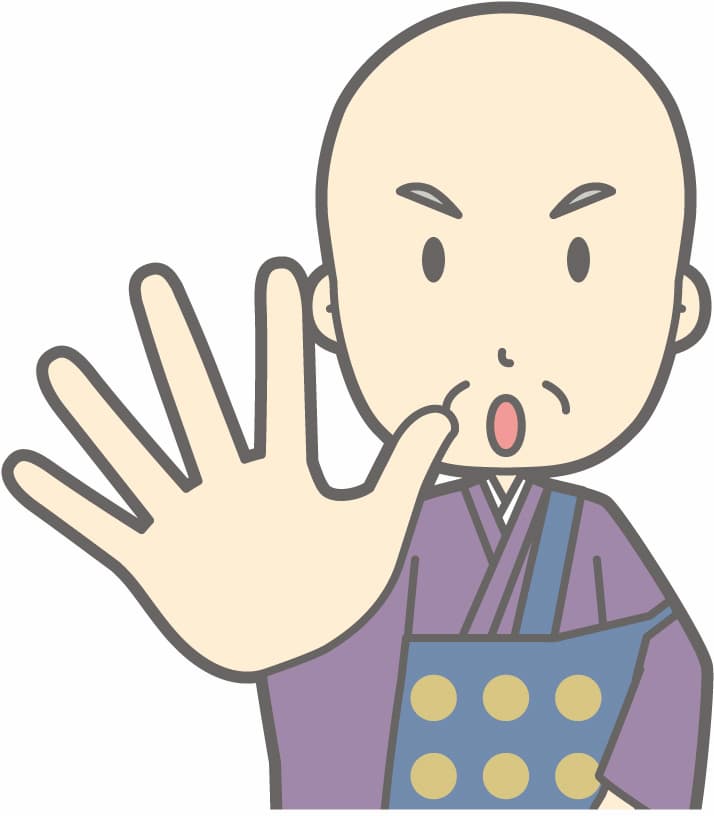
いやそう言わずにこんなに暗いのだから泊まっていきなさい。
しかし尼僧さんはそれでもさっさと行ってしまうのですね。
そのように尼僧さんに言われたものだから俱胝和尚はくやしくてしょうがありません。
女性のお坊さんに負ける、女性のお坊さんの質問に答える事も出来ない。何たる情けなさ。もうこの寺を辞めてもう一度修行し直そう。住職をやめて一から出直しをしようと思った。
そのように心に決めた同じくその日の晩に、「山の神」が夢の中に現れ、次のように俱胝和尚と対話をしたと言います。



お前はこれからどうするんだ?
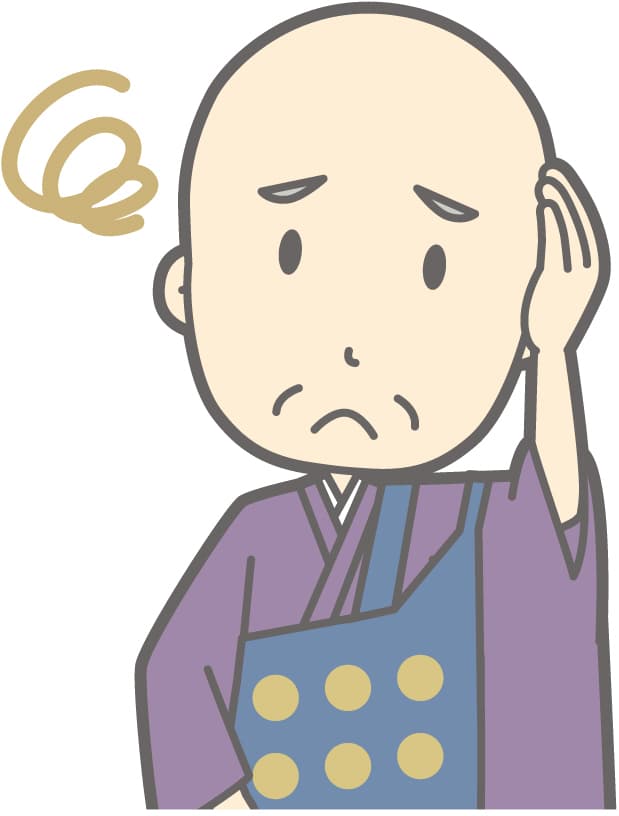
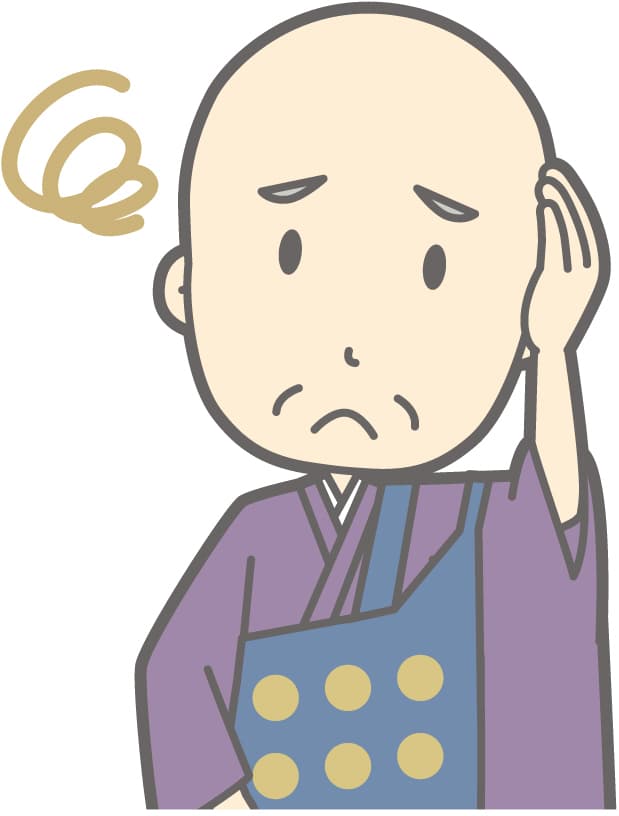
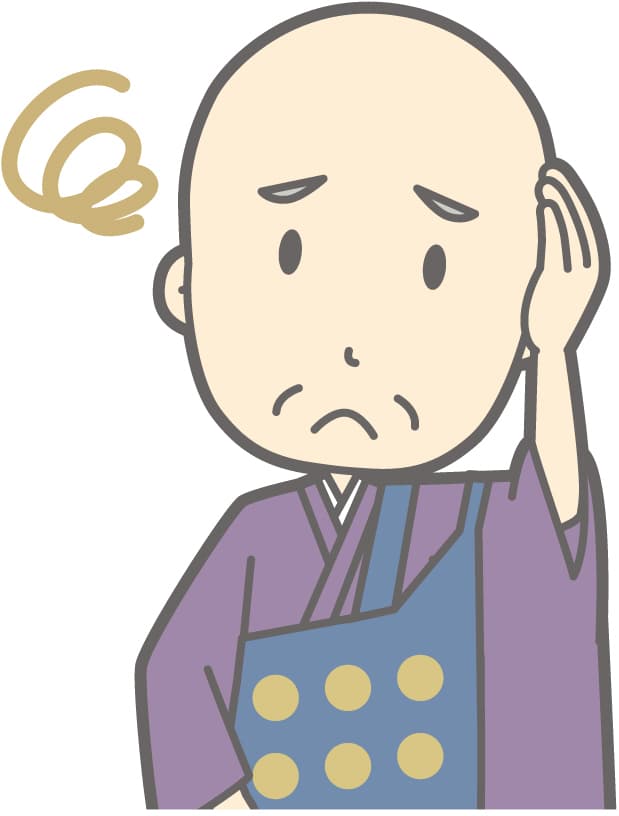
私は女性のお坊さんの質問すらまともに答える事ができません。非常に情けない人間であります。寺を畳んでもう一度修行を一からやり直したいと思います。



いや、そう言わずに少し待ちなさい。お前は未熟かもしれないが、もう少し待っていれば立派な人間がお前のもと現れるから、その立派な人間に就いて指導を受けなさい。
このように山の神が予言をされていくんですね。
すると何日もしない内に、その予言通り、ある僧侶がこの俱胝和尚の元を訪ねてきたのです。
この方こそ、後の俱胝和尚の師匠となる天竜和尚でした。
訪ねて来た天竜和尚に早速相談をするんですね。
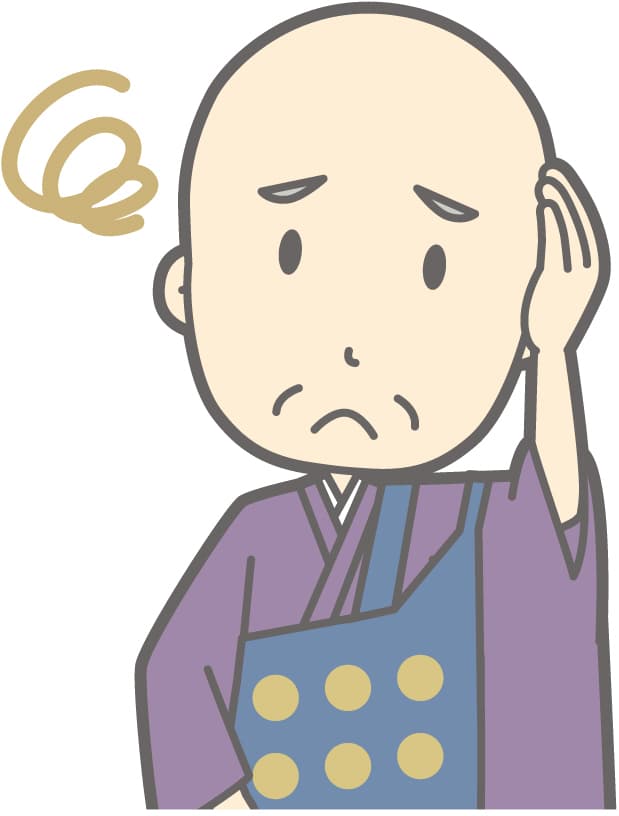
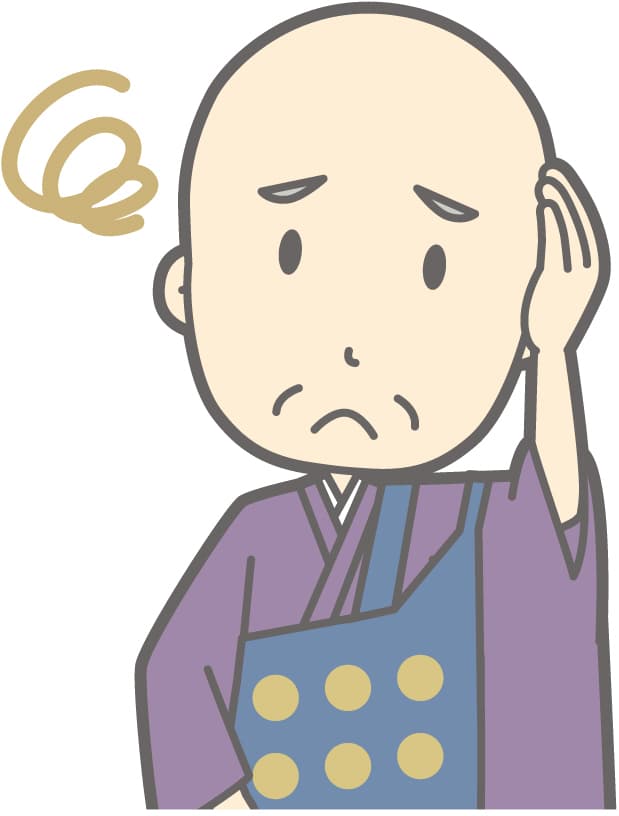
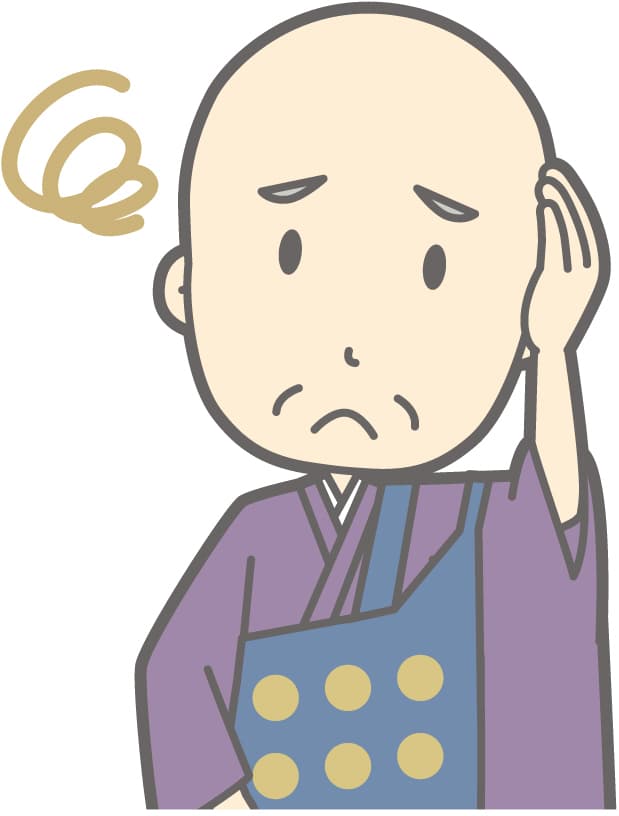
私にはこのような事がありました。非常に情けなくてしょうがありません。



そうか、そうか。だけど心配するな。お前一つ私に質問しなさい。そしたら私が何でも答えてあげよう。
そのように言われた俱胝和尚は、それではということで、あの尼僧さんと同じように質問をします。



如何なるか是仏法の大意。
すると天竜和尚は「右手の人差し指」をスッと立てたんですね。
そしてそれを見た、俱胝和尚は真実に目覚めることができたという逸話があります。
これを「一つの指の頭の禅」と書き、「一指頭の禅」と言います。
「如何なるか是仏法の大意」と聞かれ、「人差し指」をスッと立てる。
それからというものどんな質問をされても、この俱胝和尚は、天竜和尚と同じように「右手の人差し指」をスッと立ててその質問に答えたといいます。
一生そのやりかたで通したんですね。
そしてこの俱胝和尚が亡くなる時にも「私の一生はこの一指頭の禅で、一生縦横無尽である。」という様な言葉を残されてお亡くなりになられている。
生涯にわたってこの一指頭の禅を貫かれたんですね。
そして「あの時天竜和尚から教えて頂いた一指頭の禅を使い尽くす事が出来ませんでした」という風に言って亡くなって行った。
何を聞かれても一指頭の禅。人差し指をスッと立てる。これが「仏法ギリギリの教え」だと言うんですね。これが仏法の大意。これ以外に仏法は何も無いと言うんですね。
それではこの「人差し指」を立てるということは一体どういう事なのか?
真実の在り方を説くのが「仏法」
今から二万年前、我々人間の先祖である「ホモサピエンス」と「ネアンデルタール人」が共存している時代がありました。
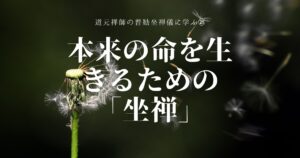
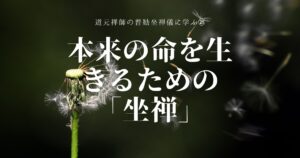
「両者」の見た目はほとんど変わらない。
「ネアンデルタール人」の方が少し体が大きかったと言われておりますが、それ以外は、見た目はほとんど変わりがない。
どちらとも髭をはやし、同じように二本足で歩いている。
また「火」を使って収穫した獣を焼いたり、それを食料として生活していたという点も何ら我々ホモサピエンスと変わりません。
しかし両者において一点だけ違っていた所があります。それはネアンデルタール人は顎の形成上、言葉を喋る事が不得手であったということです。
それに対して我々の祖先でもある「ホモサピエンス」は顎が発達していた。そのおかげで「言葉」を喋る事ができ、そして使いこなすことができたと言われているのです。
要するに我々の祖先である「ホモサピエンス」は言葉を使い、その言葉で物事を概念化し、それを第三者に「言葉」でもって伝達する事が出来た。
一方のネアンデルタール人はそういう事が出来なかったんですね。
「ホモサピエンス」だけが、「言葉」をもって伝達する事が出来たおかげで、生き延びることができた。
時に天敵揃いの大自然を生き抜き、ひいては今日のような現代文明を作り上げる事ができたのです。
この物を概念化し第三者に伝達するという事が我々人類にとって大きな進歩の一つの糸口となった。
それ以降というもの、この「概念化」という方法を使って我々は自分の思ったことを伝えたり、やりたいことを伝えられるようになり、豊かな生活を人間同士で営むことができるようになったわけです。
しかしこの「物を概念化し言葉に表す」というのは、非常に素晴らしい能力であると同時に、本来のあり方から逸脱してしまうという側面があります。
例えば、「私」という言葉があります。この言葉によって、我々はこの自分のことを私だと判断し、自我を形成できるようになりました。
しかし本来はこの自分という体は、大自然と地続きになっている訳です。大自然の生成する酸素を吸って呼吸をしたり、鳥の声がいつも際限なく聞こえ、鳥によって自分の命がおこる。つまり鳥が自分の命そのものである訳です。
本来の物事というのは全て地続きなんですね。溶け合っているのです。一つだけなのです。
それに対して、言葉を持った我々はそれを区切ろうとしてしまう。区切れないこの地続きの命に、「私」という言葉をもって境界線を作ってしまうんですね。
このような本来のあり方から逸脱してしまうのが言葉であり、「概念化」です。
今はその「概念」だけが先走り、生命の根幹がないがしろにされてしまっているような状況なのです。概念だけが全てだと捉えられるようになってしまったわけです。
またそのせいで人類の心が傷つけられて、落ち込んだり、自殺を図ったりするようになった。
このようなことは人間だけに起こることですね。言葉をもち、概念化を図れるようになった人間だけに起こることです。
しかしそのようなことは本来の世界ではないということですね。概念というのはこの実際の世界と関係していないのです。
また先ほどのように「如何なるか是仏法の大意。」と聞かれて、それを概念化し言葉で答えるのであれば「仏法の大意というのはね、かくかくしかじかこうでありますよ、ああでありますよ。」という様に懇切丁寧にあらゆる言葉を駆使して説明をします。きっと頭の良い人間はどんなことも説明できてしまうでしょうから。
しかし「仏法」は真実の在り方をいつも説かなければなりません。この世界の真実、それは全てが1つだということです。全てが常に真実を現成している。全てが真実、つまり全てが仏なのです。
その真実を見つめ、真実の話をするのが仏法だからです。
例えば我々の生命は「概念」で生きている訳ではありません。理屈なしで腹が減る。理屈なしで呼吸をする。肌をつねれば痛く、足を組めば痛い。
これだけなんです。
どんなに頭の良い人間でも、この理屈を説明することはできません。この理屈を解明することはできない。どんなにたらふく食べても次の日にはまた腹が減っている。
しかしそれがこの世界の真実なんですね。確かな存在なのです。この世界の確かな正体なのです。
我々の生活、生きている生活に理屈などありません。概念は介入できないのです。そういった世界に我々は生きているんですね。
自分の価値観や概念、そういったものはこの世界に一切通用しないのです。
そもそも言葉や概念というのは我々の祖先が生み出した「手段」でしかありません。弱い猿人類が生き抜くために編み出した些細な手段にしかすぎず、それは何かをただ説明するための「道具」に過ぎなかったわけです。
つまり「後付け」です。説明です。
この世界には全く関わりのないことなのです。
俱胝和尚が「指一本スッと出す」のは、指一本引っ張ってくれば全宇宙がそこに付いてくるからですね。
先ほども述べたように、この「指一本」が「すべて」だからです。この世界の実物だからです。確かに存在しているのであればそれはこの世界の正体です。真実です。仏法です。
それはつまりその指がこの世界の「正体」だということです。この世界の正体を捉えているということなんです。この世界を実際に掴んでいるということなんです。この世界に直接的に関わる話なんです。
「正しい仏法」はこうでなければなりません。
「指一本スッと出す」。
言葉で言えば所詮は「指一本」。しかし「指一本」を掲げたのなら、それが「仏法の大意」になるのです。
この世界の正体なんです。真実なんです。
正しい「仏法の大意」についていくら言葉を使って、概念上で説明しようと思っても正しくはないのです。
そこは「繋がった指一本を立てる。」或いは「自分が坐禅を行じる」必要があるのです。
足を組めば痛い。それは紛れもなく「確かなこと」です。つまりこの世界の「確かなこと」だということです。この世界の全てだということです。
そしてそれが確かなこの世界の「正体」なのです。
なので「指一本」差し出すだけでいいんです。それが仏法の大意なのです。
俱胝和尚は何を質問されても「指一本をすっと立てた」と言います。
これで一生縦横不尽であったと言うのです。
これで全てが通ったというんですね。納得できたというのです。
どんな質問されてもスッと人差し指一本出した。
もし学校で「仏法の大意」とは何ですか?と聞かれ指一本スッと立てたところで誰一人として分からないでしょう。試験であればそれは0点です。
しかし「指一本を立てる。」そこには仏法における大切なことが全て表されていた。確実にこの世界の正体だった。そこにこの世界の「全て」が詰まっていたのです。
指竿針鎚の「指」-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
またその中の「指竿針鎚」の「指」の部分について解説しました。
それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。
- 「指竿針鎚」というのは昔おりました仏祖方の逸話から来ている単語を繋ぎ合わせたもの。
- 「指竿針鎚」の「指」は俱胝和尚のエピソードからきている。
- 何を質問されても「指一本」差し出せばいい。
- 何故なら「指一本」が全宇宙だから。
- 「仏法」は概念化する以前を説く。
以上、お読み頂きありがとうございました。

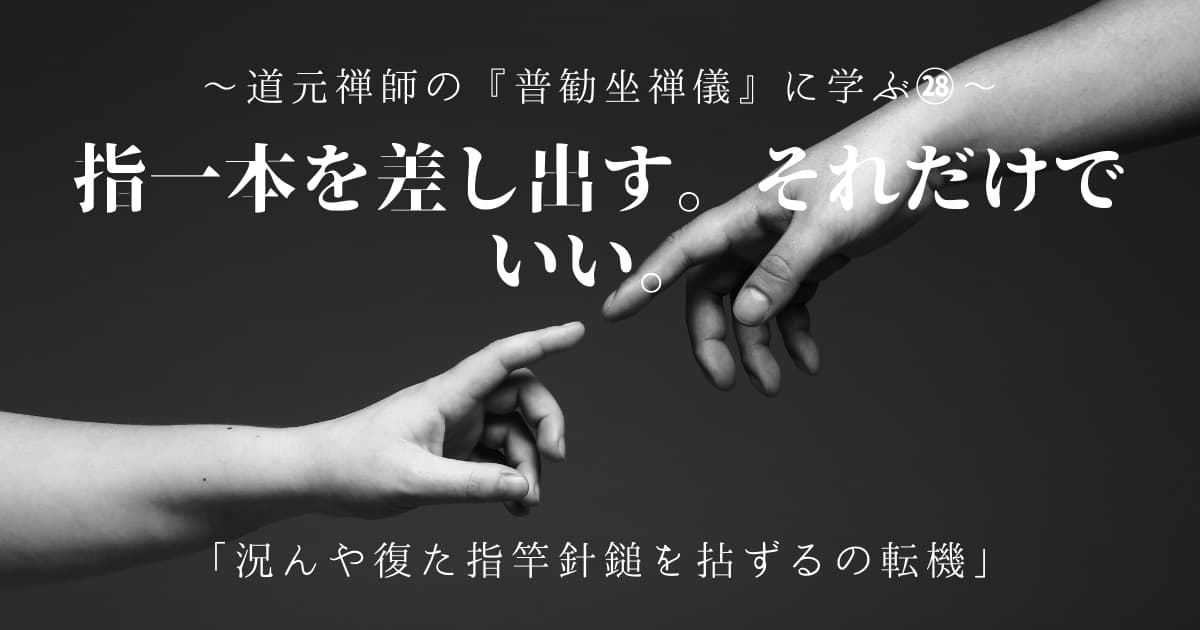
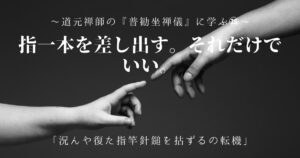
コメント