本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を読んでいきたいと思います。
まず初めに前回の、
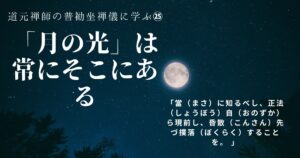
のポイントを振り返りたいと思います。
- 本当の理解とは「実践すること」で本当の理解ができる。
- 「坐禅」の「行」を行う事こそが本当の理解。
- 「昏散」とはうつうつと眠くなることと、心を乱す事。
- 「撲落」とは束縛から解放されること
- 「真実の自己」は常に目の前に展開しており、条件を満たした結果得られるものではない。
それではポイントを抑えていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。

鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。
所謂(いわゆる)坐禅は、習禅には非ず。唯、是れ安楽の法門なり。菩提を究尽(ぐうじん)するの修證(しゅしょう)なり。公案現成(こうあんげんじょう)、籮籠(らろう)未だ到らず。若(も)し此の意を得ば、龍の水を得たるが如く、虎の山に靠(よ)るに似たり。當(まさ)に知るべし、正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、昏散(こんさん)先づ撲落(ぼくらく)することを。若し坐より起(た)たば、徐々として身を動かし、安祥(あんしょう)として起つべし。卒暴(そつぼう)なるべからず。嘗て観る、超凡越聖(ちょうぼんおつしょう)、坐脱立亡(ざだつりゅうぼう)も、此の力に一任することを。況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
いつの時も「安らかに、平穏」な作法を心掛けること
今回はこの部分を解説していきます。
まず若し坐より起(た)たば、の部分。
これはそのまま、「もし、坐禅を解いて立ち上がろうとするならば、」という意味になります。
今回の『普勧坐禅儀』は、「坐禅」が終了した時のことをお話になられているわけですね。
そして、徐々として身を動かし、というのは「ゆっくりと身を動かし」という意味になります。
続いての、安祥(あんしょう)として起つべし。というのは「安らかに、静かに立つようにせよと。」という意味になります。
そして卒暴(そつぼう)なるべからず。 というのは「いきなり粗々しく立ってはいけない」という事です。
前回の、道元禅師の『普勧坐禅儀』について学ぶ⑳「坐禅」における正しい呼吸法とは?では、「坐禅」に入る前の作法についてのお話となりました。
その際、「深く呼吸をし、左右に2、3回体を振り子のようにふり、丁度重心の真ん中となる部分で止めてから坐禅に入る」という内容があったかと思います。
それと同じように今回の「坐禅」を終える時にもきちんとした作法があり、その作法に従うようにと道元禅師がお話になられるのです。
「坐禅」を始める際は振り子のように左右に大きく体を揺すって、それを段々と小さくしていき、脊梁骨(せきりょうこつ)を真っ直ぐにする。
そして「坐禅」を終える時は逆に「徐徐として身を動かし、」とあるように最初はゆっくりと体を左右に振り始め、それから段々大きくしていき、腰骨の痺れを取っていく。
こうした自然な動作で、体に負荷のないようにしてあげるのが大切です。
「安祥(あんしょう)として起つべしにみる「安祥」というのは「安らかに、静かに、」という意味になりますが、この「安らかに、静かに」というのは「禅寺」においては基本となる作法になります。
例えば坐禅堂に歩いて入ってくる際や、「坐禅」が終わって歩く際、更には普段の日常生活において歩く際も、バタバタバタバタと荒々しく歩くのではなく、一歩一歩、「安らかに歩く」ように心がけます。
これが「軍隊」であれば「三歩以上は駆け足、何ボヤボヤしているんだ!」とどやされる訳ですが、禅寺ではそうではありません。
古参和尚、新米の和尚、誰しもがこの「安祥」ということを心掛ける。
「三歩以上は駆け足!」、軍隊で言われることですが、それはつまり「目的を持って何かを行う」という意図の現れでもあります。
確かに「一般社会」においてはそのようにのんびりされたら周りのみんなが迷惑するかもしれません。「あいつは何をするにも遅くてまるで給料泥棒だ」なんていう風にもなりかねない。
しかし「禅寺」は一般社会とは違います。
禅寺は「本来」の場なのです。我々「仏」が生活をする場であるわけです。
歩き方1つとっても、人間社会のそれと同様にするわけにはいきません。
人間は本来、もっと静かに歩くべきです。動物というのは獲物を捉える側もそう、捉えられる側もそう。
決して自分の存在を知らせるように歩いているわけではありません。危機感を持って行動しているのです。
禅寺はそうした本来を行じる場所です。自然な場所です。
そこではバタバタと歩いていいわけではないのです。
何より我々仏がともに生活する場所であり、また坐禅堂や、法堂、仏殿など文殊菩薩や聖僧様などの仏様がすぐ側におわす場所でもありますので「安祥」として歩くことはもちろん、何事も「安祥」に行じなければなりません。
大きな「禅寺」もしくは「修行道場」を一度でも訪れた方ならお分かりいただけるかと思いますが、山内は本当に静かで「シーン」と静まり返っております。
所作一つ一つ、どれをとっても「安祥」に。
「坐禅」を終えて立つ時も「安祥として立つべし、決して卒暴となる事なかれ。」と道元禅師はここでお伝えになるんですね。
それが「本来の在り方」であると。
「真実」に何よりもこだわりぬく道元禅師らしい「姿勢」です。
また「坐禅」を終えると足が痺れている可能性があったり、血も滞っている可能性もあったりします。
なので「坐禅」を終えて、すぐに立とうとするとひっくり返ったり、転倒する危険があるんですね。
なのでそうならない為にも、気を付けるという意味をこめてこの「安祥(あんしょう)として起つべし 」と、お示しになっている訳です。
禅寺や修行道場での基本はこの「安祥」となります。
道元禅師は事実を重んじた
以前、道元禅師の『普勧坐禅儀』について学ぶ㉔「公案現成」の意味とは?「今」目の前に展開する一切は行き詰まりがない。の中で「竜の水を得るが如し、虎の山に靠(よ)るに似たり。」という一文があったのを覚えていますでしょうか?
これは、
そのように本当の我々の姿、真実に気付くことが出来たならば竜が水を得たような、虎が山に放たれたような力を得たということにもなる。
という意味になりますが、これにとどまらず、『普勧坐禅儀』において道元禅師はしきりにこの「本当の自分とは何か?」ということを「様々な表現」を用いてお示しになられております。
例えば以前の内容で言えば、「目の前に展開するすべてが真実。今ここにいる自分も真実」という意味で「公案現成」という言葉が用いられていたのがまさにそうでした。
「公案現成」。短いけれども大変重みのある言葉です。
また、
- 本当の自分に出会うこととはどういうことか?
- 本当の自分に行き当たるとはどういうことか?
- 本当の自分に成りきるとはどういうことか?
こういった内容のお話がこれまでにも沢山でてきては、相応しい言葉をもってして、我々に正しい見解を示してくれているのです。
言葉というのは難しいものです。使い方次第では全く別の意味にとらえてしまったりします。
道元禅師にしてみても、おそらく非常にこの言葉選びには気を使われていたのではないかと推察します。
例えば「本当の自分」とは言ったものの、それは一体何でしょうか?
参究の仕方は多岐に渡りますが、例えば「本当の自分」というとまるで「嘘の自分」というものがあるように思ってしまいます。
また「真実の世界」というとまるで「偽りの世界」があるのかとも思ってしまいます。
物事はこのように相対的に捉えれば、理解しやすいわけですが、実際にはこのように簡単に相対的にできるほど、物事というのは単純ではありません。言葉で簡単に捉えられるわけではないのです。
人間が比較しやすいからといって、言葉でそのように作り上げているだけなんです。
物事というのは本来比較もできなければ、言葉で言い表すことはできないのです。
例えばあなたが昨日、「カラオケ」にいったとしますね。
その日、喉の調子が悪く思うように歌えなかった。
その際、「本当はもっと上手いんだ!今日は本当の自分じゃないんだ!今日はダメだった・・・。」などと言ったりするのではないでしょうか?
しかしその「ダメだった」のが本当の自分なんですね。
なぜなら「いつだって自分はどこにもいかないから」です。
「嘘の自分」や「本当の自分」というのは存在せず、頭のなかの出来事でしかないわけです。
全て本当の自分なんですね。
あらゆるものが真実であり、「本当の自分」や、「嘘の自分」というのは「我々の頭の中」にだけ存在しているのです。
我々人間は常に「真実」に出会っているのです。
「本当の自分」もしくは「偽りの自分」というのは人間の「概念遊び」のようなもので、そこは慎重に参究しなければなりません。
道元禅師はこうした言葉や概念の問題と真摯に向き合い、そして答えを提示してくれております。
「本当の自分」。「真実の自分」とは何か?
この「真実」というのは、「生命の実物」だということです。今ここにいる、この私が組んでいる「坐禅」。それがこの「真実」だというのです。
つまり「坐禅をすると足が痛い」、それこそ「本当の自分」に出会っている瞬間、すべてに出会っている瞬間だというのです。
なぜならその中には今あげたようなさまざまな現象が包括されているからです。どこにも行かない、どこにも行けない自分が全て含まれている。またその自分と世界は今まさに繋がっている。全てがまさに包括されている。さらにそこには人間が言い表すことも全て包括されているからです。

そのことを知っている道元禅師は「本当の自分」、「真実の自分」に関しても適切なアプローチをすることができ、そのことを見事に言い表すことができたり、的確な回答を導き出すことができるのです。
例えば「只管打坐」という言葉がそうですね。今の「公案現成」もそうです。
言い方は様々あるにせよ、我々が「今生きている事実」に着目されておりました。この尊さを道元禅師は知っておられました。
それが全てであることを知っておられました。
「眼横鼻直」という言葉にも、それが如実に現れております。
今ここ、この私という事実。事象。それが全てだと。お悟りであり、成仏であると。
だから事実を起こせ。命を燃やせ。足を組めと。
人間どんなに辛い事があっても「生きている事実」、つまり「真実」は揺るがないんです。常に「事実」という救いが目の間に、横に、上に、下に広がっているのです。
その事実を「仏」と呼ぶのです。足を組む。痛くなるという事実。ですからこの「坐禅」のことを「仏行」と言うんですね。
そう思うと誰しもが「本当の自分」に出会えているし、「真実」に包まれた「今」があるわけです。
道元禅師のおすすめになる「坐禅」はそうした「真実」を行じております。事実の尊さ、今ある命の尊さに気づかされてくれるわけです。
いつの時も「安らかに、平穏」な作法を心掛けること-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説しました。
それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。
- 「坐禅」を終える時はゆっくりと組んでいる足をほどき、身を動かすこと
- 「坐禅」を終える時は安らかに、静かに立つようにすること
- 「坐禅」を終える時は、足が痺れている可能性もある為、いきなり荒々しく立ってはいけない。
- 「坐禅」のみならず、大自然の歩き方というのは常に安らかに平穏な作法を心掛ける事。
以上、お読みいただきありがとうございました。



コメント