『永平広録』第478段の上堂を参究する
先妣忌辰の上堂。乞児、鉢盂を打破する時、桃李縦い霜と雪とを経るとも、吾が仏の毫光、十方を照らす。光光微妙にして法を演説す、這箇はこれ仏祖の処分する底、さらに衲僧行履のところに向ってまたかつ如何。拄杖を擲下して大衆を顧視し、右手の指をもって指して云く、看よ看よ、衲僧の拄杖、巾斗を打す、触処一時に業識裂く。
高祖様が須弥壇に上られてご説法されました。
「先妣」というのは亡き母のことで、その亡き母へのご供養のために上堂をされました。
道元禅師のお母さんは藤原基房の娘、「藤原伊子」だと言われており、彼女は非常に美しい女性だったと言われております。
当時、京の街は非常に乱れておりました。平家が占領していた時代でした。
当時の世の統制者、後白河法皇の子供には源頼朝、木曾義仲がおりますが、その木曾義仲に「ある勅命」が下されます。
「京の街から平家を追放しろ」と。
その命を受け、木曾義仲は兵を上京させて、平家を京都から追い出そうとしました。
そのやり方はとても乱暴なものだったと言われ、この義仲の乱暴な振る舞いには法皇は辟易していたと言います。
京の街におった公家(平家)たちはこの木曾義仲の存在を大変恐れるわけです。
なんとかして許しを請おうとし、当時絶世の美女と呼ばれていた、先の「藤原伊子」を木曾義仲に側室として差し出し、許しを得ました。
しかしあまりの木曾義仲の傍若無人ぶりに見かねた後白河法皇は、今度は源頼朝を通し木曾義仲のいる京都に攻め込みます。
最終的に木曾義仲は宇治川の戦いで大敗してしまうのでした。
だんだんと木曾義仲の勢力も衰退していき、当時側室として仕えていた「藤原伊子」は今度は「久我通親」の側室になります。
この久我通親も同じく後白河法皇の有力な側近でした。木曾義仲が排除された後、この久我通親は、後白河法皇や後鳥羽上皇の側近として権勢をふるう存在でした。
次にその久我通親の側室となったわけです。
こうした多くの権力闘争に巻き込まれていった「藤原伊子」。彼女は朝廷の政略結婚の道具として利用された、悲劇的な女性として知られています。
そのような中、久我通親との間に道元禅師が生まれます。
しかし道元禅師が八歳の時に母であるこの藤原伊子は亡くなってしまうわけですね。母親と死別する。
非常に辛い幼少期をお迎えになります。
人の儚さ、あるいは人生に無常を感じられ、母親の親戚筋でもある当時天台宗の高僧だった人を頼って、出家を決意されます。
道元禅師にはこのような経緯があるわけです。
前置きが長くなりましたが、今回の上堂はそのような経緯と、その経緯をもたらした亡き母への年回忌法要に関するものです。
またこれは道元禅師五十一歳、亡くなる晩年、一年七ヶ月前の上堂にもなります。
乞食の道は母を安心させる
現在もそうですが、法事するときにどのような気持ちで行うのが良いのか。
一般的には両親に対して、感謝の気持ちを表すのが通例です。ありがとうございましたと。
今あるのは両親のおかげだという気持ちがあるから法要ができるわけです。
事実、今あるのは両親のおかげです。
そのように思うと、人生、誰にとってその感謝しかないはずです。そしてそれに気づくことができれば、もうそれで成仏です。
しかしなかなかそれに気づくことができない。
また亡くなった親に対し、回忌法要を行うというのは、親にありがとうという気持ちを伝えるのと同時に、心配いらないよと伝えるためのものでもある。
道元禅師のお母さん、藤原伊子にしてみれば自分で産んで、八年で死別してしまった我が子は私のことを思って心配しているだろうと思われているかもしれない。
だからどうぞ安心してくださいと。
先祖供養というのは大変意義のあるもののわけですね。
道元禅師は当時久我通親のもと、名門中の名門のもと、久我家の期待を一心に背負って、生まれてきました。
しかし出家をしてしまうわけです。周りからも心配されたかもしれない。
そのことを母親も同じく心配しているだろうから、心配してくれるな。そのような思いも込められて先祖供養を行われるわけですね。
またそれに伴う今回の上堂もされた。

乞児、鉢盂を打破する時、桃李縦い霜と雪とを経るとも、吾が仏の毫光、十方を照らす。
乞児というのは乞食のことです。
こつじき、食を乞う。
本来これが僧侶の在り方ですが、現在の日本で、お寺の住職が食を乞うなんてことはほぼありません。
托鉢もほとんどしませんし、中には多くのお金を溜め込む僧侶もいたりします。
しかし本来は乞食ですね。
またその托鉢では、お金ではなくお食事を布施してもらう。
南方仏教の托鉢では、朝一番でぐるっと町中を回る。そこで朝と昼の食を頂戴する。
そしてご飯をいただいてくる。それを朝と昼の食事とする。
午後になってしまうと食べることができませんので、寺の小僧にあげたり(彼らは午後になっても食べられる)、それでも残った場合はご供養する。
川とか池にそのご飯を魚にあげる。保管は一切しない。
そのような形が本来の基本でそれが乞食であり、僧侶のあるべき姿です。
乞児、鉢盂を打破する時、桃李縦い霜と雪とを経るとも、吾が仏の毫光、十方を照らす。
これは、そんな乞食をする子供と、道元禅師ご自身が置かれた状況を照らし合わせ、述べている内容です。
先述の通り、托鉢においては食事を布施してもらうのが基本です。
その時は「応量器」といって一番大きな器を持ってもらい歩きます。これをあるいは「鉢盂」と呼びますが、その鉢盂が破れてしまった。修行僧にとって全財産とも言えるものが無くなってしまった。
非常に嘆かわしい状況です。
道元禅師にしてみても、永平寺の冬は非常に厳く、そもそも托鉢に行くことができない。
まさに鉢盂が破れてしまった状態だったのでしょう。
大変ひもじい思いをしながら冬を越えていた。
道元禅師の亡き母親からずれば非常に厳しい時節を経験しているなと思っているかもしれない。
藤原伊子自身は時代に翻弄されながらも、豊かなお嬢さんとして育った。
我が子はこんなにもひもじい思いをしている。安心していないかもしれない。もっと豊かな生活をしていれば母親は安心できるのかもしれない。
自分とえいば乞児のようなものであります。
しかしそれが出家の道。本来大安心の道。
乞食の身になったとしても、それは必ずやお母さんに対し、長い年月が過ぎようと、仏の光が照らすと。
手塚治虫の「三つ目が通る」ではないですが、仏様には両目の間にもう一つ目がある。これを「毫光」と言いますが、この道はまさに「毫光」であると。
その毫光は十方を照らす、宇宙を照らしているから、どうか安心してくださいよと。本来の人間の生活をして、仏として生きている、だからどうか安心してくださいよと。
貧しいのが真実
光光微妙にして法を演説す、這箇はこれ仏祖の処分する底、さらに衲僧行履のところに向ってまたかつ如何。
演説するというのは、大袈裟な感じがしますが仏法における演説というのは言葉を持って懇切丁寧に概念説明するのとは違います。
10月のこの時期には金木犀の花が満開になります。
近くによると、非常に良い香りがする。そういう時期であります。
この金木犀の花は「演説」しているわけです。
例えば金木犀の花で悟った人がいます。宋の時代の、オウテイケイと呼ばれる有名な禅僧です。
そのオウテイケイが師匠に質問する。

真実の仏法への近道を教えてください
と。
その師匠と一緒に山道を歩いていたのでしょう。
ちょうど崖の上に咲いている金木犀の花、ちょうど辺りに香る金木犀の花。
そのような質問を受けた師匠は逆にオウテイケイに質問をします。
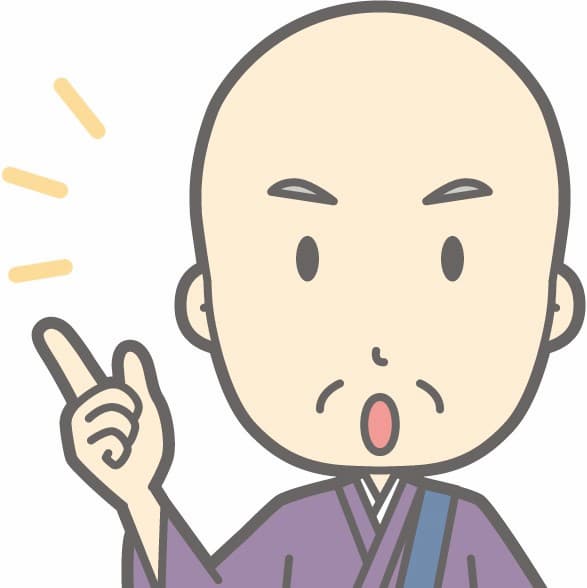
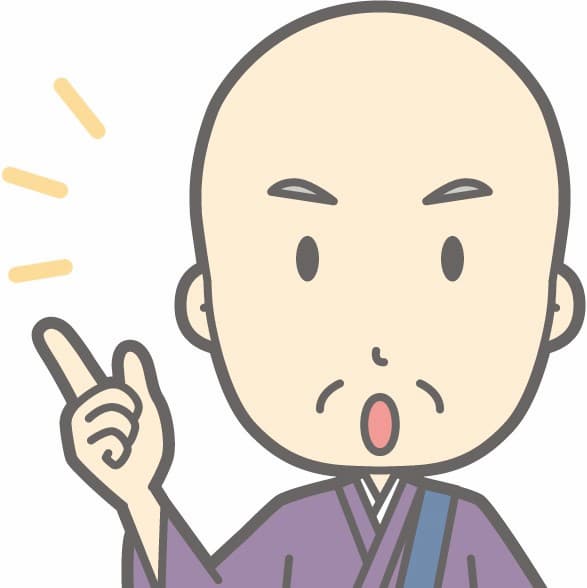
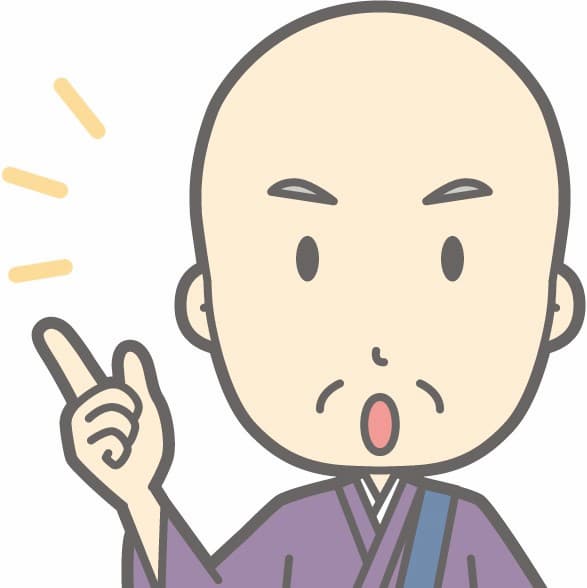
お前は金木犀の香りを聞けるか?金木犀の香りがちゃんとするか?
と。



はい!ちゃんと聞けますし、香ります!
と答える。
お師匠さんはそこでオウテイケイに



我汝に隠すことなし。
いつでも真実は丸出しじゃないか。いつでも法は演説しているじゃないかと。
そこで悟ったんですね。
このように仏法でいう演説というのはいつもむき出しの状態のことをいうわけです。いつでも説法していることをいうわけです。
金木犀の花が説法している。
ただこちらの受け止める側が、そのことを窺い知ることができない。見ることができない。真実を受け止められないだけなのです。
目の前に展開する全てのものが法を演説している。真実を表現している。
上堂の内容に話を戻すと、仮に厳しい冬場に非常にひもじい思いをしているとしても、それが真実なのですよと、いつも真実はむき出しですよと。
そのように言われるわけですね。
光光微妙にして法を演説す、這箇はこれ仏祖の処分する底、さらに衲僧行履のところに向ってまたかつ如何。
そこではお母さんへの報告と同時に、そこに集まっている修行僧たちにも言っているわけです。



これが仏祖の在り方であり、本来の自己の在り方である。
このようにしてみなさん仏法を学んでいきなさいと。
確かに仏法は貧しいかもしれない。
しかし出家したからには乞食でありますから、貧しさが基本です。
だからそれを忘れてくれるなと、修行僧にいうわけです。
なにしろ人、一人一人には食べられる量が決められている。何も心配しなくていいわけです。明日の食事の心配は明日すればいい。
仏教興隆からこの二千年の間、坐禅をして餓死したものは一人もいない。仏祖の処分とは皆そのようなものであると。貧しいものだと。だからどうぞ心配するなと、そういう内容です。
腹を減らしながら修行をしているのが一番尊いのだと。一番豊かなのだと。
斧を投げたところ、斧が投げられたところ
拄杖を擲下して大衆を顧視し、右手の指をもって指して云く、看よ看よ、衲僧の拄杖、巾斗を打す、触処一時に業識裂く。
次に道元禅師は自分の右手で持っていた杖をポンと投げ出し、そこに集まっている修行僧たちに見よ見よと。
「巾斗」というのは斧のことですね。その投げた杖をこの「巾斗」に例えているわけです。
斧というのはご存知の通り、刃の部分は非常に重く、柄が小さい。
なのでポンと投げると、簡単にひっくり返る。トンボ返りする。
その斧を投げたところ、斧が投げられたところは、今までの常識的な概念を打ち破ってくれる、というのです。
会津地方のおもちゃで「起き上がりこぼし」というのがあります。この「起き上がりこぼし」はどこへ投げても、ちゃんと立つわけです。あるいは「投げられたところに座るこぼしかな」という歌もそうであるように、どこへ投げても、ちゃんと立つわけです。
それではその「投げられたところ」というのは、一体どこなのか?一体なんなのか?
平成元年に貧乏寺の次男坊として生まれた。またそこで男として生まれた。こんなところに産みやがってとは言わない。そここそが投げられたところです。
また生まれた時もそうですし、「今ここ」がまさに投げられたところ。みんな投げられたところ。文句言わずそこで生きるしかない。「投げられたところに座るこぼしかな」。この「起き上がりこぼし」のように。
そこには今までの常識的な考えは一切通用しない。その斧を投げたところ、斧が投げられたところは、人間の常識的な概念を打ち破ってくれる。
人間は名誉や地位や、お金を得なければならない。
確かに事実ですね。あるいは生きていく上での常識です。
しかしそんなもののために生まれてきたのか?もっと大切なものがあるんじゃないのか?
名誉や地位や、お金は所詮飾りでしかない。人間同士で作りあげた常識でしかない。真実では無いわけです。
それにそんなものを持ってあの世にはいけない。
お母さんどうか、そのことをわかってくださいよと。お母さんからすれば私の今は非常にひもじそうに映るかもしれない。悲しまれるかもしれない。
しかし私はちゃんと自分をいただいて、今を一生懸命生きていますよ。だからどうぞ安心してくださいと。
このような道元禅師のお母さんに対するおもいが込められた上堂であります。

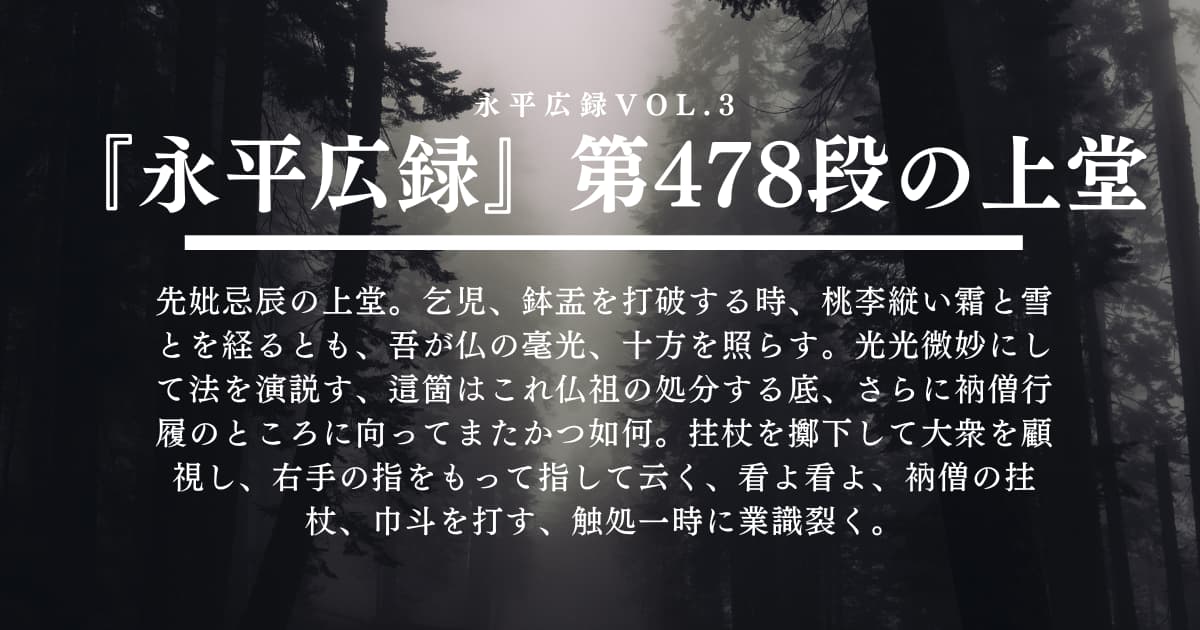
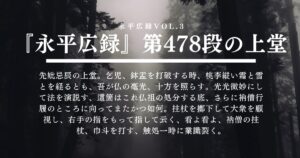
コメント