本記事では仏具、「木魚」の由来について解説していきます。
それでは早速参りましょう。
木魚を使うお経と使わないお経がある
「大悲心陀羅尼」というお経をご存知でしょうか?
大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)とは正式には「千手千眼観自在菩薩広大円満無礙大悲心陀羅尼(せんじゅせんげんじざいぼさつこうだいえんまんむげだいひしんだらに」と言います。
そしてこの大悲心陀羅尼というのは、観自在菩薩(観音さま)の大慈悲をあらわした経典だと言われております。
道元禅師がおひらきになった「曹洞宗」においては毎朝、「朝課(ちょうか)」というお務めを行います。
毎日毎日、朝早くにこの「朝課」というお勤めをするのですが、そのお務めの中には今回の「木魚」を使ってお唱えするものと、「木魚」を使わないでお唱えするものとがあります。
この「大悲心陀羅尼」ではこの木魚をついてお経を唱えていくんですね。
このように「木魚」を使うお経と使わないお経とで分かれる理由は何なのでしょうか?
「木魚」が用いられるようになった経緯

そもそも「木魚」というのは、「黄檗宗」をお開きになった黄檗隠元(おうばくいんげん)禅師が伝えたものだと言われております。
それまでは「木魚」という仏具は日本にはなかったんですね。
そのためこの「木魚」を打つという習慣も日本にはありませんでした。
しかしこの「黄檗禅師」が日本に到来し、「木魚」をお経の中でも使うようになったのです。
「ポクポクポクポク・・・」
「木魚」とは要するに「音頭取り」ですね。
木魚をすべて燃やした
しかし、お経の中でその「木魚」を使って音頭取りをする習慣を、当時永平寺の五十代住職であられた「玄透即中(げんとうそくちゅう)禅師」という方が非常に拒もうとするわけです。
というのも道元禅師から由々しく、「正伝の仏法」を守り続けてきた当時の永平寺においても、この「黄檗宗」の伝承と同時に、その習慣に乗っかるような形をとっていたのです。
要するに当時の流行に流されてしまい、多少ながらも永平寺内でもこの「木魚」の使用が認められるようになっていたのです。
木魚の影響力が結構あったというわけなんですね。
因みに現代の永平寺においてはこの「木魚」の使用は一般的に認められております。
それでもそこから五十世の「玄透即中(げんとうそくちゅう)」禅師が晋山(住職になること)された際、法堂(本堂)や仏殿にある「木魚」を全部、山門頭に放逐して燃やしてしまったという経緯があるんです。
意図としてはこうして「木魚」を使い、「音頭」を取って気持ちを高ぶらせてお経を読むのは「仏法」にふさわしくないというんですね。
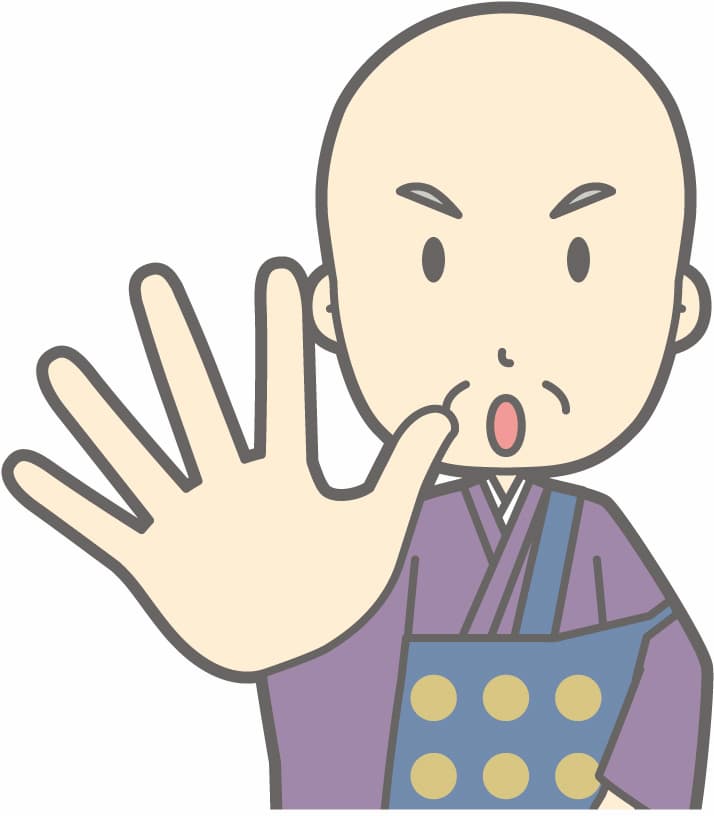
そのような読経(お経を読むこと)の仕方を我々が真似してやらなくても良い。あれでは念仏宗と違いないではないか。
といって、永平寺山内にある「木魚」を全て放逐したという経緯があるんです。
木魚が世間に広く根付いていった経緯
「木魚」を使うと、お経が音頭に乗せられて聞こえてしまうんですね。
例えば、「木魚」を使った「大悲心陀羅尼」では、「な~む~か~ら~た~ん~の~と~ら~や~や♪」と始まっていくのですが、「木魚」が伝えられる前までは、息を吸って吐くだけの呼気読み形式で、この「大悲心陀羅尼」を読んでおりました。
しかし「木魚」の使用というのは永平寺にも確かに伝わっていきます。
そうした木魚を用いる風習は本山にも大きな影響を与え、それからというもの、直下の全国のお寺でも「木魚」を用いた音頭読みが用いられるようになったと言われているんです。
それが今日にも残っている。
これが「木魚」が広く世間に根付いた要因だったんです。
ただそんな中でも、現在の神奈川県横浜市にある「西有寺(さいゆうじ)」というお寺では、当時世間でこの「木魚」を使った音頭読みが流行していたにもかかわらず、律儀にその呼気読みを遵守していたと言われております。
現在は「木魚」は大切な仏具として全国で用いられているし、曹洞宗でも「木魚」を用いての「大悲心陀羅尼」の読経が広く一般的になっております。
「木魚」には確かにメリットがあるんです。
「木魚」を使って音頭を取りながら読経していくことで、大衆みんなで調和を揃えて読経することが出来るからです。
「木魚」のおかげで、お経が揃って聞こえるんですね。
お経は揃って聞こえるとかっこいいですよね。大衆一如が僧堂における基本です。皆が揃って同じことをする。そして一つの大心に向かって精進していく。
その点を考えると「木魚」を使い、修行僧たちの調和をとることは決して悪いことではないわけですね。




コメント