本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を読んでいきたいと思います。
初めに前回の、
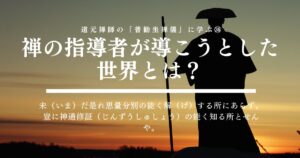
のポイントを振り返りたいと思います。
- 禅の指導者が導こうとした世界は、「我々が今ここに生きている実物の世界」のこと。
- 「一部分」から「全体」は見れない。
- つまり「思量」の世界とは「生命の一部分」でしかない。
- 「考え」ばかりが先行しては、生命の本当の姿にはたどり着けない。
- 神通力が「悟り」のように思ってしまう。
- 仏法には手応えが無い。「これ」というものがない。
- 「仏法」とは大自然の在り方。「実物」。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
「感覚」や「知識」の延長にあるのが「仏法」ではない

今回はこの部分の解説をしていきたいと思います。
声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。の流れ
まずは、
という部分から参りましょう。
ここは少し長い説明とさせていただきます。
この部分にはある故事が由来しています。
昔、香厳智閑(きょうげんしかん)」禅師という非常に立派な禅僧がいました。
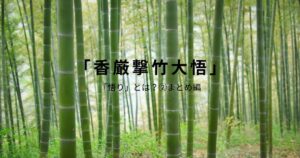
潙山霊祐(いさんれいゆう)禅師という、こちらも禅界では有名な方として知られる人ですが、その弟子にあたる人物です。
この香厳智閑禅師は、幼少の時から出家の志があったとされ、百丈懐海(ひゃくじょうえかい)禅師の道場で出家をされました。
非常に聡明な方だったんですね、この香厳智閑禅師は。
しかし、残念な事に彼が一人前になる前に「得度の師匠」であるこの百丈懐海禅師は亡くなってしまいました。
それから香厳智閑禅師は師匠のすすめで、彼の兄弟子にあたる潙山霊祐禅師の所を訪ねていきます。
これはその時にまつわるお話です。
初めて潙山霊祐禅師にお会いした時、潙山霊祐禅師から次のように言われるんですね。
 潙山霊祐禅師
潙山霊祐禅師お前は非常に頭が良いと聞いている。一つを質問したならば十を答える、十を質問したならば、百を答えられる程、頭脳明晰であるというではないか。しかしお前が答えるのは悉く皆、『仏教経典』に書いてある言葉ばかりだ。そこでだ、お前さんの「父」、「母」がこの世に生まれる以前の「自己」についてどうか一言、私の為に説いてくれないか。
これは当時の香厳智閑禅師からしてみれば間違いなく難問だったに違いありません。
今の我々でもこの問いに答えることはおそらく難しいはずです。
「父」、「母」がこの世に生まれる以前の「自己」について一言説いてくれと言われても、それが一体どういう類の話なのか見当もつかず、さらにそれを説いてくれないか?と言うのですから。
父、母が生まれる前の自己とは何か?
この香厳智閑禅師は非常に聡明な方だったので、自分の知識には自信があった。
しかし自分の持っている経典、或いはその道場にある経典、それらを全て読み返してみてもどこにもこの「父母未生以前の自己」については語られていない。そんな言葉すらない。関連しそうな話も教学もない。
それでも香厳智閑禅師は自分の頭脳を振り絞って今度から新しい師匠となった潙山霊祐禅師の下へ向かって様々に答える訳です。
しかしことごとく、師匠の潙山霊祐禅師から、



それは父母未生以前の話ではない。お前がこの世に生まれてから習い覚えた話であろう。
と否定されてしまう。
何度も何度も行くんのですが、ダメなんですね。
「その答えは皆、お前がこの世に生まれてから後習い覚えた話ではないか。」
と。
そこでこの香厳智閑禅師は、ついに嘆き悲しんでしまうんですね。
そして今まで自分がかき集めて来た『経典』を本堂の前で全て燃やしてしまうんです。



私は今生において真実の教えに目覚める事はない。仏法の真実を会得する事はできないんだ。
そういって山の中に入っていき、そこで一人静かに生活する事に決めたんですね。そしてその山の中で、尊敬する祖師の「墓守」をすることに決めたのです。
香厳撃竹大悟
そのようなこともあって、実際に墓守の生活が始まった。
ある日この香厳智閑禅師が一生懸命庭掃きをしておりました。
すると掃いた箒の先にイシツブテがあって、それが勢いよく飛んでいき、竹に当たった。そこで「カチーン」と音がした。
その「カチーン」という音を聞いて、忽然としてこの香厳智閑禅師はお悟りを開いたと言われております。
これを有名な「香厳撃竹大悟」と言います。非常に有名な故事です。
詳しくは以下の記事でも考察しておりますのでご参考ください。
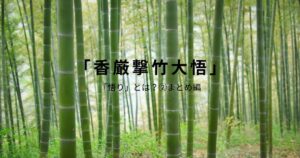
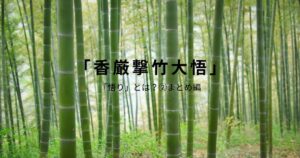
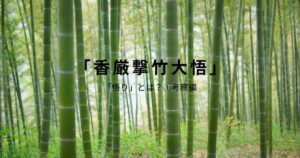
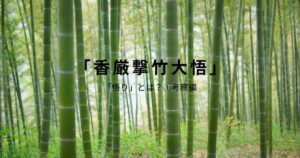
潙山霊祐禅師からは「父母未生以前の自己について。あるいは父、母が生まれる以前の自己について。お前さんが生まれてから習い覚えた事ではない話をしてくれ。」と言われていた訳ですね。そこを正しく示しなさいと言われていたわけです。
この香厳禅師と同じく、我々人間は実に知識が豊富で頭でっかちであります。知識で何事もあてがおうとする。あるいは自身の主観で物事捉えようとする。そしてそれで物事が分かった気でいる。捉えられた気でいる。
それが我々人間です。
当時の香厳禅師もなんとかして頭や知識、概念で、わからないことを解決しようとした。
しかしそのようなことに対して、師匠の潙山霊祐禅師は「お前が生まれてから習い覚えた事ではない事を私に話なさい。それが仏法の真実だ」というんですね。



お前が習い覚えた事はそれは「習い覚えた事」でしかない。それは仏法の真実ではない。私の言う生命の実物ではない。自己の正体ではない。そこをどうか私に話してくれ。
このように言うわけです。しかし同時に潙山霊祐禅師はヒントも一生懸命出してくれていたんですね。
つまり、
という事を一生懸命説き、香厳智閑禅師に提示していたのです。
経典にも載っていない、習い事ではないのが言うならば自己の真実。これが父母未生以前の自己であると。またそれが仏法の大意であると。そのように述べられるわけです。
それに対しこの香厳智閑禅師は「あぁでもない、こうでもない」と言う。ここぞとばかりに『経典』を引っ張りだしてくるも、悉く却下をされてしまうわけですよね。
そこで致し方なく山の中に入っていくわけですが、竹箒に当たったイシツブテが竹に当たったその「音」を聞いて忽然と大悟することができた。そのことに気づくことができた。父母未生以前の自己に出会うことができた。
これは一体どういうことでしょうか?そこで自己の真実、仏法のギリギリのことが分かったと言いますが、何がどのように分かったというのでしょうか?
まず、誰でも竹に石ころをぶつけ、その「カチーン」という「音」を聞けば悟りが開けるのかというと、それはどうでしょうか?
おそらく違いますね。
これは「イシツブテ」が竹に当たるという事自体が重要ではないわけです。
竹に石が当たることが重要なのではなくて、それはただの「契機」にしかすぎないわけです。
これを「契機」にして、尚且つ「香厳智閑禅師」だから「父母未生以前の自己」に触れる事ができた、真実に目覚めることができたという事です。
誰でもいいわけではありませんね。
私が同じようにやったところで「悟り」には出会えない。
私が一生懸命庭掃きをして、「竹」に「石ころ」をぶつけたとして悟れるわけではありません。
そこにはそれぞれの「契機」があるわけです。
「声色の外の威儀たるべし」は「香厳撃竹大悟」の故事にみる
香厳智閑禅師にとってはそれが「契機」だった。その「契機」を経て見事に、「お悟り」に出会えたわけです。
香厳智閑禅師が「大悟」した場所というのは、墓守をしていた場所で、そこは師匠である潙山霊祐禅師のいるところから遠く離れたところがその場所でした。
香厳智閑禅師はその嬉しさのあまり、その遠く離れた場所から潙山霊祐禅師のおられるお寺に向かってお拝をするんですね。
「あの時私に親切に教えてくれて、本当にありがとうございました。やっとお師匠様の骨身に染みる教えがちゃんと分かりました。」と言ってお拝をするわけです。
その時に感謝の意を込めて次のような「詩」を作るんです。
これは簡単に言えば、
たった一度、「カチーン」という音を聞いた。その音を聞いたとたん、今まで覚えていたいろんなことが、どこかへ行ってしまった。その瞬間「大悟」した。それは別に修行や鍛錬の結果ではない。本来常にそこにあったものだ。またこれまでに耳で聞いた声などで培った世間の威儀に囚われるものではない。
といったところでしょうか。
潙山霊祐禅師は「父母未生以前の自己」とは何か?を香厳智閑禅師に問われました。
その答えがこの「詩」でも言われている通り、「生まれてから経典で学んだものではなく、本来常にそこにあったもの」だったと気付いたということですね。
生まれてから経典で学んだものではなく、本来常にそこにあったもの、これが自己の正体、父母未生以前の自己、ひいては仏法の大意であると。
この追求に関しては後ほど行っていきますが、この詩には「声色威儀」という言葉があります。
今回の普勧坐禅儀の内容は、
というものですが、ここでいう声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。というのは元々はこの「香厳撃竹大悟」の故事の、この詩から来ていたのです。
「声色」の世界は「感覚」の世界。
さて、香厳智閑禅師は「父母未生以前の自己とは本来常にそこにあったもので、我々が耳や目で、習い覚えたもの以外の在り方だったと理解する事が出来ました」と、この詩で言っている訳です。
『般若心経』に「色声香味触法」というフレーズがでてきます。
「声色」とはこの「六境」の事を指すんですね。
「色」、「声」、「香」、「味」、「触」、「法」ですね。
我々の「外界」にある、「六境」の事を指します。
或いは「眼耳鼻舌身意」という「六根」。
「眼」であったり、「耳」であったり、「鼻」であったり、「舌」であったり。
そういう我々の持ってる感覚器官で、先の「六境」とやりとりをしているのが我々の人間生活である。
つまり人間生活というのは感覚生活なんですね。今述べて来た感覚によっていつも生きているんです。
これを「声色」と言います。
なので今回の、
というのは、真実の在り方はその声色によるところではない、人間の感覚によるところではないという事なんですね。
そのことが以下の詩に現れているわけです。
冒頭でも述べた通り、我々人間というのはこの「感覚」から離れる事ができません。
感覚や概念、主観が全てであります。
例えば、家のない人は路上で「新聞紙」にくるまって寝る時があるでしょう。
永平寺にいる修行僧は寒い僧堂で「柏蒲団」にくるまって寝る。
或いは新婚夫婦に至ってはふかふかの気持ちいいベッドで、温かい「羽毛布団」に包まれて寝る時もあるはずです。
しかし「新聞紙」にくるまれて寝ようが、「柏蒲団」にくるまれて寝ようが、「羽毛布団」に包まれて寝ようが、寝てしまえば同じなんですね。
もちろん寝るまでの「ムード」で言えば「新聞紙」と「羽毛布団」では「天」と「地」ほどの差があるでしょう。
しかし寝てしまえばそんなものは一切関係ない。寝ているという事実においては、両者に差はないわけです。
この寝るまでの「ムード」に振り回されているのが我々人間です。感覚に惑わされているということです。
或いは食べ物を頂く際。
美味しい、おいしくないという、喉元までの世界で我々は生きているのが我々だということです。
しかし胃袋に入った地盤でいえば両者に差はないのです。いずれであってもきちんと消化してくれる。
このような感覚に振り回された世界の事を、「声色」の世界というんですね。
しかしそれは真実ではないと。
「真実の世界」というのは、喉元過ぎて胃袋で消化し、吸収されるまでの実際の過程、これだけなんです。「声色の外」なのです。
それにも関わらず人間は、その真実の世界を別の世界に捏造し、またその「声色の世界」で振り回されている。
あるいは何でもかんでも概念ではかる。概念で解決しようとする。
これは全く見当違いなのだと。真実とは関係がないぞと言うことなんです。
我々は感覚とは関係なく、腹が減りつづける。眠り続ける。生き続けているわけです。
香厳禅師は竹に石が当たる音を聞いて、お悟りを開くことができた。
風鈴は四方八方、どの風から吹かれようがチロンチロンと音を鳴らします。
同じようにそこではただただ竹の音がなんの妨げもなく四方八方に広がっていくような感じがしたのでしょう。
それをきっかけにこの世界というのは常に「ありのまま」。そこでは妨げるものは何もないと。常に真実が展開しているということに気がついたのです。「声色の外」が真実なのだと言うことに気づいたのです。
なのであくまでも「契機」だというのは、この世界のすべてがそのように真実が展開されていて、それらが我々を待っている状態だからです。そこには我々の概念も必要なければ、学も必要なく、いかなるシチュエーションでもその真実に出会うことができるからなのです。常に出会っているからなんです。
また世界もそうだが、自分自身においても肌をつねれば痛い。足を組めば痛い。そういうありのまま、妨げるものが何もない命を、真実の命を生きている。先ほどの風鈴と同じような命を生きている。
それがこの世界の真実だと言うことです。また我々の命の正体だと言うことです。世界と私は同じく真実の命を生きているんですね。自分も世界も、そこではこの世界の正体をきちんと現成しているのです。またこの世界のすべての恩恵を常に、今この瞬間にもいただいていること、そういうことに気づかれたわけです。
いつ、どこでにいても、これ以上も以下もない命を自分自身が生きているということに気づかれたわけですね。
これ以上も以下もないもの、それがこの世界の真実。それが仏法の正体だと。そしてそれがこの自己だと。足を組めば痛いこと。肌をつねれば痛いこと。世界の真実はそれだけなのだと。
そこにはこの世界の恩恵がすべてあると。仏の恩恵がすべてあると。またそれはいつの世も変わらないものだったと。いつの世も変わらないこの世界の正体、つまり「父母未生以前の自己」であったと。
今、ここ、この自己にこの世界の正体が含まれていることに気づいた。この世界の全てが含まれていることがわかった。
この自己こそが仏法ギリギリであるという師匠の話も分かった。そしてその自己というものに一歳人間のしがらみ、概念というものが関与していないということにも気がついた。
こうした様々な出会いを一瞬の内にされたわけです。
その契機がこの「香厳撃竹大悟」だったわけです。
師匠である潙山霊祐禅師はこのことをしきりに香厳智閑禅師に示そうとしていたのです。
父母未生以前の自己。それは真実とは何か?ということ。しかしこの世界は常に真実のみで、今、ここ、この自己こそが仏法の大意であるのだと。
またこのことは経典に載っているものでもなければ、いずれ概念で捉えられるものでもない。概念や学を必要とするものでもなければ、介入すらできないものなのだと。
今、ここ、この瞬間、全てが仏法のみなのだと。しかしそれを妨げているのが人間の「声色(感覚、概念)」なのだと。
それに気づけるかどうかだと。そこにどうか気づいてくれよと。


これは今日にも伝わる非常に重要な故事です。これまでにも様々な時代、様々な場所で、師匠と弟子との間で取り上げられた公案でもあります。
道元禅師もこの公案を取り上げられるのには、これがあまりにも重大な内容だったため、念を押す狙いもあったことでしょう。
「感覚」や「知識」とは別にあるのが「大自然」
今の部分に関して説明が長すぎてしまいすみません。
続いての、
という部分に移りましょう。
ここは少し駆け足で説明しますが、「知見」というのは、我々の頭の中の思量分別の事ですね。
「知識」と言ってもいいですね。
我々はその思量分別、知識によって日常生活をやりくりしています。
「声色(感覚)」と同様、それが全てでありますね。
しかしここで言うのは、思量分別(知見)の前の軌則です。
「軌則」というのは、我々の日常生活の事を指しますので、知見の前(さき)の軌則 というのはつまり「思量分別以前が我々の本当の在り方」という意味になります。
そして、非ざる者ならんや。 というのは「仏道」を志す者とでもここでは言っておきましょうか。
なので、那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。というのは、
思慮分別に基づく、知見下、知識、見下、以前の規則(在り方)が大自然の法則である。
もしくは、
思慮分別に基づく、知見下、知識、見下、以前の在り方を仏道を志すものは目指しなさい。
という意味になります。
今回の、
をまとめると、
仏法は「感覚」に囚われたり、「思慮分別」に基づくものではない。それ以前の「大自然」の在り方がそのまま「仏法」の法則である。
という風に今回はまとめさせて頂きます。
道元禅師がこのように『普勧坐禅儀』で引用されたのは、香厳智閑禅師と潙山霊祐禅師の故事から「仏法」の大意を見たからでした。
そのことを念を押さねばならない。仏法は契機の違いこそはあれど、常に今目の前に展開しているのだと。
それに気づくことが全人類の使命であると。
道元禅師のお勧めになるこの「坐禅」。そこでは「だんだん足が痛くなる」という確かな事実が起こります。
しかしそれがこの世界の正体だということです。嘘偽りのないこの世界の正体だということです。
上も下もない。この世界の正体をこの坐禅が現している。
いわばこの「坐禅」こそがこの世界のすべてなのです。「仏法」そのものなのです。
この世界の本来ということで、我々として本来おるべき場所、常に目指すべき行、それが坐禅だということですね。
誰一人として例外なく、この坐禅を目指すべきだと。
このことを要するに言いたいわけです。
言ってしまえば今回の「声色外の威儀」というのは「坐禅(仏法、大自然)」のことを指しているんですね。
この「声色外の威儀」を常に目指してくださいと。そういうことをお話になっているわけです。
坐禅が、あるいはこの自己がこの世界の正体なのです。
なので道元禅師は自己に親しむことを強くお勧めになるわけですね。
「只管打坐」をお勧めするわけであります。
「感覚」や「知識」の延長にあるのが「仏法」ではない-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
の部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 「声色の外の威儀たるべし」はかの「香厳撃竹大悟」の故事から引用した
- 「声色」というのは、「人間」の感覚の世界
- 「知見」というのは、「人間」が培った知識の延長の世界
- 仏法はその「声色」や「知見」の延長の世界を指すのではない
- それらとは別にある「生命の実物」こそが「仏法」であり、「大自然の在り方」である
- そしてその「大自然の在り方」を「実践」しているのが「坐禅」である
以上、お読みいただきありがとうございました。

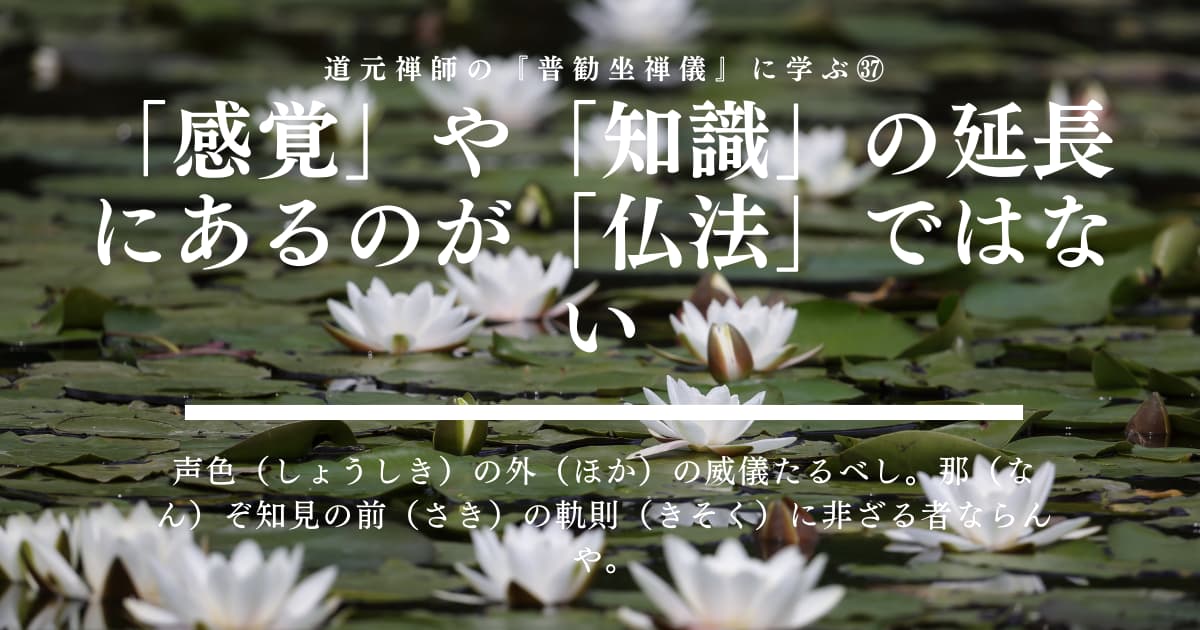
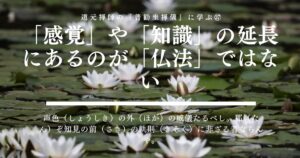
コメント