禅にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第5弾といたしまして、「典座(てんぞ)」についてをお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
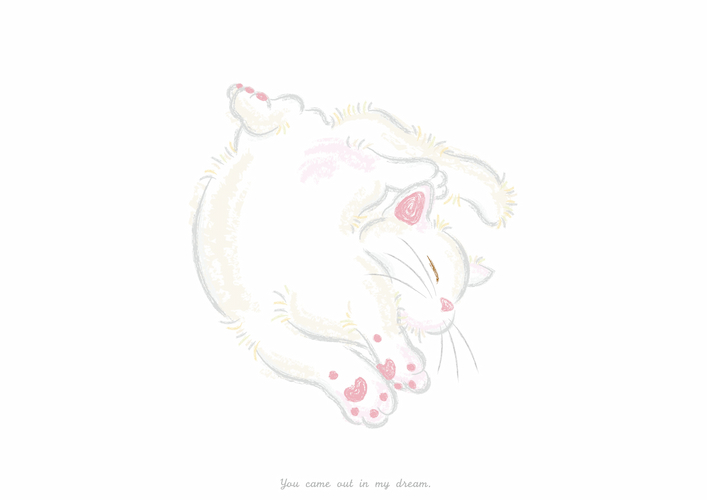
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

典座とは?
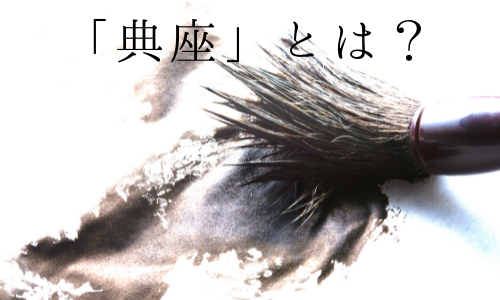
今回は恐れ多くも「典座」についてお送りします。
恐れ多くもといったのは、この「典座」が非常に重要な意味を持っているからです。
「典座」は禅宗の修行道場において、修行僧、及び雲水の食事をつかさどる役職のことを言います。
つまり食料の調達、調理、給仕まですべてを司る責任者の事をこの「典座」といい、またその「典座」が率いる寮舎のことを「典座寮」と呼びます。
例えば福井県にある曹洞宗大本山「永平寺」では、振鈴(修行僧の起床時間)より2時間早くこの「典座寮」が起きて、「小食(朝食)」の準備を始めます。
普通の修行僧が3時半(冬場は4時半)に起床するのに対し、この「典座寮」はそれよりも早く起き、役務につくわけです。
大衆の数が200人近くにも及ぶので、そのくらいしないと間に合わないんですね。
我々人間にとって最も大切なことは「食べること」です。
特に修行僧にとっては厳しくも辛い日々を乗り越えられるのはこの食事があるからです。そこできちんと栄養を摂ることができるからですね。
もとより、穀物にしても、お粥にしても、野菜にしても、それは命であり、そのような命をいただくことによって生きながらえることができる。
この食事は命を扱う出来事。非常に大切な行いだということを我々はもっと意識しなければなりません。
そうした大切な行事を司るのがこの典座寮で、またこの「典座」が修行僧の命運を握っているといっても過言ではありません。
山内において他の役職にくらべても高尚な務めとされており、敬意をはらわれる立場なのです。
一般社会でいえば「食事係」や「飯炊き係」、「お勝手がかり」というと雑務としての位置づけです。
そのために下っ端の人間が行う事が多かったりするわけですが、修行道場においては全くの「逆」です。
大勢の仲間の命をあずかり、縁の下の力持ちを演じなければならないため、修行を長く積んだ修行僧や、古参和尚さんでしか務まらないような仕事なのです。
典座の心得え
「典座」が扱う食材は、どれも尊い「仏様の命」です。
仮に「ご飯粒一粒」であったとしても、大切に扱わなければなりません。
にんじんの皮も無駄にしない。
大根や皮も無駄にしない。
普段は捨ててしまうような「ヘタ」や「種」であっても大切に調理され、大衆にふるまわれます。
繰り返しになりますがそれらはすべて「仏様の命」だからです。
この世界に無駄なものなど本来一つもないのです。全てが仏様の命です。
実際の「食材」だけではありません。
道元禅師は『典座教訓』の中で、「什器に関してはきちんと整理整頓するように」と書き記しております。
道元禅師がいうには「調理場」や「洗い場」、食材を盛り付ける「什器」も食材と同様に大切に扱わなければならないぞ、ということですね。
それも全て仏様の命だからです。
そのため永平寺ではこのような什器も大切に扱われ、保管されております。
典座寮は見方を変えれば大変厳しい修行場なのです。
そのようなこともあって「典座寮」は常に厳粛な空気に包まれております。怖い古参和尚さんでいっぱいです。
道元禅師と典座の出会い
栄西禅師の勧めもあり、1223年、道元禅師は24歳という歳で、真の「仏法」をもとめ中国へと赴きます。
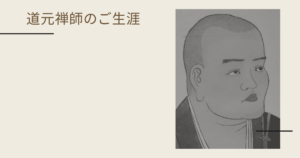
中国に到着した折に、「道元禅師」は一人の中国僧と出会うんですね。
その中国僧は中国の「阿育王山」という修行道場のまさに「典座」であり、食材の材料を求めに来ていたところ、船で停泊していた道元禅師ご一行と出会います。
道元禅師からすれば初めて出会う異国の僧だったわけです。しかも今から熱心にその教えを請おうとしている中国の僧だったわけです。
その際、色々話したい事があった「道元禅師」はこの「典座」を引き留めて接待しようとしました。
しかしその「典座」は、自身がいなければ道場は大変なことになってしまう。一日たりとも休むことはできないと告げ、そこでは「典座」という役職の大切さを説き、早々に帰ってしまうのでした。
「道元禅師」はこの「典座」から「修行」とは坐禅をしたり、教本を読んだりすることだけでなく、日常生活のあらゆる事が大切な修行であるという事を教えられたのです。
またこれも「道元禅師」が「天童山景徳寺」でご修行をされていたときのお話です。
「道元禅師」はある年老いた「典座」が仏殿の中庭で「海草」を干しているのを見つけました。
その「典座」は手に竹杖を持ち、炎天下のもと、笠もかぶらずに「海草」を干していたんですね。
その姿があまりにも辛そうにみえた、「道元禅師」は「何故その仕事を、仕様人に頼まないのですか?」と尋ねるんです。
するとこの「老典座」は「他人がやったのでは私の修行にはなりません」と返答します。
再度、「道元禅師」が「何故、日中の暑い時間にやるのですか。」と尋ねると、すぐさまこの「老典座」から「今やらないで、いつやる時がありますか。」という返答がかえってきたのです。
「道元禅師」はこの「老典座」から自分でやらなければ自分の修行にならないこと、いつかやろうと思っていたら結局出来る物ではないという事を教わることができたんですね。
あるいは今ここ、この自己の展開が、仏法の全て、この世界の全てだということを教わったのです。
道元禅師にこうした尊い気付きを与えてくれたのが、まさに今回の「典座」という役職についていた修行僧だったのです。


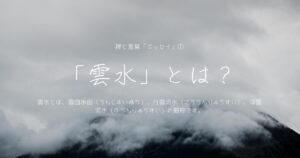


コメント