本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を解説していきたいと思います。
まず 初めに前回の、

のポイントを振り返りたいと思います。
- 「修証は自づから染汚ぜず、」とは慧能禅師と懐譲禅師の問答の一部を道元禅師が引用されたもの
- 「何者か恁麼来?」その質問に答えられず、七年間も念提していた懐譲禅師。
- 人間は社会的な生き物
- 自らを苦しめる「檻」を率先して作っている
- 「檻」は妄想でしかない。人間がスムーズに事を運ばせるための共通認識でしかない。
- 絶対的な事実とは、「生命の実物」の事、「説示一物即不中」
- そしてその「生命の実物」は言い当てる事ができない、言ったことは全てはずれてしまうだろう。
- 今、行じている「坐禅」が「何者か恁麼来?」の答え
- 「坐禅」が「絶対的な行事」、「命の行事」、「確かなる行事。」
- 本来「修行」だとか「悟り」だとか区別は一切できない
- 本当の修証は「汚されない」、人間判断で「区別できない」
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
「平常心是道」とは?

今回はこの部分を読んでいきたいと思います。
それでは参りましょう。
趙州禅師と南泉禅師のやりとり
趣向更に是れ平常なる者なり。というのは、
その赴くところは何も変わったところのない当たり前の所である
という意味になります。
昔、趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)禅師とその師匠に当たる南泉普願(なんせんふがん)禅師という二人の禅僧がおられました。
ある日弟子の趙州従諗禅師が師匠の南泉普願禅師に質問をするんですね。
 趙州従諗禅師
趙州従諗禅師如何なるか是道。
つまり「何が本当の在り方ですか?」と、もしくは「何が本当の我々が歩むべき道でありますか?」、「真実というのは一体なんですか?」と師匠に聞くんです。
すると師匠の南泉普願禅師が次のように答えて言われます。



平常心是道。
総持寺の御開山である「瑩山紹瑾禅師」がこの「平常心是道」のお示しによってお悟りを開いたという話は有名ですが、元々はこれは南泉普願禅師の言葉であったんですね。
平常心是道
これは非常に有名な言葉ですね。「普段の心がそのまま仏道である」という意味です。
とても重大な話なので、本記事ではその周辺を深掘りしていきます。
またこれもとあるお坊様がお話ししていたことですが、
「我々で一番大切なのはな、普段着だぞ。普段着が一番大切なんだ。」
要するに、いつも着ている「普段着」が一番大切だと。
それに対して冠婚葬祭の時や、晴れの舞台に着る特別な着物を「晴れ着」と言います。そしてこの「晴れ着」というのはとってもきれいな物ばかりで、高級なものばかりですよね。
このような晴れ着でいつも生活していたい。豪華な衣装を身に纏って生活していたい。
しかしやはりこのような衣装というのは落ち着かないですね。どうも肩身が狭くなる気がする。我々が最も輝く瞬間、それが普段着なのだと。それにこの「晴れ着」というのは、貸衣装で十分間に合うんですね。滅多に着ない物だから貸衣装で十分なのだと。
我々がいつも着ている「普段着」こそが尊い。普段着は生きていく上で手離す事ができないんですね。疎かにすることができないんです。
そういう話をされていたお坊様がいたんですね。
これも今回の「平常心是道。」だということです。
ご飯にお味噌汁。そしてお漬物。毎日変わり映えしない食事。それが三度も続いたりする。
しかしこの簡素で質素なお食事こそがありがたい。それがあるから毎日生きていける。
勿論滅多に食べない「フランズ料理」という高級な食事というのも、ありがたいご馳走です。人によってはこれが普段着になっている人もいるでしょう。
しかし何ともない、いつもの食事。どんな人にとってもこれがあるはずです。
これが一番尊いんですね。
それに、
でも毎朝の食事は食べなければ生きていけない。毎朝食べるものこそ、本当のご馳走なんです。
追いかけようとすれば離れていってしまう
南泉普願禅師は「如何なるか是道」、「何が真実ですか?」、「何が本当の道ですか?」という質問に対して「平常心是道。」とお答えになりました。
つまり「我々の日々の生活、何ともない在り方が一番尊いんだ。」という風にお答えになったんですね。
すると再度、趙州禅師が質問をされます。



かえって趣向すべきか否や。
ここで今回の『普勧坐禅儀』の内容でもある「趣向」という言葉が出てきました。
この「趣向」というのは「〜へ向かう」ということ。
なので「かえって趣向すべきか否や」というのは、「それ」に対して道を求めた方が良いのでしょうか?それとも求めない方が良いのでしょうか?ということです。
そしてここで言う「それ」というのは「平常心是道」のこと。
「平常心是道。」つまり普段の在り方、これが一番尊いのであれば、それを求めた方がよいのでしょうか?求めない方が良いのでしょうか?と聞く訳です。
- 希望したほうが良いのでしょうか?どうでしょうか?
- 目的をもって修行したほうがよいのでしょうか?どうでしょうか?
- 狙いを付けて、自分の思い描いた世界に向かった方が良いのでしょうか?どうでしょうか?
- 自分の好みに狙いを定めて、そこへ向かう為に修行をした方が宜しいのでしょうか?
このような質問をするわけです。
すると師匠の南泉普願禅師はその質問に対し、次のように受け答えをします。



向かわんと持すれば即ち背く。
「平常心」というものに向かおうとしたならば、或いはこれこそが「真実である」というものに向かおうとしたならば、「即ち背く」というんですね。
「離れる」、と。
例えば、この内容に似た詩で、次のようなものがあります。
追えば逃げるぞ赤とんぼ。待てば止まるよ竿の先。
有名な詩ですね。これは「赤とんぼ」を追いかけたならば、どんどん逃げていってしまうということです。
逆に追いかけるのを止めた時に竿の先に止まるというんです。
「趣向すべきか否や。」、「向かわんと辞すれば即ち背く。」
我々が狙いを付けて、その「平常心(真実)」を追いかけようとしたならば、たちまち「平常心(真実)」から離れてしまうぞと。
何かを求めようとした時点で、それは普段ではなくなる。
本来ではなくなるということです。
概念は元々自然界には無かった
我々人類と言うのは、「アフリカ大陸」で生まれたと言われております。
過去における我が人類は非常に生存競争の中では弱い立場であったとされているんですね。
我々の祖先は「ホモサピエンス」です。これは今のお猿さんと同じ「猿人類」であったわけですね。
仮に「猿」のままでいたならば、基本的に木の上にいて生活をしていたので危険はそんなに多くなかったはずです。
しかし我々の祖先はその「木」から下りて二本足で大地を歩くようになった。
この「大地」の真上というのは危険が非常に一杯でありますね。例えば「チーター」や「オオカミ」などの肉食動物がいます。
これは昔テレビで見た内容なんですけども、「チーター」に噛まれた「ホモサピエンス」の「頭蓋骨」がいまだに化石として残っているというのがあったんですね。
我々の先祖である「人類」が、そのように「チーター」に日々追い掛け回されていたというのです。
何しろ人間というのは足が遅いです。
また「ゴリラ」や「チンパンジー」に比べても「握力」もないし「体力」もない。取り柄が何もない。そのような弱い立場であった「人類」がなぜか危険一杯の大地に下りて来たんですね。よりによって最も生存競争の厳しい世界に我々の先祖たちは根を下ろし、大地を歩み始めたのです。
そんな弱い立場であった人類にもかかわらず、自分より強い肉食動物とか色々な動物たちに捕食されない為に、どうやってた生き延びてきたのか?このように繁栄してこれたのか?
我々の祖先はそこで「我々は体力無ければ、足も遅い、他の動物よりも何もかもが劣っている。」ということを「課題化」したんですね。「問題化」していったんです。もっと分かりやすく言えば、「どうしたならば問題を解決できるのか?」ということを「考えられるようになった」のです。
例えば、「どうしたならば猛獣たちから逃れる事ができるか?」という事を考えて、「彼らは火を恐れる。だから火を使って遠のければいいんだ!」ということができるようになったり。或いは「槍を作って使えば、そういう猛獣たちを退けられるかもしれない!」と考えたりとかですね。「冬の時期になると、あの河を動物たちが必ずやってくるからその時にみんなで力を合わせて捕まえれば、体力の劣っている我々でも捕まえる事が出来る」とかですね。
どうすれば生き残ろうことができるかについて「概念」をもって問題化、課題化することで、実際の問題を解決していったんです。
このような恩恵にあやかれたのは、人類は二足で歩くようになってから「脳」が急激に発達したと言われているからです。だから課題化できたんですね。問題化できた。考えることができるようになった。
しかしここで気付かされるのは「課題」も「目的」も「考え」もそもそも元の自然界にはなかったということなんです。
つまり「課題」も「目的」も「考え」も元々はこの自然界にはなく、我々の祖先である「人類」が作り出したものだった訳です。
事実今もこうして、概念というのは「人類」の「頭の中」だけにあるものです。
人類を助けた概念が、人類を苦しめている
このように「概念」に基づいて「行動」を取るというのは他の動物にはできないんですね。
人類だけができることです。
これは非常に優れた武器であったことでしょう。
こんな体力のない、足の遅い「人類」。あの「ウサイン・ボルト」が早い!っといってもチーターにはとても敵わない。
そのように体力もなく弱い人類が、頭の中で「課題化」できることになったというのは、とてつもない武器を手に入れたということでもあったんです。
だから実際に我々人類は生き延びる事ができたんですね。
「目的」も「課題」も、そもそもの概念も、元々大自然にはなかったわけですから、当時の「自然界」においてまさに画期的な発明だったことでしょう。
そのおかげもあって生き長らえることができたわけであります。
そしてそのような「概念」は、「チーター」とか「ハイエナ」などの肉食動物たちと戦わなくなった現代においても非常に我々の生活を支える為の重要な役割を果たしております。
この「概念」が現代社会を作り出し、今も支えている訳ですね。
しかし、思い出してみてください。この「概念」というのは元々自然界にはなかったものだということを。人類が生き延びるために「作り出した」手段だということを。
今はその「概念」が主になってしまっているんですね。
この元々自然界には無かった「概念」だけが「全て」だと思っている。この概念は大自然に反しているものです。この世界に存在しないものなのです。事実、この概念を差し出そうと思っても差し出すことはできません。
存在していないのです。本当に不思議なものです。それがまるで存在しているかのように思われる。その概念でやり取りをし、一生をその概念に支配されてしまう。
今は人類を助けた「概念」が、今度は人類を苦しめているんです。
まさに本末が転倒してしまった。
勿論、現代社会で生きていく以上ある程度「概念に縛られる」と言うのは避けられないかもしれません。
しかし我々の本当の安らぎというのはこの数値化された、相対化された、或いはノルマがある世界とは別物なんですね。
例えば「坐禅」を組んでいると、何を考えようが、足が痛くなってきます。人間の概念が通じない。本来の世界の出来事です。大自然の出来事です。
言い方を変えれば、本来の我々の祖先、概念化がなされる以前の話であります。人生以前の話であるといっていい。あるいは「父母未生以前」、「父」、「母」が生まれる以前の話であると言ってもいい。
それを「行じている」んですね。つまりこの世界の真実を、大自然を、仏を、悟りを、本来を行じている。
これが「坐禅」です。それが我々の一番の安らぎであると。なぜならこれこそが本来であるから。本来の我々の生きるべき世界だから。
平常心是道、こそ真実だった
今回「如何なるか是道。」、「本当の在り方とは一体なんですか?」と質問をした。
すると師匠の南泉普願禅師は、「平常心是道」とこたえたわけです。
しかし「如何なるか是道」ときかれたならば「如何なるもこれ道」と答えるしかないんですね。
というのも今回の質問もそうですが、そもそもの「質問」とそれに対する「答え」というのは、「概念化」の延長で行われるわけです。
しかしそれは先ほどの概念化の話にもあったように本来ではないわけですね。大自然ではない。真実ではないわけです。
何しろ質問というのは「ワタクシガ」という「自我」を立てて、質問をするわけです。そして答えを得る。「如何なるか是道」と聞けるのは、あるいは「何が真実ですか?」と問うことができるのは、「真実なるもの」を自分の「外」に求めているからこのような「質問」ができるわけです。
自分を立てることで質問ができる。
しかしこれは誤りなのです。
人間同士だけで行われるコミュニケーションにしか過ぎないんですね。それはこの世界には通用しない話なのです。
質問と答え、これがそもそも間違っているということなんですね。
なので「如何なるか是道」ときかれたならば「如何なるもこれ道」と答えるしかないんですね。
それに、概念化が本来の大自然に反しているわかりやすい例として、概念かとは「自我」を立てることで、その「自我」を立てるとすべてが「他者」になるということも挙げられるかと思います。
例えばそこでは我々は「私が見た」と言います。しかし「私」が見る前にもうそれは見えていたはずです。あるいは「私が呼吸した」と言います。それに気づく前に呼吸はできていたはずです。
概念とは単なる気づき、実物には一切関係していないことなんですね。あるいは「私が」というのは、単なる人間勝手な後付けなんですね。本来はさまざまな植物などの力によって酸素が生成され、そのおかげで呼吸できている。また肝心の「私」が寝ている間にも呼吸器官がしっかり働いてくれるから呼吸ができている。
あるいは鳥の声が聞こえるのは、鳥の声が自分の耳を震わせる。鳥が自分の命を起こす。その鳥が自分の命だからです。
この世界には私なんてものはなく、全てが1つに繋がっているわけですね。
物事を頭の中で「概念化」したり「相対化」しようとすると、私のこの「命」も「手足」も、「体」も或いは「仏」さえも、或いは「宇宙」も全て「他者」となるんですね。
それは事実ではないのです。概念化が大自然に反しているというのはこういうことなんです。
実物には一切、関与していない。この世界には一切関わりを持っていないのがこの概念なのです。
今回の質問もそのように「物事」を「他者」として眺めるからこそ、「如何なるか是道」という質問が出てくるわけです。「自分の外」に「真実」を設けてしまうからそういう「質問」になるわけです。
なので「如何なるか是道」ときかれたならば「如何なるもこれ道」と答えるしかないとはこのことなんですね。
聞いた方は答えになっていない!と思うかも知れない。しかし本当はそんな質問自体が間違っているというお示しなんですね。



如何なるか是道。



平常心是道。
「如何なるか是道」と質問に対し、師匠の南泉普願禅師は「平常心是道」と答えられました。
しかし本来であれば「自分」もこの「道」の中、「真実」の中にどっぷりつかっているわけですから「そういう質問」そのものが「出てこない」はずですね。
「他者」として眺めない。常に仏のたった一つの道。常にその道。
我々は「平常心是道」の「道」の中に常に「自分」がどっぷり浸かっている状態なんですね。
自分が坐っているこの「座布団」を自分の力で引っ張ろうとしてもどうしても引っ張れないというのと同じですね。
自分を自分で引っ張れない。
要するに「平常心是道」というのは真実のことなんです。私と仏とが一体であるこの世界の真実、それを表している言葉なんです。この世界は自分のみだという真実の話なんです。
平常心是道。全てが1つ。全てが仏法。お前自身がその1つ。
そこを傍観者になることでわからなくなってしまう。あるいは「質問」と「答え」といったやりとりが出てくる。誤りが生じてしまう。
ですから先ほどもありましたが、「趣向せんと要せば即ち背く。」と。
「真実」を求めて向かおうとしたならば即ち背いてしまうと。
「平常心が最も尊いぞ、そしてお前自身がその平常心ではないか」
ということを言っているんです。
「お前自身が道」ではないかと。「お前自身が仏ではないか」と。それなのに「どうしてお前は他人事のように傍観者として物を見ているのだ?」と。
冒頭で普段食や普段着が最も尊いという話がありましたが、それ以上に全てが尊い。全てが仏法であるという深いお示しでもあるのがこの「平常心是道」ということなのです。
「平常心是道」というと、「平常なる心が真実である」といった話をよく聞きます。普段の心が尊いと。それも当然ですね。全てが尊いわけです。
今回の、
というのは、冒頭でもお伝えした通り、
その赴くところは何も変わったところのない当たり前の所である
という見解で問題ないと言えます。しかしその当たり前がとても尊いということですね。その当たり前にこの世の全てがあるからです。
そのことを道元禅師もこの「普勧坐禅儀」に引用されたという訳です。
そしてこの「趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。」という短い言葉で納めている訳です。
我々の「命」というのは決して他人事ではない。この世界には自分その人しかいないからです。そして我々はその当事者であります。
しかしその「当事者」ということを証明するのは「概念」ではありませんね。
「当事者」とはあくまでも実際のことです。事実です。「行じる」ことです。
すなわちそれが「坐禅」であります。
先ほども述べましたが「坐禅」を組んでいると、何を考えようが、足が痛くなってきます。人間の概念が通じない。本来の世界の出来事です。大自然の出来事です。
言い方を変えれば、本来の我々の祖先、概念化がなされる以前の話であります。人生以前の話であるといっていい。あるいは「父母未生以前」、「父」、「母」が生まれる以前の話であると言ってもいい。
それを「行じている」んですね。つまりこの世界の真実を、大自然を、仏を、悟りを、本来を行じている。
だから足を組み、坐禅に親しみなさいと、自己に親しみなさいと。この自己こそが真実だからです。この世界にはこの自己しかないからです。
今、我々は本末が転倒してしまっております。
「ノルマ」だとか「課題」そういう目に見えない「概念」によって生きづらくなっているのです。
しかし本来の「大自然」には一切の行き詰まりがないように、この「坐禅」においてもそのような行き詰まりはありません。
「坐禅」が大自然の行、当事者の行であるというのはそういうことで、なので道元禅師は強くこの「坐禅」をおすすめになるわけです。
平常心是道とは?-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
と言う部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 今回の『普勧坐禅儀』で道元禅師が一番言いたいのは「その赴くところは何も変わったところのない当たり前の所である」ということ。
- 「平常心是道」という有名な言葉には趙州従諗禅師と南泉普願禅師とのやりとりがある。
- 「平常心」とは我々の普段の生活、普段の在り方
- そしてこの「普段の生活」が一番尊い
- ご馳走は食べなくても生きていけるが、普段の食事は食べなければ生きていけない
- 「平常心」こそ、真実。その「真実」に向かおうとすればかえって遠のいてしまう。
- 自我を立てると全てが「他者」になる。
- この世のあらゆるものが「二つ」として分かれない。一つの「仏の命」
- 二つとして分かれない、「当事者」そのものがこの「坐禅」という行
以上、お読みいただきありがとうございました。

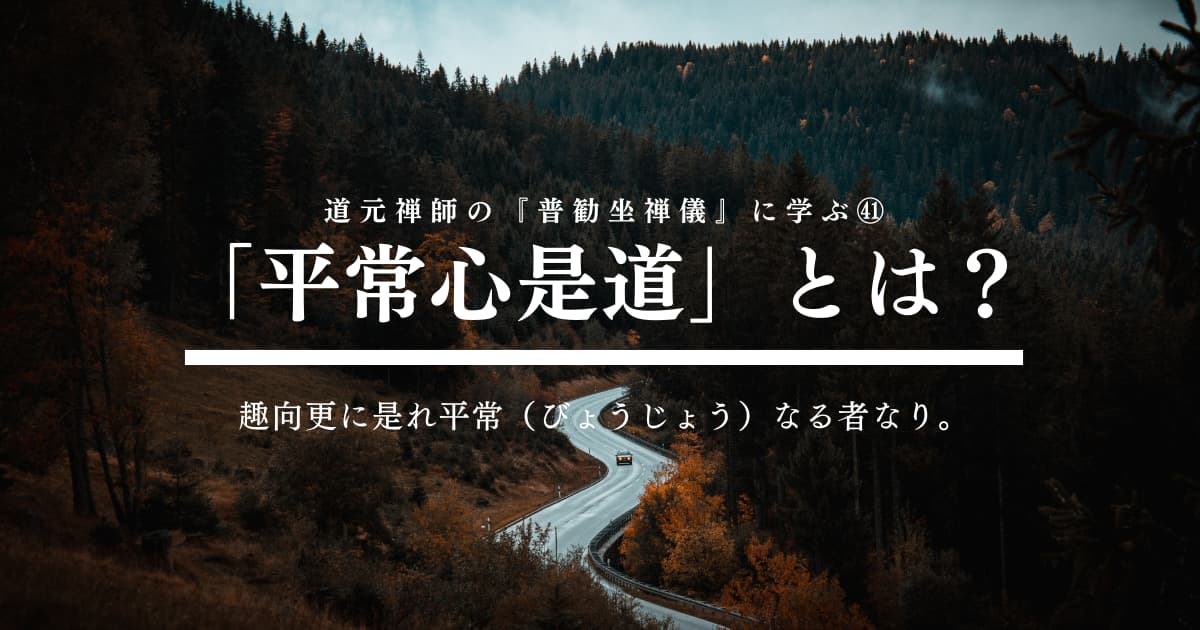


コメント