禅にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第4弾といたしまして、「参堂(さんどう)」についてをお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
この記事を書いているのは
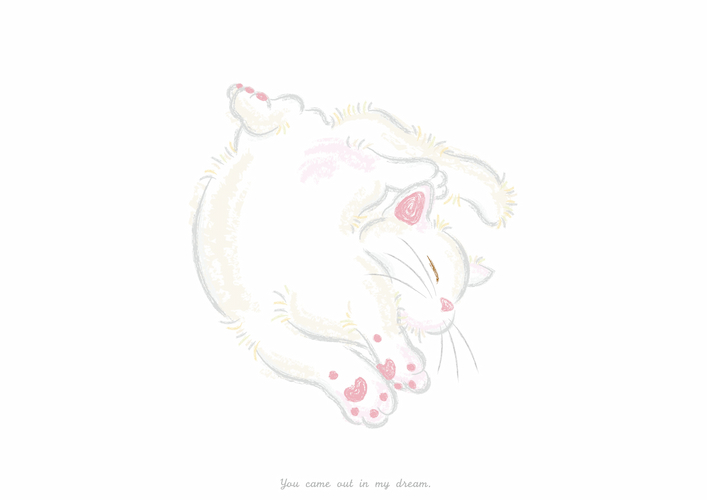
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。
あわせて読みたい


「道元禅師の旅」キーワードごと簡易検索システム、「禅旅」。
ここでは、当ブログ「道元禅師の旅」において重要となる「キーワード」に関連した記事を、簡単に見つける事ができます。 いわば「しおり」のようなものです。同時にそれ…
目次
参堂とは?
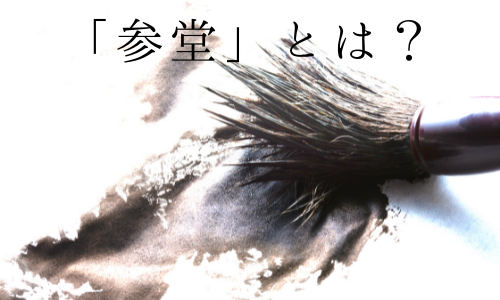
「参堂」とは、「禅」の修行道場で「修行僧」及び、「雲水」がお堂に参じることを言います。
その「お堂」には「修行僧」を見守って下さる「文殊菩薩様」が祀られておるのですが、「修行僧」はその「文殊菩薩様」に失礼がないように「低頭」をして入堂するのが決まりです。
その一連の所作については残念ながら窺い知ることができません。僧堂は元来一般公開されておらず、実際にその場で修行した雲水しか僧堂での出来事を知らないからです。
またその修行道場で正式に修行することが決まった「雲水」たちは、その僧堂において「入門式」をとりおこなわなければなりません。
これを「掛錫」といったり、「僧堂掛搭式」といったり、あるいは今回の「参堂」という風に言ったりもします。
こうしたさまざまな言われ方をする今回の「参堂」ですが、今は「お寺」だけでなく「神社」にあるお堂に地域の人が参じる際にも用いられます。
似た言葉で「参道」がありますが、これはお寺や神社の社殿へと続く道、そのもののことをいうので少し意味合いが異なります。


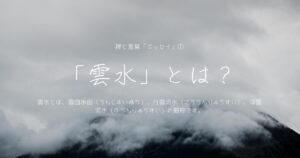

コメント