道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第⑨弾といたしまして、「阿羅漢(あらかん)」についてをお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
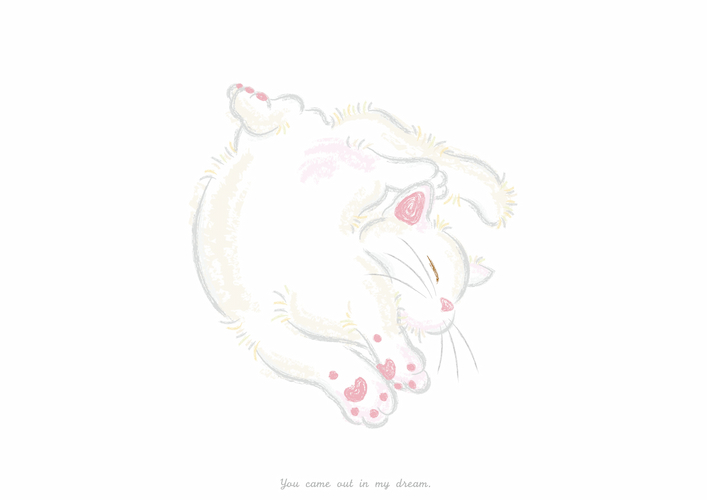
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

阿羅漢とは?
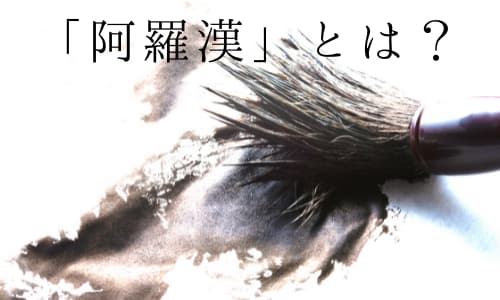
「阿羅漢」とは、サンスクリット語の「arahat:アラハト」を音写したものです。
すべての煩悩に打ち勝ち、もはや学ぶべきものもなく、人々に敬われる価値に到達した聖者のことをいいます。
お釈迦様が生きた原子仏教時代においては、煩悩をたちきった聖者たちを、さらに修行の進行状況によって次の四つに分類しておりました。
- 預流果(よるか:修行をすれば解脱できる)
- 一来果(いちらいか:一度欲望や迷いの世界に戻っても解脱できる)
- 不還果(ふげんか:もはや迷いの世界にもどることはない)
- 阿羅漢果(あらかんか:もはや学ぶべきものはない)
今回の「阿羅漢」はその中でも、もっとも最高位に位置しているものです。
「もはや学ぶべきものはない」とあるように、この「阿羅漢」のことを「無学」とも称したりします。
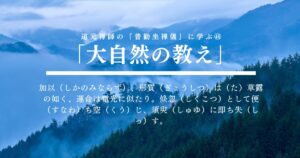
また当時、お釈迦様に付き添い、共に仏道修行した最高位の聖者たちを指す言葉に「五百羅漢」や「十六羅漢」という言葉がありますが、そこにもこの「羅漢」という言葉が入っており、これは聖者に対して使われる名称です。
仏教国である日本では、古くからこの「阿羅漢」あるいは「羅漢」に対する信仰心があったため「五百羅漢像」を作ったり、それを安置する「五百羅漢寺」などを建立し、大切にする文化がありました。
例えば、「五百羅漢像」が有名な寺院では、大分県中津市にある耶馬渓の羅漢寺だったり、埼玉県川越市にある喜多院、東京都目黒にある羅漢寺などがあげられます。
また京都市の大徳寺や東福寺などにも「五百羅漢の画幅」があったりしますね。
現代に阿羅漢はいるの?道元禅師の見解
教学的には「阿羅漢」はもはや学ぶべきものはない存在、あるいは非常に尊い存在としてのちの人々の信仰の対象にもなってきました。
しかしもはや学ぶべきものはない存在、非常に尊い存在とは実際にはどういうものか、ここをもう少し参究してみたいと思います。
道元禅師は『正法眼蔵』第36、「阿羅漢の巻」というものをのこされております。
そこでこの「阿羅漢」に関し、
真実の出家が真の「阿羅漢」である。また自分が「阿羅漢」になったこともわすれ去ったものが真の「阿羅漢」である。要するに難しいことは何もなく、真実そのものを「阿羅漢」と呼べばいいのである。
というようなことを述べられております。
春夏秋冬。この四季が約束通り、巡る。それは大自然の恩恵です。また我々が普段当たり前のようにしているこの呼吸1つとっても、それは大自然の恩恵です。大自然の力というものは非常に尊く、また偉大です。
この私も含め、この世界は全て大自然によって支配されているのです。この大自然に勝るものはこの世界にはありません。言い方を変えればこの世界には「大自然」しかないのです。
そこに身を投じること、その道を歩もうとする者。あるいはそれと「同時」である修行者、出家者。そのような人物こそが「阿羅漢」なのだと。
もしかして現代でいう「阿羅漢」とは、こんなところで噂されるているともしらずこの寒い冬空の下、庭掃きや「坐禅」を組んでいる「出家者」のことかもしれませんね。


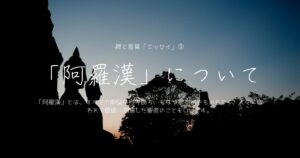
コメント