道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は「衣鉢(えはつ)」についてお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
衣鉢とは
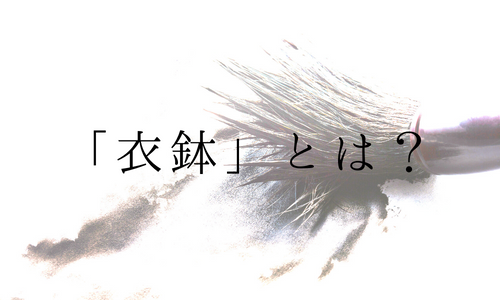
「衣鉢」と書いて「えはつ」と読みます。
そもそもこの「衣鉢」とは「三衣一鉢(さんねいっぱつ)」という言葉から来ており「出家修行者が身に付けることができるものは、三つの衣と一つの鉢」だけだという意味です。
「衣」というのは「お袈裟」や「法衣」を指し、「鉢」というのは、修行僧がお食事を頂く際に使ったり、「托鉢」の時に使ったりする「鉢盂(食器)」のことを指します。
修行僧は必要最低限のものしか持つことが許されていないんですね。
衣鉢を継ぐとは
またこの「衣鉢」は、お釈迦様から摩訶迦葉尊者、またインドから中国へ仏法をお伝えになった達磨様から慧可様へなど、師匠から弟子へ法を伝えるときに、その証として伝授されるものでもあります。
弟子は師匠の「衣鉢」を受けがい、また使い、さらにそれを同じように後世に渡していくんですね。
こうして仏法というのは相続されていくのです。
「法を伝える」という時には「衣鉢を伝える」と言い、弟子が「衣鉢を継いだ」というのは、「正伝の仏法」を引き継いだという意味になるのです。
このように「衣鉢を継ぐ」というのは大変なことで、仏法正伝の象徴として重要な意味を持つのです。
一方、1987年に出版された五味康祐さん著の『柳生天狗党』の中には次のような一節がでてきます。
昨夜よりつくづく眺めて参ったが、亡き柳生十兵衛が衣鉢を継ぐほどの者、当然とは申しながら、よう切ってある
本来は「三衣一鉢(さんねいっぱつ)」を継ぐ意味での「衣鉢」ですが、このように師匠から弟子へ「奥義」が継承される際や、事業が継承される際など、一般社会においても「何か重大な引き継ぎ」を行う際に使われる言葉として知られております。




コメント