禅にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第⑥弾といたしまして、「托鉢(たくはつ)」についてをお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。

托鉢とは?
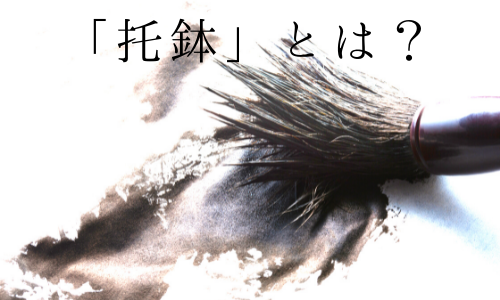
托鉢とは簡単に言えば、仏弟子が自身の最低限の糧を得るために「食糧」や「浄財」を集める事をいいます。
例えばタイなど、仏教を信仰する諸外国では本当に沢山のお坊さん方が、この「托鉢」と共にしながら日々の修行生活を歩まれているし、日本国内でもこの托鉢僧が駅のロータリーや地下鉄の入り口に立っているのを街角で見かける事がありますが、その為です。
その一方でこの「托鉢」は、修行僧、信者、両者にとって大切な仏道修行でもあります。
そこでは修行僧の方から信者の方に「浄財」や「布施」をお願いしたりせがんだりすることもありませんし、また「浄財」や「布施」をしてくださった信者の方にお礼を言う事もありません。
どういうことか、以下で詳しく見ていきましょう。
托鉢の目的

「托鉢」は前述したように、修行僧が自身の最低限の糧を得るために「食糧」や「浄財」を集めることを目的としております。
いわば、修行僧が生き抜くために必要な修行なのです。
タイなどでは今でも修行僧が生き抜くための主な手段としてこの「托鉢」が用いられています。
ただ「托鉢」の目的はそれだけではありません。
というのも、信者や布施をしてくださった方に功徳を積ませる意味もあるからです。
信者の方にこの「托鉢」を通し自分の財産や、金品、持ち物をお布施していただくということは、ご自身のいわゆる執着を断ってもらうことにもつながるんですね。
信者の方からすると托鉢僧に布施をすることは、己の執着を断ち切る修行にもなり、功徳を積むことにつながるのです。
よってこの「托鉢」のことを「喜捨」と言うのもそのためなのです。
これが「托鉢」における、もう1つ大きな役割なんですね。
托鉢僧が、駅のロータリーや街角など人目の多くつく場所でこの托鉢を行っているのは、信者の方が気付きやすいようにという思いからでなのです。
決して托鉢僧の方から信者のお家の扉をあけるようなことはありません。
また一般に言われているお布施に関しても、これはお坊さんが信者のために行う誦経や法話など「法施」に対するお礼の気持ちを表したものです。
それはあくまでも信者の「志」であり、決められた金額はありません。その「志」に意味があり、我々僧侶もその志をいただいているわけです。
例えば一千円という額も、金額で言えば一千円ですが、貧しくてその日の暮らしにも困っているような人からすると、全財産を傾けてもらったほどの重みがあるわけです。
お金を布施してもらっているのではないんですね。志を布施してもらっているのです。
このような意味が「托鉢」ないし「お布施」にはあるわけですね。
お坊さんだけでなく、信者からしてもお坊さんにお布施をすることは立派な仏道修行であるわけです。
個人の持ち物を捨てさせる。
悩める個人を、本来の世界へ帰してあげるのがお坊さんの本来の仕事です。本来の世界、真実の世界とはどういうものなのかを布教していく。これがお坊さんの務めです。
坐禅や托鉢がその役割を担っているわけですね。とても尊い大自然の修行だということです。
お金や財産、そのようなものは単なる概念で、本来この世界にそうした個人の持ち物というのはありません。そのような目に見えない、存在していない概念に縛られてもがき苦しんでいるのがいつの世も人間なのです。
そのことに気づいてほしいという思いで行われるのがこの「托鉢」の本当の目的なのです。
托鉢の経緯
古代インド仏教、及び原始仏教では、非常に厳しい仏道修行が繰り広げられておりました。
そんな中、出家者は三衣一鉢(大・上・内の三枚の衣と、鉢1つ)の最低限の生活必需品しか所有を許されていなかったんですね。
まさに乞食修行です。
ただそれも仏にお仕えする僧侶、仏に一番近しい存在であるがゆえ、避けられないならわしだったのです。
繰り返しになりますが大自然には個人の持ち物がありません。財産がありません。
その姿を、大自然の姿を行じるのがお坊さんだからです。
そんな中さらに、殺生戒が重んじられていた為、害虫捕殺が避けられない畑仕事は行えなかったんですね。
しかしそんな状況におかれた修行僧であっても、何かを食べなければ生きていけないし、何かを食べなければ肝心な仏道修行も行えません。
なので、僧侶が生存するための最低限の食料は、「托鉢」によって外部の信者から調達する以外なかったのです。
それが「托鉢」の始まりです。
お釈迦様の時代からこの「托鉢」は行われていたと言われており、午前中に托鉢に出て、その日、食べる分だけを頂くというということがならわしで、またそこで得た「食糧」や「浄財」を蓄える事はしませんでした。
その日にいただいたものはその日にいただく。決して備蓄しない。備蓄したいというのは、翌日の食事の心配をするということでもあり、それは欲の現れでもあったからです。
また当時、山地や森林で修行しており他との関りが一切ない出家者と、町村で生活している信者との間に密接な交流関係をもたらしたのもこの「托鉢」だったといわれております。
托鉢のいわれ
この「托鉢」はそのようにして、お釈迦さま在世の紀元前からの習慣であったわけです。
サンスクリット語でこの「托鉢」のことを「ピンダパータ」といいますが、この「ピンダパータ」は中国宋(そう)時代には中国へと伝来し、それから「托鉢」という言葉として広く用いられるようになったと言われております。
日本にもこの「托鉢」は中国から仏教の伝来と共に伝わりました。
日本において仏教の歴史=托鉢の歴史でもあるわけです。
その「托鉢」ですが、「手(托)」に「鉢」をもって行います。
禅宗においてその「鉢」に用いられるのは、食事をいただく際に修行僧たちが実際に使っている「応量器」と呼ばれる器です。
この「応量器」ですが、修行生活において非常に重んじられるもので、修行僧にとって欠かすことのできない仏具でもあります。
これがないことにはお食事をいただくことができないからです。修行僧の命を司っているわけです。
そのためこの「応量器」は、仏様の「命」と同様に大切に扱わなければならず、普段の修行生活でぞんざいに扱う事は決して許されません。
例えば地においたりすることは禁物で、修行僧がこの「応量器」を使って食事を頂く際も「頭」と同じ高さ、目よりも高い位置で食事をいただくよう厳しく指導されます。この「応量器」を片手で持っていたりでもしたら、古参和尚さんにブチ叩かれます。
その何よりも尊い「応量器」を用いて行う「托鉢」のわけなので、禅宗ではこの「托鉢」を「頭陀行」と言ったりもします。
或いはその他にも「乞食(こつじき)」や、「行乞」、「鉢開き」などとも呼ばれます。
またその際の形式として、修行僧が一列に並び、集団で歩きながら行う「連鉢」。個別でその場所に留まりながら行う「軒鉢」があります。
永平寺の托鉢

福井県にある「永平寺」でも修行僧によるこの「托鉢」が毎年欠かさず行われております。
そしてそれは修行僧が「食糧」や「浄財」を集める事を目的としているわけではなく、信者の方に徳を積んでもらうことを目的としております。
また福井県の門前の方々からすればこの年に何度かしかない「托鉢」は、唯一永平寺の修行僧との交流をもてる機会ですのでこの「托鉢」を待ち望んでいる信者の方も多くいます。
集まった「浄財」は社会福祉事業支援に寄附されます。





コメント