「清浄本然、云何が忽ち山河大地を生ずや」
これは、
本来清浄なものから、どうして山河大地など色々な差別相が生じるのでしょうか
という意味になります。
「楞厳経」という仏典の中に出てくる一文に対し、とある修行僧が疑問をいだきました。
要するに「万物は全て平等のはずなのに、実際は違うのではないか」と悩んでしまうのです。
それからその修行僧はこの書物の書き手にあたり、また当代随一と称された「慧覚禅師」に迫り、このことに関しての正しい見解を求めました。
しかし「そんなのを求めてくれるな。ただ日常の中にいて、その日常を徹しろ、それが全てだ」と言われてしまうんですね。
確かに我々の目の前には、山があったり、河があったり、大地があったり、私が居たり、あなたが居たり、色々な物事が同時に展開しています。
また例えばそこでは不細工な人と美人な人。あるいは綺麗な沼と澱んでいる沼。このような差別相があります。
私はこんな顔なのに、一方で男でも見惚れてしまうような美形男子がいるわけです。
純粋になぜか?と思うわけです。私もそうですし、この修行僧もそうだったのでしょう。
しかし残念ながらどうしてそのような差別相が生じるのか、誰にも解りません。
また同じように、あの汚れた泥沼から、どうしてああして美しい蓮の花が咲くのかということも誰にも解りません。
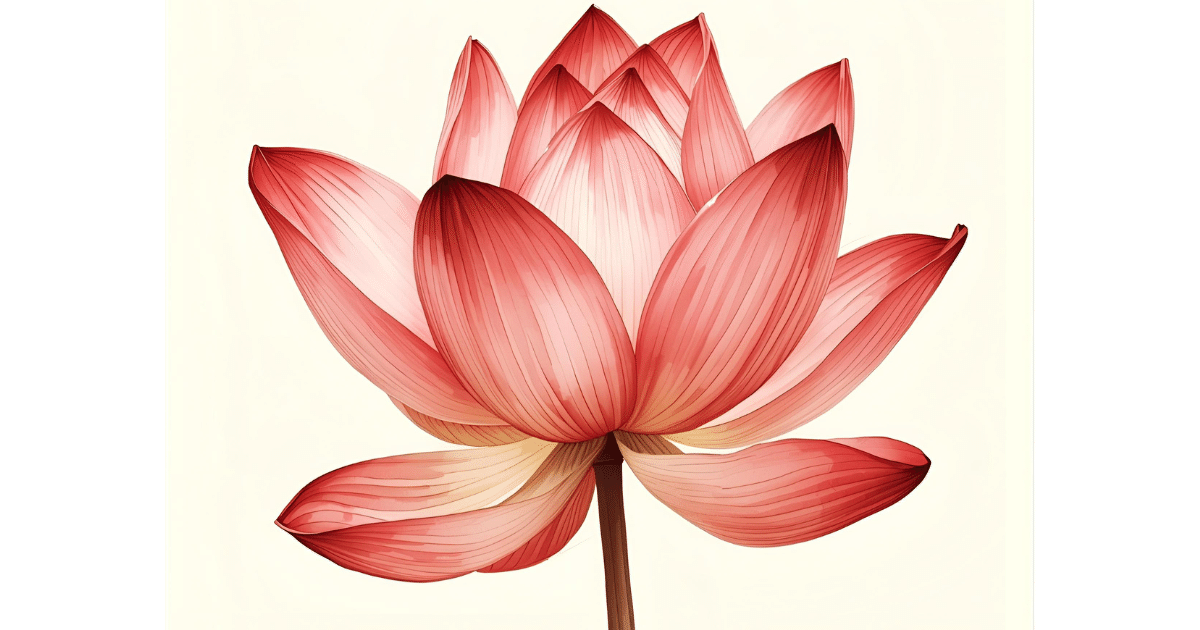
あるいは私が平成初期代に男性として生まれ、またあのような父や母を親に持って生まれた事も、またあるいは私の鼻が顔の真ん中であぐらをかいている事も、この小さな眼が横に並んでいる事も誰にもわかりません。
これらは既に出来上がったあとの姿であって、我々にはどうする事も出来ないことなのです。
辛いですが、人生なんてのは、そうしたものばかりですよね。
そしてそのような我々にはどうする事も出来ない大自然の事実のことを、仏教では「無為法」といいます。
この「無為法」については、いちいちその理由を考えても答えが出ません。
不細工な人と美人な人。あるいは綺麗な沼と澱んでいる沼。そして汚れた泥沼から美しい蓮の花が咲くこと。こうしたことは人間の「なぜ?」という探り合いとは関係なく、そこで存在するものだからです。
「実物」とは全てこの「無為法」で成り立っているからです。
そうした「実物」が先に存在していて、単にそこを「表現」しているのが、この言葉や理論、概念というものなのです。
しかしそのようなことはあくまで「後付け」であり、本質の部分は「無為法」だということです。その「無為法」については、いちいちその理由を考えても答えが出ないものだということです。
我々はただその「後付けの説明の違い」によって、苦しんだり、悩んだり、喜んだりしているのです。
また我々が今必死になって求めたり、戦ったり、解き明かそうとしていることは、こうした大元の「大自然の理」をいかに表現するかという見え方の部分だけの話なのです。
そのようなことは一切、本質とは関係していないわけですね。
例えば我々はたくさん朝食を食べても、お昼になるとチャンとお腹がすきます。このことに関して頭の良い人がどんなにそれっぽい考察をしてくれたとしても、誰においても、どこにあっても、事実としてはただただ、腹が減ってしまうのです。
その事実に対してああだ、こうだ言ってもしょうがないことなのに、人間はそれがなぜなのかと解明しようとしたり、労力を使ったりしてしまうのです。
あるいは「うちわ」で仰ぐと風が起こりますが、なぜ本当にそのようなことが起こるのかということです。火打石でカチッとやると火が起こりますがなぜ本当に起こるのか?ということです。なぜ温度が上がると火がつくのか、そもそもなぜ熱くなるのかということです。
こうした解析不明の「動き」が我々の大元、世界の大元にはあって、ある種「魔法」のような魅力的な世界がこうして世界を支配しているというのに、それを蔑ろにしたり、つまらなくしてしまっているのが人間という生き物だということです。
「火打石で火が起こるのは、火打金から剥がれた小さな鉄の欠片が空気と急激に反応して燃えるため」
このようなことを理屈と言いますが、これは我々の都合の良い風に物事を受け取ったものでしかないということです。
解析不明の理があって、それに対して人間が都合の良いように説明を加えているもの。これが理屈です。
綺麗な川があるのも汚い川があるのも、美人がいるのもそうじゃない人がいるのも、要するにそれらは全て同じ紛れもない大自然のお姿なのです。
「こちら」が本来なのです。我々は常に天地一杯の「ところ」で生き、誰もが天地一杯の「ところ」からは逃れられないというわけですね。
そこを差別的に捉えたり、比較してみたりするのは単なる人間の好き勝手な見方であり、またそれは本来の見え方ではないということなのです。
我々の理屈や理論というのは、人間の頭だけに存在し、またそれは実際には存在していないもので、真実とは一歳関わりがないわけですね。
もちろんこうしたことを明らかにしてきたからこそ、我々は前もって食事の準備をしたり、仕事先での食事時間を計算して、予定をたてることも、トラブルの防止も出来るようになりました。
しかしお腹がすいたり、夜になると眠くなる、あるいは疲れたら横になる、という事実においては、人間の理屈は通用しません。これらは「人間の理屈以前の、真実の話」なのです。
そこを混合させるのは非常に危険なことだし、この人間以前の話が、普段の我々の日常生活の根本であるということを知らないのも非常に危険なことなのです。
我々が頭で理解した事は、皆な父母既生以後(父母が既に生れた以後)の話であり、実物が既に存在した以後の話です。
要するにそれは単なる事実に対する後付け説明なのです。二次的なものなのです。
ヨハネ福音書第一章のように「初めに言葉があった」という捉え方であれば、創造主と被創造物という物事を2つに分けることができ、すべての物事は創造主のワザであると言えるのかもしれません。そしてそれを唯一教として生きることが我々の幸せになるはずです。
しかし事実としては初めに「無為法」があって、後付けで言葉や概念が生まれたわけです。
実際に真冬に雑巾掛けをしようと思い「バケツの中の水」に手を突っ込むと、驚くほど冷たいし、痛くなるはずです。それはまさに宇宙と自己との「間」に命の垣根がないからなのです。「宇宙」がそのまま「自己」であり、「自己」がそのまま「宇宙」なのです。
言葉や概念など、そこには一切介入していないことがわかります。
不細工な人と美人な人。あるいは綺麗な川と澱んでいる川。このようなことは、そうした本来の物事であり、決して比較のできない、大自然として文句のつけようのない真実のお姿です。
差別相というのは人の頭だけに存在している、実物とは一歳関わりを持たない、存在していないものだということです。
「そんなのを求めてくれるな。ただ日常の中にいて、その日常を徹しろ、それが全てだ」
確かに不安や悲しい気持ちはあるけれども、決して何かと比較せず、強く自分を保つこと。そして今、ここ、この自分を引き受けて生きること。そこにある日常を引き受けて生きること。そして明日も明後日も普段通り生きること。
これが我々にとっての使命であり、あるいは「無為法」であり、「大自然の理」のわけですね。
それが本来の生き方だというわけです。
簡単なようで実に深い意味の込められた言葉です。

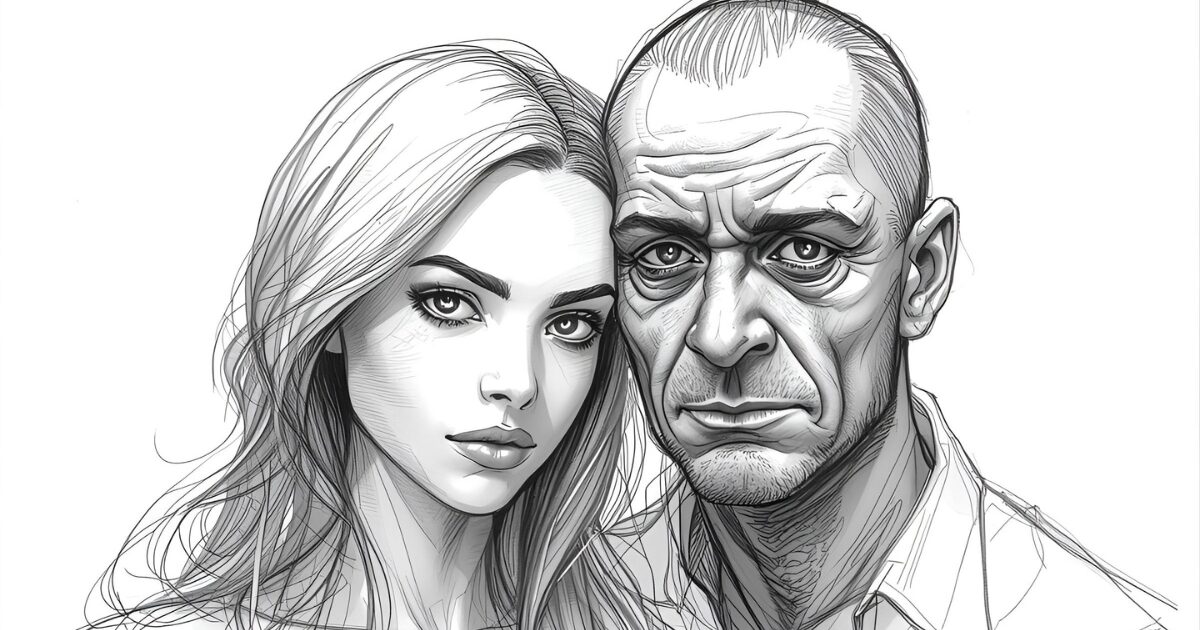


コメント