本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を読んでいきたいと思います。
初めに前回の、

のポイントを振り返りたいと思います。
- 「払拳棒喝」というのはそれぞれ単語を繋ぎ合わせたもので、それぞれに過去の仏祖方のエピソードがある。
- 「払拳棒喝」の「拳」は知事である李渤刺史と帰宗智常禅師によるエピソード。
- 「払拳棒喝」の「拳」は「拳骨」の「拳」。
- 「分からない」が仏法の真実。
- 「羊羹」をどんなに詳しく説明したところで、実際の「羊羹」は分からない。
- 「仏法」はいつでも「実物」を提示する。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。
「払拳棒喝」の「棒」

今回はこの部分の解説をしていきたいと思います。
今回の「払拳棒喝を挙するの証契も、」という部分。
この「払拳棒喝」とは「払」、「拳」、「棒」、「喝」それぞれの単語を一つにまとめたもので、それぞれの単語には仏法の大意が隠れ、それぞれ重大な意味を持っております。
なのでこうして道元禅師もこのようにしてお話になるわけですね。
それは仏道を真剣に守り抜こうとした祖師方の逸話でもあります。
今回はその「払拳棒喝」の「棒」の部分に関してみていきましょう。
棒使いの名人「周金剛」
かつて「棒使いの名人」が仏祖の中にいました。
「徳山の棒、臨済の喝」とは有名な言葉ですが、徳山宣鑑(とくざんせんがん780年 – 865年)という人間がその人で、この「棒」を使ってなんでも殴りつけて人を導いていったという話があるんですね。
今回はその徳山宣鑑禅師にまつわるお話をしていきます。
徳山宣鑑は、有名な学者で、非常に熱心な勉強家であったとされています。
特に『金剛般若経』に関しては右に出る者がいなくらいに『金剛経』の注釈に関しては他の学者より長けていたとされています。
徳山禅師の元々の俗称、俗名は「周」でした。それで自分の事を、「周金剛」と言っていたんですね。
周りの人からもその技量を買われて「周金剛」と呼ばれていたそうです。
その徳山禅師ですが、四川省の山奥にある地で常々「法」を説いておりました。
そこではいまで言うところの「大学の教授」のような役をやっておったんですが、ある日この徳山禅師は、
「最近南方の方で、(南方というのは湖南省や、江西省)お釈迦様から滴滴相承して、我こそが正しい仏法を受け継いだと言っている、変な輩が出回っており、それが新興宗教として流行っているらしい。」
というような情報を耳にします。
「我々こそは真の無常の仏法である。そして正統なお釈迦様からの跡継ぎである。」
そのような事を聞いたもんですから、もうこの「周金剛」はいてもたってもいられなくなってしまう。自分の仏道こそが真なるものだ。そのような気概も持っていたことでしょう。
この「周金剛」は、自分が注釈した書物も非常に多く持ち合わせていたわけですね。沢山の書籍を収集しておった。
なので、そういった噂を耳にした「周金剛」は早速、自分が注釈した「金剛経」を箱に包み、自分の肩に背負って、その南方の新興仏法、新興宗教である、仏祖正伝と言われている禅宗を負かしてやろうと、四川省の山奥から南方の地へやって来るわけです。
これ当時からしたら大変な事ですよ。
だって「四川省」から「湖南省」というのは1000km以上もある訳ですからね・・。
そんな遠方まで荷物を担いで歩いて行った。
過去の心、未来の心、現在の心、どの「心」に餅を授けるのか?
南方の「湖南省」に到着した徳山宣鑑、「周金剛」は龍潭(りょうたん)という地にやってきました。
ここにはかの有名な「龍潭寺」があるわけですが、長旅で大変な荷物を背負ってきたので非常に疲れてしまったんですね。
「龍潭寺」の門前にある岩陰に腰を掛けていたんです。
するとその場所で商売をしているお婆さんとでくわします。
店で何かを売っているそのお婆さんにこの「周金剛」が質問をします。
 徳山宣鑑(周金剛)
徳山宣鑑(周金剛)お前さんは一体どういう人かね。
そうするとお婆さんが答えます。



ワシかね?ワシはただの餅売りの老婆だよ。
「餅」を売っていると聞いた、「周金剛」、



そうか、ワシは腹が減ってしょうがない、餅を売ってくれないか?
とお婆さんに聞いた。
するとその商い人のお婆さんは、



和尚さん餅を買って一体どうするんですか。
と「周金剛」に尋ねるんですね。
すると「周金剛」は、



餅を買って「点心」にするのさ。
と答えます。
「点心」というのは、最近よく耳にするあの「ヤムチャ」ですね。
お茶を飲みながら昼と夕食の間に食べるあの「ヤムチャ。」
まぁおやつのようなものですね。
お凌ぎ程度に食べる物を「点心」と言うそうで、因みに日本で言う「月餅」とか、「ゴマ団子」とか、「杏仁豆腐」とか、或いは「餃子」等も点心の部類だそうです。
正式な食事ではなくて「点心」という正式な食事の時間が中国にはあるんですね。
話が脱線しました。
「周金剛」は長い旅路で非常に疲弊し、空腹も重なって「お餅」をどうかわけてくれとお願いする訳です。
するとそのお婆さんは次のように「周金剛」に聞きます。



そうか、そうか。ところで和尚さん、その背中に担いでいる箱の中には一体何が入っているのかね?
このようにお婆さんに聞かれた徳山禅師は得意になって、



よくぞ聞いてくれた!お前さんは「周金剛」という人物の名を聞いた事がないかね?『金剛経』の知識に関しては誰にもに負けたことがない程、『金剛経』に通達しているその「周金剛」というのが実はこの私なんだ!そして私がこの背中に担いでいるのは他でもないその『金剛経』の注釈書だ。
という風に自慢して話すわけです。
そのように聞かされたお婆さん、



それじゃ私に一つの質問があるんだ。和尚さんに尋ねても良いかね?
このように「周金剛」に尋ねます。
このお婆さんは「龍潭寺」の門前で商売をやっているだけあって、『金剛経』についても多少理解があったのでしょう。
それでこの『金剛経』に関して疑問に思う所も兼ねてからあったのかもしれません。
そのような所にこの徳山禅師がやってきたので、一つ質問してみたいと思ったのかもしれない。
すると次のように「周金剛」に質問します。



私は以前、この「龍潭寺」の住職に『金剛経』について聞いたことがある。その金剛経の中には「過去の心も得べからず、現在の心も得べからず、未来の心も得べからず。」そのような文章が出てくる。それでは和尚さんは一体どの心にこの「点心」を授けようというのですか?
とんでもないお婆さんですね。
「周金剛」はこんなことを聞かれると思ってもいなかっただろうか、さぞ驚いたに違いありません。
これは勿論「言葉の綾」ですね。
「過去心不可得、未来心不可得、現在心不可得。」
つまり過去、現在、未来。どの場面に本当の心はあるのか?というわけです。
これは「言葉の綾」であり、「概念遊び」です。
どの場面をもってしても、本当の「心」など得る事が出来ないはずなのに、その心によって「点心」を授けるのか?と聞くのですから。
正確に答える事は誰であっても叶わないでしょう。
そしてお婆さんは、



和尚さんがもし、今の質問にきちんと答えてくれるなら私は和尚さんに「餅」を売ってあげましょう。しかしもし答える事が出来ないのなら私は「餅」を売らないよ。
と、こういう訳です。
さて、このように言われた「周金剛」は困ってしまう訳ですね。
『金剛経』に関しては人に負けたことがないと啖呵を切ってしまった割には徳山禅師は呆然としてしまった。
何と答えて良いか分からなかったんですね。また誰であっても答えられません。どんなに『金剛経』に通じている「周金剛」であっても答えられません。
つまり頭を使って「概念」で立ち向かおうとしては決してこの質問には答えられないのです。
そこでお婆さんは、「何だこいつは、何にも分かっていないな。」というので踵を返して結局は徳山に餅を売ってくれなかったという逸話が残っております。
あえなく徳山禅師は餅を食い損ねてしまいました。
我々が身を置くのは「真っ暗闇」の世界。暗闇では何も通用しない。
そのような老婆とのやりとりもあり、徳山禅師はさぞ悔しかったに違いありません。
このような婆様を仕立て上げたのにはきっとお寺が絡んでいると睨む。そのお寺の住職とやらを一目見てやろうと「龍潭寺」にいきます。
龍潭禅師もわざわざ遠方から徳山禅師が来たという事もあったので、二人はそこで丁寧にあいまみえます。
この龍潭禅師は後の徳山の師匠になられるわけですが、その二人はすぐに親しい間柄になります。
そして夜遅くまで話をしておった。
するとそのお寺の住職で、のちの師匠ともなる龍潭禅師が、



もう外はすっかり暗くなった。明日も早い事だし、お前は部屋に帰って休みなさい。
このように徳山禅師に声を掛けます。
夜遅くまで話し込んでしまったんですね。これまでの旅の話だとか、北方の話とかをしていたのでしょう。
この徳山禅師もすっかり後の師匠になるこの龍潭禅師に心酔してしまい、時を忘れて話し込んでいたのでしょう。
もうこんなに夜が更けたのかとふと気が付くんですね。
そして部屋に帰ろうとした。
すると、外はもうすでに真っ暗だったんですね。
そこで龍潭禅師は部屋に帰ろうとする徳山禅師に「紙燭」を手渡します。「紙燭」とはその名の通り、紙で出来た蝋燭で、紙を台材にして、その上に蝋燭を乗せるというものです。
徳山禅師がその「紙燭」に火を付けると外がホワーっと明るくなって、辺りがよく見えた。
しかしその時、その「紙燭」を手渡した龍潭禅師がフッとその「紙燭」をの「火」を吹き消してしまったんですね。
その時にこの徳山禅師はお悟りを開くことができ、その真っ暗闇の場で龍潭禅師に向かって礼拝をしたと言われております。
その際龍潭禅師は聞きます。



お前は一体どうして礼拝しているのか?早く部屋に戻りなさい。
すると徳山禅師が次のように言います。
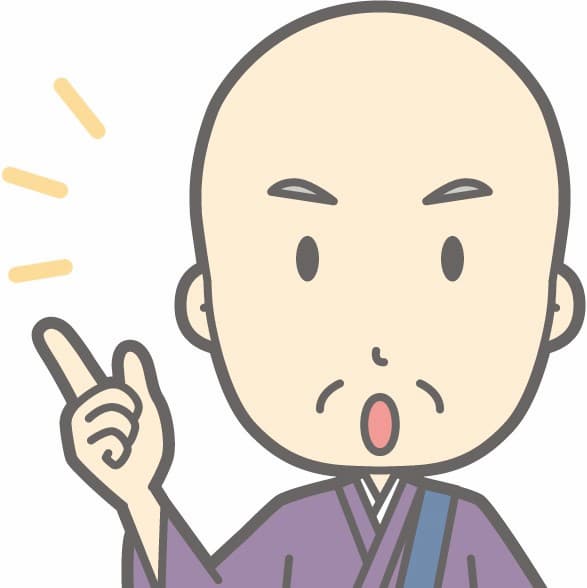
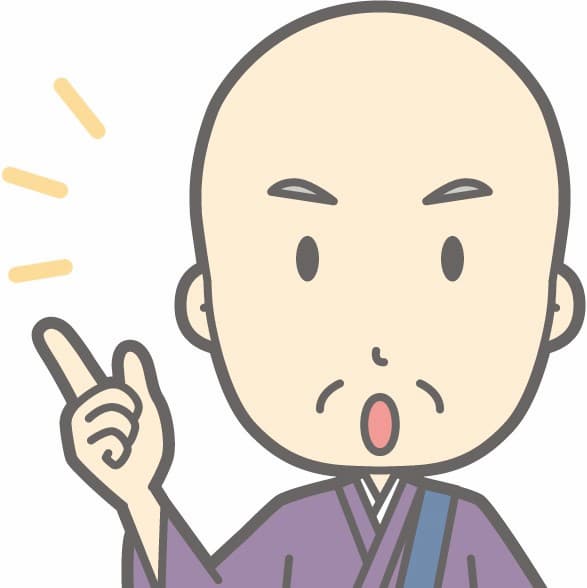
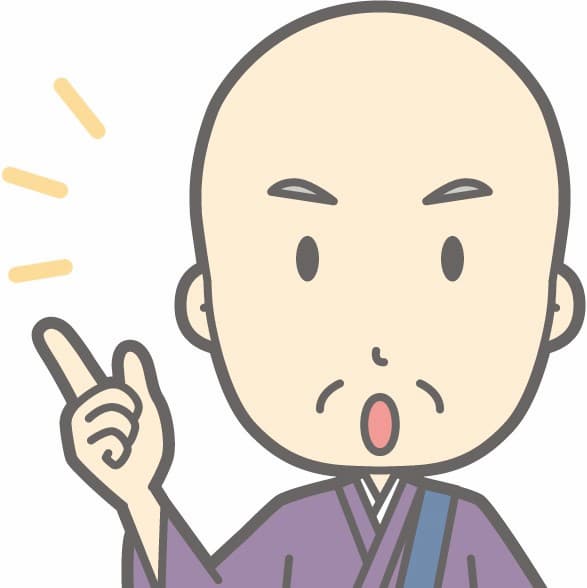
私は今後、お師匠の言われる事を信じて、そのまま受け入れます。
そのようなやり取りをされるんですね。そこから徳山禅師と龍潭禅師の師弟関係が築かれていったのです。
それまでの徳山禅師は「概念」の世界だけに拘束されておりました。『金剛経』さえあれば何でも解決出来るという風に思っておったんですね。
しかしそれでは門前で出会った老婆の質問には答えられなかったわけです。
そこでのちの師匠となる龍潭禅師に「実物」というものを見せてもらったんですね。その「実物」を見てすっかり今ままでの「概念」が崩されてしまった。
この世界には「実物」しかないという事に気づかされたんです。
暗闇だと何も見えない。見えるわけがない。ただそれだけなんですね。それ以上も以下もないのがこの世界なのです。その当たり前の出来事に仏法の大意を見た。それ以上も以下もない仏法の大意を見せられたわけです。
今の我々もこの徳山禅師と同じようにいつも「概念」の世界だけに振り回されおります。
「概念」と付き合っていけば物事は解決できると思っている。実際に解決できることもあるでしょう。しかしそれは人間同士のやり取りにおいてのみです。この世界の土台はそのような人間同士のやり取りではないということですね。大自然が土台なのです。
予想もしないのに大地震が起こる。自分が見ると思う前に見えている。聞こえている。香っている。そういう世界に生きているわけです。あるいは納得なしに腹が減る。納得なしに排泄をする。消化をする。そういう世界に生きているわけです。
我々の本当の世界は「真っ暗闇」なのです。一切明かりがない。「概念」が通用しない。手立てがない。
徳山禅師はその「実物」を龍潭禅師に見せつけられたんですね。本当の世界をみせられたのです。
「紙燭」の「火」を吹き消される事によって「真っ暗闇」の実物の世界を見せつけられた。それ以上ない世界を、ありのままの世界を見せられた。
そしてその時初めて気が付いた。
あぁそうか、実物の世界というのは真っ暗闇なんだな。
今まで自分が必死に学んできた学問は、この「暗闇」の前ではなんの役にも立たないではないか。
そして、
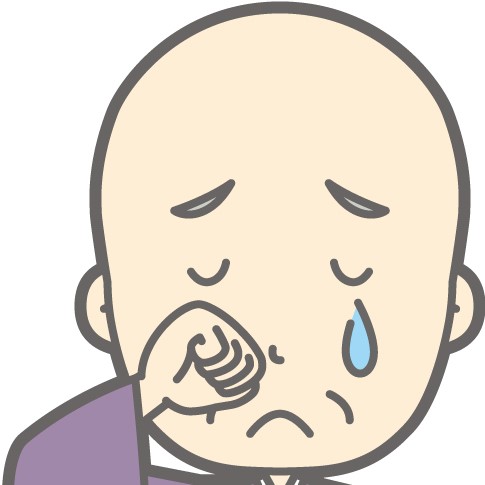
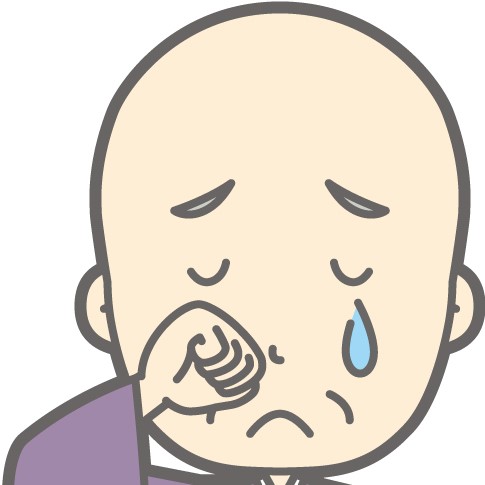
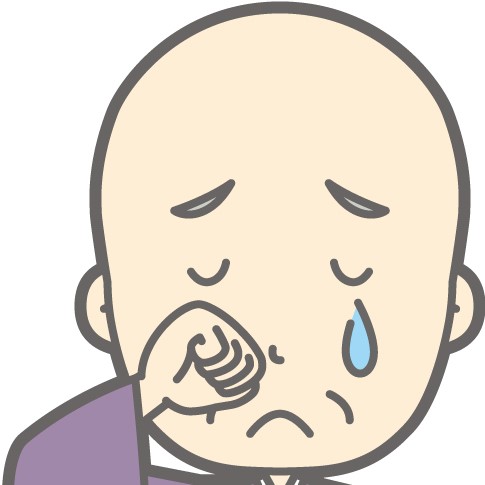
諸々の言弁を究めるも一毫の太虚(たいきょ)に置くが如し。世の枢機(すうき)を尽くすも一滴を巨睿(きょえい)に投ずるに似たり。
という言葉を残します。
つまりこれは「言葉を尽くして理論を纏めたとしても、それは所詮一本の細い髪の毛を大宇宙の片隅に置くようなものである。また世間の重要な、問題を解決したとしてもそれは一滴の水を大きな谷底に注ぐようなものである。」という意味です。
いかに自分がこれまで「概念」だけの世界に囚われていたのかを知った徳山禅師は、このような「偈」を作って、龍潭禅師に提示します。
そしてその次の朝、自分がこれまでずっと携えて持ってきた『金剛経』の注釈書をなんと全部焼き尽くしてしまったんですね。
周りの人々からも「周金剛、周金剛」と崇められ、それこそ「命」の如くに大切に扱ってきた『金剛経』の注釈書を本堂の前で焼いてしまうんです。
門前で出会った「老婆」に太刀打ちできなかったが、今ならあの問いにも答えらえれる。
過去の心、未来の心、現在の心、概念で探そうとすると「心」はどこにも見当たらない。本当の「心」とは今、ここ、この自分のことであると。心とは概念ではなく、今ここ、この事実のことを指しているのだということに。
概念では腹は満たされない。絵に描いた「餅」では一つも腹を膨らませられないのだ。という事にそこで気が付く訳ですね。
頭の中の出来事だけを解決する為に生きているのではない
このようにして見事に「真実の仏法」に出会えたこの徳山宣鑑禅師でしたが、その後「棒使いの名人」として有名となります。
「言い得るも三十棒、言い得ざるも三十棒。」という有名な言葉がありますが、弟子にいつも理不尽に「棒」を食らわせておったんですね。
「今日は私は何にも話さない。問う者があれば三十棒だ。」という様な事を弟子たちにいつも言う訳ですね。
質問する者には三十棒を食らわすぞと。
ある日一人の修行僧が徳山禅師の前に出てきて「お拝」をしました。
すると徳山禅師がさっそく、その棒でその修行僧を殴り付けてしまう。
そしてその修行僧が文句を言う訳ですね、



私は何も質問していません。ただお拝しただけじゃないですか。どうして私をぶん殴るのですか?
ご最もですね。
「もし質問するものがいたなら三十棒を与えると言われたのに私はまだ何も質問しておりません。なのにどうして私をぶん殴るのですか。私はただお拝をしただけですよ。住職さん早とちりも甚だしいじゃないですか。」と言う訳です。
すると今度は徳山がその修行僧に質問した。
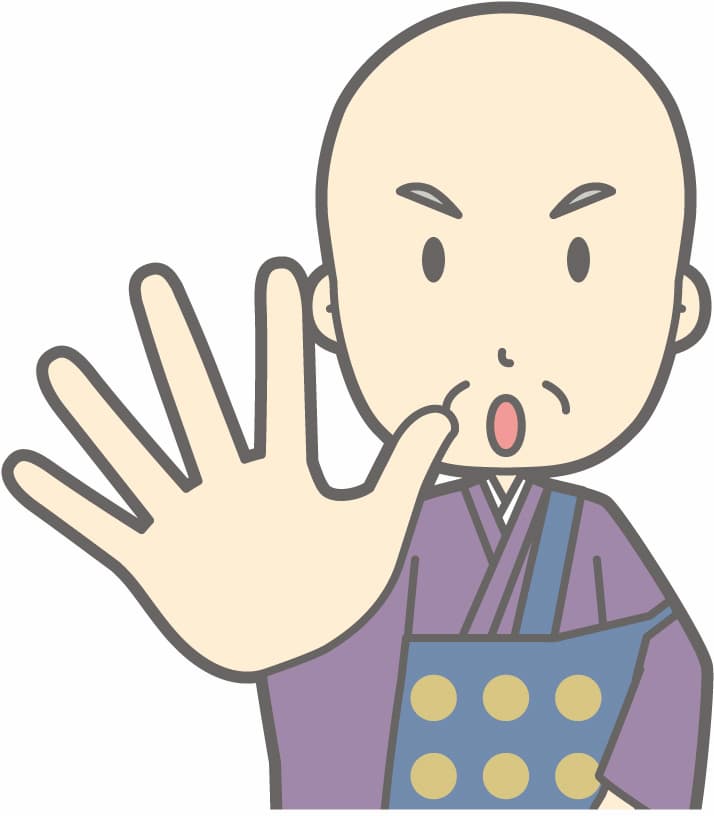
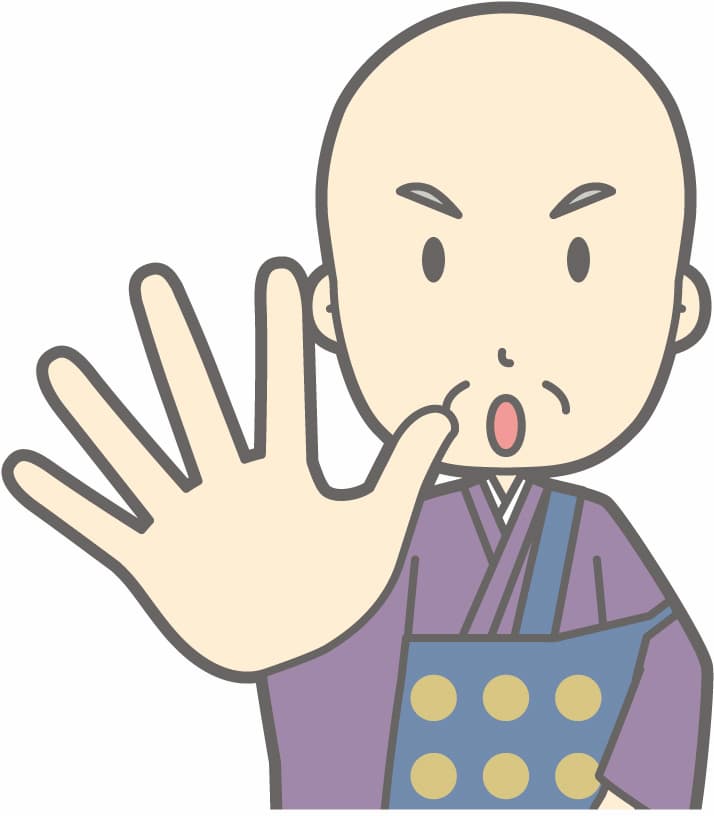
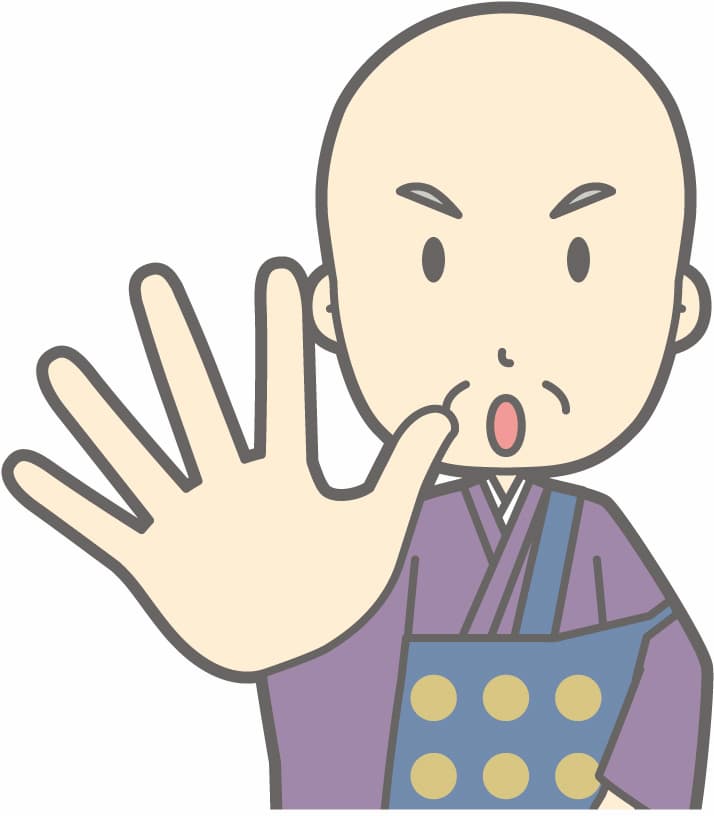
お前はどこの国の出身だ。
修行僧が答えて言った。



新羅の出身です。私は朝鮮から来ました。
「私は朝鮮の人です。」と、その修行僧は答えたんですね。
すると徳山宣鑑禅師は次のようにいいます。
それではお前がまだ舟縁を跨ぐ前に三十棒を与えよう。
と。
つまり、
お前が新羅の国を出ようとする、お前が家の玄関を出ようとする、舟で朝鮮から中国へ渡ろうとする、その前にお前に三十棒を与えよう。
と言うんですね。
「何をいっているんだ、この人は・・・」。理不尽に「棒」でなぐられた当時の修行僧はこのように思ったに違いありません。
我々人間が「道を求める」時は、自分の疑問を解決する為に道を求める訳です。自分に分からない事があった時それを解消する為に質問したりするわけです。そして自分の納得する答えが見つかると「ありがとうございました。」と言って感謝をする。逆に納得できなければふてくされて、不躾な態度を取ったり、受け入れなかったりする。
しかし我々が生きている事実の世界には「疑問」というものが何一つないですね。
先ほども述べたように納得なしに腹が減る。納得なしに呼吸しているのです。なぜ?が全く通用しません。概念がそこには介入しないのです。絶対なのです。
またあるいは「坐禅」をすると足が痛くなる。しかしなぜ痛くなるのか?そのように疑問に思ったとしても、痛くなるから痛くなる。それ以外ないんですね。
もちろん、なぜ痛くなるのか?と聞かれれば、
足を同じ時間ずっと窮屈に折り曲げて、血の血行が悪くなり、また太ももの同じ部分にずっと足を乗せておるから、その部分がその重みのせいでだんだんと痛くなってくる。
このように答えることもできるかもしれません。
しかしそれがわかったところで、それは止められないんです。誰でも足を組めば痛いんです。足を組んで痛くならない方法はないんですね。誰でもそうなってしまうんですね。つまり絶対なのです。
そのようなことは「単なる後付け」なのです。その事象に対して人間が説明書きをしているだけなんですね。
仮にそのようなことをしたところで、何も真意には触れられていないですよね。
なぜ足を組むと痛くなるのか?なぜ呼吸できるのか?こんなことは解明などできるはずがないのです。痛いから痛い。それだけなのです。
さっき食べた「食べ物」やさっき飲んだ「お茶」がどうやって消化され、体内に吸収されるのかの「メカニズム」を知らなくても平気で「食べ物」も「お茶」も消化できてしまっている。
そんな疑問とは関係なく、我々は常に、
- 安心してお茶を飲んでいる。
- 安心して寝ている。
- 安心して呼吸している
美味い、不味いという我々の好みはあったとしても平気で安心して食べて消化している。
それが大自然の、この世界の「法」なんですね。この世界というのは納得や概念が何も通用しないのです。それは我々だけに通じる話だということです。
我々の「命」や「本来の姿」には「疑問」が一つもない。概念が通用しない。
我々は頭の中の出来事を解決する為だけに生きているのではない。頭の中の疑問を解決する為に坐禅しているのではない。
そうではなく、「生命の実物に帰る」為に、「本来の世界に帰る」ためにこのように足を曲げ、手を組んでいるわけです。
この世界の本当のこと、それが坐禅を組んだ世界です。坐禅が我々の本当にいるべき場所です。常に目指すべきこと、それが「坐禅」です。
「言い得るも言い得ざるも三十棒。」何でも棒でブチ叩いてしまう徳山宣鑑禅師。
見事なことを「言っても」、「言わなくても」とにかく三十棒を食らわす。
「礼拝しただけ」のその修行僧にも三十棒を食らわす。
その痛みとも言える実物がこの世界の法であると、仏法の大意であると。それ以上も以下もない、その痛みにこの世界の全てが詰まっているのだと。
ただ冷静に考えてみれば、これはただの理不尽な行為ですよね。しかしそれでも「理不尽だ」と思うのも、概念が生み出している世界である。頭の中の概念のネットワークの中の出来事である。
叩かれれば痛い。そしてそこに伴う痛み。そんな当たり前のことが真なる「仏法」なのです。
普段我々が頭を悩ませている事象というのは、みんな頭の中の出来事でしかないわけです。そしてそれは存在していないものなのだよと、本来の世界に気づかせる、本来の世界に戻してあげる。その大切な役割をこの「棒」が担っていたわけです。
この我々が生きる世界には疑問や理不尽なことなど一つもないということを徳山宣鑑禅師は見抜いていたから「言っても」、「言わなくても」、礼拝しただけでも「棒」でブチ叩く。
それが「真実」だという事に気付いていたから。それ以外にないということに気づいていたから。
食べたものをなぜ消化し、どうやって消化するのか?そんなことは到底解明できるはずがありません。答えのないことに疑問を持つ。人間というのは本当に愚かな生き物です。
我々にできるのは「後付け」だけです。その事象において、人間だけがわかるように説明をするだけです。
何でも「棒」で殴ることで人を導いた徳山宣鑑禅師のお話を見てきました。
しかしそんな徳山宣鑑禅師にも元は迷っていた時間があったということもどうか忘れずに。
「払拳棒喝」の「棒」-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
について解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返ってみましょう。
- 「払拳棒喝」というのはそれぞれ単語を繋ぎ合わせたもので、それぞれに過去の仏祖方のエピソードがある。
- 「払拳棒喝」の「棒」は「棒」で殴ることで人を導こうとした徳山宣鑑禅師にまつわるエピソード
- 「疑問」は人の頭の中にしか存在しない。
- その「疑問」を解決するために生きているのではない。
- 我々の生きる世界に「理不尽」なことなどない。
お読みいただきありがとうございました。

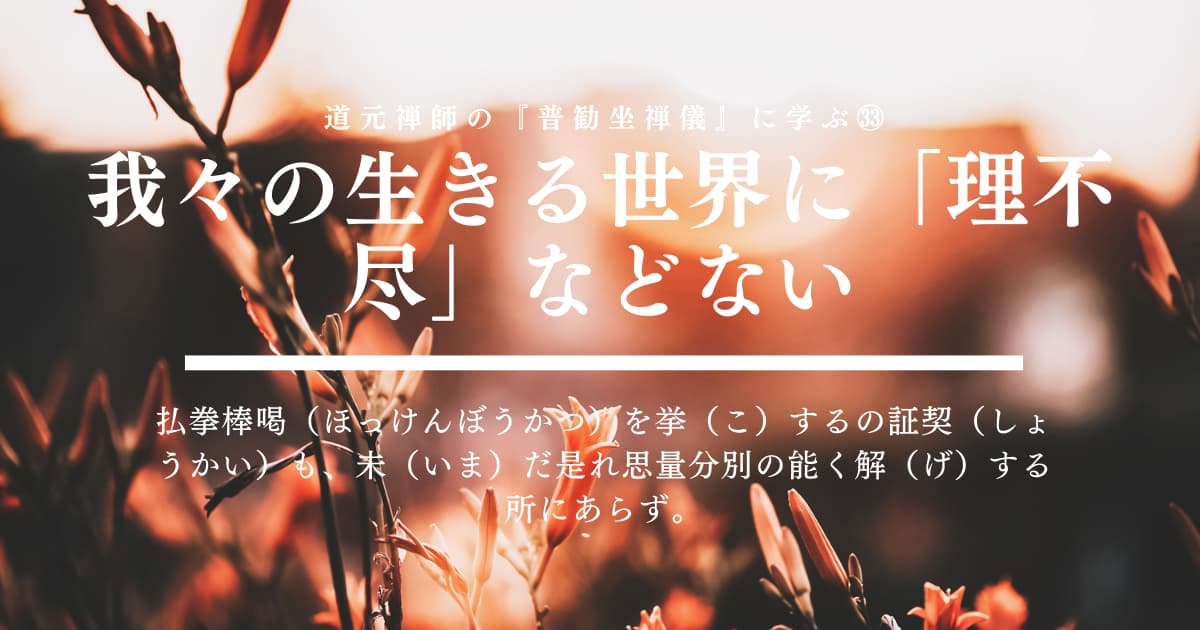

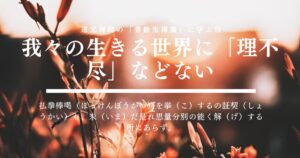
コメント