本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を解説していきたいと思います。
まず初めに前回の、
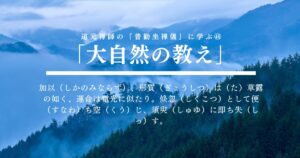
のポイントを振り返りたいと思います。
- 我々の一生というのは稲妻のようなものであり、たちまちに消えてなくなってしまう。それほど儚い物である。
- 須臾(しゅゆ)というのは時間の単位で今で言う「48分」を指す。
- 人間の命は非常に短い。
- 二度と「仏法」に出会う事ができないかもしれない。
- 「仏法」生命の実物をよりどころにする。
- 自分の命を大切にするということは、他人の命を大切にするということ。
- 大自然の教えを説いたのが「仏教」
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
唯、打坐(たざ)を務めて、兀地(ごっち)に礙(さ)へらる。万別千差(ばんべつせんしゃ)と謂ふと雖も、祗管(しかん)に参禅辦道すべし。何ぞ自家(じけ)の坐牀(ざしょう)を抛卻(ほうきゃく)して、謾(みだ)りに他国の塵境に去来せん。若し一歩を錯(あやま)らば、当面に蹉過(しゃか)す。既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。仏道の要機を保任(ほにん)す、誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん。加以(しかのみならず)、形質(ぎょうしつ)は(た)草露の如く、運命は電光に似たり。倐忽(しくこつ)として便(すなわ)ち空(くう)じ、須臾(しゅゆ)に即ち失(しっ)す。冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ。直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ。久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし。宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。
終わり
参学の高流と大徳
今回は『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説していきます。
道元禅師は「坐禅」を志し、「真実」を求めようとする者のことを「参学の高流」と言っております。
そこから今回の内容は始まります。
「高流」というのは、「非常に尊い方」たちに向かって、敬いを見せる際に使われる「言葉」です。
なので「参学の高流」というのは、「坐禅を志す、尊い皆さんよ」というような意味になります。
また一度でも「真実の道」を求めようとしたの者であればみんな「高流である」というんですね。
臨済宗の開祖様であられる「臨済義玄禅師」も、この「高流」と同じような意味合いで、真実の道を求めようとするものの事を「大徳」という言葉でもって表現されます。
このように過去の祖師方は、真実の道を求めようとする者、あるいは一度でも「真実の道」を求めようとした者のことを非常に敬おうとされるのです。
続いての「久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ」という部分ですが、ここは少し複雑なんですね。
この部分は『涅槃経』の逸話に由来しております。
摸象
昔、インドにおいてある教員が大勢の人達を、「象」の所に連れて行きました。
教員というのは現在で言えばいわゆる「旅行ガイド」のようなものですね。
そこでその「象」を多くの人達に撫でさせるんですね。
「手で象に触れる」。これが要するに「摸象」 ですね。これをその参加者にさせる。
すると人によって「足」を撫でたり、「背中」を撫でたり、「鼻」を撫でたりするものがいる。
人によって撫でる場所が異なる訳ですね。
そこで足を撫でた人は「象」のことを「丸太のようです」と言う。
または「象」の「しっぽ」を撫でた人は「箒のようでした」と言う。
或いは「象」の「腹」を撫でた人は「太鼓のようでした」と言う。
撫でる箇所はてんでバラバラで、一つの「象」に対しても人によってそれぞれの感じ方、捉え方をするわけですね。
それは毎回のことだったのでしょう。
それを先導する「ガイド」はいつも、そのことを周りの仲間達に報告するんですね。
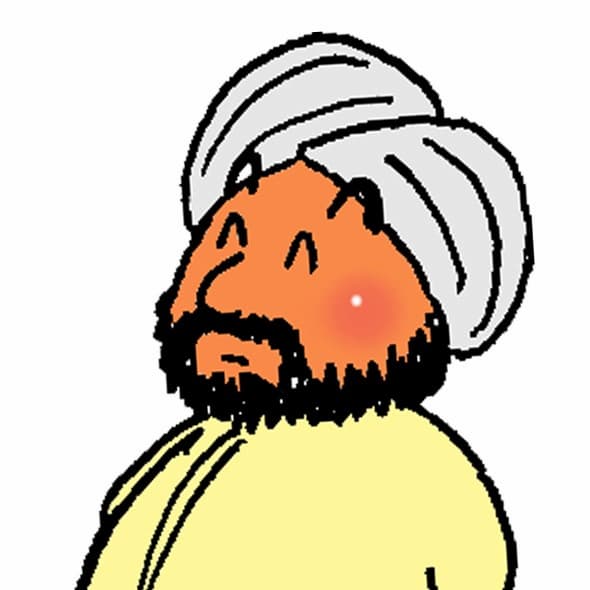
かくかくしかじか。こうで、ああで。
するとみんなが笑うというんですね。
「象をまるでわかっていない」とあざけ笑うというんです。
このような逸話が『涅槃経』に残されているんです。
命の現場はここしかない。
この『涅槃経』の逸話が言わんとしていることはなんでしょうか?
道元禅師はこの経緯を非常に非難されるわけですね。
というのも、我々が実生活を体験した現場というのは上から眺めて、ああだこうだと文句を付けられることは何もないというのです。
我々がこの身体をもって、現場で感じること、捉えることが我々の本当の現場であり、出会いの場であると。それが全てで、それ以上も以下もないと、そう言われるんです。
誰かがとやかくそれを非難することはできないというんですね。
その場所でその人の感じたこと、それは他の誰かが感じることのできない、紛れもない出会いです。そこだけの唯一の出会いです。命の出会いです。それ以上も以下もない確かな出会いであり、誰かが難癖つけられるものではないのです。そして確かに感じたこと、感じてしまったことであるわけで、それに対し正しいも正しくないも、ないわけです。
そういうことをおっしゃっているんですね。
それを踏まえると、私が生きる日常も全てが尊く思えてきます。普段の現場というのも「ここしかなく、それ以上に勝る物はない」ということだからです。
常に我々はそうした尊い機会に際しているわけですね。
「象」の「鼻」をもって「縄のようだ」と感じたとしても、それがその人の「命の現場」であり、「すべて」だということです。
あるいは仮に目が悪く、その象を太鼓のようだ、縄のようだといったとしても、それはそれ以上も以下もない至高の出会いなのです。
我々が与えられている今、ここ。この「命の現場」というのは、仮に目が不自由な人間であっても、目が良い人間であったとしても紛れもない、唯一無二のものなんですね。今「ここ」というのは誰においても、どこにおいても唯一無二のものなのです。
我々が今こうして息ができたり、鳥や車の音が聞こえてくるのは、世界と私とが1つだからです。例えば呼吸というのは市外か、県外か、はたまた国外か、どこからやってきたかわからない酸素を吸うことによってできることです。
あるいは鳥の声がこうして聞こえるのも、鳥の鳴き声が自分の耳を震わせている。鳥が自分の命を起こす。鳥が自分そのものだから聞こえてくるわけです。
世界と私とは同時なのです。1つなのです。物事というのは決して2つに分かれないんですね。世界と私とは溶け合っているわけです。
この世界というのは全て、今ここ、この自己の展開だというわけです。
その世界というのは常に宇宙いっぱいです。常に真実むき出しの姿をしております。無論我々も真実いっぱいです。嘘偽りのない命をこうして生きております。1秒ごとに年をとり、足を組めば痛い。肌をつねれば痛い。こうした紛れもない命を生きているわけです。
そんな真実いっぱいの宇宙と我々は1つのわけですから、そこでの出会いに上下や優劣などあるはずがないのです。
あるいはそれは真実いっぱい同士の出会いなのだから、上下や優劣などあるはずがないということなんです。
そのようなこともあって道元禅師はこの『涅槃経』に出てくるこの話を非難されるわけなんですね。
なのでこの「久しく摸象(もぞう)に習つて」 というのは、



本当の「命の現場」というのは第三者が上から覗き込んで評価したようなものではない。みんなそれぞれが「ここ、この命」を通して実体験した現場こそ「命の現場」である。それは真実の展開である。
というわけです。
ですから「象」の「鼻」をもって「縄」のようだといったのであれば、それがその者の命である。宇宙の真実であると。
だからそこを間違えるなよ、と道元禅師は今回の「象を撫でる」という出来事にちなんで、「摸象」という言葉をもってお示しになるわけですね。
真龍を怪しむことなかれ
続いての「真龍を怪しむこと勿(なか)れ。」というのはこちらもある逸話が由来しております。
昔、「葉公子(ようこうし)」という「竜」を非常に愛する人がいました。
「竜」を愛するあまり、自分の住むくつろぎの居間には、「模型の竜」や「彫刻で掘った竜」、「絵に描いた竜」などが沢山飾られてあった。
毎日、毎日その大好きな「竜」を眺めて暮らしていたんですね。
そのような事が行われているということを知った「真龍」は、



模型にしてまでも私のことを好んでくれるのなら実際に私がこの葉公子の所に赴いたならさぞや喜んでくれるだろう。
と言って天から下りてきてその「葉公子」の所に顔を出すんです。
するとこの「葉公子」は、喜ぶどころか肝を抜かしてそこで失神してしまったという逸話が残されているんです。
そのことがこの「真龍を怪しむことなかれ」という内容の由来になっているんですね。
これはどういうことかと言うと、「模型の竜ばかりを好み、真龍を怪しんではいけないぞ」という意味なんですね。
先の「摸象」の話もそうですが、我々は概念による比較や妄想ばかりを好み、肝心の体験、またそこで生じる感覚を疎かにしてしまいます。
そこを、



真実を志す、尊い皆さんよ。摸象や偽物の竜ばかりにとらわれ過ぎないで、どうか肝心のものは手放さないでください。
そういった道元禅師の願いが込められた今回の内容であったわけです。
良寛さんの生活は真似できない
越後の「良寛さん」と言えばその名を知らない人はいないほど有名な禅僧です。
その「良寛さん」は純朴な方として知られており、過去から現在に至るまで非常に多くの人から親しまれているお人です。
本屋さんに置かれている仏教書の中で一番多く読まれているのはこの良寛さんにまつわる書籍だとも言われているほどですし、「私は良寛さんが大好きです!」という人が世の中にはいっぱいいますよね。
中には「良寛さんのような自由な生き方をしたいなぁ」という憧れを持っている人もいる。
しかしいざ「良寛さん」のような世界を生きるといったらこれは大変なことですね。
というのもその自由奔放な気質には隠されていますが、この「良寛さん」は一生涯を厳しい修行生活に捧げたお方です。
長い修行を経て、そのあとは「五合庵」と呼ばれる小さな庵で、物もおかない、財も持たない、食物も持たない、実に質素な生活を貫かれました。
贅沢もせず、毎日が非常に貧しい生活であった。
時には、親しいお医者さんに「味噌が足りません、薬が足りません、助けてください」という手紙もしたためていたというのです。
おそらくこのような生活に耐えられる人は、この世にはいませんね。
なので現代人がいざ「良寛さん」のような生活をしたいと思ったとしても、とてもじゃないですが務まらないのが現実です。
今回の「摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむ」のように、竜の「模型」は好きだけどもいざ真龍に出会ったら腰を抜かしてしまう羽目になるでしょう。
寿司職人になるには「人生」を学ぶ必要がある
もう一つ余談をさせてください。
かの「ライブドア」を設立した「堀江貴文」さんという方がおりますね。
彼が書いたブログ記事は面白いといつも話題です。
時に「寿司の職人さんが何年も修行するのは馬鹿だ」というような内容の記事を書かれたんです。
寿司職人は「飯炊き3年、握り8年」と言われますが、そのように何年も何年もかけて修行するのは馬鹿であるというような内容だったんですね。
確かに「飯炊き3年、握り8年」も掛けなければやっと一人前の寿司職人になれないというんだったら、実に効率が悪く、だったら見習いなんてせずに、初めから寿司学校にいけよ、と思うわけですね。
今やそういった学校は結構あって半年でもそういった学校にいけば簡単に免許をもらえたりしますからね。
「確かに・・。」と私も思う訳です。
そのブログ記事に対しては色々なコメントも投稿されていました。
「おっしゃる通りだ!」という人もいる。一方で「本当にそれが馬鹿なのか?」という人も勿論いる。
この「ホリエモン」からすれば例えば「禅道場の修行」なんていうのも本当に馬鹿の諸行に思われるんでしょうね。
何も生まれない。またその修行をしたことに関して何も実績や証明書が手に入らない。
「ホリエモン」はよく言っていましたね。「お金をだせば買えないものはない」と。「お金さえあれば何でも手に入るんだ」と。
そのような価値観の人から言わせれば、何にもならない禅道場での修行経験や何の得にもならないこの「坐禅」を生涯かけて行じていくということは非常に馬鹿らしく感じられることでしょう。
しかしこうも思う訳ですね。
確かにテクニックを学ぶと言う意味で言えば調理学校に半年行けばお寿司が実際に握れるようになるのかもしれない。
飯炊きもできるようになるのかもしれない。
なのでテクニックや資格を学ぶという点から考えればそれで十分かもしれませんね。
しかし将来僧侶を志すものが「禅道場」で学ぼうとしているのはそのようなテクニックや資格の話ではないんですね。
それでは「禅道場」で一体何を学ぶのか?寿司職人が「飯炊き3年、握り8年」という期間を通して何を学ぶのか?
それは「禅道場」を通して真実を学んでいくんですね。この世界の真実。規則。こうしたことを学んでいる。
それが「人生」で生きてくるのです。
お金や効率の話を学んでいるのではないのです。
「飯炊き3年、握り8年」を通して「人生」を学んでいく。
時にはトイレ掃除があったり、住み込みの生活があったり、何年間も親元を離れ寒い山奥で坐禅生活をしたり、親方や古参に殴られたりもします。
しかしそのような一見、非効率で無駄だと思われるようなことが実はとても重要なんですね。
それにその経験は、お金では決して買えないほど高貴なものだから、我々のような新米修行僧は「耐える」ことができるわけです。
人生を学ばなかったらお寿司屋さんにはなれなかったんですね、昔は。
お客さんもそういう人が握る寿司を食べたくてお寿司屋さんにも通った訳です。
確かに今日ですと、「味さえよければいい」。という風習もあります、美味しいに越したことはありません。
しかし本当の味、本当の人生というのはそのような上っ面だけをすくっただけでは再現できないわけです。
今回の『普勧坐禅儀』の内容は、
というものでした。
そしてその意味は、



真実を志す、尊い皆さんよ。摸象や偽物の竜ばかりにとらわれ過ぎないで、どうか肝心のものを手放さないでください。
というものでした。
我々は「模型の竜」ではなく「真龍」にこそ出会うべきです。全てが真実の出会いです。
非効率なことでも、そこでじっと耐え忍んで行うことに意味があるのです。
我々はいつか死ななければならないわけです。
人生の幕をいつか閉じなければならない。
それなのに「模型」や「テクニック」ばかりに出会おうとして人生の幕を閉じたならもったいない。
限りあるこの人生の中で一体何に重きをおいて生きて行けばいいのか、是非本記事で道元禅師が語ることを踏まえ「真実の人生」を学んでいってください。
まとめ
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
と言う部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 一度でも真実を求めようとした人に対し、「高流」や「大徳」という言葉をもって尊敬の意を表す。
- 「手」で「象」に触れることを「摸象」と言う。
- 「実体験」に勝る物はない。他人がとやかく言う事では無い事。
- 「命の現場」は「ここ」。
- 「ここ」には「良い」、「悪い」といった人間の尺度は一切ない。
- 「真竜(真実)」にこそ、怪しまずに出会ってほしい。
以上、お読みいただきありがとうございました。

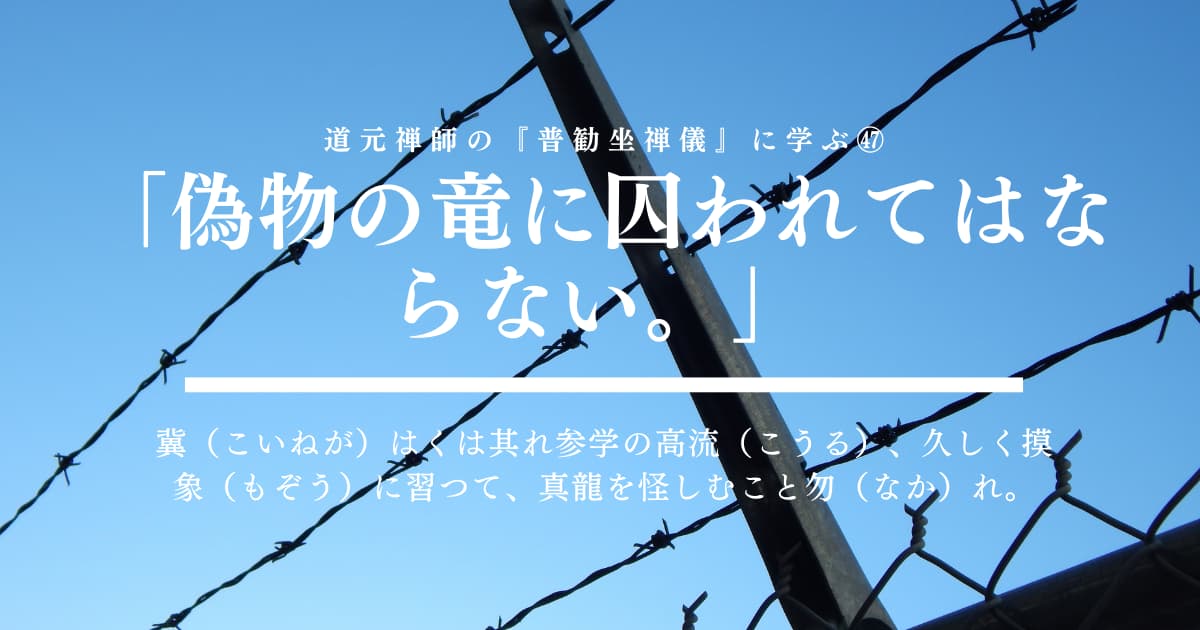
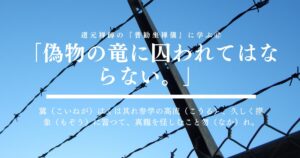
コメント