本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を解説していきます。
まず初めに、前回の
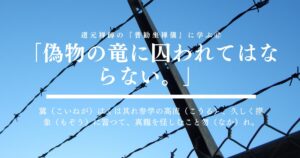
のポイントを振り返りたいと思います。
- 一度でも真実を求めようとした人に対し、「高流」や「大徳」という言葉をもって尊敬の意を表す。
- 「手」で「象」に触れることを「摸象」と言う。
- 「実体験」に勝る物はない。他人がとやかく言う事では無い事。
- 「命の現場」は「ここ」。
- 「ここ」には「良い」、「悪い」といった人間の尺度は一切ない。
- 「真竜(真実)」にこそ、怪しまずに出会ってほしい。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
唯、打坐(たざ)を務めて、兀地(ごっち)に礙(さ)へらる。万別千差(ばんべつせんしゃ)と謂ふと雖も、祗管(しかん)に参禅辦道すべし。何ぞ自家(じけ)の坐牀(ざしょう)を抛卻(ほうきゃく)して、謾(みだ)りに他国の塵境に去来せん。若し一歩を錯(あやま)らば、当面に蹉過(しゃか)す。既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。仏道の要機を保任(ほにん)す、誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん。加以(しかのみならず)、形質(ぎょうしつ)は(た)草露の如く、運命は電光に似たり。倐忽(しくこつ)として便(すなわ)ち空(くう)じ、須臾(しゅゆ)に即ち失(しっ)す。冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ。直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ。久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし。宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。
終わり
直指とは、認識のことではない
今回は『普勧坐禅儀』の、
という部分を読んでいきます。
まずは「直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、」というところから参ります。
「直指」というのは、そのままの意味で言うと「直接指す」ということですね。
ただ、ここでは「その人が持ち合わせる知識や価値観などの障害物なく、直接実物を見る事、生命の実物にであうこと」と言う意味になります。
この「直指」というのは、要するに認識のことですが、我々が普段行っている「認識」とは違う方法になりますね。普段の「認識」とは違うんです。
我々が普段行う「認識」。これは前もって持ち合わせた「ネットワーク」や「知識」、「先入観」を駆使し、頭を使って「理解」していくことを行なっているわけです。
例えば、こんな話があります。
初老を迎えた女性グループがある日、紅葉シーズンに山に登りに行きました。
すると一人の女性がその山頂から見下ろす景色を眺めて「まぁ綺麗!絵はがきを見ているようだわ!」と言ったんです。
つまり、その時、その女性は「目の前に直接の景色があるのにももかかわらず、絵はがきを通してその景色を見てしまった」わけです。
以前「絵はがきで見た映像」が頭にこびりついており、その概念と実際の景色を見比べながら物を眺めていたというわけです。
直接その物事を見ることができず、概念フィルターを通してそれを見る。これが今回で言う所の「直指」ではなく、「認識」にあたる行為です。
「直指」というのはこのような人間の「認識」とは異なるんですね。
坐禅こそ直指端的の道である
「直指」とはどういうことか、もう少し詳しく見ていきましょう。
過去の祖師方が真実に目覚められるきっかけは、全てこの「直指」があったからでした。
潙山霊祐(いさんれいゆう)禅師の弟子に、霊雲志勤(れいうんしごん)禅師という方がおります。
その霊雲禅師が山道を歩いていた時の事です。
山間の道に「桃の華」が咲いていたんですね。
非常に美しい「桃の華」が咲いており、その「桃の華」を見てお悟りを開いたんです。
その「大悟」の様子についてはここでは割愛させていただきますが、これも「直指」であります。
自分で持っている知識や価値観などの障害物を介さずに受け入れたから真実に目覚めることができた。
そこに到達させたのが今回の「直指」だったんですね。直接「桃の華」を見たという「直指」であります。
お悟りは個人の境地ではありません。真のお悟りを開くと言うのは大自然と一体になること。認識をすることでも、何かを理解することでもないのです。
そこでは「直指」が必要になるんですね。
あるいはもう少し我々に身近な話で言うと、「針」で自分の「人差し指」を刺したとします。
反射的に「痛っ!」となるはずです。
これも一切障害物なしの「直指」であります。大自然との一体。大自然の呼吸、大自然の息づかい。
これがお悟りであり、すなわち「直指」であります。
「針」で多少「人差し指」を刺しただけなのに実際には飛び上がるほど痛いです。その痛みは誰とも比較できない痛みでもあります。
認識や比較、人間の概念が介入していないんです。
それが大自然であり、宇宙です。またそれが「直指」であり、お悟りです。
また実は我々が行じているこの「坐禅」も「直指」です。お悟りです。
何故ならこの「坐禅」は認識や価値観などの思い手放しの行であるからです。
これが今回いうところの「直指(じきし)端的の道」であります。
この「坐禅」は認識や価値観などを介せず、「生命の実物」を行じ、「生命の実物」を直接見ているから行だからです。大自然に出会っている行。大自然そのもの。この世界の正体。あるいは「生命の実物に出会う行」、「仏に出会う行」なんですね。それがこの坐禅です。
大自然の行、大自然そのものだと言うことです。すなわちこの坐禅が「直指」だと言うことなんですね。
「直指」というのは普段我々に馴染みの深い「認識」や「概念」とはベクトルが違います。
「直指」は認識ではないのです。頭の中の出来事ではないし、個人の持ち物でもない。大自然のお話なんですね。
そもそも世界には概念がありません。個人の所有もないのです。今こうして息ができるのも、酸素を供給してくれる他があるからです。つまり自分の命にここからここまでという線引きを敷くことができないのです。
「俺」という概念というは人間の「脳」があたかも本当にあるかのように見せかけている、実際には存在しないものです。人は「俺が見た」と言いますが、俺が見たと思う前からそれは見えていたわけです。
実際に目の前に概念を出せと言われても出せない、これが何よりもそのことを物語っています。
概念はない。世界に個人はない。無我。全てが1つに溶け合っているわけですね。
ですから、仏法では自我を認めません。「諸法無我」と言い続けるわけです。あるいは今回の「直指」の意義と重要性を説くわけですね。
勿論この「認識」や「観念」というものがあるおかけで、我々人間は他の人達と通じ合う事が出来るわけです。
また現代において、他人とコミュニケーションを取ることが重要ですがその為の手段としてこの「認識」や「観念」は非常に役立つんですね。
しかしこの「認識」や「概念」というのは実物ではありません。
この世界にあるのは「実物」のみなんですね。
仏法で取り上げるのは「認識」や「観念」ではなく「実物」、「直指」の話です。
先ほども言いましたが、「針」で「人差し指」を刺し、「痛っ!」となる。
これは「認識」や「観念」、「概念」の話ではありませんね。
何故ならその「痛み」に関して説明できる話でもなければ、比較できる話でもなく、「宇宙一杯の痛み」だからです。
この「坐禅」もそれと同様に、誰とも比較できない「実物の命」を行じているんです。
この坐禅こそが、大自然そのもの。「直指」そのものなのです。
だから今回の「直指(じきし)端的の道(どう)」ということなんですね。
そして道元禅師は我々にその「直指(じきし)端的の道(どう)」をおすすめになられるわけです。
それは本来だからです。大自然のあり方、人間本来のあり方だからです。
「直指(じきし)端的の道(どう)」に精進してくださいと。「直指端的の道に精進し、」というのはそういうことなんですね。
絶学無為の人を尊貴し
続いて「絶学無為の人を尊貴し、」という部分についてです。
まずこの「絶学」と同じような言葉に「無学」というものがあります。
「無学文盲」という言葉にもあるように世間では、「学問がない」ことをこの「無学」といったりします。
しかし仏法でいうこの「無学」というのはそれとは逆に「学びつくした人、学ぶことがなくなった人」のことを「無学」というんですね。
この「絶学」においても元々は同じ意味でした。
「学ぶことを絶した無為の人」、「学びつくした人」という意味でこの「絶学」という言葉が使われていたんです。
昔、馬祖道一禅師という方がおられました。
その馬祖道一禅師は弟子たちに「仏法の大意」は「即身即仏」であるという風にお示しになっていた。
「あなたが仏そのものだよ」ということをお示しになっていたんですね。
「悟り」というと何だか外にあるように感じる。「幸せ」というと何だか外にあるように感じる。
何でも外に求める人に対して「お前さん自身が仏ではないか」と「それなのにどうしてお前は外ばかりに物を求めるのか」という意味を込めてこの「即身即仏」という言葉を用いていたんですね。
この「絶学」はこうした外に求めない人のことを指すんですね。
「学ぶことを絶した無為の人」、「学びつくした人」という意味でもあるのですが、実はこの「絶学」にはこうした意味があり、本来学ばないこと。学ぶ必要はどこにもないということです。
世界というのは学び必要はないのです。悟りも学ぶ必要もない。仏法も学ぶ必要はない。
ただ坐ればいいのです。ただ坐ればその場所がお悟りです。そこにこの世界の正体が全て詰まっております。
なので「坐禅」が「絶学」なのです。何も一切外に物を求めない。求める必要がない。あるいは「声色外の威儀」です。
自分が生命の実物、世界の実物を実践するだけです。坐るだけです。
そしてそれを行じる人こそ本来の人であり、ここでいう「絶学無為の人」であり、それはとても尊いことだということなのです。
人類誰しもが目指すべき人ということですね。
ここまでの話をまとめます。
今回の「直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、」というのは、「我々が行じているこの坐禅が直指端的の道であり、その道に精進する人を絶学無為の人と呼ぶ。だからそういうひとを尊びなさい」ということなんですね。
まとめ
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 「直指」は「認識」とは違う。
- 「直指」とはその人が持ち合わせる知識や価値観などの障害物なく、直接実物を見る事、生命の実物にであうこと。
- 「坐禅」こそまさに「直指」で、「直指端的の道」である。
- そしてその「直指端的の道」に励む人を「絶学無為の人」という。
以上、お読みいただきありがとうございました。

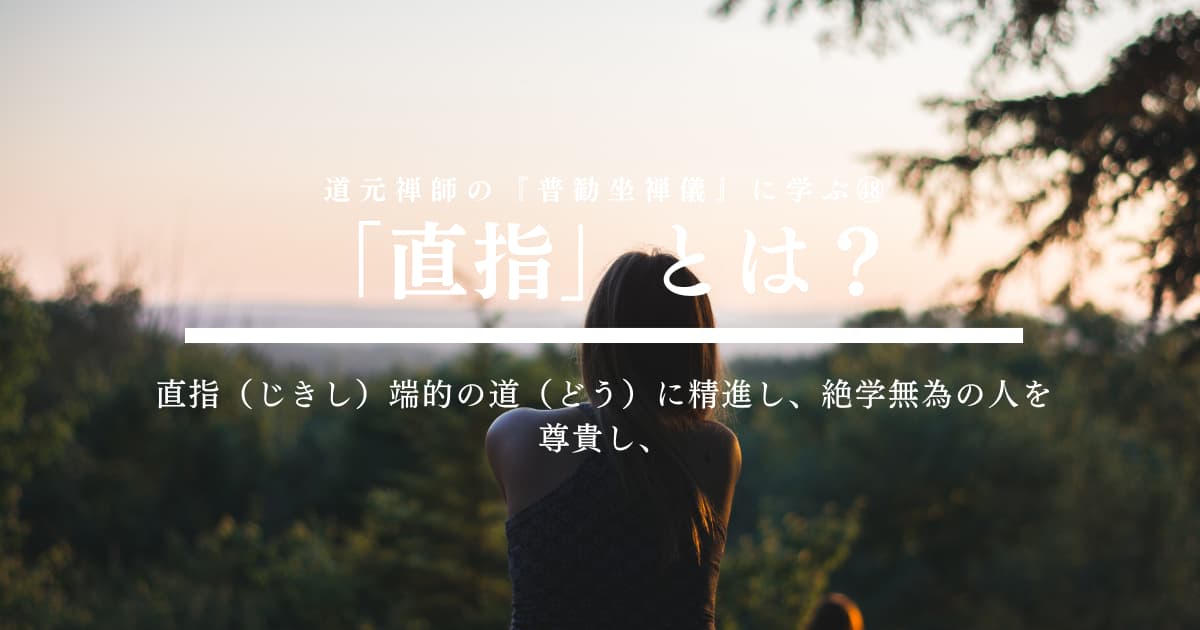

コメント