道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第⑦弾といたしまして、「愛語(あいご)」についてをお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
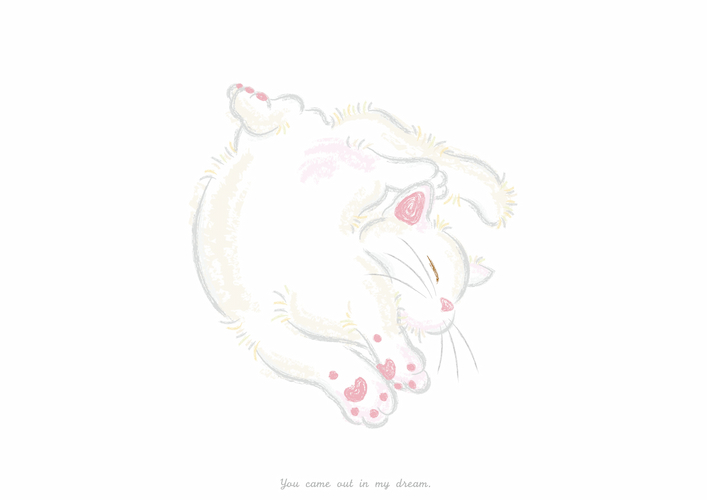
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

愛語とは?
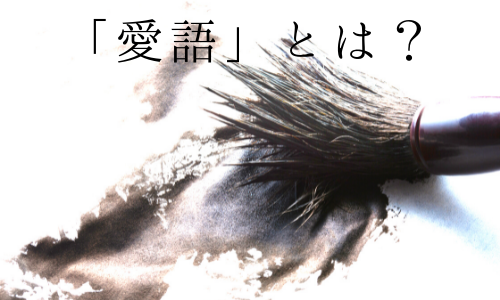
「愛語」については、最近では新聞やテレビ、スマートフォンニュースでもよく聞かれるようになりました。
「愛語」とは簡単にいえば「やさしいことばを他者に語りかけること」をいいます。
仏教においては、「菩薩」が我々衆生を導くために設けた四つの方法として「四摂事(ししょうじ」というものがあります。
「布施(ふせ)・愛語(あいご)・利行(りぎょう)・ 同事(どうじ)」がそのことですが、今回の「愛語」もその1つに含まれるというわけですね。
これは要するに我々衆生が実生活で行うべき、修行法の1つという考え方なのです。
道元禅師は『正法眼蔵』、『菩提薩埵四摂法(ぼだいさったししょうぼう)』の巻で次のような言葉をもってこの「愛語」について触れておられます。
むかひて愛語をきくは、おもてをよろこばしめ、こころをたのしくす。むかはずして愛語をきくは、肝に銘じ、魂に銘ず。しるべし、愛語は愛心よりおこる、愛心は慈心を種子とせり。愛語よく廻天のちからあることを学すべきなり、たゞ能を賞するのみにあらず。
これは以下のような意味となります。
自分の素直な気持ちに寄り添えば、そこには慈悲の心があることが分かる。そして誰しもがその慈悲の心からなる愛語で他人に語りかければ、相手は嬉しい気持ちになるだけでなく親愛なる思いで自分に接してくれるようになる。そのようにしていけば仮に敵対しあっていた人物とも仲良くしていける。そのような愛語のもつ力を我々は学ぶべきである。
我々は本来皆仏です。この世界では仏行を行うこと。仏弟子としての規律を守ること。「四摂事(ししょうじ」を行うこと。今回の「愛語」も、仏弟子としては当たり前の行為であるとされており、人に優しい言葉を投げかけることは自身の修行にもつながっているということなのです。
この「愛語」によって自身も豊かになる。他者も豊かになる。
「菩薩」が我々衆生を導くために設けた方法として、非常に適切なものであると非常に納得してくるわけです。
いまこの瞬間からでも、この「愛語」をもってすれば自分だけでなく他人も幸せな気持ちにさせることができるのです。
曹洞宗でよく聞かれる「和顔愛語」とは?
今述べた「愛語」には「和顔愛語(わげんあいご)」という関連語句があります。
よく曹洞宗などで、お寺の住職が説法をする際に使う言葉ですね。
この「和顔愛語」に使われる「和顔」はやわらかな顔と書きます。
なので「和顔愛語」とは文字通り、笑顔で愛情のこもった言葉で語りかけることを言うのです。
またこの「和顔愛語」ですが、もともと『無量寿経(むりょうじゅきょう)』というお経の中に出てくる言葉で、そこには「和顔愛語にして、意を先にして承問す」とあります。
つまり、「相手のこころをなによりもまっさきにくみ取り、愛情のこもった言葉とやわらかな笑顔で接しなさい」という意味になります。



コメント