今回は、
という部分を解説していきます。
それではまず初めに前回の、
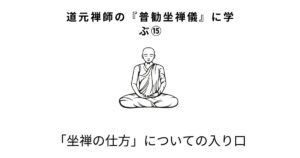
のポイントを振り返りたいと思います。
- 道元禅師の言う「参禅」とは「坐禅」のことをさす。
- 「坐禅」はしずかな場所で行うこと
- 「坐禅」をする際は「腹六分目」が相応しい
- 「坐禅」中は感覚はそのままにしておく
- 「善悪」は時代によって変化し、「人」の価値観によって変化する。
- なので「善悪」とは時なり
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。夫れ参禅は静室(じょうしつ)宜しく、飲飡(おんさん)[飲食(おんじき)]節あり、諸縁を放捨し、万事を休息して、善悪(ぜんなく)を思はず、是非を管すること莫(なか)れ。心意識の運転を停(や)め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて、作仏を(と)図ること莫(なか)れ。豈に坐臥に拘(かか)はらんや。
思いに「ブレーキ」や「ストップ」をかけずにそのままにしておく
今回は、
という部分を読んで参ります。
冒頭の「停める」という字は「停止」の「停」という字です。
これには「ブレーキ」をかけることや、「ストップ」をかけるというようなイメージが湧くかと思います。
しかしここで言う「停める」というのはブレーキやストップをかける事ではなく、自然現象の在り方のままにするという意味で「停める」という言葉を用いているんですね。
頭の働きをストップする事ではなく、ありのままの姿に置く。
「おーい」と言えばとっさに返事をしてしまう。
あるいは意識せずとも鳥のさえずりが聞こえてくる。
そのような状態を「心意識の運転を停めた」と言うんですね。
我々は生きていると次から次に色々な思いが浮かんできます。
しかしそれは我々人間の頭のメカニズムとしては当たり前の状態であります。
自然の風景であり、命の躍動であります。
その自然の風景を止めたり、手を付けない、管理しない、そのままにしておく。
そのままにしておけば思いが次から次に湧いて出たとしても自然と消えてしまうんですね。
ほったらかしにすれば、いつの間にかどこかへ行ってしまう。
しかし我々はそこを注意しないと、その自然に湧いた思いを「相手」にしてしまうんですね。
浮かんできた「思い」をまともに受けてしまうというか。
独り相撲をとってしまうんです。
「アイツが俺の事を悪く言った!」などと言って、自然に湧いた思いのあとをどんどん追いかけてしまう。
こうした「概念」と独り相撲しないというのが、「心意識の運転を停め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて、」ということであります。
生命の実物のしっぱなし
繰り返しになりますが、「心の動き」というのは私がやっている訳ではないんですね。
自然に湧き上がってくるものです。
この次から次に浮かんでくる思いは、「大自然の姿」そのものであります。
どんな下卑たる、破廉恥な事が浮かんできたとしてもそれが自然の風景なのです。
それに人間の手を施してはいけない。
その「思いを」我々の思いで管理してはいけないんです。
ほったらかしにしておくんです。
生きている事実はそのままにしておく。
生きている事実を行じていく。それが「坐禅」です。
ですから「坐禅」は「大自然の行」であり、あるいは「身心脱落」であり、「悟りの姿」なのです。
決して「悟り」というのものは「心境」の話ではないんですね。
「生命の事実を行じていること」
それが道元禅師が言われる「悟り」であります。
今回の話の「心意識の運転を停め、念想観の測量を止め」というのは「ブレーキ」をかけることでも「ストップ」をかける事でもありません。
今湧き上がる思いに「ブレーキ」もしくは「ストップ」をかけるというのは、「思いを管理する」ということです。
そういった「管理」を一切手放す。
「生命の実物」のしっぱなし。
それが我々人間の目指す「悟り」であり、道元禅師のおすすめになる「坐禅」なのです。
だからこそ「坐禅」をする際はこの「心意識の運転を止め、念想観の測量を停める」という事を心掛けてくださいよ、とおっしゃるわけです。
これは「坐禅」における基礎的な心構えとなり、そのことについて道元禅師が説いてくださっているのです。
勝負するからには勝ちなさい。

余談をここで少しさせてもらえればと思います。
「仏教」では、生きとし生けるすべての命が、平等の価値であることを説いております。
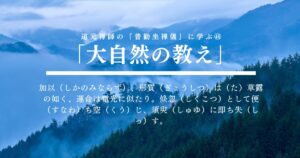
仏教というのはこの世界の事実を説くものですが、そこでいうと今の話はこの世界の事実そのものだからです。
例えば会社において、私と社長。私と部長。両者には大きな違いがあります。会社により貢献できるのは決して私ではありません。給料も多くもらっていて日本の経済に貢献しているのも確実に私ではなく、社長や部長です。
しかし社会においてはそうかもしれませんが、基礎生命の地盤、いわゆるこの世界の事実という観点から言えば両者に違いはありません。
双方が今坐禅を組む。するとどちらも足が痛くなる。私より部長の足の痛みの方が柔らかい。あるいは厳しい。そんな違いは決して生まれません。痛いものは痛い。その痛みは決して比較ができないのです。
あるいは双方こうして生きているうちは、呼吸をします。部長の方が呼吸が上手い、あるいは社長の方が上手いなんてことはありません。
双方、排泄や屁も必ず自分で行わなければなりません。社長だからといってその屁を別の誰かがこいてくれるわけではないのです。
生命の地盤、生命の事実という観点からすると、双方に決して優劣がないということがわかるわけです。
もしかしたら普段美味しいものを食べたり、アルコールを摂取している社長や部長の屁のほうが多少臭いかもしれない。
しかし屁を自分でこくという生命の地盤は変わらない。命の価値は変わらない。
これが事実であり、このような事実を説くのが仏教です。人類は皆平等だと言えるのはこうした理由があるからなんです。
しかしそれは小学校の徒競走のように、みんな手を繋いで一斉にゴールインするというような事を説いている訳ではありません。
例えば社会においては、サラリーマンは営業成績によって順番が付けられていく。
これは今のべた我々一人ひとりの本来の存在意義に反しています。
しかしこれも非常に大切な事でありましょう。
社会においてはそうしたノルマを課さないと、会社は倒産してしまいますからね。そうなるとお金を稼ぐことができない。生きていくことができなくなります。
それに成績があがれば評価もあがり、自分の立場や地位も保障される。
ですから誰もが他人を虐げてまで勝負に勝とうとするのです。
これは私があるお寺の友人の所で、ソフトボールをやっていた時の話です。
「坐禅」の余暇に戯れとしてソフトボールをやったら、その友人の師匠である老師に非常に怒られた事がありました。
その老師は、
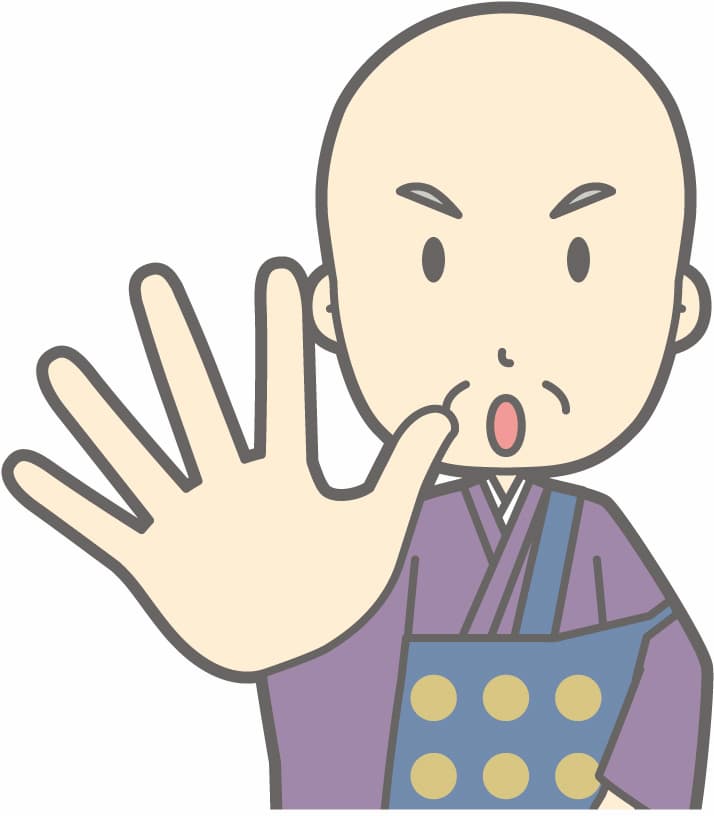
真剣にやりなさい。やるからには勝ちなさい。
と言うわけですね。
なんで修行をこれまで長く積んだ老師ともあろうお方が、小さい行事にも関わらずそこまで勝つことにこだわるのかなという思いがその時してしまったのです。
冒頭でも述べましたが、我々人間の命というものは一人一人平等で、尊いものである。
それは当然の事です。決まっていることなんです。
しかしある営業マンであれば、売り上げが高ければその分会社から評価される。
或いは塾講師においては、沢山の子供達を一流高校、一流大学に入れたその比率によって保護者から評価される。
そのように社会においては人間同士で評価を付け合う事は当然必要であります。
何故なら我々は仏様に平等に生かされている「仏」であるのと同時に、人間社会においては「塾講師」でもあるわけで、「サラリーマン」でもあるわけだからです。
ビジネスマンとしての、研究者としての、或いは親としての、学校の先生としての。社会に生き、そこでのレッテルがさまざまにあるわけです。
その社会性や、社会のレッテルというのも、本来仏である我々によって生み出されたもので、そこでは仏という事象に含まれるわけですね。
ある種ゲームのようなものです。この社会というのは。
仮にそれが本来の世界とは関わりのない概念であっても、そこで生きる我々は仏そのものなのです。ですからそのようなゲームや世迷言も大切にするべきなのです。
もちろん大元には我々一人一人「仏」という絶対的な事実があります。辛かったらそこに帰って来ればいいのです。
しかし我々人間はそうした「人間の大元にある尊厳」というものを、「人間社会における成績」によって考えてしまう。
所詮は概念にしか過ぎない「肩書」を、人の命の尊厳に混合させてしまうのです。ゲームを実際の世界のように捉えてしまうんですね。



あの人に営業成績で負けた、テストの点数で負けた、俺はもうだめだ、生きる価値無しだ。
そのように混同してしまうんですね。
これは過ちの考え方であるし、実にもったいない事です。
なぜなら「命の尊厳」はそのような「概念」とはまったく無関係だからです。
「命は平等」だと教わりながらがらも、その大切さをまったく理解できていない方が非常に多いんですね。
「概念」の延長に「命」を考えてしまう方が本当に多いんです。
概念は概念として遊んだらいい。演じたらいい。人生に遊びはなくても生きていけますが、せっかくならあった方がいい。
それにどんなに社会にけなされようと、大元には決して揺るがない尊厳がある。
そこをきちんと切り離して考える事ができれば、いくら他人と比較したり競争で負けるようなことがあってもいつでも笑っていられるはずです。
当時、老師は「ソフトボールやる時には真剣にやれ。そしてやる以上は勝ちなさい」と言われました。
その時は分からなかったですが、今思えば人間社会におけるそれはマナーのようなもので、勝負をするからには勝つこと。こういったことを伝えたかったんだと思います。
我々はせっかくこうした概念遊びをさせてもらっている。社会に椅子を用意してもらっている。ならばその「概念遊び」をとことん楽しめばいいのです。
思いに「ブレーキ」や「ストップ」をかけずにそのままにしておく ーまとめー
すみません。
記事後半は余談となってしまいました。
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の
という部分を解説しました。
それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。
- 「停める」というのは思いに「ブレーキ」を掛ける事でもなく「ストップ」を掛ける事でもない。
- 「ブレーキ」や「ストップ」をかけることは「思い」を管理している
- 「思い」は生命の実物。
- ただしい「思い」の管理はそのままにしておくこと
- 「概念」は人間だけに通じる遊び
以上お読みいただきありがとうございました。

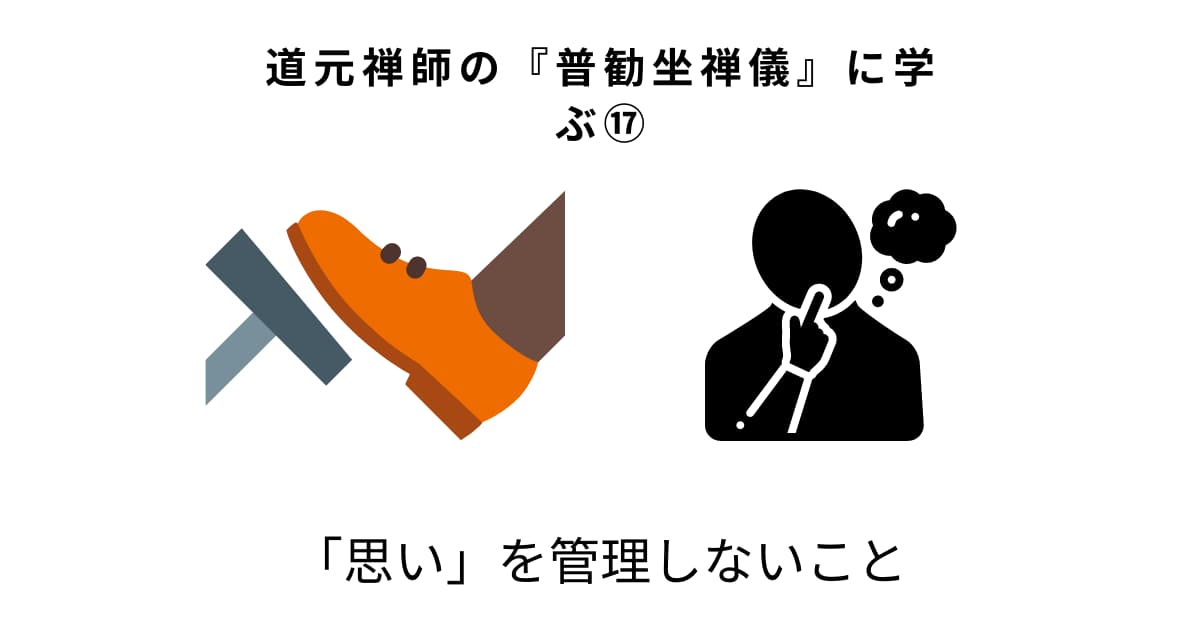
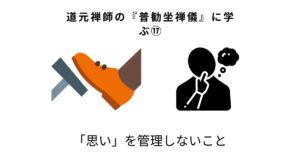
コメント