本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
それではまず初めに前回の、
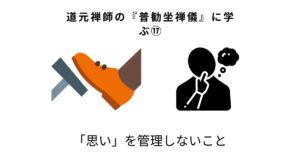
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「停める」というのは思いに「ブレーキ」を掛ける事でもなく「ストップ」を掛ける事でもない。
- 「ブレーキ」や「ストップ」をかけることは「思い」を管理している
- 「思い」は生命の実物。
- ただしい「思い」の管理はそのままにしておくこと
- 「概念」は人間だけに通じる遊び
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

所以(ゆえ)に須(すべか)らく言(こと)を尋ね語を逐ふの解行(げぎょう)を休すべし。須らく囘光返照(えこうへんしょう)の退歩を学すべし。身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目(めんもく)現前(げんぜん)せん。恁麼(いんも)の事(じ)を得んと欲せば、急に恁麼の事(じ)を務(つと)めよ。夫れ参禅は静室(じょうしつ)宜しく、飲飡(おんさん)[飲食(おんじき)]節あり、諸縁を放捨し、万事を休息して、善悪(ぜんなく)を思はず、是非を管すること莫(なか)れ。心意識の運転を停(や)め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて、作仏を(と)図ること莫(なか)れ。豈に坐臥に拘(かか)はらんや。尋常(よのつね)、坐処には厚く坐物(ざもつ)を(と)敷き、上に蒲団を用ふ。或(あるい)は結跏趺坐、或は半跏趺坐。謂はく、結跏趺坐は、先づ右の足を以て左の腿(もも)の上に安じ、左の足を右の腿(もも)の上に安ず。半跏趺坐は、但(ただ)左の足を以て右の腿(もも)を圧(お)すなり。寛(ゆる)く衣帯(えたい)を繋(か)けて、斉整(せいせい)ならしむべし。次に、右の手を左の足の上に安(あん)じ、左の掌(たなごころ)を右の掌の上に安ず。兩(りょう)の大拇指(だいぼし)、面(むか)ひて相(あい)拄(さそ)ふ。乃(すなわ)ち、正身端坐(しょうしんたんざ)して、左に側(そばだ)ち右に傾き、前に躬(くぐま)り後(しりえ)に仰ぐことを得ざれ。耳と肩と対し、鼻と臍(ほぞ)と対せしめんことを要す。舌、上の腭(あぎと)に掛けて、脣歯(しんし)相(あい)著け、目は須らく常に開くべし。鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。
「仏」になろうと思って「坐禅」をするということは、自我の延長でしかない
今回はこの部分を解説していきたいと思います。
まず初めの、「作仏を(と)図ること莫(なか)れ、」という部分。
これに関してはとある昔の「エピソード」があるので、今回はその「エピソード」を交えながらご紹介したいと思います。
昔、「馬祖道一(ばそどういつ)禅師」という人と、そのお師匠さんに当たる「南嶽懐譲(なんがくえじょう)禅師」という二人の有名な禅師様がおりました。
弟子にあたるこの馬祖道一という方は、非常に修行熱心だったと言われております。
いつでも一人で静かに「坐禅」をされておったんですね。
そんなある時、師匠の南嶽懐譲が熱心に坐禅をしている馬祖道一の元へ訪ねてきます。
「本当に間違いない仏法の坐禅をしているのか」、或いはそうではない「間違った人間的な坐禅をしているのか」という事が非常に心配になり弟子の馬祖道一の元へ訪ねるんですね。
そして次のように聞きます。
 南嶽懐譲
南嶽懐譲お前は何の為に坐禅をしているのかね?
すると弟子の馬祖道一が、
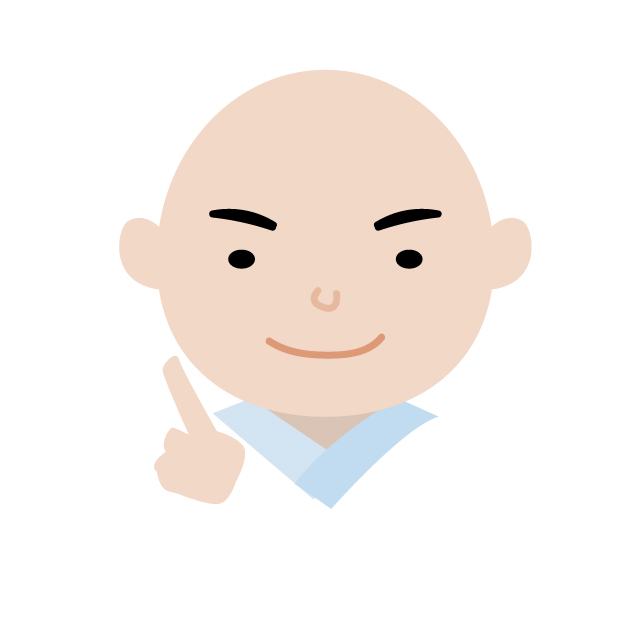
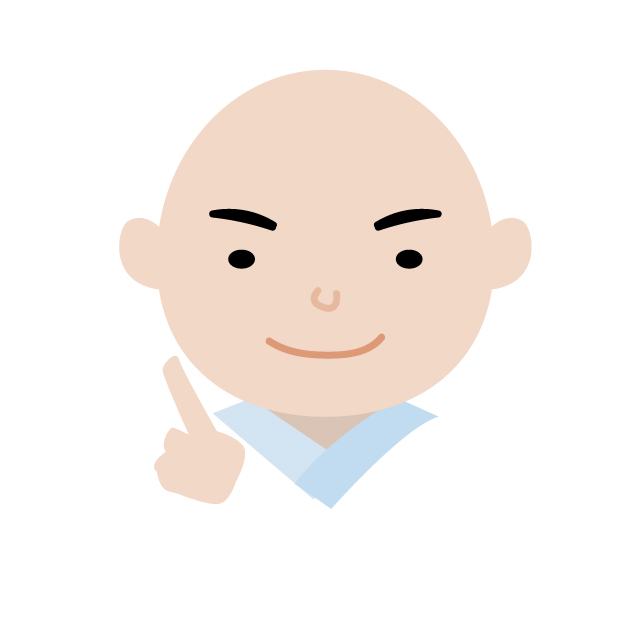
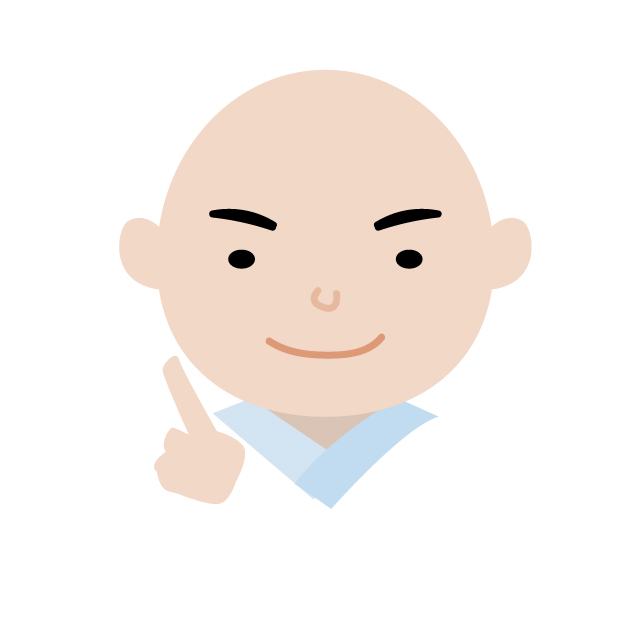
はい、お師匠様!私は「仏になる為に」坐禅をしています。
という風にお答えになるのです。
師匠の南嶽懐譲は、



あぁやはり思った通りだったな。
と考え、馬祖道一が一生懸命「坐禅」をしている脇で、一枚の素焼きの「瓦」を取り出して磨き始めるのです。
昔は今のような「ガラス鏡」ではなく、「銅鏡」と言う銅の鏡しかありませんでした。
昔の人は「銅」を一生懸命磨いて「鏡」にしていたんですね。
仮にこの時南嶽懐譲が磨いていたのが「銅」であれば鏡になりましょうが、素焼きの「瓦」をいくら磨いても人の形をきれいに映しだすような鏡になんかなるはずがないのです。
それなのに何故、南嶽懐譲は「瓦」を磨くのでしょうか?
弟子の馬祖道一もそこに疑問を感じ、
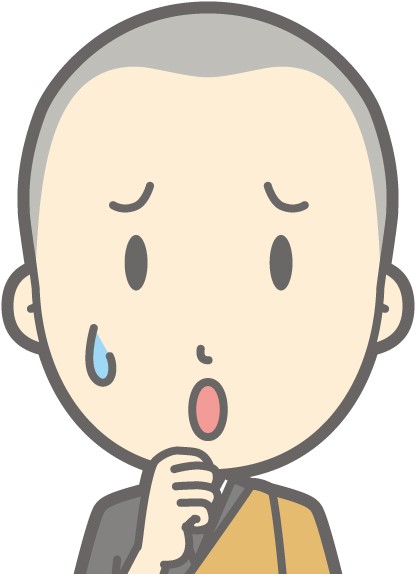
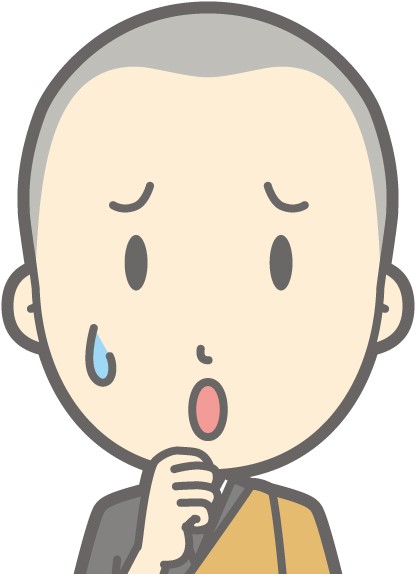
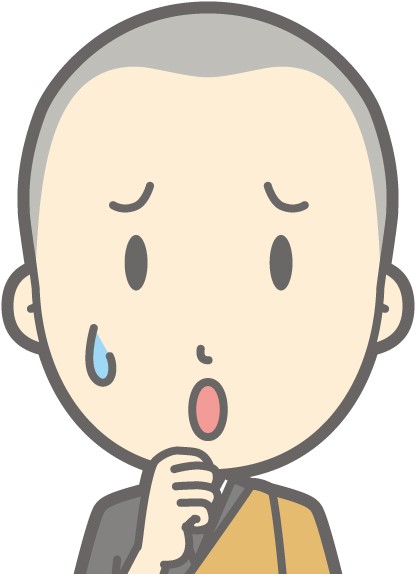
お師匠様は一体何をなさっているのですか?
という風に質問しました。
するとお師匠様の南嶽懐譲が、



そうか。今私はな、この「瓦」を磨いて「鏡」にしようと思っているんだ。
という風に答えました。
そして弟子の馬祖道一は、
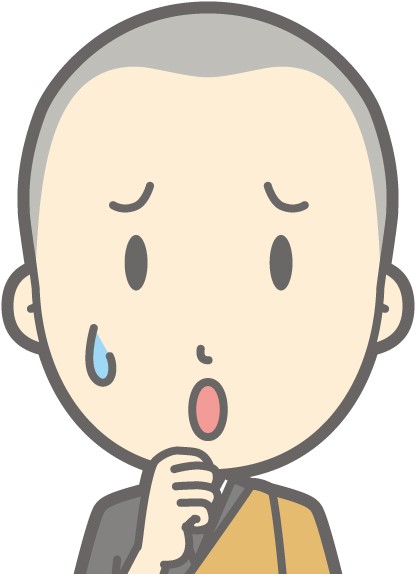
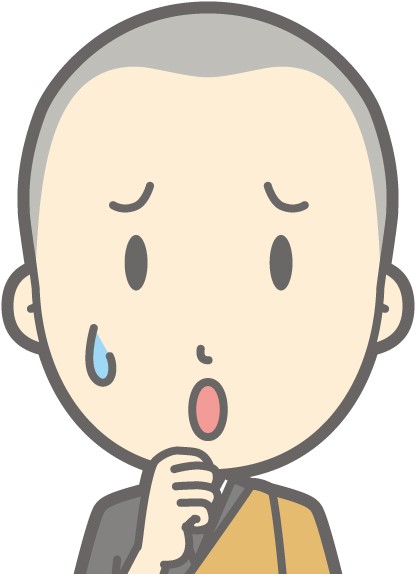
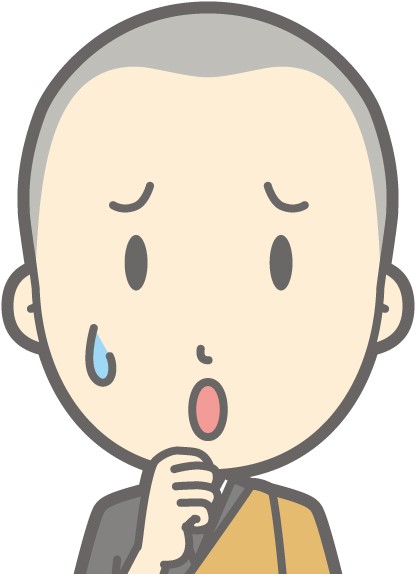
お師匠様、いくら「瓦」を磨いたところで決して「鏡」になんかなりませんよ。
と答えます。
するとすかさず、お師匠さんの南嶽懐譲は



そうか。それじゃ私も言わせてもらうが、いくら「坐禅」をしたところで決して「仏」になどなれはせんよ。
そう言うのです。
このようなやりとりがあったとされているんですね。
それが今回の、 「作仏を(と)図ること莫(なか)れ。」という部分に由来しているのです。
「仏になろう」と思う事自体が、大自然からかけ離れた人間の思惑
我々は生きているといつも頭の中で物事を判断し、相対的にものを見ております。概念で物事を見ようとするんです。
そうなると本来2つに分かれない物事を2つに分けてしまうことにつながります。我々は本来の世界に生きているにも関わらず、このような生き方をしているとその本来のあり方と逸れていってしまうんです。
例えば今回の馬祖道一のように「何か(仏)」を得たいと思い「何か(坐禅)」をする、という風に。
しかし、本来の大自然にはそのような人間の思惑は一切通用しませんよね。
なので今回で言えば、
「瓦を磨く」という事、その事自体が、「仏行」である
ということを師匠の南嶽懐譲禅師は言いたかったのです。
つまり「坐禅」をすること自体が「仏行」であるという事を弟子の馬祖道一に言いたかったのです。
この馬祖道一禅師と同じように、今日の我々の生活においてよく知られている坐禅も、
坐禅という「行為」自体が「仏行」であるにもかかわらず、「仏」になるための「手段」としてその「行為」を用いる。
ということをしてしまいます。
本来二つとして分かれない、評価の付けられないこの世界。その世界そのものである「仏行」を人間の思惑で判断し、自己満足(悟り)の材料にしてしまうのです。
この公案で言えば、馬祖道一禅師は「坐禅」をして「仏」になろうとした。
つまり、物事を「手段」と「目的」という二つにわけてしまった。
しかし本来の大自然においてはそのような分け方はできません。「手段」だの「目的」だのという区別はできないのです。
ここからここまでは俺の命。ここからここまでがあなたの命。という線引きが一切ない世界なんですね。平然とカラスの鳴き声が自分の耳を震わせる。夜自分が寝ている間にもどこからかやってきた酸素によって無限に呼吸が行われる。
このような世界であるわけです。


大自然そのものを行じているのがこの「坐禅」です。坐禅が「大自然」なのです。
なので決して手段だとか、悟りだとかという型に収めることはできないんですね。
もちろん、普通の人間からすれば「何のご利益もない坐禅」をただひたすらに行じることなど馬鹿馬鹿しくてとてもやっていられないでしょう。
「何が仏行だ、実にくだらないし、時間の無駄だ!」と思われるかもしれない。
しかし仮にそんな風に思ったとしても、世界というのはそのように味気なく動き続けています。
私自身も事実、そのような世界にいきております。
でも逆に言えばそれがすごいことなんですね。こうして平然と生きることができている。平然と呼吸をし、平然と食べたものを消化する。食っても食ってもまた腹が減り、そして生きることができる。そんなとんでもないことも誰もが必ずやってのける。
これ以上に何があるでしょう。これが事実としてあって、我々はこうして生きることができる。そこでさまざまな思いをさせてもらったり、経験をすることができる。こんなにも恵まれた人生をいただいている。
大元としてそこには人の価値観など一切通用しない命があるわけです。
本来人間の思惑が一切通用しない命を生きているんです。
今回の「エピソード」に戻すと、「鏡を磨くこと」、その行為自体が非常に尊いというわけですね。
どんなにくだらないと思っても、それが成仏であり、仏行なのです。この世の全ては大自然のみで、そこでは常にむき出しの真実が展開しております。鏡もそう。鏡を磨く自分もそう。仏いっぱい。真実いっぱいです。
「坐禅」も同じです。この大自然そのものです。
坐禅をし続けていけば段々と「仏」になっていくという話ではなく、「坐禅」そのものが「悟り」であるとい言いたいのです。
「坐禅」がそのままで「仏行」であるということを言いたいわけなんです。
ですから今回の「作仏を(と)図ること莫(なか)れ。」というのは、そのような内容に因んで、道元禅師が我々に、
「仏」になろうと思って「坐禅」をしないでください。
ということをおっしゃりたいのです。
「仏になろう」と思う事自体が、大自然からかけ離れた人間の思惑であり、大自然の「坐禅」に垢を付けるようなもの。
そのような心配を道元禅師がされた一文となります。
「坐禅」は日常生活の延長ではない
それでは続いての、「 豈に坐臥に拘(かか)はらんや。」という部分。
この「坐臥(ざが)」というのは行住坐臥、のことを言っており、我々の日常生活のことを指しております。
つまりこれは、
- 行ったり(行)
- 留まったり(住)
- 坐ったり(坐)
- 寝たり(臥)
という四つの生活姿勢のことをいっているのですが、「 豈に坐臥に拘(かか)はらんや。」とは、その四威儀に「拘(かかわら)ない」という意味です。
今述べた生活姿勢の中に「坐ったり(坐)」というものがあります。
普段我々が行う「坐る」という行為はほぼ無意識で行われており、自分の好きな時に自分のやりたいよう坐ります。
しかしここでいうのは、「坐禅」は日常生活の延長ではないということです。
つまり、
坐りたいときに坐るなど日常生活の延長のような「坐禅」と、道元禅師がおすすめになる「坐禅」とでは全く違うという事ですね。
坐禅を人間の生活の一部として行ってはならないということです。
例えばこの坐禅を日常生活の延長のように考えてしまうと、テレビを見て酒を飲みながら「坐禅」を行う人間もでてくるでしょう。
そういう日常生活を延長とした「坐禅」と道元禅師がおすすめになる「坐禅」はまったく違うという事ですね。
つまり日常生活を延長とした「坐禅」というのは、自我を中心とした「坐禅」でもあるからです。
それはただ勝手気ままに行う「行住坐臥」と変わりません。坐禅を悟りを得る手段として捉えてしまう方法と変わりません。
それはあくまでも人間の好き勝手な行為であり、大自然そのものである本来の坐禅とはまったく関係のないものになってしまうのです。
さきほども言いましたようにこの「坐禅」は「仏行」であります。
「坐禅」そのものが「悟り」であり、「坐禅」を行じることで「悟ることができる」という事ではありません。
人間の日常生活の延長としてではなく、大自然の行いとしてこの「坐禅」を行う。
過去の祖師方もそれこそ命がけでこの「悟り」を得てきました。
- 洞山良价禅師は川を渡って悟った。
- 臨済義玄禅師は黄檗禅師に顔を叩かれて悟った。
- 香厳智閑禅師は竹に石が当たった音を聞いて悟った
- 天竜禅師は指を一本食べられて悟った
このようにそれぞれの契機をもってして「悟り」を得られてきました。
これは前述を裏切るような内容になってしまいますが、坐禅をして悟りを得たんですね。
それではその得た「悟り」とは一体どういうものだったのか。
それはつまり「坐禅」が真実を行じているという事にみんな悟りを通して気付かれたのです。
「坐禅」こそが「真実」であり、「大自然の行い」ということに気付かれた訳ですね。
どうしてもここはこのように述べるほかありません。ご了承ください。
そのような実に尊い「坐禅」ですから、人間の思惑でしないでください。
或いは人間の日常生活の延長でしないでください。
というのが「 豈に坐臥に拘(かか)はらんや。」 ということなのです。
「仏」になろうと思って「坐禅」をするということは、自我の延長でしかないーまとめー
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の
という部分を解説しました。
それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。
- 「仏になろうと思って行う「坐禅」は自我の延長でしかない。
- 「坐禅」は日常生活の延長ではない
以上お読みいただきありがとうございました。

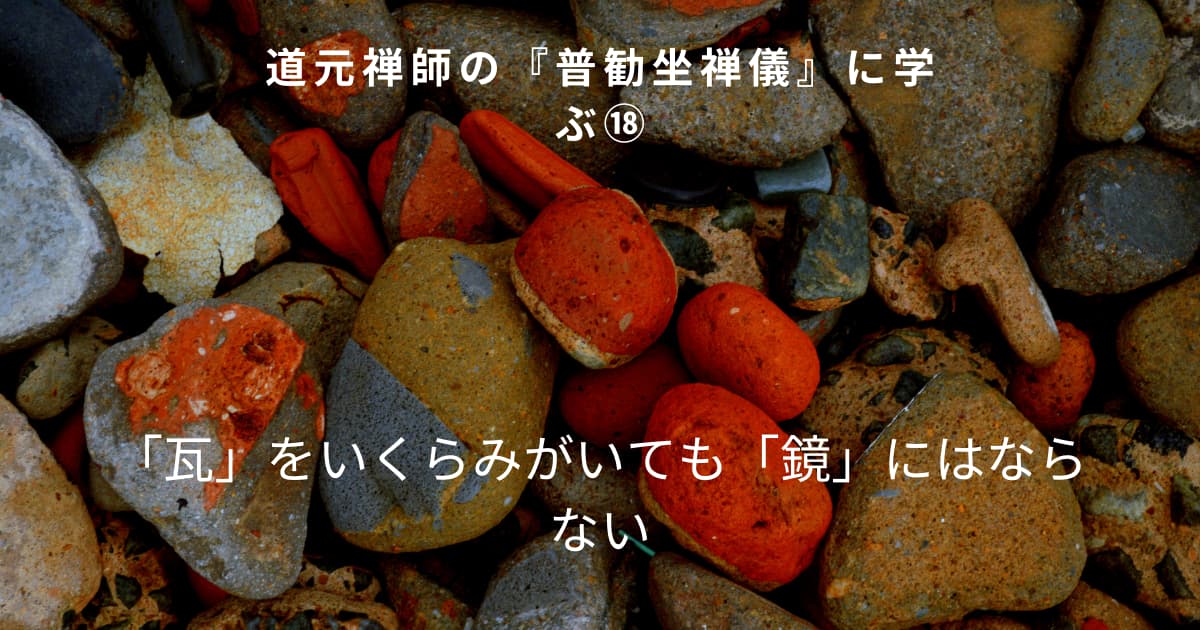
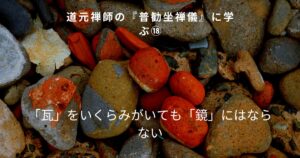
コメント