道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第⑮弾といたしまして、「一箇半箇(いっこはんこ)」についてお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
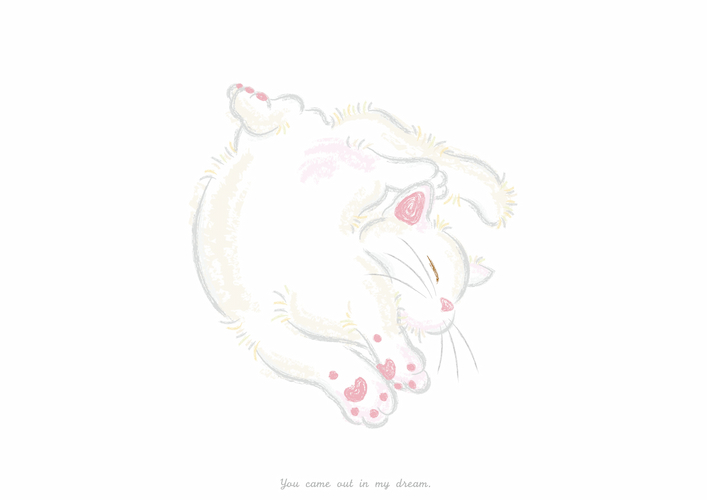
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

一箇半箇とは?
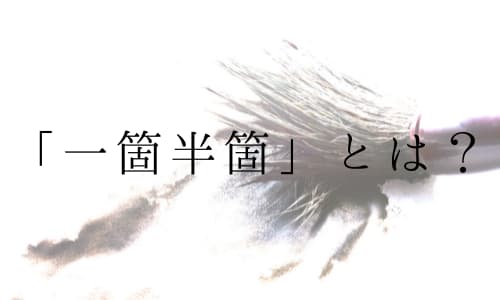
この「一箇半箇」とは、そのままの意味でとらえると「ひとつ」と「半分」ということですね。
これを普段の我々の状況における言葉に置き換えると「数のごく少ない人」という意味になります。
「三人」よりも「二人」。「二人」よりも「一人」という数の問題ではなく、極めて希有の人のことを指し、得難い人物のことを指します。
そしてそのような人材を育てることを、この「一個半箇の接得」といいます。
一箇半箇の人とは?
それではそうした「希有で得難い人」というのはどういった人のことを指すのでしょうか?
それが「仏法の人」ですね。
まず「仏法の人」は、「世間」にはいません。
「世間」から生み出されるものでもありませんし、ましてやそれは「知識」や「知恵」がある人のことでもありません。
だから「希有で得難い人」なんですね。
世間でいうところの「これをこうすればこれが生まれるといった」やり方では、この「一箇半箇の人」は作り出せないんです。
しかし例えば、世間で騒がれている人、人気な人、戦争を止めた英雄、○○会社の創業者など、世間にも立派な人は大勢います。
そうした「立派な人」も十分、「希有で得難い人」なのではないかと考えてしまう。
ところがそうではないんですね。
お釈迦様を始め、達磨様も、道元禅師もこの「仏法」に生涯をささげた人が、「一個半箇の人」と呼ばれる理由は「真実」をひたすら見つめてこられた経緯があります。
そして世間がどんな状況であっても、家族がどんな状況であっても、よそ見一つせず、この全宇宙における「真実」をただひたすら実践し、守って来られた経緯があるのです。
まさに「仏」に身をささげた人。これが「一箇半箇の人」だということです。
世間ではなく仏に身を捧げるんです。世間の兼ね合いを気にするのではなく、それは理にかなっているか、道理を追求する。自然を追求する。こうしたことに身を捧げてこられるわけですね。
簡単には育ちませんし、世間からは生まれない人だということです。
お釈迦様は家族を顧みず、出家をされ、真実の道を歩まれました。
そしてそのご生涯を「仏道」にささげ、いまにも続く「仏教」という宝を我々に残してくださいました。
その仏教を今度は達磨様が南インドから中国へとお運びになります。
少林寺で面壁九年の坐禅修行に励まれ、真実の仏法をお伝えになりました。
そして今度は慧可様が達磨様からその真実の仏法を受け継ぎます。
その際、慧可様は達磨様からこれを授かるために、自身の肘を断ち切ったとも言われております。
そのような凡人では計り知ることのできない覚悟を持って、この仏法と向き合ったわけです。
同じく道元禅師も幼い頃に、なぜ「真実」であり、また「仏」でもある我々一人一人なのに、修行をしなければいけないのか?という大きな疑問を抱え、中国へと渡ります。
そして如浄禅師と接見し、その疑問を解決されます。
そして過去の祖師方と同じく坐禅を通して、この真実を日本で布教していくわけですね。
いま申し上げた方々には、それぞれこのような背景があるんですね。
誰もができることではありません。
そこには自身の力ではどうする事もできない多くの因縁があり、またその因縁に対する因縁があり、それがあるべき方向へと向かっていったことで成されたのです。
自身でどうにかできない問題も絡んでいる。その上で果たされている。非常に希少である。
だからこのように「仏法」に生涯をささげた人のことを、「一箇半箇の人」と呼ぶのです。
あるいはこのような真実が受け継がれていくこと自体を「一箇半箇の接得」と言います。
とてもこの世のものとは思えないほど非常に稀な出来事、そこには当事者たちの努力もあり、その当事者たちの努力以外にも複雑な因縁が絡んだ上で成されているというのです。
その中身は非常に稀だということ。真似しようと思ってもできないということ。
師匠にもその器量があること。弟子にもその真実を授かるための器が備わっていること。さらにさまざまな因縁が絡んで、初めて仏法というのは伝授されていくわけです。
後に脈々と受け継がれていくわけです。
今こうして我々は道元禅師の教えに触れることができるわけですが、これはとてもありがたいことだというわけですね。
一箇半箇と道元禅師
いま述べてきたように「仏法の人」が「希有で得難い人」と言われる理由は、このような「一箇半箇の接得」が必要だからなんです。
道元禅師は、師匠である如浄禅師より次のように言われました。
城邑聚洛(じょうゆうじゅらく)に住することなかれ、国王大臣に近づくことなかれ、ただ深山幽谷に居りて一箇半箇を接得し、吾が宝として断絶せしむることなかれ。
どういうことか、恐れ多くも解説しますと、
「都や人の集まるところに住むのではなく、また権力者にも近づかず、山深いところに居て、真実の教えを継ぐものを育て、そんな彼らとの日々を宝とし、その日々を決して絶えさせてはならない」。
となります。
このことを如浄禅師より承っていた道元禅師は、京都から越前に移り、小さな「永平寺」を開いたと言われております。
以上お読みいただきありがとうございました。

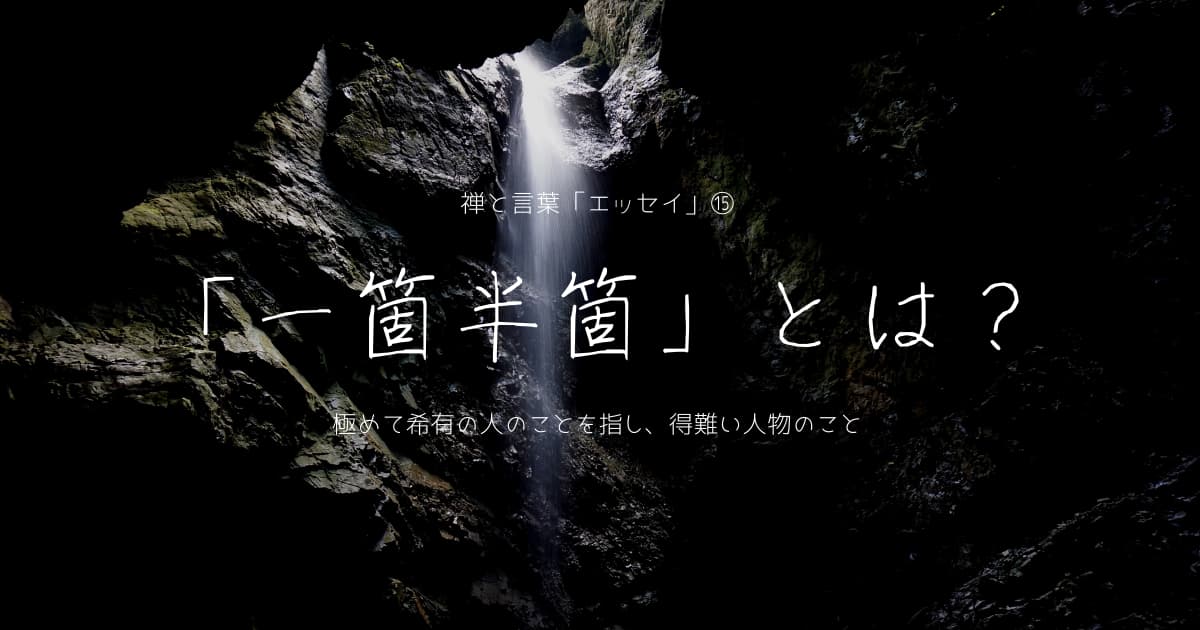


コメント