本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を読んでいきたいと思います。
まず 初めに前回の、
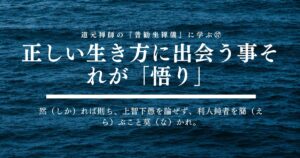
のポイントを振り返りたいと思います。
- 仏道修行(命)において能力があるとか、ないとか。頭が良いとか悪いとかは一切関係ない。
- 誰でも彼でも坐れるのが「坐禅(命)」であり、道元禅師のおすすめになる『普勧坐禅儀』である。
- 仏道修行(命)は、「志」によるから頭が良いとか悪いなどは「論ずる」までもない。
- 「正しい生き方に出会う事」それが「悟り」
- 「正しい生き方」というのは「命」の実践、「全体」の実践。つまり「坐禅」
- 「概念」は「命」の「一部分」でしかないのにそれだけに囚われているのが今の人間。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
本当の「救い」とは?

今回はこの部分の解説をしていきたいと思います。
それでは参りましょう。
体を使って物事を只管に行じていく事
まずは「専一に功夫せば、」という部分から参りましょう。
「専一」これは「専心一意」の略語ですね。
「物事を只管に行じていく事」を「専一に」と言います。
つまりよそ見をせず、一生懸命行じていく事を「専一」とか「只管」と言うんですね。
続いての「功夫せば」というのは何か?
我々には「概念」があります。そしてその概念によって物事を判断したり限定していく。これは人間の特性であり、それに従うことが我々の人間活動の特徴です。しかし本来の世界にはそうした人間の概念事は関与していないんですね。関与できないのです。概念というのは存在していないのです。差し出そうと思っても差し出すことはできません。
実際に存在していないもの。これが概念です。そしてそんな概念に常に主導権を握られている。それが我々人間です。
しかしそれではどうしても行き詰まる。どうしても救われない。真の「安心」は訪れない。
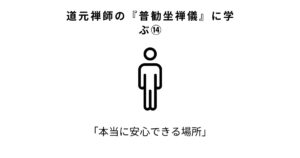
そこで今回の「功夫せば」という事。
これは「体を使って行じていく」という事ですね。この「体を使って行じる」というのが非常に重要であるという事です。
我々は物事を「概念化」してコミュニケーションを取ったり、自分の思いを伝えられたりします。またそれがお互いの共通理解となり、そこで両者が「納得する」という手段で他人とうまくやっている訳です。
とても便利です。他の動物たちにはこれができません。
しかしこれは先ほどもいったように物事の「事実」を見ているという事では無いんですね。
実際の物事とは別の世界を一度作り、その別の世界で話を進めていく。これが概念のやり取りです。またこれがいわゆる人間活動です。
要するにそれは存在していない世界なのです。
物事を概念化し他人とうまくやれるようになったとしても、それは実物の立場から見ると存在していないんですね。
我々の命とは?
ところで今の「先進医学」によっては、大学などで最初にやるのは「解剖学」だという風に言われております。
「人体」にメスを入れ、色々分析する訳です。
「あぁここに心臓があるなぁ」とか「ここにあるのが肝臓である」とか、「これが血管である」とか、「これが筋肉の細胞である」とか。
まぁそのような解剖学から入るらしいんですね。
確かにこれは人体の構造を知る上では非常に分かりやすいですよね。
実際に解剖をしながら「人体」の構造を見ていくわけですから、医学を学ぶ上でも理解しやすいのでしょう。
しかしこれが「本当の人間の命か?」と言われるとそうではないんですね。
例えば解剖した「心臓」や「肝臓」、「血管」、そのようなものが一つ一つ組み合わさって出来たのが人間の命という訳ではないのです。
ご飯粒の中には御仏様がござる
昔、大正時代に非常に「物を大切にする」あるおじいさんがいたんですね。
「全ての物には御仏様がござる。」というのがそのおじいさんの口癖で、「どのようなものも決して疎かにしてはいけないぞ」という事を盛んに言っていたんですね。
これはずっとそのおじいさんの家で代々伝わってきた教えなのでありましょう。
「物事には全て御仏様がござる。」と。「だから決しておろそかにしてはいかんぞ、」と。
そのような事を子供達にも孫にも言っておられたんですね。
例えば孫がご飯粒を床に落とすと、「決まってご飯粒の中には御仏様がござる!」と言ってかわいい孫にもうるさく注意をしていた。
まぁこのような素晴らしいじいさんがいた訳です、昔は。
その頃はというと「大正時代」でもありまして、小学校に初めて「顕微鏡」が導入された時代でもあったんですね。
「顕微鏡」というのはご存知の通り、物を拡大して見る道具です。
そのような訳であるので学校の先生に至っても、「この顕微鏡で覗いたらあらゆるものが見えるぞ、見たいものがあれば学校へ持ってこい」と得意げに言う。
「顕微鏡」で見たらなんでも見えるぞと。
そのように学校の先生に言われたものですからいつもおじいさんからご飯粒の中に御仏様がござる、という風に聞かされておったその子供が、手を挙げるんですね。
そして次のように言う訳です。
「先生!おらのじいさんはご飯粒の中に御仏様がござるといつもおらに言うんだ!それって本当なの?」
そのように言われた先生はご飯粒を見るまでもなく、即座に次のように答える訳ですね。
「何を言っているんだ!ご飯粒の中に御仏なんかおるものか!ご飯粒は炭水化物と水から出来ているんだぞ!帰ったらそのようにおじいちゃんにちゃんとおしえてやりなさい。」
まぁ当然の事ですね。
事実、ご飯粒というのは「炭水化物」と「水」から出来ております。
なのでこの先生は一つも間違ったことは言っておりません。
そのようなことで早速、その子が家に帰っておじいちゃんに言うんですね。
先生から言われた通りに言います。
「おじいちゃん、ご飯粒の中に御仏なんかおらんぞ!!ごはん粒ってのは、炭水化物と水から出来ているんだ!」
それを聞いたおじいちゃんはですね、お仏壇の前で肩を震わせて泣いたといいます。
まぁそういうエピソードが残っております。
さてそれでは何故このじいさんは泣いたのでしょうか?
当時のその男の子には分からなかったんでしょうね。
しかし、大人になって初めて気づいたんですね、その男の子は。
じいさんが言った「ご飯粒の中には御仏様がござる。」というのは決して嘘じゃなったという事に。
どういうことでしょうか?
先ほどの人間の「命」の話もそうですが、我々は物事を概念化して分析をします。
ご飯粒は「炭水化物」と「水」で出来ていると。
これはこれで間違いない話でもありますが。それは概念です。
しかし仮に「炭水化物」と「水」をいくらごちゃごちゃごちゃごちゃ混ぜたとしてもあの美味しいご飯は出来ないですよね?
我々人間は頭の中では概念化して説明したり分析したり出来るけどそれを「作り出す」までは出来ない。
お米を作るには様々なエネルギーが必要で、太陽の恵みや、そこに携わる多くの人のお協力があって作られるものです。
お米は「炭水化物」と「水」でできている。あるいは今述べたことも物事をわかりやすいように説明するために幾万通りにも及ぶ、過程を切り分けたものです。またその一つずつに関しても複数の作用が絡んでいる。
お米を作るというのはとてもても複雑なことなのです。どれひとつとっても人間が実際に関わっていることはないんですね。
説明は確かにつくかもしれないけれど、大自然が絡み合って、それは生まれているのです。
概念はあくまでも後付けなんです。単なる説明で、「名前を付けているだけ」なんですね。
お米は「炭水化物」と「水」でできている。確かにそうなのかもしれないけれど、それがいかに凄いことかということです。
頭の良い我々はいずれ呼吸のメカニズムも消化のメカニズムも、排泄のメカニズムも正確に捉えられるようになることでしょう。
しかしその呼吸を作り出すことはできない。あるいは止めることはできないわけです。それが正確にわかったところで、何も変化が生まれない。その「結果」に対して説明を加えている。
我々がやっているのはこれだけなんです。概念というのは直接的には一歳関わっていないんですね。概念は物事とは一歳関わりを持っていないのです。
言葉遊びをしているだけなんです。なので概念というのは真実と関わり合いがあるようでないとはこのことなんですね。
まぁ概念があれば組み立てる事は出来るかもしれませんね。
例えば「車」を組み立てたり、「テレビ」を組み立てるという事は出来るかもしれない。
しかしお蚕さんのように口から糸を出すことは出来ないわけだし、お米の苗を植え、収穫できるとしてもそもそもを作りだすことはできない。
要するに概念でもってして偉そうなことを大層並べ挙げたとしても、それは単に名前を付けているのに過ぎないのです。
「炭水化物」であろうと「水」であろうと、なんであろうと、そこには人間の説明が決して関与できない、大自然の、この世界の恵みが息づいている。
その事をこのじいさんは「ご飯粒の中に御仏様がござる。」という風に言われたわけなんですね。あるいは先の先進医学の学びの場の話においても同じです。
それにも関わらず我々人間と言うのは、「な~んだ、米なんてただの炭水化物と水で出来ているだけじゃないか!」とその尊厳や偉大さを軽視します。
これはとても危険なことです。
桜の花は何もないところから綺麗に咲きほこる
とんちで有名な一休禅師おります。
その一休禅師は綺麗なソメイヨシノの桜の花が咲いた時、何故こんなきれいな花が咲くのか?という事をいつも疑問に思っていたといいます。
そしてつぎのような詩を残します。
 一休禅師
一休禅師年ごとに咲くやよしのの山桜。木を割りて見よ花のありかを。
この詩は「桜の木を切って、あのように綺麗な花を咲かせる花のありかは一体どこにあるのか探してみよう。」という事をうたっているのです。
木を切って花の元はどこにあるのかを探ろうというんですね。
しかし桜の木を切ったところで、花の元なんかどこにもありはしません。どこを切ってもそんなものは出てきません。
今のお米の話ではないですが「桜の花なんざ春になれば必ず咲くものだ」と高をくくってしまう。あるいは桜の木の「どこかしらに」桜の花の元があるのではないかと思ってしまうのが我々人間なんですね。
しかし桜の木の元から桜の花など見つからないし、物の命も見つからないんですね。桜の花が「何もないところ」から咲き、あのように綺麗に咲き誇るのには理由などありません。
人間の理論や概念が一切通じない「命」が現に芽生えているのです。
「なにもない」というと語弊があるかもしれません。
恐らく「花」を咲かせる養分が木々の枝枝に流れているのがきっかけなのでしょう。
しかし何故そもそもそのような養分が「桜の木」に流れているのかわからないし、流れ続けるのか説明もつきません。仮に説明がついたところでその命を止めることはできません。そしてあのような綺麗な花を咲かせる。
物事というのは全てそのようなあり方なんです。この世の全ての物事は。人間の概念が通用しないんですね。説明がつかない「何か」によって作られているのです。
こと自分に関してもそうです。肌をつねれば痛い。足を組めば痛い。なぜ痛いのですか?人はつねるから痛いんだ!と言うかもしれません。しかしなぜつねれば痛いのでしょうか?
誰が決めたのでしょうか。
当たり前のように思われることも、決して当たり前ではないんですね。
そこには得体の知れない何かが息づいている。しかし同時に事実でもあり、何かはわからないけれど、確実にこの世界の正体がそこにはある、息づいているということなんです。
この自己が仏、この自己がこの世界の正体、悟りだということです。


なので道元禅師はこの自己に親しんでくださいと言われるわけですね。そこにこの世界の全てが詰まっているからです。その足の痛みに。
生命の真実は人間が「分析」して捉えられるものではない
しかしそうは言っても人間は「我々は一体何者なのか?」、「坐禅をする意味は一体何なのか?」、「こんなくだらない事に四十分も拘束され痛い思いまでして坐る意味とは一体何なのか?」
このように色々思案するわけです。
色々こう頭の中で考え、分析をする。
人間の頭で考えれば本当にくだらないですよね、たとえばこの「坐禅」というのは。
人生においてなんの足しにもならない。
しかしそれでいいんです。それが正しいわけです。くだらないのがいいんです。人間生活の足しにならないのがいい。
この「坐禅」は人間生活の延長ではありません。人間生活の足しになってしまったらそれは「坐禅」ではない。
「坐禅」をして「給料がUPした!」とかですね、「女の子にもてるようになった!」など、そんなことには絶対ならないんです。
「坐禅」はそんな「人間の損得感情」とは一切関係ありません。
繰り返しになりますが「坐禅」は「大自然の在り方そのもの」であり「仏行」なんですね。
坐禅こそが人間の概念から離れたこの世界の正体なのです。
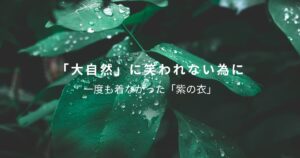
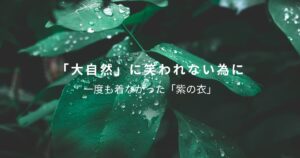
しかしそんな「真実の実践」でもある「坐禅」を行じているのに、色々と思案をし始める。それが人間です。
「坐禅とは一体何なんだ?」「何の意味があるんだ?」そんなことばかり考えているんです。
繰り返しになりますが「お米は炭水化物と水で出来ているんだ!」とそのようなことが分かったとしても、その頭で考えた答えは「生命の真実」とは関係がないということですね。
逆に我々が物事を概念化して「分析」することによって「生命の真の姿」、「我々が今ここに生きている生命の実物」というのはどんどん失われてしまうんです。
この世で確かなことは、お米です。この坐禅です。この足の痛みです。説明など要りません。そこにこの世界の全てが詰まっているのです。
それをああだこうだ、説明するのはもうやめようということですね。それは結局は人間だけに通用する話で、実際の物事とは関係のないものだからということです。
今回の内容でもある、「専一に功夫せば、」において「功夫」というのは頭の中で考えて、ああだこうだと分析したり考えたりする事をやめることを言います。
そしてただひたすらに「この世界の真実(実物)を行じる事」を「専一に功夫せば」と言うのです。
本当の救いとは「大自然の在り方」を行じること
頭で考える事をやめ、生命の実物を行じていく。それを「専一に功夫せば、」といいます。
そしてその頭で考える事をやめ、生命の実物を行じていくことを「正に是れ弁道なり。」というんですね。



まさにこれが正しい道で、私が訴えたい「只管打坐」ですよ。
と道元禅師が言われる訳なんです。
我々の行じているこの「坐禅」は真実(生命)の実物であります。この世界の正体がそこには詰まっているわけです。
坐禅がそのままお悟りなのです。だから坐禅を行ってください。ということです。
道元禅師の記した名著『正法眼蔵』、『生死』の巻に次のような言葉が出てきます。
ただわが身をも心をも、はなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなわれて、これにしたがひもてゆくときちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ仏となる。たれの人か、こころにとどこほるべき。
「ただ我が身をも心をも放ち忘れ」とありますが、これは「全て」を放棄する事を言うんですね。
頭で「こうでもない、ああでもない」という「考え」そのものを投げ出してしまう。
「自我」を放棄するとも言えるでしょう。
「俺こそ!」とか「ワタクシガ!」といった「自我」があると、物事を二つに分けるようになってしまうんですね。
「俺が考える。」とか「ワタクシのもの」とか。
本来この世の全てが「一つ」に繋がっております。
「一つ」の仏の命です。
例えば「壁を殴ると痛い」ですね。
「椅子の角」に指をぶつけると物凄く痛いでしょう?
何を食べても際限なくこの身体が消化してくれるのもそう。
木々が作ってくれている「酸素」を吸って呼吸ができているのもそう。
カラスの声が耳に入ってくるのもそう。
自動車の排気ガスが臭いと感じるのもそう。
この世の全ては「一つ」なんですね。この俺という命に際限や境界線はないのです。
これが真実です。
もしこれが「一つ」でなければ「壁」を殴ったところで痛くも痒くもないでしょうし、カボチャは消化するけどピーマンは消化しないということもあり得るのかもしれません。
しかし実際はそんなことはあり得ない。
誰しもが壁を殴れば痛いし、誰が食べても同じようにこの体は消化をするし、呼吸もするでしょう。
そのように本来は「一つ」に繋がった世界で、これが「二つ」に分かれるはずがないのです。
つまり「俺の考え」とか「ワタクシの物」なんて考えを起こすのは「妄想」でしかないんですね。
そのような考えは「真実」とはかけ離れているんです。
真実とはそのようなあり方なんですね。全てが1つにつながっているんです。ということは、今ここで私が坐禅をするということは世界が坐禅をするということなんです。
世界が動き出し、世界が呼吸をされるということなんです。
あるいは先にも述べたように、この坐禅がこの世界の本当の真実です。この世界の本当のありようです。この世界の正体です。つまり坐禅をしている世界が本来だということです。坐禅をしている世界が我々が常にいるべき場所、目指すべき場所だということなんです。
我々の「本当の家」なんですね。
だから坐禅を組んでくださいというわけですね。
坐禅の意義についてはやはりなかなか一言で言い表すことはできません。
とにかくこうした大義があるわけです。坐禅には。
結論としてその「坐禅」をしたならば、
ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ仏となる。
と道元禅師はおっしゃるんですね。
「本当のお救い」がそこにありますよという風に道元禅師は、言われている訳です。
「本当の救い」とは「大自然の在り方」を行じることだと。「本来の命の姿」を行じることだと。
坐禅をして、「一つに繋がった真実の仏の世界に飛び込むこと」だと。「真実の行い」をして「真実の世界に帰っていく。」これが「本当のお救い」だと。
そうおっしゃるわけなんですね。
その時気を付けなければならないのが「それに気づくこと」ではないんですね。
「あぁ本当の救いは坐禅をして大自然の在り方を行じることなんだなぁ。」と気付くことではないという訳です。
それに気付くのではなく、実際に「行じなければ」ならないんですね。
「気付く」というのは結局は「俺が気付くという事」で、物事を二つに分けている行為ですから。
ただ真実であり続ける、それが我々の本当の信仰でありますね。
本当の「救い」であります。
吉野山ころびても亦花の中
柳宗悦という人が残した詩につぎのようなものがあります。
「吉野山」という千本桜、三千本桜で有名なお山がありますね。
その吉野山では春になると桜の花がほころび、下一面花びらだらけになる。
そのような吉野山においてはどこで転んでも花の中だと、そういう意味ですね。
つまり全てが私の命であると、どこで転んでもわが命だと、全ては花一面であると。
これはもう全てを頂くという事ですね。
すべてが「自分の命」であると。
これこそが本当の救いですね。
我々は本来この「本当の救いの中」で生きております。
二つとして分かれない、一つの仏の命として溶け合っているのですから。
しかし「頭」を使って計らう事をしていては救いは生まれてこない。
「本当の救い」とは何か?ということを頭で考えるだけでは「本当の救い」には出会えない。
まぁ難しい話でもありますよね。
我々には頭がありますので、どうしても理屈で考えてしまうのですから。
どうしても受け入れられないところも出てきてしまうはずです。
なのでそのどうしても受け入れられない部分を、「専一に功夫する」。
つまりは信仰をもってしっかりと行じていく。
それこそが「正に弁道なり。」という訳です。
今回の内容は『普勧坐禅儀』において非常に重要となる部分であったかと思います。
本当の「救い」とは?-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
と言う部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 物事をただひたすらに「行じていくこと」を「専一に功夫する」と言う。
- ご飯粒の中には御仏様がいる
- 全てが一つに溶け合った仏の命。二つとして分かれない。
- つまり「俺の考え」とか「ワタクシノ物」というのは妄想にしか過ぎず、真実とかけ離れている。
- 「本当の救い」とは大自然の在り方を行じること
- 「本当の信仰」とは真実の為に真実の行を行う事。
- この世界においてどこを転んでも「花の中」、全部自分の命
以上、お読みいただきありがとうございました。

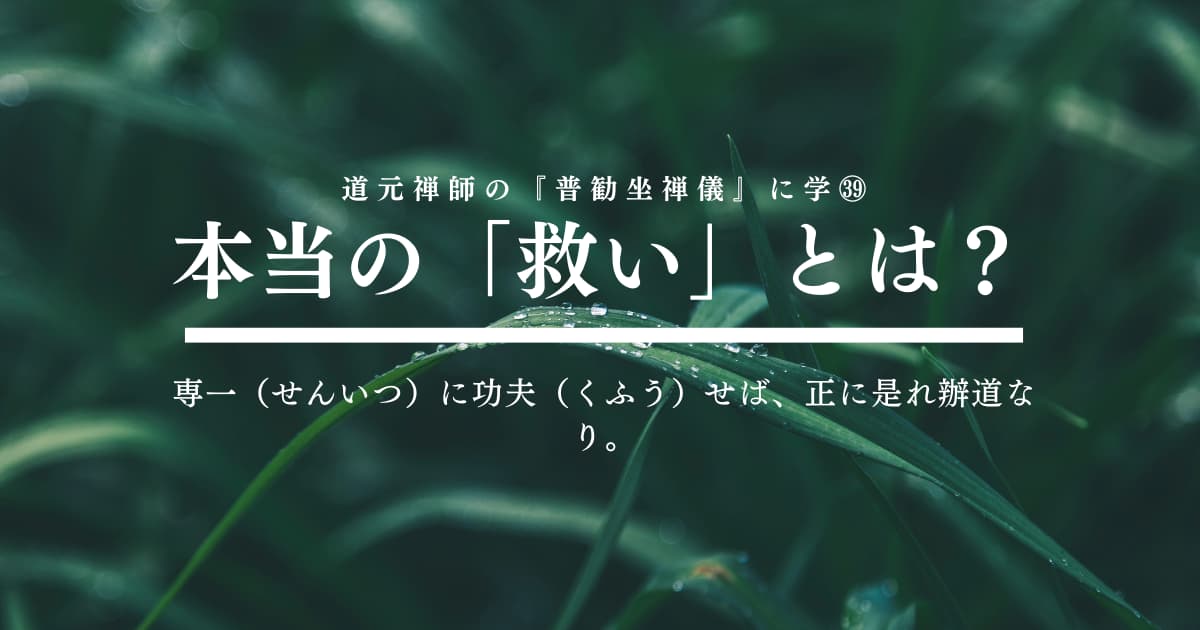

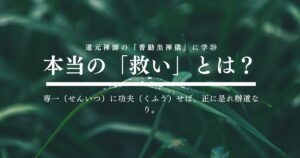
コメント