人間には欲があります。地位を獲得したい。名誉を獲得したいというような欲。
そんな地位や名誉とは縁遠い山奥の地で、多くの弟子達と坐禅修行に励み、自身の生涯を「坐禅」に捧げてこられた道元禅師。
そして真実の追求のために、ただひたすら「坐禅」に打ち込む。その「坐禅」を行うことこそが人間の本来行うべきことだと信じておりました。

道元禅師にとっては地位や名誉を得ることよりも、この坐禅を行うこと。坐禅をし続けること。これが人間にとって最も価値のある行いであると信じ、ただひたすらにその坐禅を打ち込める環境を求めていたのでした。
今回はそんな道元禅師の生き様と、その道中で起こった1つのエピソードをご紹介していきます。
三度目にしてようやく受け取った紫の衣

道元禅師は、当時天皇をされておりました後嵯峨天皇(1220-1272年)から、「紫の衣」を頂戴する機会が合計三度あったといわれております。
当時「紫の衣」というのは、名誉の最高位であり、「高僧」として認められた者のみしか天皇からもらうことが許されておりませんした。
その「紫の衣」をもらうことは、いわば「お墨付き」もらったようなものであります。
我々凡夫の頭からすれば、そのような「紫の衣」をいただき、天皇からお墨付きをもらえたということは大変名誉に感じることでしょう。「自分の仏法」が全国に認められたように感じられてしまうわけであります。
そしておそらくそれを鼻にかけてその後の人生を横柄に歩んでいくはずです。
そんな中、道元禅師はこの後嵯峨天皇から「紫衣(しえ・・紫の衣の事)」を頂く機会が三度もあったと言われているんですね。
何度も断り続けたわけです。そして三度目にしてようやくその「紫衣」を頂戴したと言われております。
何故、三度目にしてようやくお受けになられたかと言いますと、恐らく道元禅師自身が「久我家」という皇族と縁の深い方お生まれであったため、周りの者に迷惑をかけまいと考慮されてやむを得ず頂戴したのだと推察されます。
生涯身に纏う事のなかった「紫の衣」
昔は僧侶も世間の「官職」としての位置付けだったので、世間体を気にすること、そしてその際最高の権威の象徴としてこの「紫の衣」が身に付けるのが相応しいという習わしがありました。
現代でもその名残で、「紫衣」は「高僧」の象徴と言われております。
しかし「紫衣」を頂戴した道元禅師は生涯その「紫の衣」を身に着ける事はなかったと言います。
何故なら道元禅師にとって「紫衣」というのは世間との兼ね合い。仮に権威の象徴だとしても、それは単なる概念にしか過ぎないからであると感じていたからでしょう。
概念は実物ではない。実物のみが全てである。
道元禅師はいつも「実物」、そして「実力」を重視されておりました。
なぜならこれしか存在していないからなんですね。概念とは結局は存在しているようで存在していないのです。
今この瞬間にどんなものでもいいから差し出せ、と言われてもどれも差し出すことができないものなんです。
その点目に見えるものこそが「実力」であり、それというのは自我の延長でもなければ「概念」でもない。
確かに存在しているもの。つまり「真実」であったわけです。
そしてそれは今ここにしっかりと「お坐り」になる「坐禅」が証明している。この坐禅こそが真実であり、「真の実力」であったわけです。
誰よりも真なる道を求めてひたすらに「坐り続ける」。それこそ人間の評価されるべき、本当の「実力」であります。
道元禅師はその「実力」をもってして「布教」をされました。
何か説法をするわけでもなく、大義名分を掲げる訳でもない。
ただひたすらに「坐る」ことで布教を行ったわけです。
いまで言う布教とは訳が違いますよね。しかしそれこそがこの真実の世界における本来の布教だったわけです。
目にみえる確かな形。実力。実物。これこそが仏教の或いは「真実」における正しい布教のあり方だったんですね。
大自然の「猿」や「鶴」に笑われてしまう
道元禅師はこの「紫衣」を天皇から頂戴した折に、次のような「偈本」を残されております。
永平の谷、浅しと雖も勅命重きこと重々かえって猿鶴に笑わる紫衣の一老翁
これは次のような意味です。
 道元禅師
道元禅師後嵯峨天皇から頂戴した「紫衣」、非常に勅命であり重たいものである。勿論それは私も存じておる。しかしそのような「権力」に認められて喜んでいるようでは、大自然に生きている猿や鶴に笑われてしまうし、私のような年老いた爺さんが紫の衣を身に纏っておったら、余計に大自然に笑われてしまうだろう。
と言われるんですね。
大自然はみんな実力で生きております。
概念や権力をふりかざして生きている生物は誰もいないですよね?
猿も、鶴も、昆虫も、トナカイも、きつねも、ライオン、猫も。
本来みんな生きるために必死です。
僧侶として「大自然の生き方」、及び「真実の生き方」を追求する立場であるのに、そのような権力を誇示した「紫の衣」などを身に着けたら「猿」や「鶴」に笑われてしまうではないか、という意味の偈本を残さたというわけです。
道元禅師は常に、
「大自然の生き方」つまり、「真実の生き方」とは何か?
を追求されておりました。それが仏教のみならず、真の出家者、真の人間にとって大切なことだと信じていたからです。
道元禅師は一生涯その「紫の衣」を身に纏う事は無かったと言われております。
常に「実物の世界を行じること」、「真実の生き方」を徹しておられた道元禅師。
「坐禅」は、その「実物」そのものであります。
「坐禅」においては「権利」や「概念」は何一つ通用しません。仮に総理大臣だろうと、有名人であろうと、足を組めば痛いのです。鳥の鳴き声が耳を震わせ、呼吸もただ繰り返される。
坐禅こそがこの世界の真実なのです。坐禅を組むことがこの世界の真実を生きること。人間の本来の生き方なのです。それをいかに行うことができるか。道元禅師が見据えておられたのはこの1点だけだったのです。


人間の頼りどころ
生命の実物そのものであるこの「坐禅」。紛れもなく痛い。紛れもない生命。つまりそれはこの世界の真実だということです。
その「真実」を追求された方というのは、過去においてこの道元禅師以外にも沢山おりました。
ある人はこの「真実」及び「坐禅」のことを「独坐大雄法」と言った。
たった一人、大自然の中に坐っている姿をこの「独坐大雄法」と言いますが、「坐禅」はこの「独坐大雄法」であると言ったんですね。
つまり、大自然を生きている動物たちのように「権力」も必要なければ、他人からの「認知」も必要ない。
人間が「実力」で生きた世界、人間が「成仏」した姿の事であるから「独坐大雄法」だと言ったのです。
そもそも我々が生きる上で獲得した、「自我意識」。それはつまり概念です。
先ほどもお伝えしたとおり、存在しているようでしていない概念なのです。
それでもこの概念は便利なもので、その概念によって今日の様な文明社会を築き上げることができました。
しかし動物たちに「概念」は存在しません。「紫の衣」を纏いたいと思う者はおりません。
「概念」や「権力」は人間の頭の中だけに存在するものであり、「実物」ではありません。
例えば日本語には「別れ霜」という言葉があります。この言葉の意味を知らない人にとってこの「別れ霜」という世界観は存在しないんですね。その言葉を知っているものの中のみ存在している世界線なのです。
しかし今その言葉の意味を調べることで、たちまちにその世界線があなたの人生にも引かれます。
概念とは単なる脳内の作用なんです。単なる言葉なんです。単に脳内にイメージとして定着するのみで、実際には存在していないんですね。
ですから概念というのは非常に不安定であり、危険を伴うのです。存在していない上、誰にも共通してイメージ化されているわけでもなく、その捉え方も異なるからです。
つまりこの「概念」とは、テレビで見ているような「バーチャル世界」と同じようなもので、予想がはずれたり、目標が達成できなかったり、理由も無く理不尽であったりする訳です。
そういう「バーチャル世界」があたかも真実の世界だと思い込んでいるのですから、人間がいつまでも安心できないのは当然なのです。
概念は存在しておらず、存在していないのであればどんなに頑張ったところでその「概念」には寄りかかることができないからです。
そこで、是非考え方を反転してみるべきなんです。
人間にとって「概念」とは「構築」するものではなく「手放していく」ものなのです。
そして「坐禅」を通し、確かな実物の世界を行じる。本来の真実の世界に帰る。本来の真実の世界で生きる。
ついには我々にはこの「自分と言う生命の実物」というまぎれもない「頼りどころ」があることがわかるんです。
ですから道元禅師は「坐禅」そのものを布教とし、人々におすすめになるわけで、また人の真実の「生き方」として「坐禅」をおすすめになるわけであります。
大自然に笑われない為に
永平の谷、浅しと雖も勅命重きこと重々かえって猿鶴に笑わる紫衣の一老翁
道元禅師は人の真実の生き方とはなにかを追求しました。そこでは「猿」や「鶴」に笑われないような「大自然の生き方」とは何かを意識されていたのです。
「人が真実にいきること」や、「人の本当の安心とは何か?」という、この世界における人間の本来のあり方なるものを追求されたのです。
よって権威の象徴である「紫の衣」は一度も身に纏わなかったと言われております。

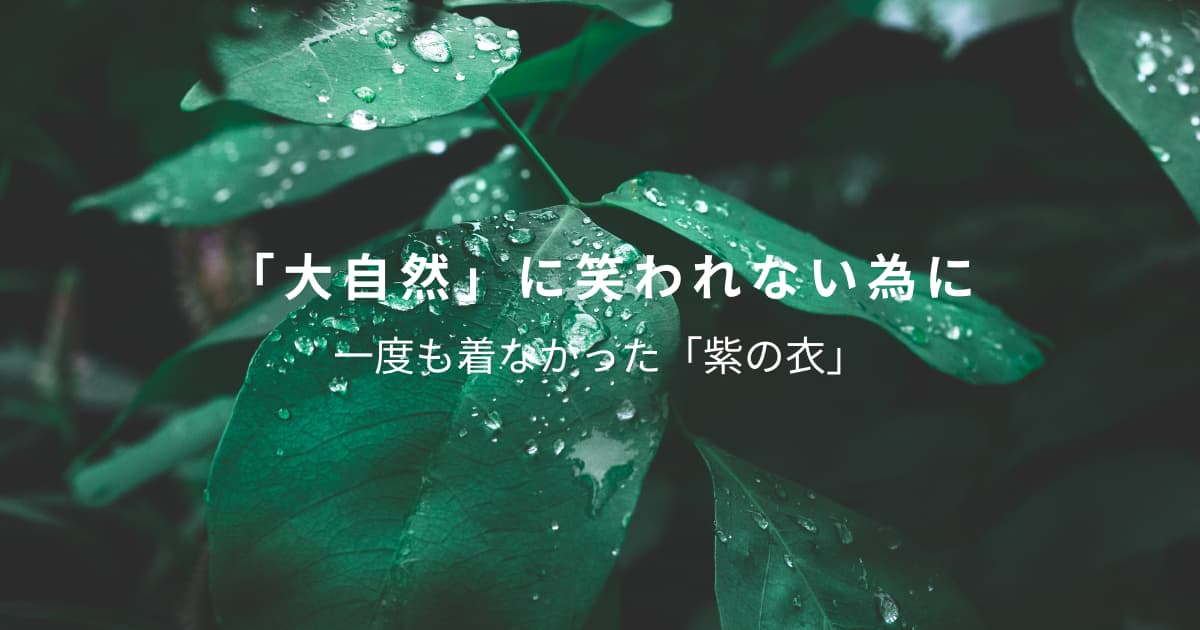
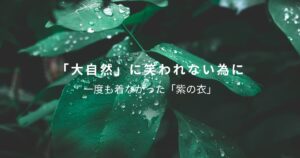
コメント