道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は「家常(かじょう)」についてお送りいたします。
目次
家常とは?
道元禅師がしるした『正法眼蔵』、第五十九巻の中にこの「家常」があります。
以下は「家常」の中一文を引用したものです。
いはゆる此間は、頂にあらず、鼻孔にあらず、趙州にあらず。此間を跳脱するゆゑに曽到此間なり、不曽到此間なり。遮裏是甚麼処在、祗管道曽到不曽到なり。このゆゑに、 先師いはく、誰在画樓沽酒処、相邀来喫趙州茶(誰か画樓沽酒の処に在つて、相邀へ来つて趙州の茶を喫せん)。しかあれば、仏祖の家常は喫茶喫飯のみなり。
これは寛元5年(1243年)に越前の禅寺峰(やましぶ)で説かれたもので、「家常」=「かじょう」と読みます。
この「家常」の巻では日常生活のあり方について具体的に説かれており、「日々の生活がそのまま仏道である」ということが説かれております。
また道元禅師はこの「家常」の巻の中で、「芙蓉道楷(ふようどうかい)禅師」が「投子義青(とうすぎせい)禅師」に尋ねた言葉、
仏祖の意句は家常の茶飯のごとし、これを離れて余に、また為人言句あいりやいなや
や、天童如浄禅師の
飢え来たれば喫飯し、困来たれば打眠す、炉鞴天に亙る
といった言葉を引き、仏祖方における日常の喫茶・喫飯のあり方についても説いています。

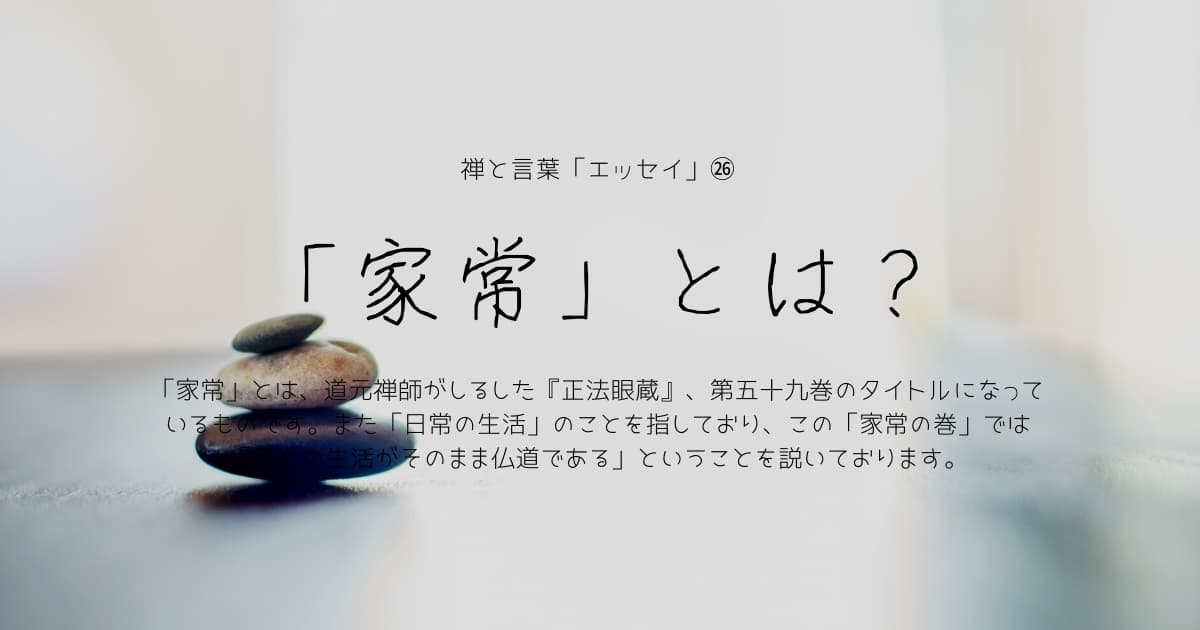

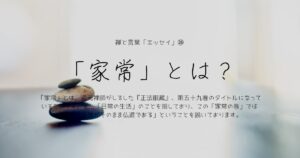
コメント