道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は「看経(かんきん)」についてそこにおける意味と、使い方についてお伝えします。

筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。

看経とは?
「看経」とは、もともとは「諷経(ふぎん)」のことを指し、さらに声をださずに経典を黙読するという意味でしたが、のちに「読経(どっきょう)」と同じ使い方をされるようになり、声を出してお経を唱える際に使われるようになった言葉です。
そのため今はこの「看経」という言葉は、勤行や礼拝、読経、諷経などといった言葉と、同じ意味で使われることが多くなりました。
そのほかにもこの「看経」は「経典を研究する」という意味でも用いられる場合があります。
看経と道元禅師
道元禅師がおしるしになった書物、『正法眼蔵』の中にこの「看経」について詳しく説かれたものがあります。
それは仁治2年(1241年)に興聖寺にて、大衆に示されたもので、タイトルも同じく「看経」になっているものです。
この「看経」の巻では、経典を低い声で読誦することの大切さや、経典を読誦する際に正しく持ったり、正しく開いたりすることの大切さについて詳しく説かれております。
いわゆる「諷経」、「読経」に関しての具体的な方法について、ここでは述べられております。
加えて道元禅師はこの巻のなかで、仏法の本質的な部分にも触れており、無上の悟りを得るためには良き指導者(善知識)、及び経典が必要であるとお説きになっております。
ここで道元禅師が述べる良き指導者(善知識)とは、「すべてが自分と一体」である人のことをいい、大自然そのものの人。それが仏祖あるいは指導者(善知識)とおっしゃるわけです。
また道元禅師がいうには、経典とは「すべてが自分と一体である仏祖の経典」のことをさしており、経典を読むことが世界の動きそのもの。世界の行なのであって、そこでは経典の尊さと、読経の尊さを言わんとしているわけです。
そのようなものが相まって、無上の悟りに到達すると。
その際、具体的な経典作法についても説かれており、
- 念経(経典の言句について思念すること)
- 看経(経典の黙読)
- 誦経(経典を唱えること)
- 書経(経典を書写すること)
- 受経(経典の伝授)
- 持経(伝授された経典を保持すること)
そこにはいくつかの種類があり、今回の「看経」もこのような形で組み込まれているわけですね。
「看経」及び、経典そのものの意義。
道元禅師はこの『正法眼蔵』、「看経」の巻でそのようなことについて説かれているのです。
道元禅師はさらにこの「看経」の巻の中で、六祖慧能禅師禅師が、「法達」という弟子に、
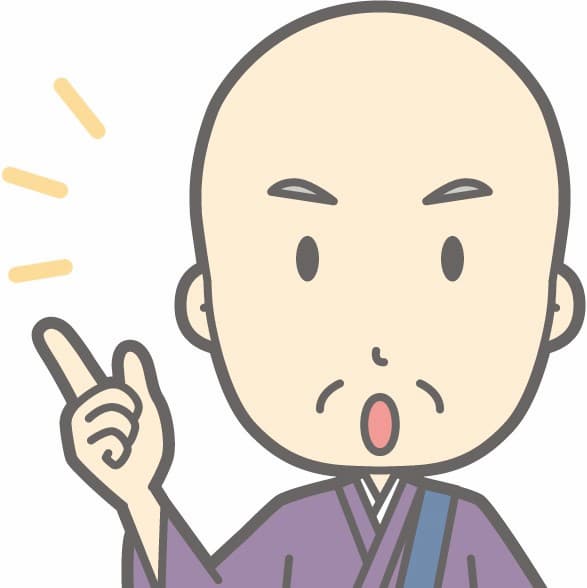
心迷えば法華に転ぜられ、心悟れば法華を転ず。
と説いた言葉をあげられ、



心が迷っているままで「法華経」を読めば、自分の主体性はなくなり、「法華経」に支配されてしまうだろう。逆に心が悟っているならば「法華経」を自由にすることができるだろう。
とお説きになっております。
修行者が本来の道を歩めるようにと、このような注意事項についても触れているわけです。
それ以外にも禅院における「看経」の作法についてくわしく説き、その意義について明らかにしております。

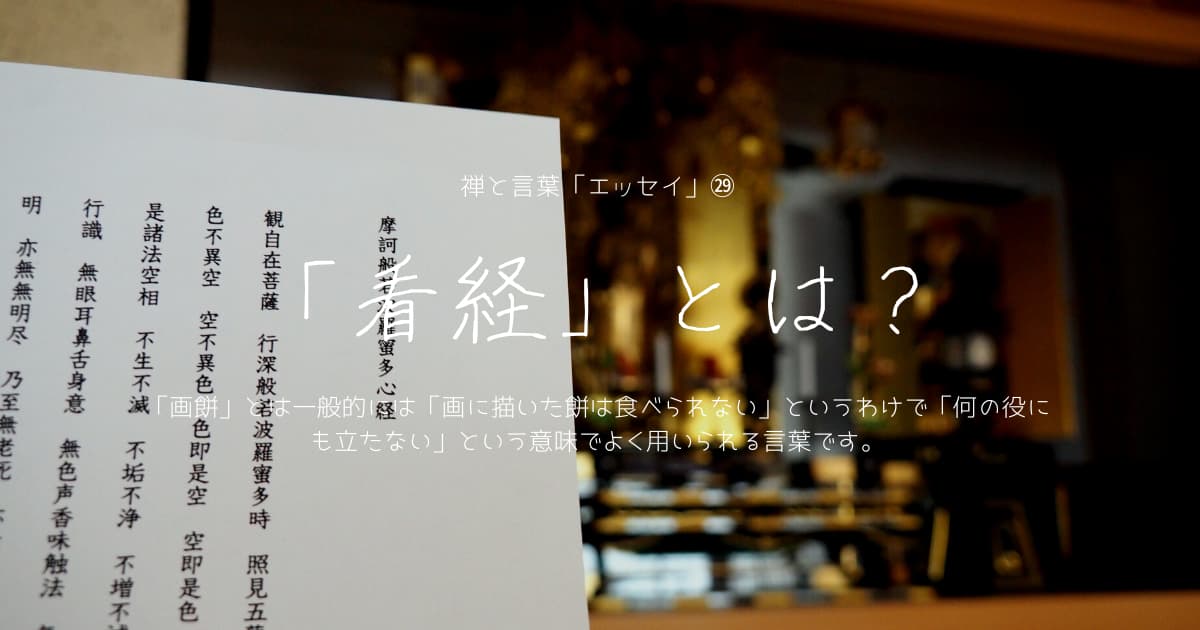
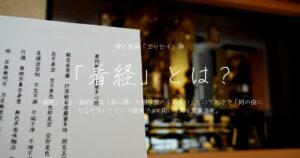
コメント