本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を読んでいきたいと思います。
初めに前回の道元禅師の『普勧坐禅儀』について学ぶ㉛その日、お釈迦様がお示しになった本当の説法とは?のポイントを振り返ってみたいと思います。
- 「指竿針鎚」は昔いた仏祖方にちなんだそれぞれの逸話から来ている単語を繋ぎ合わせたもの。
- 「指竿針鎚」の「鎚」はお釈迦様と迦葉仏尊者のエピソードからきている。
- お釈迦様は高座の上られ、そのまま高座から下りられる。それこそが真実の「説法」であった。
- 真実の世界は自分の納得とは関係のない世界。
- 「指竿針鎚」に出会う事ができたなら真実の世界に巡り合える。またそこが人の本当に安心できる場所。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
凡(およ)そ夫れ、自界他方、西天東地(さいてんとうち)、等しく仏印(ぶつちん)を持(じ)し、一(もっぱ)ら宗風(しゅうふう)を擅(ほしいまま)にす。唯、打坐(たざ)を務めて、兀地(ごっち)に礙(さ)へらる。万別千差(ばんべつせんしゃ)と謂ふと雖も、祗管(しかん)に参禅辦道すべし。何ぞ自家(じけ)の坐牀(ざしょう)を抛卻(ほうきゃく)して、謾(みだ)りに他国の塵境に去来せん。若し一歩を錯(あやま)らば、当面に蹉過(しゃか)す。既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。仏道の要機を保任(ほにん)す、誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん。加以(しかのみならず)、形質(ぎょうしつ)は(た)草露の如く、運命は電光に似たり。倐忽(しくこつ)として便(すなわ)ち空(くう)じ、須臾(しゅゆ)に即ち失(しっ)す。冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ。直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ。久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし。宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。
終わり
「払拳棒喝」の「払」
今回はこの部分の解説をしていきたいと思います。
今回の「払拳棒喝を挙するの証契も、」という部分。
この「払拳棒喝」とは「払」、「拳」、「棒」、「喝」それぞれの単語を一つにまとめたもので、それぞれの単語には仏法の大意が込められております。
それが非常に重大なものであるから、こうして道元禅師もこのようにしてお話になるわけですね。
またそれは過去、仏道を真剣に守り抜こうとした祖師方の逸話です。
今回はその「払拳棒喝」の「払」の部分に関してみていきましょう。
大鑑慧能禅師の弟子達
この「払」というのは「払子(ほっす)」のことです。
「払子」とは上記のように住職が持つハタキのような物をさします。
今日ではお葬式や法要の時などに用いられ、どこか権威的な役割を持った道具になっておりますが、本来は「蚊」や「アブ」などの虫を払う道具として使われていたんですね。
インドでは現在でも一般の家庭でもこの払子は用いられております。
昔の仏教者も同等に、権威道具としてではなく日常生活においてこの「払子」を用いており、夏の暑い季節に「蚊」や「アブ」を払う為に使っておりました。
昔、青原行思(せいげんぎょうし)禅師という祖師がおられました。

この方は六祖慧能(ろくそえのう)禅師の弟子であり、中国の唐時代のお人です。

この青原行思禅師の所にある日、石頭希遷(せきとうきせん)禅師という、のちに自身の弟子となる方が訪ねて行きます。

尋思去
この石頭希遷禅師も、もともと青原行思禅師と同様、六祖慧能禅師の元で出家をし、修行をしておられました。
いずれ兄弟子となるこの青原行思禅師や、他の兄弟弟子たちは石頭禅師が慧能禅師の元で修行している時には既に、それぞれの故郷やそれぞれの場所で立派に法を説いておりました。
石頭希遷禅師は一番最後の弟子であり、また慧能禅師が歳を取ってから出家をされた方なので、慧能禅師の側で仕えるような形で修行をしておりました。
六祖慧能禅師は非常に年老いていた為、いつあの世へ行ってしまうか分からない。
そこで石頭希遷禅師はまだ一人前の僧侶にもなっていない、真実に目覚めていない自分の将来の事を案じて、師匠の六祖慧能禅師に尋ねます。

「百年後」、私はどうしたら良いでしょうか?
ここで言う「百年後」というのはお師匠様がお亡くなりになった後という事ですね。
私はどう人生を歩んでいったら良いでしょうかと、そのような意味で「百年後一体どうしたら良いでしょうか?」という風に質問する訳です。
すると師匠の六祖慧能禅師は次のようにお答えします。



尋思去。
「尋思去(じんしこ)」、この「尋」は尋問の「尋」で、尋ねるという意味です、。
そして「思」は、「思う」ということで、「去」は「去る」。
このように言われた石頭希遷禅師。師匠の慧能禅師が亡くなった後、慧能禅師の道場に残り、そこで師匠に言われたように「尋思去」、思を尋ねていた。そこでは瞑想に耽っていた。
そして師匠が私に説きたかったのは「ひたすら坐禅に打ち込みなさい」という事だろうと思い、亡き六祖禅師の道場でひたすら坐禅をしていたのです。
「尋思去」の「去」というのは「喫茶去」の「去」、ただひたすら「打ち込みなさい」という風にこの石頭希遷禅師は捉えていた訳ですね。
「ひたすら坐禅をしなさい。」
これが慧能禅師が最後にお伝えしたいことだったと思ったのでしょう。
その折、いずれ師匠となる当時の兄弟子にあたる青原行思禅師が石頭希遷禅師の元を訪ねてきます。
そして次のように問いかけます。



お前は一体何をやっているんだ?
そして石頭希遷禅師は答えます。



実は師匠がお元気な時に尋ねた事があります。そしたら「尋思去」という風に言われました。なので私はひたすら坐禅に打ち込んでいるんです。
そのように言われた兄弟子の青原行思禅師はすかさず答えます。



いや、お前は勘違いをして坐禅をしているようだけども、そうではない。「尋思去」というのは六祖の一番弟子である、私「青原行思」に従って法を尋ねさいという意味だぞ?
とお答えします。
青原行思禅師の名前には「思」という字が付いております。
「尋思去」というのは、慧能禅師の一番弟子であり、石頭希遷禅師の兄弟子でもある青原行「思」を尋ねなさいという意味だったんですね。
そしてそれを知った石頭希遷禅師は「あぁそうだったのか!」という事でこの青原行思禅師を尋ねる訳ですね。
青原行思禅師が質問したその意図とは?
そのような経緯で今後二人は生活をともにすることとなる。
そして青原行思禅師の修行道場に訪ねてきた石頭希遷禅師に青原行思禅師が次のように質問をします。



汝いずれの所から来る
お前は一体どこから来たのだ?と尋ねる訳です。
すると、石頭希遷禅師はその質問に対し、このように答えます。



曹渓より来る。
「はい。わたくしは師匠の六祖慧能禅師のおられた曹渓山より参りました。」と答える訳ですね。
そこで青原行思禅師が「払子」を拈じて言います。
「払子」というのは冒頭でも申し上げたように「蚊」や「アブ」を払ったりする道具ですね。
その「払子」をグッと立てて石頭希遷に質問した。



曹渓に帰って這涸ありや。
つまり「慧能禅師のおられた曹渓ではこのような物があったかね?」と言って「払子」を石頭希遷禅師の前で立てるわけです。
「これがありましたかね?このような姿がありましたか?」と言って「払子」をスクッと立てるんですね。
さて青原行思禅師は一体何を質問したのでしょうか?この質問の意図はなんでしょうか?
まったく訳が分かりませんよね。
恐らく石頭希遷禅師も同じだったはずです。
「このようなものが曹渓山にあったか?」と言って、「払子」を立てた。
「この風景がありますかね?」「このやりとりがありますかね?」、「師匠と弟子の間でこのようなやりとりがありましたかね?」という風に質問するのですから。
青原行思禅師と石頭希遷禅師の間で行われた「仏法」の相続
かつてお釈迦様も霊鷲山の山頂において梵天王から預かった金波羅華を拈じられました。
そしてそれを高く掲げて、万四千という大勢の仏弟子の前で拈じられた。
多くの仏弟子達はポカーンと口を開けてその様子を見ておった。
ただしかし、摩訶迦葉尊者のみがその様子をご覧になって「ニッコリ」と笑われたんですね、微笑んだ。
その時お釈迦様が、



我に正法眼蔵涅槃妙心あり。今、摩訶迦葉に付属す。
という風に宣言をされるんですね。
「真実の仏法は摩訶迦葉に相続したぞ」と言って、「仏法」が師匠から弟子へと相続されてしまうという逸話があります。
「拈華微笑」という有名な逸話です。
そのようなやりとりを勿論この青原行思禅師は知っており、そこでは「拈華微笑」と同じような景色を演じられたんですね。
「払子」をスクッと石頭希遷禅師の目の前に出し、「曹渓に帰って這涸ありや。」と尋ねる。
「このような風景が曹渓山にありますかね?」という風に弟子の石頭希遷に尋ねる。
そのような質問をされた石頭希遷禅師は次のように答えます。



ただ曹渓のみにあらず、西天にもまたなし。
つまり「そのような事は私たちの師匠である、六祖慧能禅師のいた曹渓山にはありません。それどころかお釈迦様のいたインドにもそのようなことはございませんよ。」
と言う訳です。
すると後の師匠となる青原行思禅師がこの小癪な石頭希遷禅師に質問をします。



汝かつて西天に至ることなしや。
「ほほう、お前はこのような風景がインドにもないという風に断言するがお前は実際にインドに行ったことがあるのかね?」と質問をするわけです。
すると、石頭希遷禅師が次のように答えます。



もし至らばすなわちあらん。
つまり「もし行ったならば、ありましょうよ。」と。「このような風景も、もし私がインドに行ったならあるのでありましょう」と。
このような遣り取りで弟子師匠の間で「仏法」が相続されてしまうんですね。
石頭希遷が「もし至らばすなわちあらん。」と答える。
この一連の問答の遣り取りで「仏法」の相続が青原行思禅師と石頭希遷禅師の間で成される訳です。
払子を拈じるその意図とは?
この時用いた道具が今回の「払拳棒喝」の「払」に当たる「払子」であります。
そこでは仏法の相続がなされるわけです。それを成立させたのが今回の「払子」であったわけですね。
お釈迦様は「金波羅華」を拈じられた。青原行思禅師は「払子」を拈じられた。趙州従諗禅師であれば「庭前の栢樹子」とおっしゃたかもしれない。或いは雲門禅師であれば「幹屎橛(くそかきべら)」という風に言ったかもしれない。
色々なその時その時の場面に応じて、禅僧たちによってこうした真実のやり取りが繰り広げられて参りました。
それが「金波羅華」であろうが、「払子」であろうが、「庭前の栢樹子」であろうが、「幹屎橛」であろうが別にその違いに意味がある訳ではありません。
「金波羅華」が必ずしも「仏法」の相続に必要かと言われればそうではありません。
同じようにこの「払子」が必ずしも「仏法」の象徴であるという訳ではありません。
師匠と弟子による「真実」のやり取りに意味があり、そうさせる「風景」が大切だという訳なのです。
その風景に「金波羅華」だったり「払子」だったり「庭前の栢樹子」や「幹屎橛」が用いられたわけですね。
今回、青原行思禅師は弟子の石頭希遷禅師の前で「払子」を拈じられました。
お釈迦様においては「金波羅華」を拈じられた。そして他の弟子達はポカーンと口を開いていたが摩訶迦葉尊者だけが、微笑んでしまった。
それらは一体何の象徴なのか?何を言わんとしたのか?
「払子」は目の前で実物としてあるから「払子」である。頭の中の「払子」は「払子」ではない。
我々は何か物を判断する時は必ず自分の「物差し」で判断をします。その自分の「物差し」というのを人間であれば必ず誰しもが持っている。
それは生まれ育ってからの習い性であり、仕方のないことでもあります。
ただこの「物差し」というのは自分にとって都合の良いものだけを寄せ集めて作られております。
つまりは自分基準であります。
しかし「仏法」の基本は「無我にて候う。」です。
これが仏法の基本の「き」であります。なぜならこの世界に「個人」はないからです。
この私だと思っているものは、本来存在していないんですね。いつどこでも鳥の声が耳を震わせ、自分の命が生じる。いつどこでも呼吸ができ、生きていくことができる。
自分の命は他によって起こっている。つまり他が自分の命なのです。
このように大自然は個人と関連しておりません。当たり前ですが自分都合の「物差し」は通用しません。


しかし人間は育っていく過程でいつの間にかこの「物指し」だったり「自我意識」という物が形成されてしまう。
そしてあたかもそれが全てとでも言う様に、目の前に展開する大自然や他者との間に自分の「物差し」を当てがって、自分都合で行動していく。
これが人間の誤った行動なんですね。その価値観の違いによって、争いが起きたりする。
しかし前述したようにこの世界に個人はあり得ません。
また世の中のあらゆるものが「無常」です。変化し続けているんですね。あらゆるものは変化し続けている。
今目の前にある「石ころ」であっても「一秒後」には姿を変えている。
しかしこの頭の中の「物差し」や「自我意識」というものは決して変化をしません。
そしてこの変化しない「自我意識」や「物差し」で人生を歩む以上、そこには誤りがあり、例えば「生死」というものが生まれます。
「入り口」と「出口」が生まれる。固定化したものがある以上、そこには生と死があるんですね。
しかし今目の前で展開している真実の在り様は、「生死」ではなく、全て「無常」であります。
常に変化をしている。
自分の体一つ取り上げてもこの「細胞」、「骨」、「血液」、「皮膚」どれをとっても常に変化をして止まない状態である。
そして我々がよく言うところの「死」なるものも、骨となり、空に舞う、そしてそれが雲となり雨となり、地に降り注ぐ。
そこには本来何一つ滞りがありません。固定がないのです。個人がないのです。無常ですね。
我々人間は「自我意識」や「物差し」をこの世界に持ち込み、「生死」や「入り口」を作り出してしまう。
「生と死」これは固定です。つまり物事の概念化なんですね。物事の真実はそうではない。
全てが繋がっている。全てが1つの命なんです。そして真実はいつも変化をしている。「無常」である。
我々が生き詰まる理由はそれを知らないからです。概念という本来、存在しないものにしがみつくから苦しいのは当たり前です。
青原行思禅師が「払子」をスクッとお立てになった。
普通の人間であれば「ただの払子だ」、「何をしているんだ?」、「どのような意味だ?」とそれで終わってしまいます。
このような「払子」が曹渓山にあったかね?、お前のおった六祖慧能禅師の所にあったかね?
確かに「払子」だからどこにでもありますよね。どこにでもあるんだけども、弟子であるの石頭希遷禅師は、



ただ曹渓のみにあらず、西天にもまたなし。
「そんな物は曹渓山にはないし、インドにだってありませんよ。」と答える訳です。
その「払子」だって常に無常しているのだから「曹渓にだってない」、「西天にだってない」、「昨日のどこにもない。」。
有るのは今の「払子」だけである。
世界は今ここしかないのだから。
その「今」を除いたならば、どのような世界にも「払子」はありません。
そして、



もし至らばすなわちあらん。
と続け、「もし私がインドに行ったならばその払子はありましょう。」と答える訳です。
的を射た、ごもっともな答えですね。
我々には「今、ここ」しかないように、今ここの払子を除いたならば、払子はどこにも存在しないと言うのです。それでももしインドにいる今が今なのであれば、そこには払子は存在できる。なので「もし私がインドに至ったならばありましょう。」と。
本当の「払子」というのはというのは「今」のここにしか存在しないのです。
「今、ここ」以外の「払子」は、「払子」ではなく、「概念」です。なのでそれは「払子」ではないんですね。頭では「払子」と言われれば「払子」をイメージし、「そんなものどこにだってあるじゃないか」となるかもしれません。
しかし本当の「払子」というのは「今、ここ」、目の前に出された「払子」以外ありえないのです。
これは「払子」以外にも言える事でしょう。
どんなものであっても「今、ここ」の実物以外ないのです。
全ては「今、ここだけ」なのです。


過去も今で、未来も今。今が全て。
我々は頭で考えると「払子」なんてものはどこにもあるように思える。「曹渓」であっても存在するだろうし、「インド」であっても当然存在するだろうと。
しかし、「存在」というのは頭の中の証明によって「存在」している訳ではありません。そのような話は単なる「概念」であり、空論です。
個人の主観で、なんの意味もない話です。
大自然に個人はありません。個人の主観もありません。それらは存在していないのです。空論や個人の主観も存在しておらず何の意味もないのです。想像だけでは何も生まれないからです。
存在は目の前に「実際にあり、触れるから」存在しているのです。
実物だけがこの世界の話です。いわんや仏法の話です。全ての話です。話すべき話です。
この実物によってこそ、人は安心できる。正しい話ができる。仏法の話ができるのです。そして何かを生み出すことができる。
実物だけが全ての基本です。これは実物だけが基本だという話です。実物の尊さを説く話なんですね。
今回の青原行思禅師と石頭希遷禅師禅師のやりとりは非常に有名で、今日にも受け継がれております。
青原行思禅師は石頭希遷禅師を真実に導くためにスクッと実物の「払子」を石頭希遷禅師の前に出されます。
そしてその実物である「払子」を目の前で見た石頭希遷禅師は真実に出会う事ができたという訳です。
「払拳棒喝」の「払」-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
について解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返ってみましょう。
- 「払拳棒喝」というのはそれぞれ単語を繋ぎ合わせたもので、それぞれに過去の仏祖方のエピソードがある。
- 「払拳棒喝」の「払」は師匠である青原行思禅師と弟子の石頭希遷禅師によるエピソード。
- 「払拳棒喝」の「払」は「払子」の「払」。
- 世の中のあらゆるものが一秒後には姿を変え「無常」であり続けている。
- 本当の「払子」というのは「今ここの払子」を除いてどこにも存在しない。
- 存在とは「頭」の中で証明するのではなく、目の間に実物として展開しているから「存在」している。
- 実物だけが尊い。実物だけがすべて。実物から全てが生まれる。
以上、お読みいただきありがとうございました。

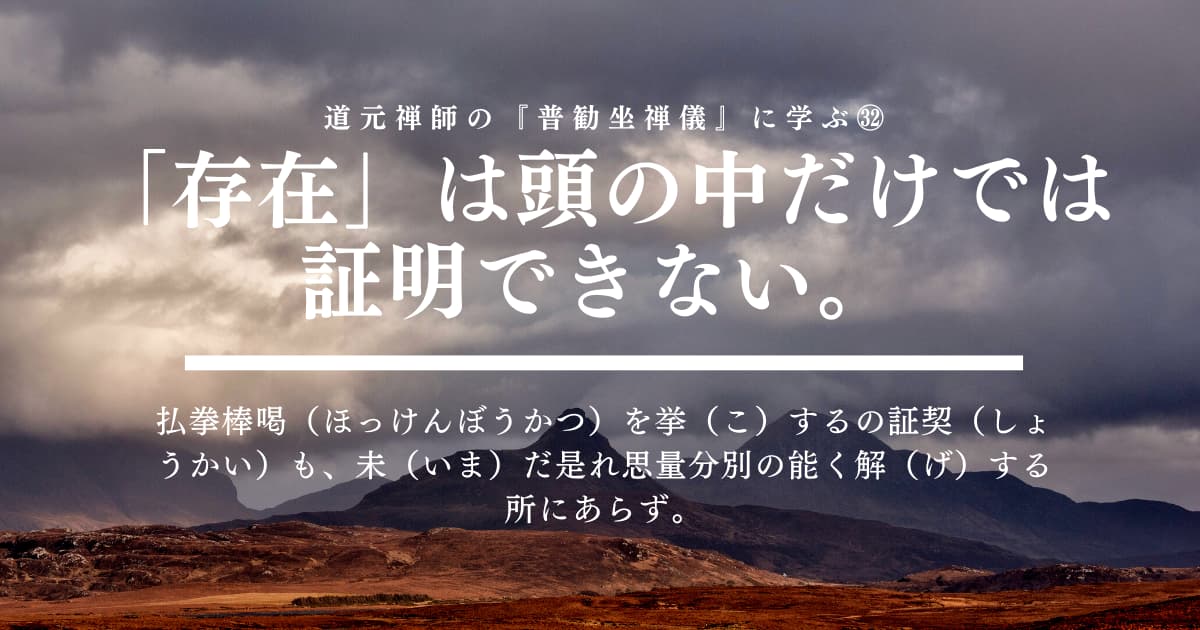




コメント