本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を読んでいきたいと思います。
初めに前回の、
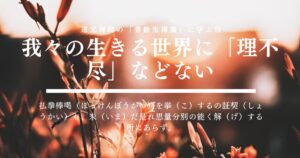
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「払拳棒喝」というのはそれぞれ単語を繋ぎ合わせたもので、それぞれに過去の仏祖方のエピソードがある。
- 「払拳棒喝」の「棒」は「棒」で殴ることで人を導こうとした徳山宣鑑禅師にまつわるエピソード
- 「疑問」は人の頭の中にしか存在しない。
- その「疑問」を解決するために生きているのではない。
- 我々の生きる世界に「理不尽」なことなどない。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
「払拳棒喝」の「喝」

今回はこの部分の解説をしていきたいと思います。
この「払拳棒喝を挙するの証契も、」という部分。
この「払拳棒喝」とは「払」、「拳」、「棒」、「喝」それぞれの単語を一つにまとめたもので、それぞれの単語には仏法の大意が隠れ、それぞれ重大な意味を持っております。
なのでこうして道元禅師もこのようにしてお話になるわけですね。
それは仏道を真剣に守り抜こうとした祖師方の逸話でもあります。
今回はその「払拳棒喝」の「喝」の部分に関してみていきましょう。
臨済禅師と三聖慧然
今回の「喝」は「払拳棒喝」の最後の一文字となります。
またこれはかの臨済宗をお開きになった、臨済義元禅師にまつわるお話となります。
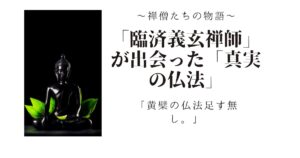
これは臨済禅師が「ご臨終」される際、弟子の三聖慧然(さんしょうえねん)と交わした際のやり取りのお話です。
臨済禅師のご臨終に際して、弟子の三聖慧然(さんしょうえねん)という人が臨済禅師の側でずっと看病をしておられました。
そしてずっと側に付き添っていた三聖慧然に、臨済禅師はつぎのような言葉を掛けます。
 臨済禅師
臨済禅師我が遷化した後、我が正法眼蔵を滅却してもらったら困るぞ。この正法眼蔵涅槃妙心、仏法の真実を滅却してもらっては困る。ちゃんと相続してもらわなければ困るんだ。
すると弟子の三聖慧然が、次のように答えます。



どうして師匠の「仏法」を滅却する事がありましょうか。決してそのような事は致しません。ちゃんと正法眼蔵を相続してまいります。
そのような答えを聞いた臨済禅師は再度この三聖慧然に言葉を掛けます。



もしお前に「道」を問うものが現れたら、お前はその時に何と答えるのだ?
すると弟子の三聖慧然が答えて言います。



喝!!!
それを聞いた臨済禅師が答えます。



誰か知らん、吾が正法眼蔵、這(こ)の瞎驢辺に向かって滅却せんとは。
「瞎驢辺(かつろへん)」という言葉が出てきましたが、これは決して良い言葉ではありませんね。
この「瞎驢辺」とは、「目の見えない驢馬」のことを指しており、 ここでは「まったく何もしらない愚かな者」という意味として捉えられるでしょう。
つまり「一体何を言っているであろうか。私の正法眼蔵はこの何も分からない弟子のせいで滅却してしまうだろう。」と言うんですね。
これが臨終に際しての、臨済禅師のお言葉です。
「仏法の相続をちゃんとしてくれよ」と弟子の三聖慧然にお願いをしようとした臨済禅師。
弟子の三聖慧然もきちんと「どうして私がお師匠様の正法眼蔵を滅却しようと言うのでしょうか。決してそのような事は致しません。ちゃんと相続していきますよ。」とその意気込みを語っておりました。
そして臨済禅師の「もし道とは何かと聞かれたならばお前はどうやって答えるのか?」という質問に対し、「喝!!」と答えた三聖慧然。
それから、



誰か知らん、吾が正法眼蔵、這(こ)の瞎驢辺に向かって滅却せんとは。
という言葉を残してこの遣り取りは終わってしまうんです。
非常に師匠の臨済禅師がはがっかりされたような言葉を残されるんです。
しかし実は、この遣り取りは「あ~ぁ、私の弟子の三聖慧然で我が正法眼蔵涅槃妙心も滅却しちゃうんだなぁ。」という様な嘆きの公案ではないんですね。
一体どういうことか?
「喝」は励ましの言葉



どうして師匠の「仏法」を滅却する事がありましょうか。決してそのような事は致しません。ちゃんと正法眼蔵をを相続してまいります。
と弟子の三聖慧然は自信を持って答えられます。
そこで、臨済禅師は言いますね。



もしお前に「道」を問うものが現れたら、お前はその時に何と答えるのだ?
すると弟子の三聖慧然は、



喝!!!
という風に答えます。
この「喝」という言葉ですが、例えば今は毎週日曜日の朝にやっている「サンデーモーニング」というテレビ番組がありますよね?
そこで張本勲さんが「喝!」とか「あっぱれ!」という評価をつけていますけど、実はこの「喝」という言葉は決してあのように人を批判したり、けなす言葉ではありません。
あれは少し間違った使い方をしていますね。
それではこの「喝」というのは言葉は一体何なのか?
前回の、
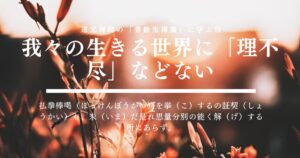
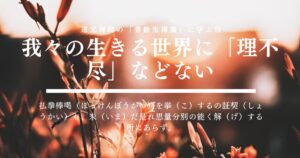
では、「言い得るも三十棒。言い得ざるも三十棒。」の徳山宣鑑禅師にまつわるお話をしました。
その内容の中で、「お前が仏法そのものについて言い得たとしても三十棒。言い得なかったとしても三十棒だぞ。」というような事を徳山宣鑑禅師は弟子に述べる訳です。
「言い得る」、「言い得ない」、「理解する」、「理解しない」、「よく分かった」、「よく分かりません」というのは対照的に位置しているように見え、あたかもそのどちらかに答えがあるように思えるけれどもそもそも、どれも頭の中の話であって、実際の世界にそんなものは一切通用しないぞ、というような内容でありました。
いずれも「真実」ではないというわけですね。
だから徳山宣鑑禅師は、「言い得るも三十棒。言い得ざるも三十棒。」の姿勢で、その間違いから抜け出させようと、真実の世界というものを修行僧達に見せていったのです。
それは仏法の大意であるのと同時に「励まし」の作法だったわけです。
今回のやりとりにおいても「道?(仏法の真実)そんなものは今ここに間違いなくあるではないか。」その証明が「喝」という言葉(響き)だったんですね。
また「最後の最後でなんでそんな詰まらない事を言っているんだ、何てくだらない事に当てはめようとするのだ。」と、逆に弟子の三聖慧然が臨済禅師を励ましていたのです。
そういう励ましの意味合いでこの「喝」は本来ある訳なんですね。
「仏法」の相続とは、今ここに生きている自己
すると臨済禅師は、



誰か知らん、吾が正法眼蔵、這(こ)の瞎驢辺に向かって滅却せんとは。
とお答えになります。
このことに関しても「私の仏法がこのでたらめで愚かなこの三聖慧然の所で滅却してしまうとは一体誰が知る。」と、文字通りに読めばそのまんまの意味で捉えてしまいがちですが、臨済禅師がこの言葉に託した本当の意味はそうではありません。
事の始まりは臨済禅師は「我が正法眼蔵を絶やすことなく相続せよ」という風に弟子の三聖慧然に言明した事です。
今、世間で言われる相続と言うのは「家屋」や「田畑」、「有価証券」、或いは「預金」、「現金」、そのような遺産を後世に相続することを指します。
そのように「実際の物」があれば相続という形が見えやすいかもしれない。
しかしこの「仏法」においては、「どんなものを相続するのか?」その実際の対象が見えるわけではありません。
また世間と同じように実際に「田畑」やら「有価証券」や「預金」や「現金」など相続する実際の「物」があれば、「放蕩息子が使い果てて、相続が滅却してしまった」という事にもなりましょうが、「仏法」における相続というのはそういう事ではありません。
そもそも「仏法」は「今ここ、この自己に生きている事実」しかありません。
今この自己に生きている事実でありますから、「仏法」は滅却のしようがないんです。
この世界、丸ごと仏法、ということでもありますから一生使っても使い尽くす事がないんです。
例えばそれが自己であれば、肌をつねれば痛いこと、足を組めば痛いこと。こうした紛れもない確かな作用。真実。この世界の正体。つまり仏法。そうしたものを常に抱えております。常に展開しております。


あるいは世界においても花が枯れ、鳥がちゅんちゅんと鳴く。雷がおき、地震が起こる。こうした紛れもない真実、この世界の真実、この世界の正体。つまり仏法を常に展開しております。
この自己も世界も、今、ここ、全てが仏法というわけです。
世間一般であれば、「ギャンブル三昧の放蕩息子のせいでいつの間にか遺産がなくなってしまう。」なんて事も有るでしょう。
しかし「仏法」の相続は一生の間、縦横不尽である。使い尽くす事が決して出来ない。
もし仮に使い尽くす事が出来たならばそれは仏法の相続ではないわけですね。
繰り返しになりますが、「仏法」というのは今ここ、この自己に生きている生命の事実、そしてそれを自覚するしかないわけです。
それを一人一人が自覚したならば、この「仏法」は滅却のしようがない。
遺産相続であればいつの間にかなくなってしまう。
そのようなちっぽけな相続ではないですね、仏法は。
臨済義玄の仏法は臨済義玄で滅却してしまう、それでいい。
そこで話を戻すと、



誰か知らん、吾が正法眼蔵、這(こ)の瞎驢辺に向かって滅却せんとは。
ここで言う「滅却」の本当の意味とはどういうことでしょうか?
それは、臨済義玄禅師の「正法眼蔵涅槃妙心(仏法)」は、臨済義玄禅師においてすっかり滅却してしまうということです。
しかし滅却しても、仏法はきちんと受け継がれるということですね。
後を継がれる三聖慧然は臨済禅師亡きあとも自己の生命を生きる。
「三聖慧然」が自己の生命を生きる事が立派な「仏法」の相続であるわけですので、仮に臨済義玄禅師の「仏法(今、ここ、この自己)」が滅却したとしても、「仏法」の相続は三聖慧然が、三聖慧然の自己の命を生きることで相続される。
今、ここ、この自己が仏法ですので、自己がなくなれば、仏法もなくなるわけです。いずれは無くなるのが人の命ですから、つまり滅却するのが仏法なのです。
先ほどの話と矛盾するようですが、仏法というのは決して滅却しないんです。それはこの世界の全てが仏法だからですね。しかしこの自己で言うと、滅却する。滅却しなければおかしいのです。滅却しなければならない。それと仏法は同義ですから、その観点で言えば滅却しなければいけないわけですね。
我々の命は不滅です。この命は世界と繋がっているからです。世界が自分だからです。なので決して無くなることはない。しかしこの自己という単位で見ると、最後はきちんと死ななければならないわけですね。そうでないとおかしいんのです。それが自然なのです。それが仏法なのです。
滅却するのが正しいのです。自然のあり方なのです。
しかしそうやって「仏法」は相続されていく。失われる事なく、受け継がれていく。仏法は常にそこにあり続けるわけです。仏法だけが常に残っていくわけです。仏法だけが常にある、生きている。そのような世界なのです。
我々が死のうと世界が生きていると言うのはこういうことです。それはどんなことがあっても仏法は常に生きているということなんです。


臨済義玄禅師はしっかりと自己の生命を生き抜いて、「仏法」を滅却し尽くした。
そしてそれを今度は弟子の三聖慧然が「自己の命」にまた生きて、自己の命として、自己の命を歩んでいく。
それが「仏法」における相続であります。
誰も代わってくれない「命」を次世代に引き継いで生きていく事が「仏法」の相続である。
何か実際に引きずる物があったり、相続する実際の物があるというのはそれは世間の遺産相続の話。
「仏法」の相続においては、師匠から実際にもらって引きずるようなものは何一つない。
自己の命は自己で完結であります。「仏法」も同じように自己が完結すれば滅却する。
なので臨済禅師のお言葉にもあるように「正法眼蔵涅槃妙心(仏法)」が滅却する事は当然の事で、滅却することこそ自然の流れで「仏法」そのものなのです。
払拳棒喝が用いられて仏法修行者が今日まで導かれて来た。
さて今回の「喝」で、
それぞれのエピソードを一通り見終わって来たわけです。
「払子」や「拳」、「棒」や今回の「喝」。
それぞれに「仏法」の何たるかが紹介されていたわけですが、その続きの
というのは、
そのような「払」、「拳」、「棒」、「喝」それらの手段が用いられて仏法修行者が今日まで導かれて来た。
という意味になります。
そして、
と続いていく訳ですが、それはまた次回にしましょう。
「払拳棒喝」の「喝」-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
について解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返ってみましょう。
- 「払拳棒喝」というのはそれぞれ単語を繋ぎ合わせたもので、それぞれに過去の仏祖方のエピソードがある。
- 「払拳棒喝」の「喝」は臨済義玄禅師が臨終に際して、三聖慧然と問答を交わした時のエピソード
- 「喝」は相手を励ます事。
- 「喝」は生命の実物
- 個人の「仏法」が「滅却すること」で「仏法」は相続されていく
- 「払」、「拳」、「棒」、「喝」それぞれの手段を用いられて沢山の修行者が導かれてきた
以上、お読みいただきありがとうございました。

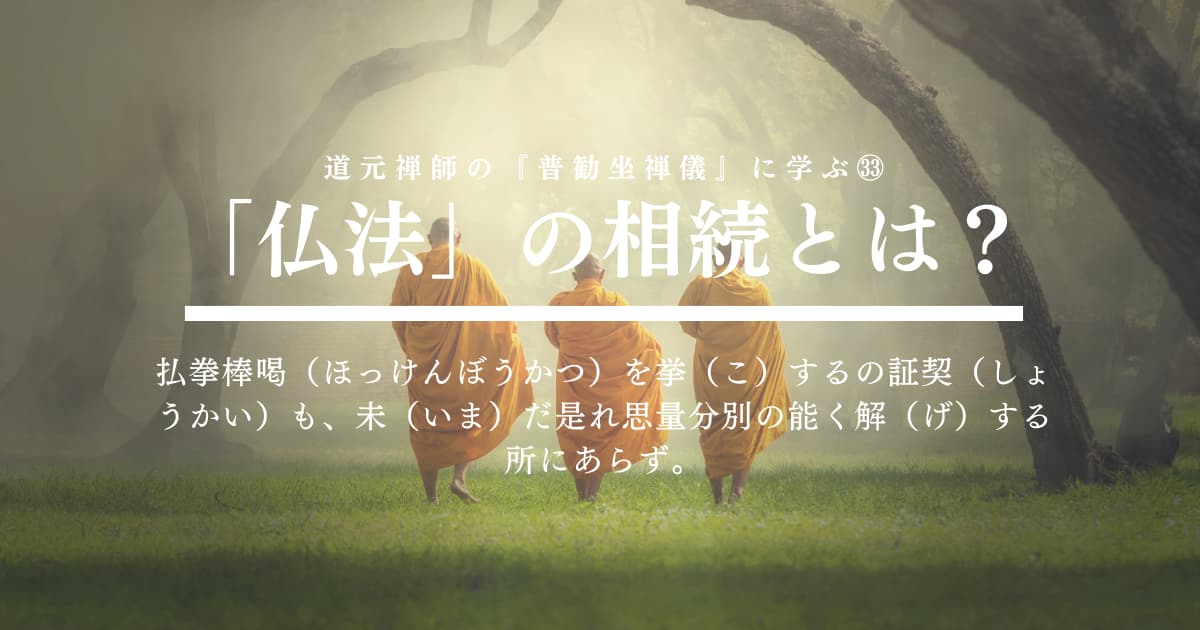
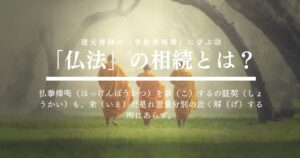
コメント