本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を解説していきます。
まず前回の、

のポイントを振り返りたいと思います。
- 生命の実物としては「塵」や「埃」というものは存在しない、実物に人間の価値判断は付けられない
- 概念としてなら「塵」や「埃」、きれいな物、汚い物と、人によって価値判断が分かれてくる。
- 物事の正しい姿は全て「実物」としての姿。
- 「塵」や「埃」は払うという実践を通して始めて、「塵」や「埃」を実物としてとらえる事が出来る。
- 「風」は至る所にあるが、仰いで始めて「風」が至る所にあるという事を証明できる。
それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。
外に求めるようなことはしなくていい
今回は、
という部分を読んでいきたいと思います。
まず「大都、当処を離れず、」というのは、
全ては今ここを離れてはいない。
という意味になります。
そして続いての、「豈に修行の脚頭を用ふる者ならんや。」というのは、
それなのにどうして仏法を外に求めて、修行の歩みを進める事があろうか。
つまりこれを繋げると、全ては今ここを離れてはいない。それなのにどうして仏法を外に求めて、修行の歩みを進める事があろうかという意味になります。
我々は自分とは別のかけ離れた場所に仏法があると思うんですね。
そしてそれを目指して歩もうとしてしまいます。
しかしここで言うように全ては今、ここであって、「仏法」及び「悟り」に関しても常に今ここにあるということなんですね。
今回はいまの内容について解説していきます。
達磨様は中国にいったはずでは?
ここで少し昔の祖師方のお話をご紹介させてください。
昔、雪峰義存(せっぽうぎそん)と玄沙師備(げんしゃしび)という二人の弟子と師匠がいました。
弟子にあたる玄沙師備という方は非常にまじめな方であったと言われております。
またその玄沙師備は日々非常に厳しい修行をしておりまして、頭陀(ずだ)和尚という風にも周りから言われておりました。
この玄沙師備は雪峰義存の道場に身を寄せていたのですが、中々真実の悟りを開くことができなかったんですね。
そこで「真実」を見出す為に、広い中国内に点在する祖師方を訪ね歩こうとするんです。
どうか真実の道を見出したいという強い思いがあったんでしょうね。
師匠である雪峰義存の道場を後にしようとするわけです。
そしていよいよ出立しようと門前を出ようとしますが、その時に思いっきり親指を石にぶつけてしまったんですね。
そこで思わず、
「アイタタタタ!!」
となってしまったのです。
昔は皆、草鞋を履いておりましてね。
なので親指を石にぶつけて飛び上がるほど痛い思いをした。
血が出てしまったんですね。
血豆もできた。
あの有名な般若心経では「色即是空」と言っているように、存在は皆「空」であるはずです。この「身」すら無いはずです。それなのにこの「痛さ」は一体どこからやって来るのか。
この痛みいずれの所から来たるか。
よっぽど痛かったのでありましょう。
そこでもう玄沙師備は中国の祖師方を訪ね歩く旅に出る事を諦めてしまうのですね。
「なんだ、大した求道心じゃないね!」と思わないでください。
この玄沙師備が中国の祖師方を訪ね歩く旅を諦めた理由は、「親指を石ころにぶつけたおかげでもう外に求める必要がなくなった。」からなんです。
そこですっかり玄沙師備はほぞ落ちすることが出来てしまったからなんです。
今まで概念だけで遊んでいた世界から、実物の世界へ。
足を石にぶつける事によって自覚する事が出来た訳です。
「真実」に出会える、「仏法」に出会えることができたわけです。
概念遊びから実物の世界に入ることが出来たとでも言いましょうか。
そして、師匠の雪峰義存の所へ戻ってくるんですね。
すると師匠の雪峰義存は玄沙師備に次のように問います。
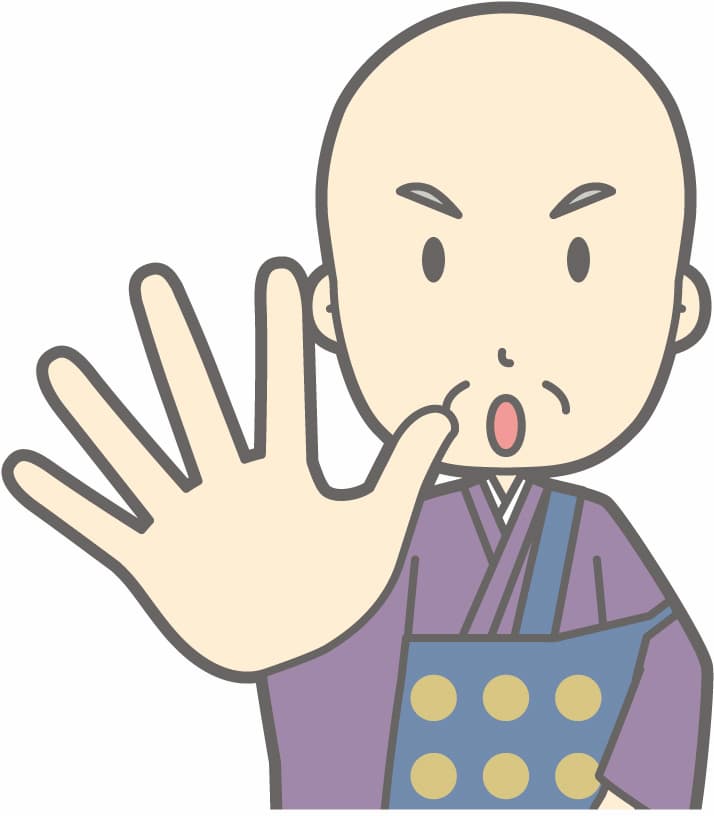 雪峰義存
雪峰義存「お前は遍山(へんざん)するはずじゃなかったのか。何ぞ遍山せざる。」
ちなみに遍山(へんざん)というのは色々な師匠達を訪ね歩く事です。
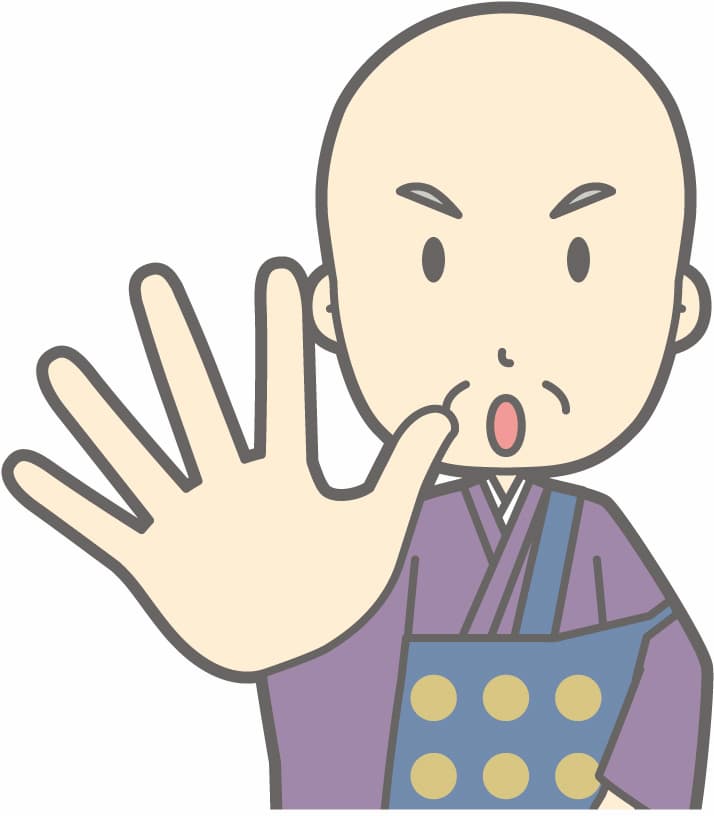
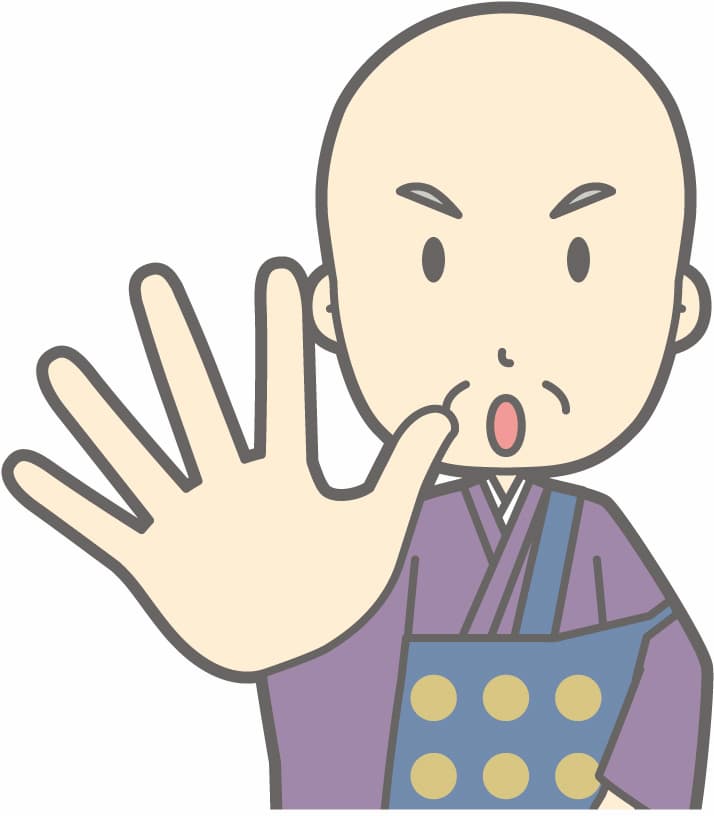
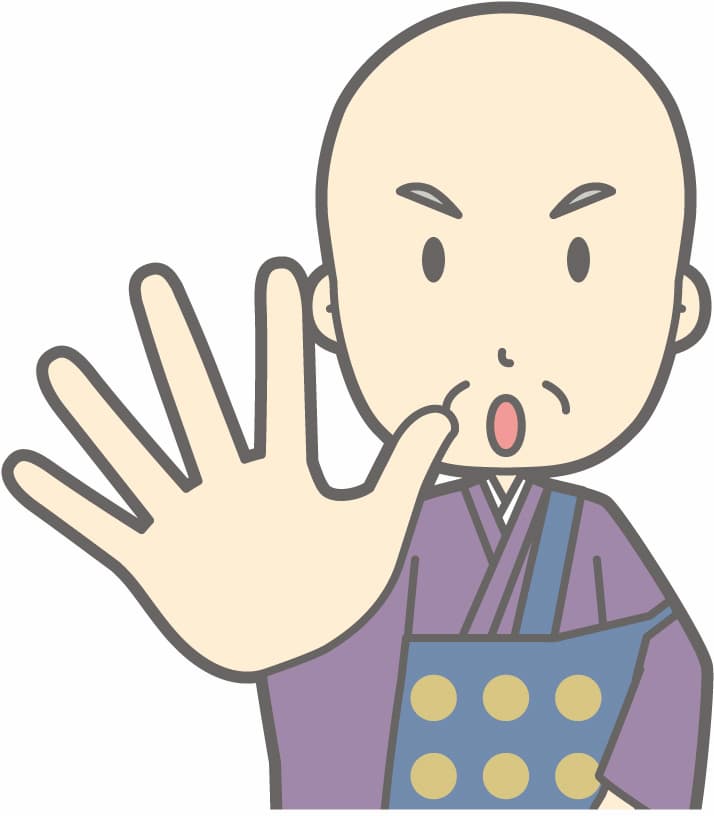
真実の仏法を求めて、今さっきお前は出て行ったのばかりではないか。なのに何故戻ってきたのか。
師匠がいうのもごもっともですね笑。
こんなにあっさりと諦めてしまったのですから。
しかし弟子の玄沙師備が次のように言われるんです。



達磨東土に来たらず、二祖西天に行かず。
ここに出てきた「達磨東土」というのは達磨様の事ですね。その達磨様は西天竺(西インド)の人です。
達磨様は西インドから中国の広東省に上陸し、「梁」の武帝と問答して嵩山少林寺に入って坐禅を生涯通された祖師でありまして、歴史上間違いなく実在したお方です。
しかしこの時玄沙師備が言うには、
達磨東土に来たらず、二祖西天に行かず。
つまり、達磨様は今まで中国に来たことなどないぞというんですね。
また達磨様の後を継いだ二祖慧可大師もインドになど行っていないぞと言う訳なんです。
二祖慧可大師に関しては確かに歴史上もインドに行ったという記録は残されておりませんが、達磨様は確かにインドから中国へ渡り、お釈迦様から伝わる正伝の仏法を中国に広めました。
それなのになぜ、玄沙師備は、
達磨東土に来たらず、二祖西天に行かず。
というのでしょうか?
これはつまり何を意味するのでしょうか?
ここでは「達磨様」を「真実」とここでは言い換えているだけで、
真実を求めて何もどこかへ行ったり来たりする必要ない。仏法は、当処を離れず。今ここに全てがある。
というような意味で言っていたんです。
自分が全体
すこしわかりづらいですよね、すみません。
例えばあなたは「一体どこから来たのですか?」という質問をされたとします。



はい、私は大阪から参りました



はい、私は北海道から参りました。



はい、私はアメリカから参りました。
このように人ぞれぞれ色々な所からやってきていることが分かりますね。
しかしみんな、「当処を離れず、今ここにいる。」というのです。
あなたが坐禅を行じている場所は一つも移動はないということなんです。
全体が移動している。
もう少し分かりやすく言うと、例えば車のナビゲーションを見ていると地図の上をグルグル回ってあたかも動いているような気がする。
しかし、全体は一つも動いていないんですね。
一つも移動しない全体の中で、皆さんが動いていると言いましょうか。
全体を引き連れて移動をしていると言いましょうか。
というのも、
自分が自分から離れる事は一切出来ません。
どこへ行こうが常に自分と一緒なんですね。
そしてその「自分」というものは「頭の中」だけに存在している架空の存在であって、本来の世界にはこの「自分」というものがありません。
いつどこにいても、どこからやってきたかわからない大自然の発する酸素をすって呼吸が出来るし、壁を殴れば痛い。足を組めばいたい、自分が命じなくても寝ている間にちゃんと食べたものを消化してくれる、カラスの鳴き声や、ストーブの音、アロハな風の音が自分の耳を震わせる。
常に世界と自分というのは一体なんですね。ここからここまでが自分、ここからここまでがあなた、という線引きができないのです。
「個人」と定義づけるものはなく、この個人と思われているものは常に「全体」として生きているんです。
全体を引き連れて生きているんです。全体と溶け合っているのです。
それを、
達磨東土に来たらず、二祖西天に行かず。
といっているわけですね。
真実を求めて何もどこかへ行ったり来たりする必要ない。仏法は、当処を離れず。今ここに全てがある。
であると言うわけです。
今回の『普勧坐禅儀』でも、
と言っている訳です。
自分がいる場所とは他の場所に、もっと違う素晴らしいものがあるのではないかと思って、我々はいつもあっちに行ったりこっちに行ったり、フラフラし続けております。
しかし自分を離れて「真実」はあり得ないんですね。ここを離れて真実はどこにもないのです。常にどこに行ってもここしかない。
何故なら「自分」がその全体だからです。つまり自分が真実だからです。
仮にどこか遠い異国の地に行ったとしてもそこにはやはり「自分がある」。
常に私は全体を生きている。そこではいつでも誰でも「今、ここ。この自己」しかない訳です。常に全体しかないわけです。常に「一つ」として溶け合った「仏の命」なんです。
生きる時も一緒、死ぬ時も一緒なんです。
遠い昔、達磨様が「インド」から中国へやって来られました。
これは紛れもない事実です。
しかしそれは達磨様が遠いインドから中国にやってきただけで、「全体」は「行ったり来たり」を一つもしておりません。
「真実」は移動もしないし、「減り」もしません。
カーナビゲーションのように画面の上から眺めたならば達磨様ははるばる、インドから中国までやってきたと感じるかもしれません。
そしてその移動した距離を測ると、物凄い距離を移動してきたのだなぁと思うかもしれません。
しかし達磨様からしたら一つも「移動」をしていない。
このことを先程の玄沙師備は言っていたのです。
この達磨様と同じように、我々の「命」も一つも移動がありません。
何故なら自分の命は世界の物事と同一で、溶け合っているからです。
このような事が今回の、
内容となっているわけです。
なので、
全ては今、ここ(自分)を離れていない、それなのにどうして仏法を外に求めて、修行の歩みを進める事があろうか。
とおっしゃるんですね。
全ては仏の命として溶け合っている
今回は『普勧坐禅儀』の、
という部分を解説してきました。
それでは最後に、本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 親指を石ころにぶつければ「痛い。」これが全てである。外に求める必要は何もない
- 今ここにある「自己」こそ真の仏法
- どんなに遠くに移動しようと、自分からは一切逃れる事は出来ない。つまり「仏」から逃れる事ができない。
- 何故ならすべては「一つ」に溶け合っているから。
- 自分は全体で、全体は自分だから。
以上が本記事のポイントとなります。
お読みいただきありがとうございました。

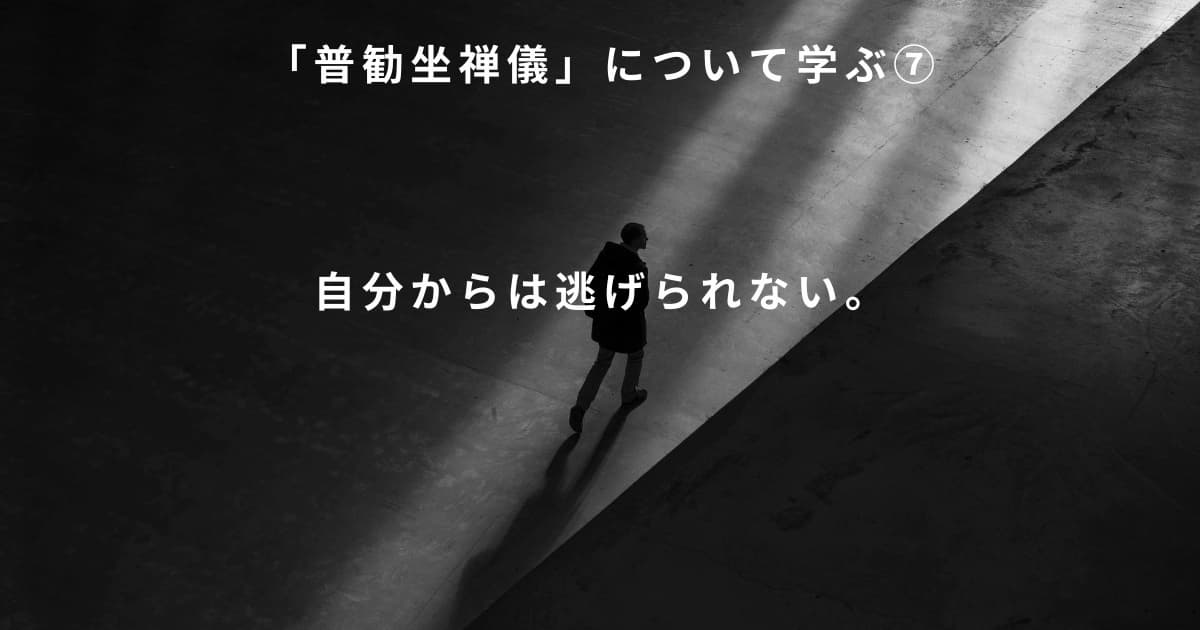

コメント