本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は、
という部分を読んでいきたいと思います。
まず初めに前回の、
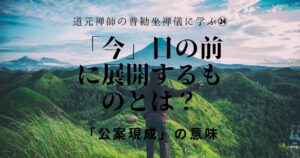
のポイントを振り返りたいと思います。
- 「公案」とは「揺るがす事のできない」という意味。
- 「現成」とは「目の前に展開している全てのもの」という意味。
- 「公案現成」とはつまり「今、目の前に展開する一切のものは行き詰まりのない真実の姿を現している」
- 「羅籠」とは「鳥かご」や「網」の意味。
- 真実の世界には行き詰まりなどがないのだから、人間の価値観や手段などが入りこむ余地がない
- そのことに気付けたなら物凄い力を得られたということになる。
それではポイントを抑えていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。

鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。
所謂(いわゆる)坐禅は、習禅には非ず。唯、是れ安楽の法門なり。菩提を究尽(ぐうじん)するの修證(しゅしょう)なり。公案現成(こうあんげんじょう)、籮籠(らろう)未だ到らず。若(も)し此の意を得ば、龍の水を得たるが如く、虎の山に靠(よ)るに似たり。當(まさ)に知るべし、正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、昏散(こんさん)先づ撲落(ぼくらく)することを。若し坐より起(た)たば、徐々として身を動かし、安祥(あんしょう)として起つべし。卒暴(そつぼう)なるべからず。嘗て観る、超凡越聖(ちょうぼんおつしょう)、坐脱立亡(ざだつりゅうぼう)も、此の力に一任することを。況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。
いきづまりのない世界
今回はこの部分を解説していきます。
まず、當(まさ)に知るべし、正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、という部分の、當(まさ)に知るべし、という部分。
「本当の理解」というのは「頭」で理解する事だったり、「心」で理解して味わえる事でもない。つまり「行い」を通してのみ「本当の理解」をすることができるという事を道元禅師は常々言われております。
そのために「生命の実践」である「坐禅」をおすすめになられるわけです。
なので「當(まさ)に知るべし」というのはここでは、
坐禅が即ち、本当の理解
という意味になります。
「坐禅」をすると、足が痛くなりますよね。
つまり「確実」な「モノ」が生まれるわけです。
そしてその「痛み」は人間の理解や認識、そういった「頭の中」が導いたものではありません。しかしそれは確かな「答え」です。
人間が思っている「理解」や「認識」といったものはあくまでも「概念」です。
人によってその理解や認識の面は異なるし、何よりも手に触れることができないため、「不確か」なんですね。
その点、「この足の痛み」というのは、人の間で相違が決して生まれない「確実」なものです。「実物」なんです。そしてそれこそが本当の「理解」であるというのが道元禅師の認識なんですね。
続いての、正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、という部分。
「正法」というのは、「真実の自己」という意味になりますが、直訳すると「正しい事」となります。
そして自(おのずか)ら現前し、というのは、「何もせずとも目の前に展開している」という意味になります。
つまり「正しいこと(真実)は、何もせずとも目の前に展開している」ということなんですね。
この部分に関しては以下の、
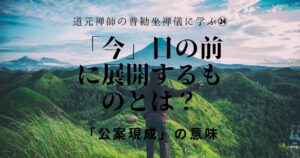
で詳しく解説しておりますのでご一読いただきたいのですが、この世界の全ては真実を現成している。真実を現成しているというのは、つまり100%ということです。それがどうとか、その正体がなんなのか?といった詮索は介入できないほど100%だということです。
例えばこうしている間にも目の前の物質もそうですし、私もそうですが、風化されていきます。歳をとっていきます。この現れが真実だということです。100%だということです。この現れが全てだということですね。そしてそれを仏と言います。
この世界の全ては100%、その現れを持っている。仏の命を持っている。完全な形を持っている。その完全な形を決して裏切ることがない。真実を現成しているということはこういうことです。
続いて「昏散(こんさん)」についてですが、そもそも眠くなる事を「昏沈」と言います。
意気消沈して眠くなってくる事を「昏沈」と言うわけですね。
また色々な事に「心」が振り回されることを「散乱」と言います。
例えば「坐禅」をしていると、色々な事が頭の中に次から次に思いついてそれがどんどん連想ゲームの如く、連なっていきます。
このように「心が散ること」を「散乱」と言うんですね。
つまり「昏散」というのは「眠くなること」と、「心が散乱すること」という意味になります。
そして、先づ撲落(ぼくらく)することを。に関してですが、 「撲落」というのは、打ちのめされることを「撲落」と言います。
「打ちのめされる」ということですから、ここでは「自分の身心を束縛する存在から解放され、自由になった状態」の事を「撲落」と言います。
ここまで急足で来ましたが、今回は「正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、昏散(こんさん)先づ撲落(ぼくらく)することを。」 ということで、本来であれば「昏散、撲落すれば正法自ずから現前なり」と訳した方が我々は理解しやすいもしれません。
何故なら「 眠くなったり、心が散乱することから解放されたなら、目の前には正しい世界が展開している」という風に捉えた方が我々人間の頭は理解しやすいからです。
しかしそうなると「昏散撲落」が条件になってしまうんですね。
言い方を変えれば「昏散撲落をしなかったならば、真実の世界は展開しない」ことになってしまいます。
先ほども申した通りこの世の全ては真実を現成しています。常に100%なのです。また前回の、道元禅師の『普勧坐禅儀』について学ぶ㉔「公案現成」の意味とは?「今」目の前に展開する一切は行き詰まりがない。でも解説したように、我々の生きている世界には行き詰まりが一切ありません。
すべてが過不足なく、真実をなしている。最高の形で存在している。
そこにおいては「条件」もなければ「手段」もない。この世の全てが生まれた時点で仏様の手の中です。
そしてそこでは「一つの命」として溶け合っております。

それが我々の生きている世界で、真実の世界の在り方です。
なので「昏散、撲落すれば正法自ずから現前なり」と「条件」を取り入れて訳すのは、人間的には理解しやすいだけで、それは間違った解釈だということに気付かなければなりません。
「条件」があるのは人間の脳みそだけであり、大自然には「条件」は一つもないのですから。
「大自然」はいつでも行き詰まりのない「真実」が広がっているだけなのです。
なので道元禅師も、「昏散、撲落すれば正法自ずから現前なり」という読み方はせず、「正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、昏散(こんさん)先づ撲落(ぼくらく)することを。」と訳し、大自然のありのままの姿をこのように言い表しているわけです。
月の光は常にそこにある
さて、せっかくですからここで一つ昔の「詩」をご紹介したいと思います。
雲晴れて後の光と思うなよ。元より空には有明の月。
これは夢窓国師の詩です。
どういう「詩」かと言うと、
雲が晴れて光が差してきたと思ってはならない。元より空には有明の月がちゃんと照っているじゃないか。
という意味の「詩」になります。

雲が晴れて、その後やっと月の光が我々に注ぐのではなく、元からそこには有明の月がちゃんと輝いておった。
ということですね。
つまりここでは、「晴れる」というのは常にもともとあって、「人間だけの条件である」ということを言っておるのです。
元々「光」はそこにあったということですね。
確かにそうですよね。
元々晴れているところに雲が覆いかぶさっただけでありますし、それをくもりとして捉えているのは人間側だけの都合です。
そしてこれは、今回でいう所の「正法自ら現前している」とも同じ意味にも捉えられます。
雲晴れた後の光ではないぞ。元々空には有明の月の光があったではないか=眠さや、心の散乱から解放されたら真実があるのではないぞ。元々目の前には「真実」が展開しているではないか。
いうならば「晴れ」も真実。曇りも真実。雨も真実。そこに評価は決して下らないのです。
真実の世界(屁の貸し借りができない坐禅)ではそのような「条件」は何もなく、おのずからそうなっているよという事ですね。
真実は常に目の前に広がっているよということなんです。
道元禅師のおすすめになる「坐禅」をしていると、カラスの鳴き声が聞こえ、サイレンの音が聞こえ、足が痛くなる。これはもうどうすることもできない命の作用です。本来の我々の命の作用です。命の正体です。
またカラスが鳴き、その鳴き声が私の耳を震わせる。つまりカラスによって私の命が起きたということであり、カラスが私であるということに気づくことができます。
この世界というのはこのように全てが1つに溶け合っており、全てが真実を現成しているのです。
そんな世界が我々が本来身を置くべき場所だから、この坐禅をお薦めになるわけですね。
我々は仏で、住まうべき場所は仏の世界だからです。真実の世界だからです。
坐禅はその目の前に展開している「真実」をとらえた「仏行」です。「真実」そのものなのです。
月の光は常にそこにある-まとめ-
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
という部分を読んできました。
それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。
- 本当の理解とは「実践すること」で本当の理解ができる。
- 「坐禅」の「行」を行う事こそが本当の理解。
- 「昏散」とはうつうつと眠くなることと、心を乱す事。
- 「撲落」とは束縛から解放されること
- 「真実の自己」は常に目の前に展開しており、条件を満たした結果得られるものではない。
以上、お読みいただきありがとうございました。

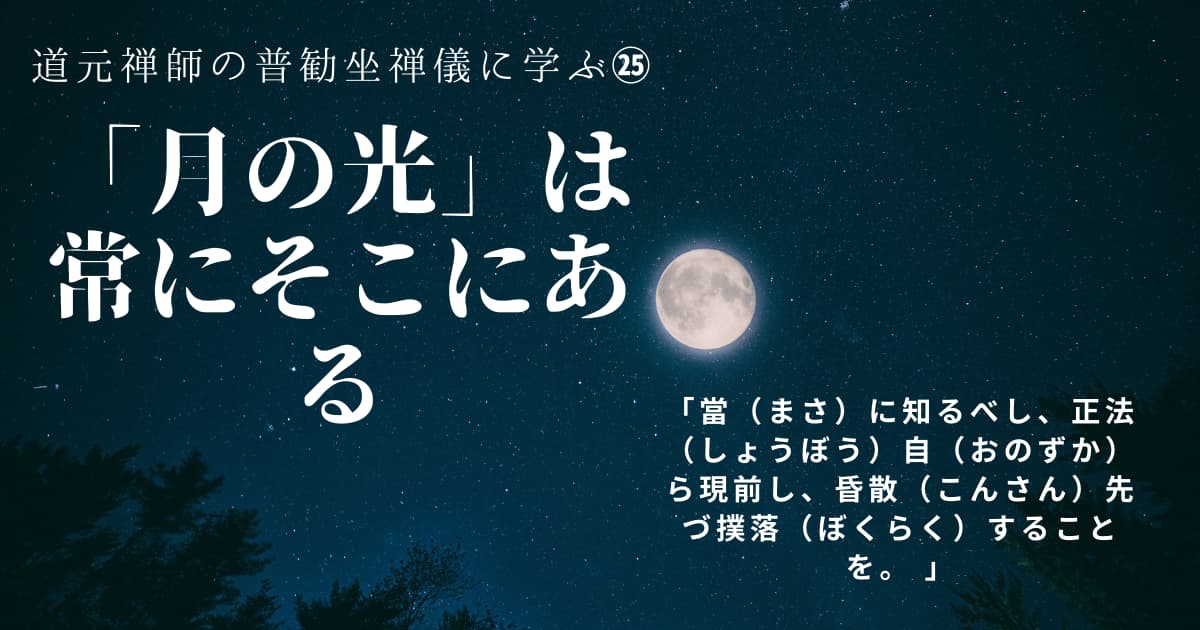
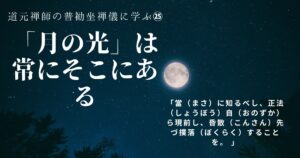
コメント