本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。
今回は『普勧坐禅儀』本文の、
という部分を解説していきたいと思います。
まず 初めに前回の、

のポイントを振り返りましょう。
- 「自家(じけ)の坐牀(ざしょう)」というのは「単布団の上」のことを指す。
- 色々な所をさまよい歩く我々にお釈迦様は救いの手を差し伸べてくれている。
- 「心」は常に不安定である。その「心」で幸せを探し歩いてもいつまでも見つからない。
- 本来みな救いの中にいるのに、その一歩目を誤れば当分の間間違えてしまうだろう。
- この世界のどこを切りとっても「自家(じけ)の坐牀(ざしょう)」である。
それではポイントをおさらいしていただいた所で、本記事の内容に進んでいきたいと思います。
唯、打坐(たざ)を務めて、兀地(ごっち)に礙(さ)へらる。万別千差(ばんべつせんしゃ)と謂ふと雖も、祗管(しかん)に参禅辦道すべし。何ぞ自家(じけ)の坐牀(ざしょう)を抛卻(ほうきゃく)して、謾(みだ)りに他国の塵境に去来せん。若し一歩を錯(あやま)らば、当面に蹉過(しゃか)す。既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。仏道の要機を保任(ほにん)す、誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん。加以(しかのみならず)、形質(ぎょうしつ)は(た)草露の如く、運命は電光に似たり。倐忽(しくこつ)として便(すなわ)ち空(くう)じ、須臾(しゅゆ)に即ち失(しっ)す。冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ。直指(じきし)端的の道(どう)に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々(ぶつぶつ)の菩提に合沓(がっとう)し、祖々の三昧(ざんまい)を嫡嗣(てきし)せよ。久しく恁麼(いんも)なることを為さば、須(すべか)らく是れ恁麼なるべし。宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん。
終わり
虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。
今回の内容は、
という部分です。
まずは「既に人身(にんしん)の機要を得たり、」という部分から。
この「機要」というのは「肝心・かなめ」という意味となりますので、この部分を直訳すると「人間の一番肝心な命を既に得ている」という事になります。
自然な訳し方としては「我々はこの世に人間として命く機会を頂いた」ということでしょう。
続いての、「虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。」というのは「虚しく月日を過ごしてはいけないぞ」という意味ですね。
そして「仏道の要機を保任(ほにん)す、」というのは、「一番重要な教えを仏祖方は伝えてこられたわけだが、今我々が受け継いで保護している」意味ですね。
そして「誰(たれ)か浪(みだ)り石火を楽しまん」。というのは、「そのような大切な物を受け取ったからには、みだりに石火を楽しまないように」ということと致しましょう。
ここで出てきた「石火」というのは「火付け石」のことですね。
石でカチーン、カチーンとやると火花がでます。
昔はその火花に燃えやすい「木くず」などを付けて火を灯していく訳ですが、あそこで生じる一瞬の火のことを「石火」と言うんですね。
なので最後の部分に関しては「我々の命というのは一瞬の石火のようなものである。それなのにその一瞬しかない命を、楽しんでいて一体どうするんだ?」という意味になります。
人身得ること難し仏法値うこと希なり
今回の「既に人身(にんしん)の機要を得たり、」の解説に入っていく前に、次のような逸話をまずお耳に入れていただきたいです。
「仏教」をおひらきになったお釈迦様。
そのお釈迦様がある日、道を歩きながら大勢の弟子達の前で説法を始めるんですね。
そして弟子達の前で一つまみの「土」を指の甲の上に乗せるんです。
そこで弟子達にある質問をします。
 ブッダ
ブッダこの私の指の甲の上に乗っている「土」と、三千大千世界にある「土」とでは一体どちらが多いでしょうか?
するとある弟子が答えるんですね。



そんなのは三千大千世界の「土」の方が多いに決まっております。比べようがありませんよ
するとお釈迦様は、



人身得ること難し仏法値うこと希なり
とお答えになります。
これは非常に有名な言葉ですが、どういう意味でしょうか?
「仏教」は元々インドで興りました。
その「仏教」には様々な「宇宙観」があるとされております。
特に「須弥山」や「極楽浄土」、「曼荼羅」などはその中でも大変有名で代表的な、今のべたような宇宙観ですね。
「須弥山」は特にその中でも代表的な宇宙観ですが、仏教では宇宙の真ん中にはヒマラヤ山脈ならぬこの「須弥山」があると考えられています。
そしてその「須弥山」の東西南北には「東勝神州(とうしょうしんしゅう)」や「南閻浮提(なんえんぶだい)」などがあり、我々人間が住んでいるのはこの「南閻浮提」だとされているんですね。
それはそれは非常に広大です。宇宙はとても広い。そのことを伝えようとしているわけです。
そんな中、我々がこの「南閻浮提」に生をうけるのは、まさに私が今指の甲に土をのせたようなものであるとここでお釈迦様は言われるんですね。
非常に稀であると。
その中でさらに、「人間」として生まれるというのは様々な「因縁」が絡み合った上で成り立っており、非常にまれな事であるということをお釈迦様がこの「土」を通して言われるんですね。
そして、



人身得ること難し仏法値うこと希なり
というのは、「人間として生を受けるのもまれなことにも関わらず、ましてや仏法に出会える事はとても稀で、とても尊いことである」。という訳なんです。
「人間として生を受ける事は本当にありがたい事であり、そこから仏法に出会えることというのは非常にまれで大変ありがたい事である」と。
せっかく人間として生まれたこの命。どうか無駄にしないでほしい。
我々人間はそのような有難い因縁に恵まれている。人間として生まれてこれただけでもとてもありがたいことなのだと。
仏教ではこのような受け止めかたをしているのです。
しかも人間世界に生まれても、他の「宗旨」に出会っていたかもしれない、他の「宗教」に出会うかもしれない。
そのような可能性だってあったはずです。
そんな中でこの「仏法」に出会うという事は非常にまれであり、本当にありがたい出会いであると言われるんです。
なので道元禅師も、



そのような有難い出会いを非常に大切にして、月日を無駄に過ごしてはならないぞ。(虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。)
と、この『普勧坐禅儀』を通して言われる訳なんですね。
例えば自分に、病気をした友人がいたとします。
その友人は「病気が治ったらまたゴルフをやりたいなぁ」と言うとしますね。
確かに病気が治れば、その友人はまた好きな「ゴルフ」ができるようになるかもしれない。
それはそれで素晴らしい事ですが、しかしまた病気になるかもしれない。
そして元気になったらまたゴルフをやる。
また病気になる。
人生はその繰り返しなんですね。そしてこれが「輪廻」です。
「輪廻」は繰り返されるんですね。何度も何度も。
しかしそれはずっと迷い続けるということでもあります。一生救われないということでもあります。
出会いがなければそれは何度でも繰り返されます。
同じような繰り返しを何度も何度もして、そしていつの日か亡くなってしまう。そしてまた生まれ変わる。今度は人間ではないかもしれない。とにかく迷い続ける。
その輪廻からは解脱しないといけない訳ですね。
今回の「人身得ること難し仏法値うこと希なり」というのは、「このありがたい命に気付いてください」という事以上に、仏法に出会えた、この今の人生をもっと噛み締めてくださいというのです。
またその仏法との出会いが輪廻から解脱する唯一の方法ですよ、ということなのです。
逆に、どこかでそのことに気付いてもらいたいから、その友人は何度も病気になれたのかもしれませんね。
それでも人間は中々気付くことができない。何度もそういった「輪廻」を外れる機会を頂いているのに気づくことができない。
ましてや現代は魅力的なコンテンツが多いですから、仏法に生きるなんてことは難しいかもしれない。せっかくの土日休みだというのに、儲けにも何もならない坐禅を組むなんてことはそうそうできることではありません。
しかし仮にそうだとしても、それは人生の延長です。我々は仏であり、仏道に生きるために、仏法に出会うために生まれてきた訳です。その輪廻からも解脱しなければいけない訳です。
我々の人生の大義は仏としていきること。仏と出会い、輪廻から解脱し、仏として死に、成仏することです。これが本当の我々の生き方なんですね。
ここで言う「また元気になったらゴルフをやりたいなぁ」というのは今までの人生の延長でしかないわけです。
そうではないと。それではいけないと。
今回「既に人身(にんしん)の機要を得たり、虚しく光陰を度(わた)ること莫(な)かれ。」とあるように「もういい加減、気付いてほしい」という願いが込められた内容となっているんですね。
もう「六道輪廻はやめてほしい」と。
坐禅とは仏行
足を組むとどうしようもなく痛いです。それは紛れもない痛みです。誰かと比較した痛みではなく、正真正銘、純度100%の痛みです。つまり宇宙いっぱいの痛みであり、その痛みは宇宙いっぱいの真実なのです。
その足の痛みがこの宇宙の、この世界の真実なのです。
この坐禅そのものが本来の世界なんです。この世界の真実なんです。この坐禅が全てであり、お悟りなんです。
坐禅が真実への回帰だと言われるのはこれがあるからなんですね。坐禅が仏行だと言われるのはこれがあるからなんです。
今回の内容にもありますが、我々はこの「坐禅」を通して「仏道の要機を保任している」ということになるのです。
この「坐禅」が、「一番仏道において肝心かなめの部分を保持している」、「受け継いでいる」というのです。
坐禅は仏行です。坐禅とは仏道にいき、仏を行じることです。
逆説的に言えばこの坐禅を通すことで、我々は仏道を生きることができる。仏として生きることができる訳です。「六道輪廻からの解脱」ができる訳です。
本当の命を生きることができる。仏として生きることができる。それが坐禅だという訳です。
なので道元禅師はこの坐禅をおすすめになる訳ですね。
先ほども申し上げた通り、我々の人生と言うのは自我の延長や納得で成り立っておることが大半です。
「ゴルフをやりたいからゴルフをやる」だとか「女の人と遊びたい」とか。
しかし我々の本当の「命」というのはこうした自我意識で成り立っているものは何もないんですね。我々の「命」というのはそのような「人間の自己満足の世界」で成り立っている訳ではないんです。概念の通じない、本来仏としての命をいただいている訳です。
こうしたい、ああしたい。これができた、あれができた。納得できた。満足できた。これが我々の人生です。
しかし実際、我々は納得なしにお腹が空きますし、納得無しにご飯を食べます。
腹が減るから腹が減る。
これだけなんです。
なぜ腹が減るか?を我々はどうしても考えてしまいますが、それは頭で考えても仕方のないことなんです。解決できないことなんです。
仮に生きるためにエネルギーが必要だからと言っても、腹は減り続けます。それは人間の単なる後付け説明にすぎないんです。
またそのように納得無しに食べたご飯を、納得無しに自然と消化もしております。
「納得云々で生きているわけではない」ということが重々に分かる訳です。
腹が何故減るのか?何故食べたものを自然と消化できるのか?なぜ呼吸をするのか?なぜ呼吸ができるのか?なぜ壁を殴ると痛いのか?なぜ足を組むと痛いのか?
何一つ納得いかないのが本来の「我々の命」であります。
説明がつかない、納得ができないというのは裏を返せば我々の考えが及ばない、無限大の命ということでもあるんですね。
そうした命を我々は生きている訳です。
そしてそれが今回でいう「要機」なんですね。
それなのに我々は何でもかんでも「説明」を求めます。「納得」を求めます。
説明や納得ができない「無限大の命」を我々はこうして生きているのにもかかわらず、その命をわざわざ限定して狭めようとするんですね。
説明が付いたり、納得ができるというのは「人間が作り出した限りあるもの」に対してだけです。
本来の大自然や我々の命というものには「一切説明がつかない」、「一切納得ができない」のです。
我々の体においても何一つ概念や納得が介さない仕組みをしている。仏として生きている訳です。
我々は本末が転倒して、あえて自我を中心とした「六道輪廻」を永遠に辿る生き方をしております。
本来の役目を忘れ、一瞬の楽しみにうつつをぬかすだけの人生を生きているんですね。
しかしそのような人生は本来ではありません。
繰り返しになりますが、我々は本来仏で、仏として生き、輪廻から解脱し、仏として死に、成仏することです。これが本当の我々の生き方なんですね。
なので、今回の内容をまとめると、



そのような人生を歩むのではなく、せっかく人間として生まれそこから仏法にも出会えたわけだから六道輪廻を繰り返したり、みだりに人生を楽しむのではなく真実に生きてください。
となる訳ですね。
説明なし、納得なしの「生命の実物」であります。またそれを仏の世界と言います。
その本来の命に立ち帰ることが我々人間の目指す生き方であり、救いであります。
そしてそれが「坐禅」です。
まとめ
今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、
と言う部分を解説してきました。
最後に本記事のポイントを振り返りたいと思います。
- 我々はせっかく「人間」として命をいただくことができた。
- それなのに「六道輪廻」から一向に抜け出せないのは勿体ないこと。
- 仏祖方から受け取った仏道における「坐禅」という宝。
- せっかく人間として生まれ、そこから仏法にも出会えたわけだから六道輪廻を繰り返したり、みだりに人生を楽しむのではなく「真実」に生きてください。
以上となります。
お読み頂きありがとうございます。

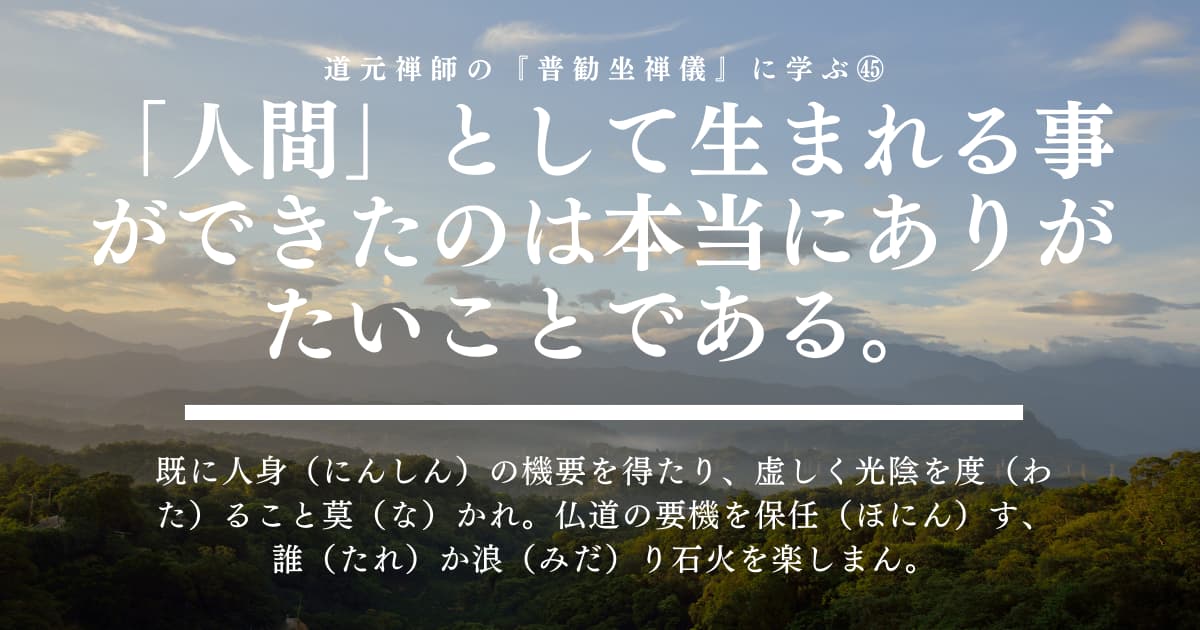


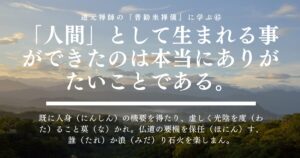
コメント