道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。
今回は第⑧弾といたしまして、「阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい」についてをお送りいたします。
筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。
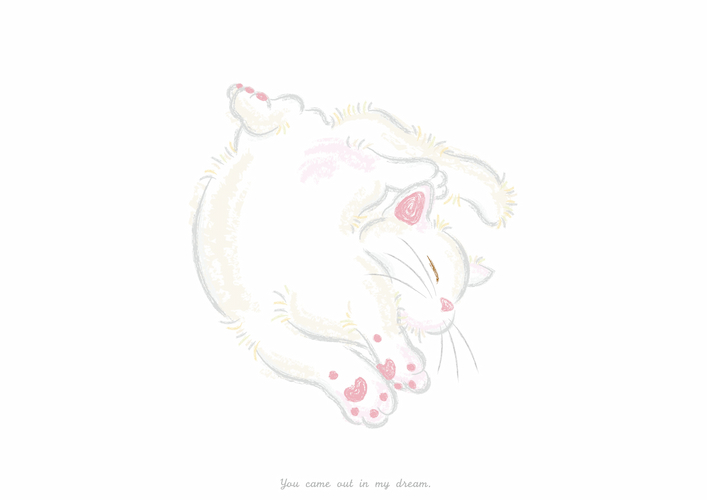
こんにちは「harusuke」と申します。
2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。
さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。
それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?
ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

阿耨多羅三藐三菩提とは?
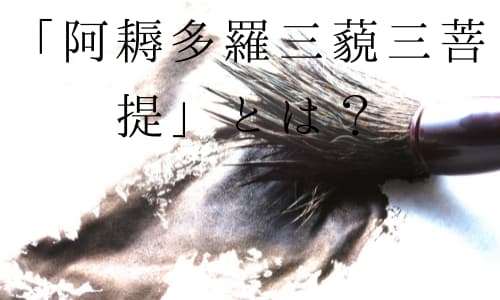
「阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)」とは簡単にいえば、この上ない極上の「悟り」という意味です。
サンスクリット語では「アヌッタラ・サンヤク・サンボーディ」と音写し、「anuttara-samyak-sambodhi」と書きます。
この「阿耨多羅三藐三菩提」ですが、この上ない極上の「悟り」ということですので、同じく「無上正等覚(むじょうしょうがく)」といったり、「無上菩提(むじょうぼだい)」と言ったりもします。
言い方はそれぞれあるにせよ、いずれも極上の「悟り」ということですね。
仏教をお開きになったお釈迦様が、お悟りを開いたとされる日が12月8日です。
この日を「成道会(じょうどうえ)」と呼びますが、その日、菩提樹の下で「結跏趺坐」をして到達した境地こそが今回の「阿耨多羅三藐三菩提」です。
その際「我と有情と同時成道」という言葉を残されておりますが、「私とこの世界のあらゆる事物は常に真実を表している」ということに気付かれたわけですね。
このお悟りが長い歳月と共に代々仏祖方に伝えられ、そして今日の我々の元までやってきたのです。
阿耨多羅三藐三菩提衣とは?
また「阿耨多羅三藐三菩提衣(あのくたらさんみゃくさんぼだいえ)」という言葉があります。
これは僧侶が身に付ける「お袈裟」を指します。
仏教においてこのお袈裟は最重視されるもので、時に「仏様の肌」と例えられたりしますが、「阿耨多羅三藐三菩提」からも分かるように、このお袈裟がお悟りそのものだというのです。
例えば禅寺で修行を始める若き修行僧たちは、まずこのお袈裟の扱い方から学びます。
これを身につけるときは、まず頭の上にお袈裟を置き、その上でお経を恭しく、三遍唱えてから身につけることができます。お袈裟をいただくときは毎回そのようにしなければなりません。
地面に置いたり、片手で持ったり、ぞんざいに扱うなどということは決して許されません。
そもそもお袈裟を身につけることができるのは正式に出家をしたものだけに限られます。「受戒」と呼ばれる正式な儀式を経て、仏弟子になってからからでないと身につけることはできません。
また元来お袈裟というのは、使えなくなって捨てられたボロ布、汚物を拭う位しか用が無くなった布を集めて作られたことから「糞掃衣」とも呼ばれたりしますが、この世界で様々な経験をした布地が元の素材となっております。
またそもそも布地というのが、この大地だったり、お蚕様のはく「糸」を素材に扱っているわけです。
お袈裟はそうしたものを大切に紡ぎ合わせて、時間をかけて作っていくわけですね。
いわば「この世界の真実」が材料となっており、言い方を変えればこの世界の真実そのものがこのお袈裟だということです。
非常に意義あるもので、誰でも構わず身につけたり、扱うこともできないのがこのお袈裟だということですが、それと同時にこのお袈裟が直ちに仏教者の証明となり、仏弟子の証明となり、あるいはこれを身につけることで仏に仕えることができ、その中でご葬儀ができたり、その他の法要を司ることができるようになるというわけです。
限られた人間、しかもそれは聖職者にあって、その聖職者の生活、あるいは存在と同義だということなのです。
ですから先ほども述べたように、このお袈裟そのものがお悟りだと、あるいは仏様の肌などと言われるわけですね。
非常に最も尊ぶべきものがこのお袈裟なのです。
道元禅師も師匠から弟子へ「正伝の仏法」が伝えられるときの証としてこの「お袈裟」を何よりも尊び、重んじられました。
特に『正法眼蔵』、「袈裟功徳」の巻の中では、「お袈裟」を付ける意義や、「お袈裟」の正しい身につけかた、「お袈裟」の作り方、「お袈裟」をつける際の心得などを細かくお説きになっております。
般若心経にも出てくる「阿耨多羅三藐三菩提」
現在では大変お馴染みになりました「般若心経」。一般の方でも唱えられる人がちらほらいたりしますよね。
正式名称を「摩訶般若波羅蜜多心経」といいますが、この「般若心経」の中にも今回の「阿耨多羅三藐三菩提」というフレーズがでてきます。
これを訳すと、
過去の仏祖方は大自然の本質を知ることによって、この上ない悟りを得てきた。なので我々も仏祖方と同じように、大自然の在り方を知るべきである。
このような感じになります。
要するに今回の「阿耨多羅三藐三菩提」というのは「極上の悟り」ということですが、それは目の前に展開している「大自然」そのものだということを、この般若心経では言っているんですね。
日常全てがお悟りだと言われたお釈迦さま。またその日常に身を置く自分もお悟りだと言われました。
例えば「坐禅」をすることで「足」が痛くなりますが、これも紛れもない大自然の恵みです。
ならばこの「坐禅」も「阿耨多羅三藐三菩提」だと言えますね。


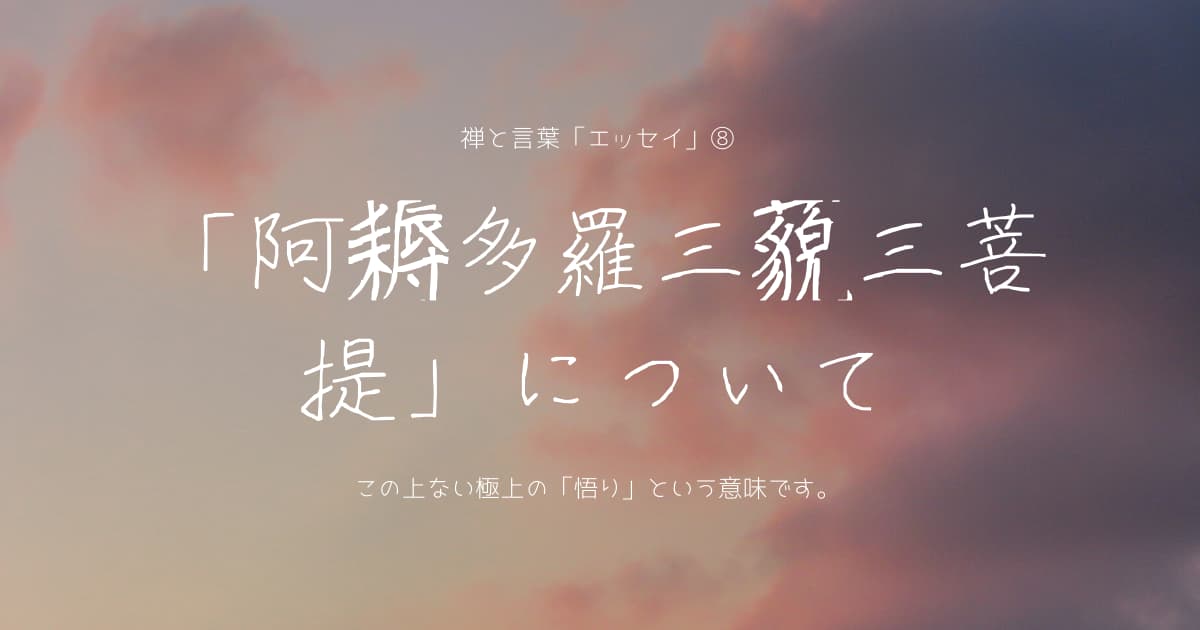

コメント