今回は、宏知正覚(わんししょうかく)禅師についてご紹介させてください。
「宏知正覚禅師」は道元禅師が非常に尊敬しておられた祖師のお一人であります。
祖師を慕う敬称として「古仏」という表現をしますが、道元禅師はこの言葉をあまり使いません。
しかしこの宏知正覚禅師に対してはこの「古仏」という言葉を使っておられるんですね。非常に尊敬をされていた人物なのです。
宏知正覚禅師は1091年にお生まれになられました。
隰州(しつしゅう)、現在の山西省出身の中国の宋時代の禅僧です。
多くの優秀な弟子を輩出し、当時「黙照禅」とい言われた、のちに曹洞宗の坐禅の大元となる面壁坐禅を、正当な「禅」と主張されたお方です。
当時、臨済宗に属した「大慧宗杲(だいえそうこう)」というこちらも有名な人物ですが、その大慧宗杲と真の禅法をめぐって激しく対立をされるんですね。
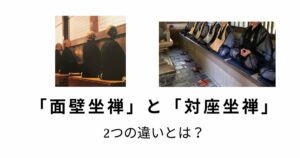
今回その大慧宗杲とのやりとりも取り上げながら、宏知正覚禅師という人物像に迫っていきたいと思います。
それでは参りましょう。

道元禅師も慕う「古仏」
道元禅師も敬う存在であった「宏知正覚(わんししょうかく)」禅師とはどういった方なのか、まずはここでその人物像について見ていきたいと思います。
「丹霞子淳(たんかしじゅん)」禅師というお方の弟子に今回の主人公である「宏知正覚(わんししょうかく)」禅師という方がいます。
またこの宏知正覚禅師は、「長蘆清了(ちょうろせいりょう))」禅師という現在の日本曹洞宗の流れに入る祖師と兄弟弟子にあたる方でもあります。
この「宏知正覚(わんししょうかく)」禅師は、現在の曹洞禅の根本でもある「黙照禅」を当時から非常にすすめられた方であり、今日で言う「只管打坐」を自らが実践し、それを沢山の方に示したお方だったのです。
先にも述べましたが道元禅師はこの宏知正覚禅師の事を、「宏知古仏」、「宏知古仏」と言って、非常に尊敬しておられました。
「古仏」というのは、禅宗において「悟りをひらいた高僧」の敬称ですが、道元禅師がこの「古仏」と慕うのは「曹渓古仏(曹渓慧能)」、「宏知古仏(宏知正覚)」、そして師匠にあたる「如浄古仏、天童古仏(天童如浄)」のこのお三方だけだったと言われております。
道元禅師がこの「古仏」と付けるのはこの三名だけで、他の方に「古仏」という表現は付けておりません。
つまりそれほどまでにこの宏知正覚禅師は、道元禅師が非常に尊敬を申し上げ、影響を与えられた祖師であったのです。
失われつつあった達磨様の坐禅。
菩提達磨(ぼだいだるま)様によってインドから中国に伝えられた「真実の仏法」。
達磨様はその「真実の仏法」を面壁九年という形で伝えられました。
「面壁九年」の九年というのは実際の数字ではなく、長い間、ひたすらということですね。長い間壁に向かって坐禅をされたということです。
つまり「壁に向かって坐禅をすること」を生涯続けられたのです。その姿が伝えられてきたんですね。
それでは何故、達磨様は壁に向かって長い期間、坐禅をされ続けたのか?
それはこの面壁坐禅こそが「真実」であり、「大自然の在り方」であることをしっていたからです。
というのも大自然には「人間の思惑」や「人間の悟り」は通用しないですよね?
どんなに多くの人間が住んでいようと、そこには大災害が起こります。大自然には人間の自我意識や概念が通用しません。
また一方で、自分が寝ている間、「俺」というものが寝ている間にも呼吸がされる。消化がされる。
外が寒ければブルっと自分が震えるのもそう、犬や赤ん坊の泣き声が自分の耳を振るわせ、そこで自分がうるさく感じるのもそう。
つまり大自然には俺がないんですね。大自然と我々は一つに繋がっているのです。
それが大自然の在り方なのです。
本来このように私と大自然は一つに繋がっているのに、「自我意識」や「概念」だけが独り歩きをしようとしたり離れ離れになろうとするのです。
例えば「これは俺のもの」とかですね。大自然と自分を切り離そうとするんです。
しかし真実の在り方はそうではありません。仮にここからここまでが俺の命、つまりはここからここまでが俺の呼吸、俺の酸素という風に仕切れるのだとしたら、我々はどこか旅先で即座に呼吸が止まり、死んでしまうはずです。しかしそうではない。
いつでも呼吸ができるわけです。そしていつでも平気で生きることができるわけです。
なので人間の思惑で「坐禅」をして「悟る」などということは決してあってはならないし、それは「真実」に背いた行為であるのです。
その「真実」の在り方を知っていた達磨様でしたから、ひたすら「大自然そのものである坐禅」を「真実の坐禅」を「無功徳の坐禅」を実践されたんですね。
はたから見ればこの面壁坐禅は他人や世間に背を向けるとも捉えられますが、壁に向かって坐禅をすることこそ、大自然の行いであったわけです。
しかし時が経ち、今お伝えしたような「真実の仏法」は達磨様の教えを受け継いだ後世のものによって趣旨が段々とずれて伝えられていってしまいます。
例えば、道元禅師が中国に入られる少し前に中国で活躍した「大慧宗杲(だいえそうこう)」という人がいます。
この大慧宗杲を中心にして公案(看話)禅というのが達磨様亡き後、中国において非常に盛んになっていくんですね。
公案(看話)禅とは内側を向き、過去祖師方における公案をもとに自身を参究していく、世界を、真実を参究していくというもので、ひいては坐禅を手段として悟りに到達するというものです。
当時の中国社会では、この大慧宗杲の公案禅が支持を受け、臨済宗が大いに隆盛しておりました。
達磨様によって伝えられた真実の仏法、「個人」を修行するのではなく、「全体」を修行するという事は、すっかり疎かになってしまったのです。
「坐禅」を手段として、その公案に参じていくという事が「仏法」の中心になっていたのです。
つまり「大自然」の行が「人間」の行に落ちていってしまったのですね。
しかしそれでも達磨様の教えをしっかりと受け継いだ方がおります。
それが今回の主役でもあり、道元禅師も慕う宏智正覚禅師です。
批判されても構わない。それでも貫いた坐禅。
この宏智正覚禅師は達磨様亡き後も、ひたすらに達磨様がお示しになった「全体を修行する坐禅」、つまり個人の感情に任せた坐禅ではなくて、全体を修行する坐禅を盛んにされておられました。
それに対して大慧宗杲はこの宏智正覚禅師の坐禅、「達磨様の坐禅」ならぬ、「黙照禅」を痛烈に批判をされます。
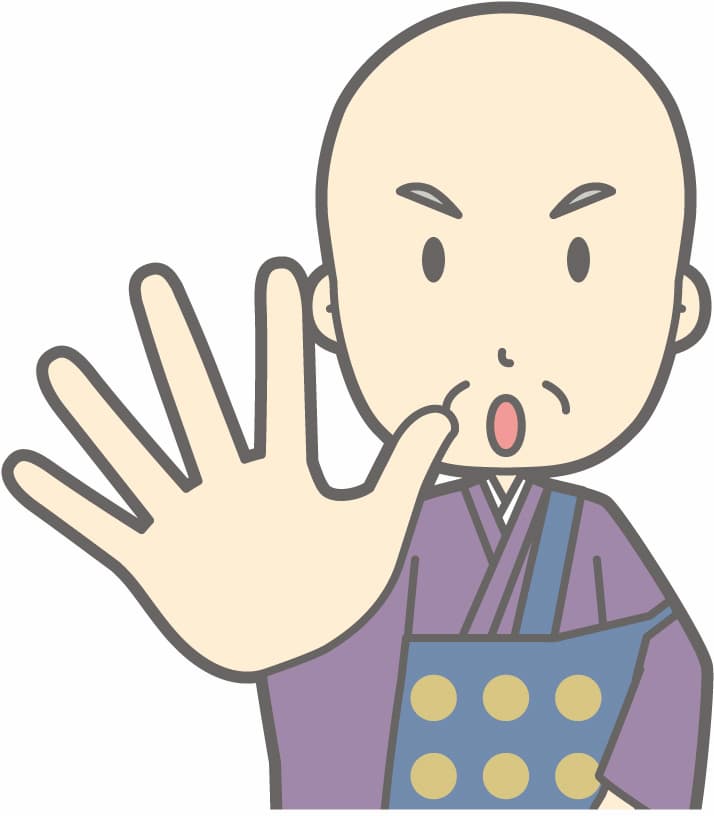 大慧宗杲
大慧宗杲壁に向かって、「面壁」などして一体何になるんだ!!人間にとっても何の功徳も無いではないか!何のご利益もないじゃないか!
とこう言う訳です。
しかし前述の通り「人間の目的」を持って修行したならばそれは個人の修行になってしまいます。そもそもこの世界に自分というものはありません。無我なのです。
つまりこうした自我の延長である「坐禅」は「仏行」ではないし、本当の修行とも言えないのです。
宏智禅師はこの大慧宗杲を始め、周りからの批判も飛び交う中、ただひたすらに達磨様から伝えられた「面壁の坐禅」をひたすらに行います。
そのような宏智禅師に向かって、大慧宗杲は
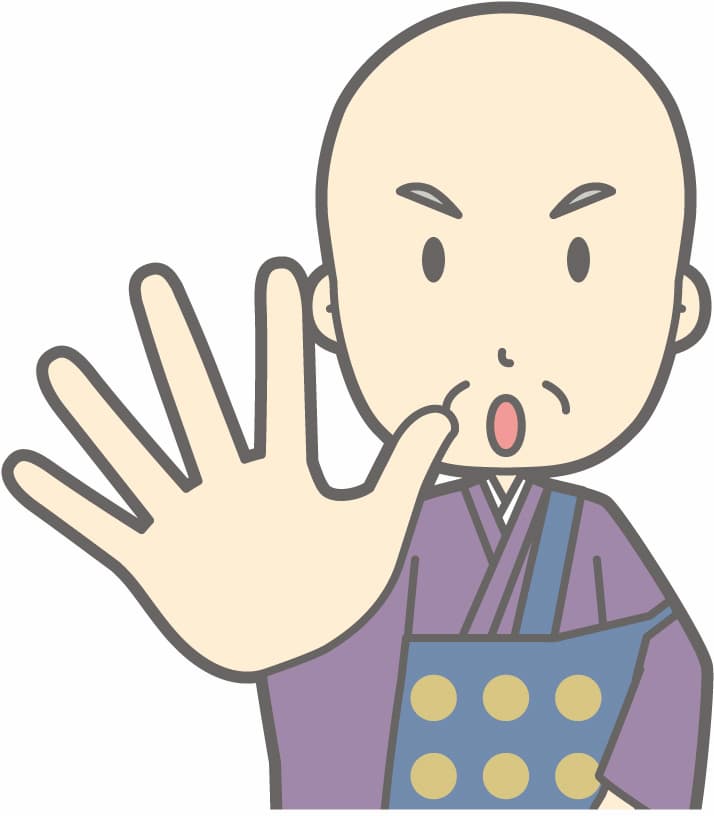
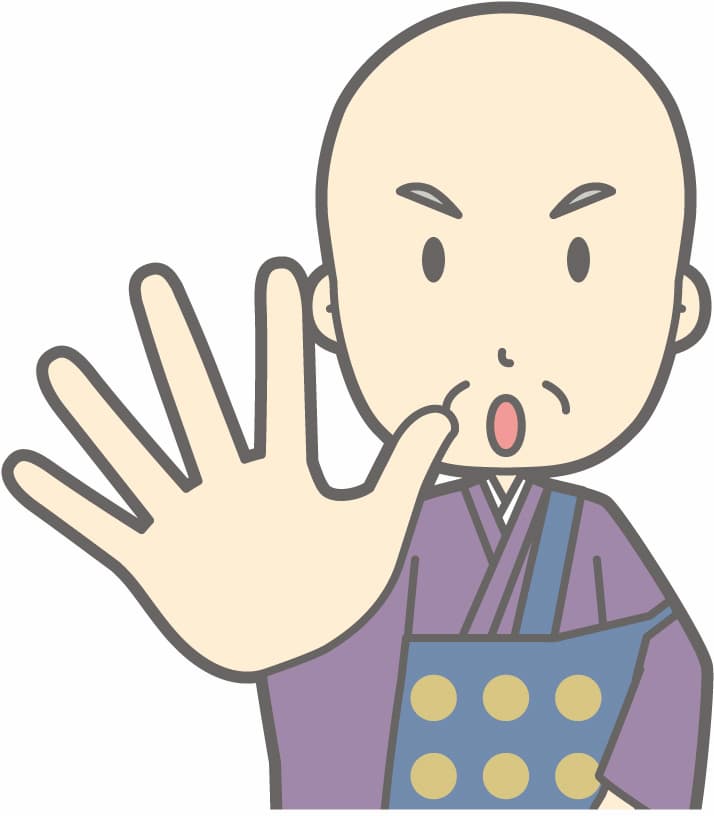
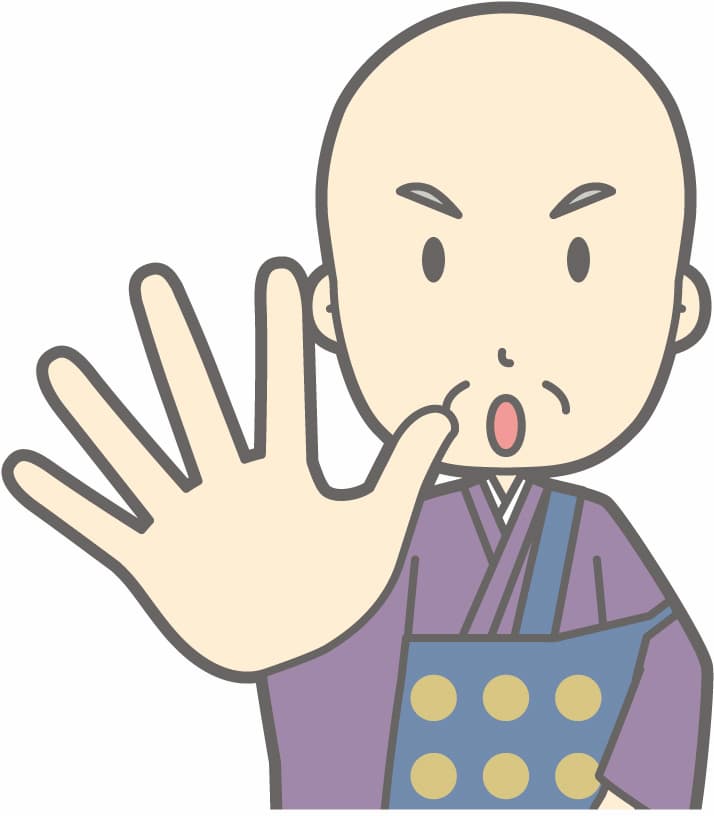
壁に向かって坐禅するなど本当にくだらない!まさに「黙照の邪禅」である!
と言われます。
「黙って照らす、黙照の邪な禅。黙照の邪禅の輩」と。
「黙照の邪禅」というのは壁に向かってただひたすらに邪を照らし続ける坐禅のことですね。
このように言って、大慧宗杲は宏智禅師の事を非常に批判をされるのです。
それに対して宏智正覚禅師は、「黙照明とはなんとありがたい言葉を受け取ったのだ!」とまるで相手にせず、この大慧宗杲の批判を見事に軽くあしらったりしています。
「黙照」という言葉を「阿呆な奴等」という受け取り、こんなにありがたい言葉は無いと受け取った宏智正覚禅師。
そしてそのようなやりとりを何度も繰り返し、「真の禅」を巡って大慧宗杲と宏智正覚禅師は激しく対立されるんですね。
現代史にも残るほど有名な「禅を巡る戦い」です。
宏智正覚禅師の坐禅は、はたからみればただ黙って坐禅をしつづけるものです。
なので確かにこの大慧宗杲や「一般の人」から見ると、「なんてくだらない!」と思えてしまう気持ちも分かります。
そんな事している間に金勘定した方がよっぽどよいじゃないかと。
ただ黙って壁に向かう。そんななにもならない坐禅をひたすら行ったところで何の意味があるんだ?
そう思われるのが一般世間の「常」です。
しかし「大自然」はそういうものなんですね。人間の思惑、損得勘定は一切通用しないのです。
今こうしている間に我々の命に目を向けるとそれがよくわかります。
この呼吸は見返りを求めてされていないし、消化も自分が寝ておきたらちゃんとされている。
これが大自然の在りかたなんです。
またその大自然と1つの命として繋がっているのが我々なのですから、その本来のあり方に準じなければいけないはずですよね。
だから宏智正覚禅師は「大自然」を貫くんです。
本当の「坐禅」は「人生以降の、個人の坐禅」ではないということを知っているからです。
そこが大慧宗杲、または一般の方々から理解をいただけず批判の的となってしまうんですね。
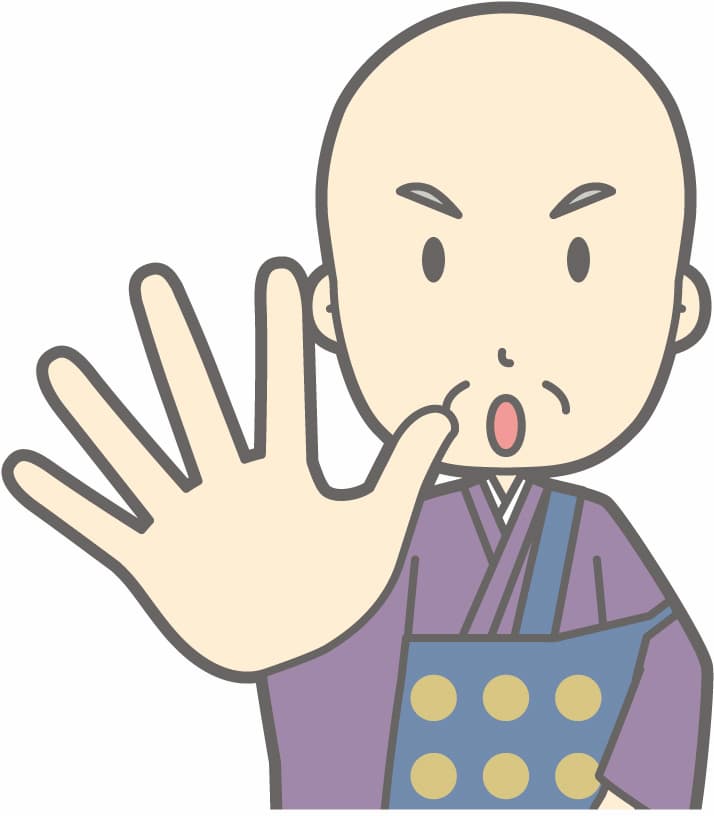
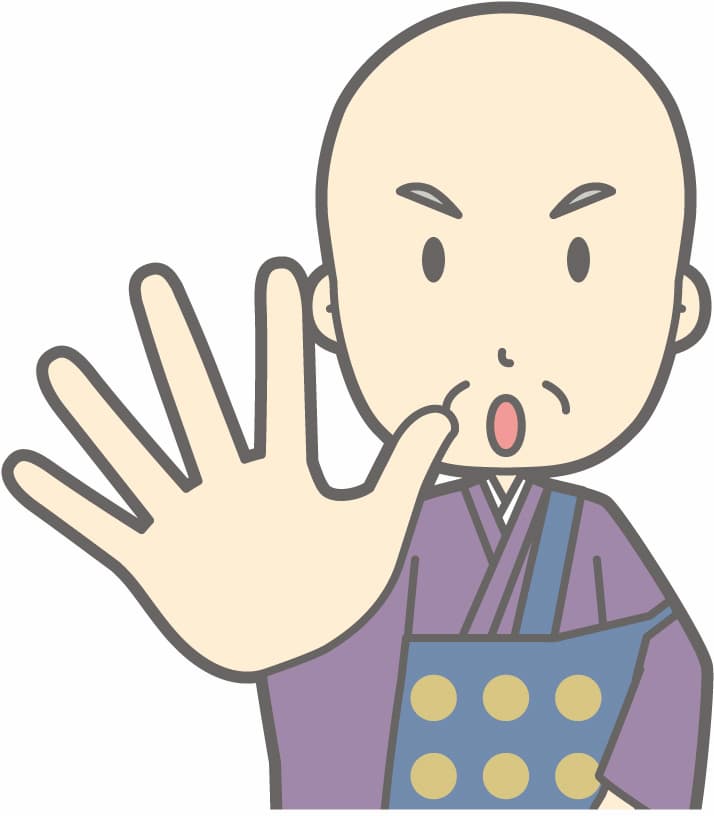
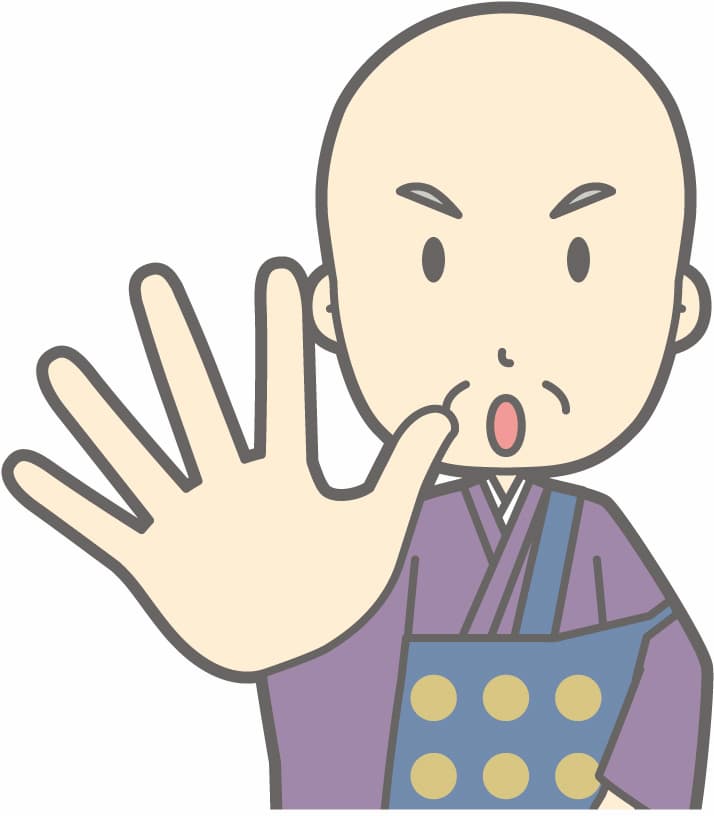
なんてくだらない、能率の無い、ご利益も無い、坐禅なのだろう
!!
と、いう風に批判を受けるのはある意味当然であったはずです。
しかしそれでも宏智正覚禅師は、



よくありがたい事を言ってくれたな。我々こそ本当の「黙照」である。何のご利益も無い、宇宙一杯の仏行をこれからもしつづけるのみ。
というお言葉をこの大慧宗杲に返しております。
このように批判されても「ありがたい、ありがたい」と言って、達磨様から伝わる面壁の坐禅を宏智正覚禅師は貫いていったというわけです。
宏智正覚禅師が守り抜いた「真実の仏法」
こうして当時、途絶えそうになった「真実の仏法」でしたが、宏智正覚禅師によって「面壁」の坐禅は失われる事なく数少ない弟子たちに継承されていきます。
もし当時宏智正覚禅師がこの「真実の仏法」を貫くことをせず、大慧宗杲や一般の波にのみこまれてしまったら、現代にお釈迦様から続く「真実の仏法」は絶えてしまったかもしれません。
一般からしたら「変人」とも思われるような宏智正覚禅師の「坐禅」。
人生がはじまる以前の、「父母未生以前」の真実の仏法。
しかし人が当たり前に考えるのは人生以降の話であります。それは仕方がない話でもあるわけです。
こんな大自然の本来のあり方など考えるきっかけがないですからね。しかし事実我々はこうした大自然の命を生きている。大自然の生き方をしている。
それに気づけないのはやはり悲しいことですよね。そして自我に支配されて死んでしまう。
それは本来の生き方ができなかったということです。本来の命を全うできなかったということで、成仏できなかったということにもなってくるわけです。
この世に生を受け、いつの間にか構築されていく「自我」。
大慧宗杲もまた、「坐禅」を個人の悟りの手段と考え、人生以降の修行をしていたためにこの両者は中々分かり合えませんでした。
今ある一般的な宗教も人生以降の「自我の延長」であります。
「自分」という個人を保証してくれる「システム」として宗教を作り、「神」を作り出してしまった。
それによって、今日の様な宗教の争いが生まれたりしております。
これらは全て人生以降の話であります。
元々は人生以前の話、「父母未生以前」の話として、この「只管打坐」が、お釈迦様や達磨様、宏智正覚禅師、道元禅師へと伝えられました。
なので我々も大自然の「坐禅」、真実の「坐禅」を実践し、継承していきたいものですね。
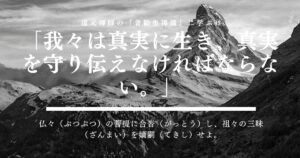
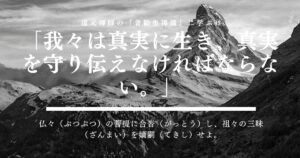

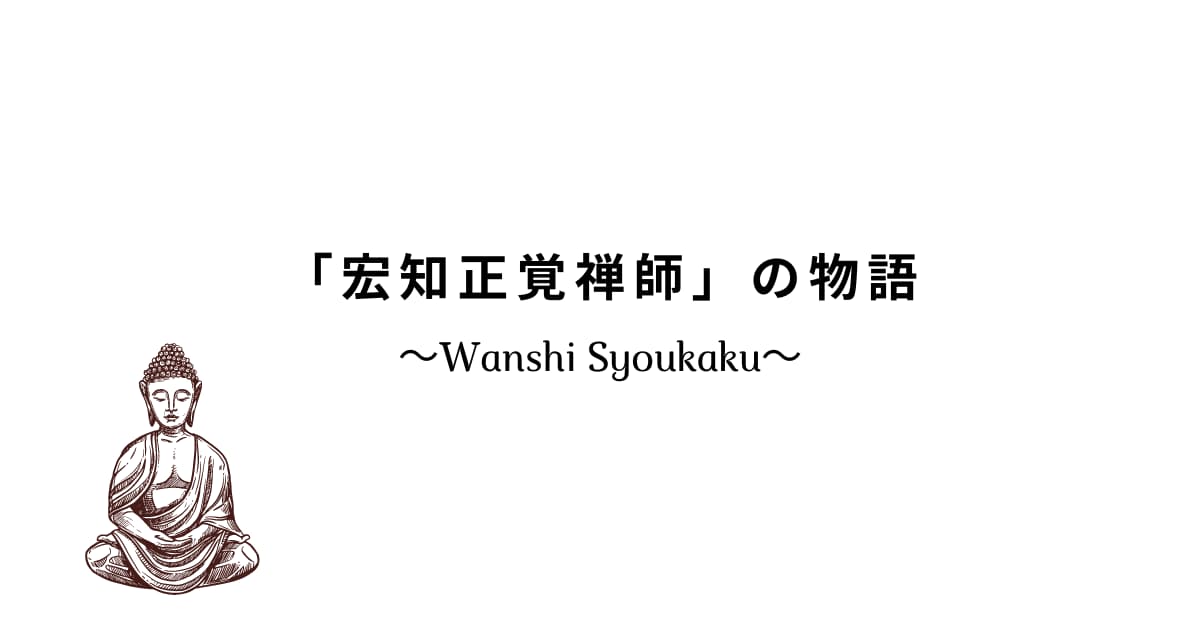
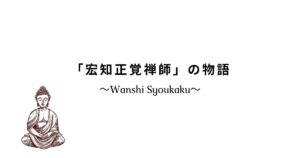
コメント